競馬の世界では「馬がかかる」や「時計がかかる」といった表現がよく使われます。
同じ「かかる」でも意味はまったく異なり、ひとつは馬の気性やレース運びに関するもの、もうひとつは馬場状態に関するものです。
初心者にとっては分かりづらい用語ですが、どちらも予想に大きな影響を与える重要なポイントとなります。
本記事では「競馬 かかるとは?」をテーマに、馬に関する「かかる」と馬場に関する「かかる」の違い、見分け方や関連用語との違いまで解説していきます。
競馬における「かかる」とは?
競馬において「かかる」とは、大きく分けて二つの意味があります。
ひとつは「馬がかかる」で、これは競走馬が折り合いを欠いて前へ行きたがる状態を指します。
もうひとつは「時計がかかる」で、馬場が重くなり走破タイムが遅くなることを表現します。
同じ言葉でも文脈によって意味が異なるため、解説や予想を聞く際にはどちらを指しているのかを見極める必要があります。
特に初心者は混同しやすいので、この違いをしっかり理解しておくことが大切です。
馬に使う「かかる」とは?
「馬がかかる」とは、競走馬がレース序盤で騎手の指示を聞かず、必要以上に前へ行こうとする状態を指します。
このような状態になると「折り合いを欠く」と表現され、馬は無駄にスタミナを消耗してしまいます。
特に中距離や長距離のレースでは致命的な不利となり、直線で力尽きて失速するケースが多く見られます。
競馬新聞や中継では「掛かり気味」「ハミを噛む」といった言葉でも紹介されます。気性が激しい若駒や、距離が合っていない馬によく見られる現象であり、騎手にとってはコントロールが難しい課題のひとつです。
かかりやすい馬を把握しておくことは、予想をするうえで大きなヒントになります。

かかる馬の見分け方
馬が「かかっている」かどうかは、返し馬やレース序盤の走りを観察することである程度見抜けます。
例えば、パドックや返し馬の段階で首を大きく振ったり、口を割って落ち着きがない動きをしている馬は注意が必要です。
レースが始まると騎手が手綱を引いても頭を上げて抑えが利かず、必要以上にスピードを出してしまうケースが見られます。
また、スタート後に想定よりも速いラップを刻んだり、無理に先頭へ行こうとする動きも「かかり」のサインです。
原因としては、気性の激しさ、馬場や距離が合わないこと、レース当日のテンションなどが考えられます。
こうした特徴を理解しておくと、パドックや直前の気配から「今日は折り合いを欠くかもしれない」と予測することができ、馬券検討にも役立ちます。
かかるとレースにどう影響する?
馬がレース序盤でかかってしまうと、本来なら温存すべきスタミナを無駄に消費してしまいます。
その結果、直線に入る頃には力を使い切ってしまい、伸びを欠いて凡走するケースが目立ちます。
特に2,000m以上の中距離や長距離戦では「折り合い」が勝敗を大きく左右する要素となるため、かかり癖は致命的な弱点になりかねません。
一方で、短距離戦では序盤からスピードを出すこと自体が有利に働く場合もあり、かかり気味でも力で押し切るタイプの馬も存在します。
このため「かかる=必ず不利」とは言い切れず、距離や展開との相性を見極めることが重要です。
騎手の技術や馬具(チークピーシズ、ブリンカーなど)で矯正できるかどうかもポイントで、ベテラン騎手ほど上手に折り合いをつけて結果を出す傾向があります。
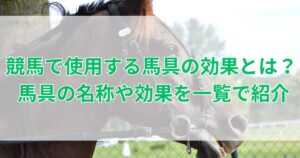
馬場に使う「時計がかかる」とは?
「時計がかかる」とは、馬場状態の悪化によって走破タイムが遅くなることを指します。
雨でダートが水を含んだり、芝が荒れてクッションが効かなくなったりすると、同じ距離でも普段より時計がかかる傾向が見られます。
この表現は「馬がかかる」とはまったく別の意味で使われるため、文脈を理解して使い分けることが大切です。
時計がかかる馬場ではスピードよりもパワーや持久力が重要となり、血統や脚質によって有利不利が大きく変わってきます。
時計がかかる意味
競馬において「時計がかかる」とは、馬場状態の影響によってレース全体の走破タイムが遅くなることを指します。
たとえば雨で芝やダートが水を含むと地面が重くなり、馬の脚が沈み込むためスピードが出にくくなります。逆に、開催後半で芝が荒れて土がむき出しになったときも同様に時計がかかりやすくなります。
同じ2,000mのレースでも、良馬場では1分58秒台で走れる馬が、重馬場では2分を超えることもあります。
こうしたタイム差は馬の能力差ではなく、馬場の影響によるものです。
そのため、予想の際には「この馬は力のいる馬場に強いかどうか」をチェックすることが非常に重要になります。
血統や過去の戦績から、時計のかかる条件で走れているかを確認すると馬券検討の精度が上がります。
時計がかかる馬場の特徴
時計がかかる馬場では、通常の良馬場に比べてスピードが出にくく、レース全体のタイムが遅くなります。
芝では開催が進むにつれて内側の芝が荒れて土が見えるようになり、脚を取られるためパワーが必要になります。
こうした馬場では瞬発力型よりも持久力型やパワー型の馬が有利になります。
血統面ではスタミナ色の強い系統や、欧州型芝血統などが浮上しやすいのも特徴です。
また、速い上がりを持つ人気馬が力を発揮できず、伏兵が台頭するケースも多いため「時計がかかる=波乱含みの条件」とも言えます。
馬場状態の変化を的確に読むことが、予想の精度を高める大きなポイントになります。
「かかる」という言葉の漢字と語源
競馬で使われる「かかる」という表現は、文章や媒体によってさまざまな漢字で表記されます。
馬に対して使う場合は「掛かる」と書かれることが多く、「馬が掛かる=折り合いを欠いて行きたがる」という意味で用いられます。
一方、馬場に対して使う「時計がかかる」は「掛かる」「懸かる」など新聞社や専門誌によって表記が異なります。
語源としては「余計な力が掛かる」「時間が掛かる」といった日常的な意味から派生したものとされます。
つまり、競馬用語として特別に作られた言葉ではなく、一般的な日本語の表現が競馬に応用された形です。
そのため同じ「かかる」でも、文脈によって意味が変わることを理解しておく必要があります。
関連用語との違い
競馬では「かかる」と似た意味合いで使われる専門用語が多く存在しますが、それぞれ微妙にニュアンスが異なります。
「折り合い」とは馬と騎手がペース配分をうまく保つことを指し、かからずにリズム良く走れる状態を表します。
「ささる」は直線で馬が内側に寄れてしまうこと、「モタれる」はコーナーで外へ膨れてしまうことを意味します。
また「ガイガイ」という表現は、馬が落ち着かずガチャガチャした動きを見せることを指し、「ハミを噛む」はかかって制御が利かない動作の一部を表す言葉です。
これらを混同せず理解しておくと、解説やパドックコメントのニュアンスが分かりやすくなり、予想に活かしやすくなります。

競馬で「かかるお金」とは?
「かかる」という言葉は本来、馬や馬場に使われる専門用語ですが、一般会話では「競馬にかかるお金」という形でも用いられます。
ここでの意味は、馬主が競走馬を所有・育成する際の維持費や出走に伴う経費を指す場合と、ファンが馬券購入に充てる資金を表す場合の二通りがあります。
例えば馬主の場合は、調教代や輸送費、厩舎への預託料など多額の費用が「かかる」ことになります。
一方で一般ファンにとっては「今週の競馬でどれくらいお金がかかるか」という日常的な感覚で使われる言葉です。
専門用語としての「かかる」とは意味が異なりますが、両方を理解しておくと会話の中で混乱しにくくなります。
まとめ|「かかる」を理解すれば予想の精度が上がる
競馬で使われる「かかる」という言葉は、一見同じように聞こえても大きく二つの意味があります。
ひとつは「馬がかかる」で、折り合いを欠いてスタミナを無駄に消耗する状態。もうひとつは「時計がかかる」で、馬場の悪化によって走破タイムが遅くなる状態です。
この二つを混同せずに理解しておくことは、予想の精度を高める上で非常に重要です。
かかり癖のある馬を把握すればレース展開を読む助けになり、時計がかかる馬場を見極めれば適性のある馬を探すヒントになります。
さらに「折り合い」「ささる」「モタれる」といった関連用語の違いも整理しておけば、中継や新聞の解説をより正確に理解できるでしょう。
競馬を楽しむためには、専門用語を知識として持っておくことが大きな武器になります。
「かかる」という言葉を正しく理解し、次の予想や馬券戦略にぜひ活かしてみてください。

