競馬において「騎手買い」という予想スタイルは、初心者からベテランまで幅広く支持されています。
「上手い騎手が乗っているから買う」「この騎手なら信頼できる」といった考え方で馬券を組み立てる人は少なくありません。
一方で、「騎手買いは回収率が低い」「結局は馬の能力がすべて」という否定的な意見も存在します。
果たして、騎手買いは本当に有効な戦略なのでしょうか。
この記事では、騎手買いの基本的な考え方から、有効な使い方や注意点までをわかりやすく解説していきます。
騎手買いとは?基本の考え方と由来
「騎手買い」とは、出走馬を評価するうえで騎手の存在に注目し、馬券の根拠とする予想スタイルです。
「馬より騎手が大事」といった考えのもと、騎手の実績や得意条件を重視して購入判断を下す人も多く見られます。
最初に、騎手買いの意味や定義、注目される理由について解説します。
騎手買いの意味と定義
騎手買いは、その名のとおり「騎手を軸にして馬券を選ぶ」予想方法です。
競馬新聞を見た際にまず騎手名に注目し、信頼できる騎手が騎乗していればその馬を買うというシンプルなスタイルです。
騎手の技術や過去の戦績、レースの駆け引きへの理解力などを高く評価する人が選ぶ手法で、特に初心者にも取り入れやすい点が特徴といえます。
また、複雑な分析を避けられるため、時間をかけずに予想したいときにも重宝されています。
騎手買いが注目される理由
近年はルメール騎手や川田騎手といった実績豊富な騎手が毎年のように好成績を残しており、「騎手の腕が馬の能力を引き出す」といった見方も定着しています。
とくにG1などの大舞台では、経験や勝負勘のある騎手の重要性が増し、信頼して買う人が多くなります。
さらに、地方競馬のように実力差が明確な環境では、騎手の力量が着順に与える影響がより顕著に表れるため、騎手買いが有効とされることもあります。
騎手買いは勝てるのか?賛否両論の実態
騎手買いは競馬予想の中でもシンプルで取り入れやすい手法ですが、必ずしもすべての人に利益をもたらすわけではありません。
実際に「騎手買いでは勝てない」と主張する人もいれば、「条件付きなら勝てる」という意見も存在します。
ここからは騎手買いの賛否について解説します。
騎手買いを否定する意見とその根拠
騎手買いに否定的な人たちは、「騎手で人気が集まりすぎるとオッズが割に合わない」「結局は馬の能力がすべて」といった主張を展開します。
特にリーディング上位の有名騎手は過剰人気になりやすく、回収率が極端に下がることもあります。
実際にJRA公式データなどを見ると、横山武史騎手やルメール騎手のような人気騎手でさえ、単勝の回収率は100%を切っていることが多くあります。
馬券で利益を出すには「期待値のある買い方」が必要となるため、騎手名だけで馬券を買うスタイルは「儲からない買い方」として警戒されがちです。
騎手買いで勝っている人の特徴
一方で、騎手買いを戦略的に活用して回収率を上げている人も存在します。
彼らは「得意条件」「競馬場」「人気とのバランス」といった要素をもとに、データを絞り込んで機械的に購入しています。
例えば、ローカル競馬場では特定の騎手が高い勝率と回収率を出していることがあり、競馬場別の成績に注目するだけでも差別化が可能です。
また、過去5走以内に好走歴のある馬に乗り替わってきた中堅騎手を狙うなど、一定のルールに従って予想を組み立てる人は、長期的に見てプラスを出しやすい傾向にあります。
リーディング上位の騎手以外にも、得意コースに適した騎手は必ず存在しているので、期待値の高い騎手を狙うことで高配当につなげることが可能なのです。
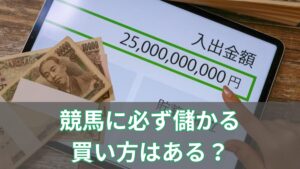
騎手買いで重要な3つのチェックポイント
騎手買いは感覚や印象で選んでしまうと、回収率が安定しにくくなります。
しかし、騎手の特徴をデータで分析し、条件を絞り込むことで、的中率と回収率の両面で有効な買い方に変えることが可能です。
ここからは騎手買いで重要な3つのチェックポイントについて解説します。
騎手ごとの得意条件を知る
騎手によって、得意な競馬場や距離、さらには逃げ・先行・差しといった脚質に偏りがあるケースは多く見られます。
たとえば、川田将雅騎手は芝でもダートでも結果を残していますが、芝の長距離レースにおける好走率は低い傾向にあります。
また、ローカル競馬場では騎手の技術が問われる場面も多く、地元騎手や実績のある中堅騎手が高回収率を記録している例もあります。
競馬場・距離・馬場状態・展開など、過去の成績から傾向をつかむことが、騎手買いで失敗しないための基本となります。
過剰人気の騎手に注意する
ルメール騎手や武豊騎手のような知名度の高い騎手は、騎乗馬の実力以上に人気が集まりやすく、オッズが割れてしまうことがあります。
こうした過剰人気は回収率を大きく下げる要因となり、長期的な収支をマイナスに傾けるリスクがあります。
特にG1などの注目レースでは初心者層の投票も増えるため、有名騎手の馬が必要以上に売れる傾向が強まります。
騎手名だけで買うのではなく、騎手が得意とする条件かどうかを冷静に見極め、人気とのバランスを考えることが重要です。
地方競馬の騎手買いは有効性が高い
地方競馬では中央と比べて騎手の技術差がはっきり表れやすく、騎手買いが通用しやすい傾向があります。
騎手の乗り方ひとつで着順が大きく変わることも珍しくなく、先行策やペース判断の巧拙が如実に結果に現れます。
また、騎乗機会が限られる地方では、同じ馬に継続騎乗している騎手が馬の癖を把握している場合が多く、そういった騎手は安定した結果を出しやすいです。
特定の競馬場で安定して成績を残す騎手に注目することで、地方競馬での騎手買いは的中率と回収率の両方で大きな武器になります。
騎手買いを活かすおすすめの馬券種と条件
騎手買いの効果を最大限に引き出すためには、馬券の種類とその騎手の特徴をうまく組み合わせることが大切です。
ここでは、単勝や複勝、ワイドや3連複など、騎手買いと相性の良い馬券種と条件について解説します。
単勝・複勝での騎手買いの効果
単勝や複勝は、1頭の馬に絞って馬券を購入するシンプルな買い方です。
「勝ち切る騎手」か「安定して上位に持ってくる騎手」かを見極めることで、騎手買いの精度が格段に上がります。
たとえば、勝率の高いリーディング上位の騎手のように、人気馬で確実に勝ち切る傾向が強い騎手は単勝向きです。
一方、2着・3着が多いタイプは、複勝や連系馬券で活用する方が合理的です。
回収率を安定させるには、過去の成績データを参考に、勝ち筋が明確な騎手に絞ることが重要です。
ワイド・3連複での軸としての活用
安定感のある騎手は、ワイドや3連複の「連軸」として非常に信頼できます。
例えば、2〜3着の経験が多い騎手や、掲示板内にコンスタントに入っている中堅騎手は、馬券に絡む可能性が高く、軸に据えることで高い的中率が見込めます。
また、ローカル競馬場や条件戦では騎手の技術が勝敗に直結しやすいため、勝率よりも連対率や複勝率を重視して選ぶのが効果的です。
3連複なら1頭軸流しで多点数を抑えられるので、少額で的中のチャンスを広げやすくなります。
実力馬に騎乗する騎手ではなく、「馬券に絡める騎手」を見抜くことが鍵となります。
騎手買いのメリットとデメリット
騎手買いは感覚的に始めやすく、データ分析もしやすいため、予想スタイルとして多くのファンに支持されています。
しかし、その一方で落とし穴も多く、状況によっては回収率を下げる要因にもなり得ます。
騎手買いのメリットとデメリットについてまとめました。
騎手買いのメリット
騎手買いの最大のメリットは、予想の軸を明確にできる点にあります。
自分が信頼する騎手や、データ上回収率の高い騎手に絞ることで、予想がブレにくくなります。
また、実力差が出やすいローカル競馬や条件戦などでは、騎手の腕が勝敗を分ける場面も多く、適切な騎手を選ぶことで高配当を得るチャンスが広がります。
特定の条件で好走するパターンを把握できれば、機械的に買うことも可能で、予想時間の短縮にもつながります。
騎手買いのデメリット
一方で、騎手買いには大きなデメリットも存在します。
ルメール騎手や川田騎手、短期免許騎手騎乗馬において顕著に見られる光景ですが、人気騎手に過剰な支持が集まるとオッズが低くなり、回収率は自然と下がってしまいます。
また、実力馬に騎乗しているだけで評価されている場合もあり、騎手の実力と馬の実力を混同しやすい点も注意が必要です。
特にG1などでは、初心者層が騎手名で馬券を買う傾向が強く、過剰人気の影響を大きく受けやすくなります。
騎手に頼りすぎることで、本来注目すべき馬の能力や適性を見落としてしまうリスクもあります。
まとめ|騎手買いは使い方次第で強力な戦略になる
騎手買いは、条件さえ絞れば非常に有効な予想手法となります。
すべてのレースで騎手だけを頼りにするのではなく、得意な条件や競馬場、人気とのバランスを見極めて使い分けることが大切です。
データをもとにした分析と組み合わせることで、的中率と回収率の両方を高めることができ、競馬をより戦略的に楽しめるようになります。

