競馬の中継やパドック解説を聞いていると「この馬はモタれる癖がある」といったフレーズがよく登場します。
しかし普段の生活ではあまり耳にしない言葉なので、初心者の方にとっては意味が分かりづらい用語でしょう。
モタれるとは、競走馬が走行中に左右どちらかへ寄ってしまい、真っすぐに走れなくなる動作を指します。
直線で外へ膨らんだり、内ラチにぶつかりそうになったりするため、スムーズな走りを妨げる要因となります。
特にG1などハイレベルな舞台では、わずかなロスが着順や馬券に大きく影響を与えかねません。
本記事では「競馬 モタれるとは?」という基本から、原因や「ささる」との違い、左右回りによる影響、さらに予想にどう活かすべきかまで詳しく解説していきます。
これを知ることで、モタれる癖を持つ馬の走りを見抜き、予想精度を高めることができるはずです。
競馬で「モタれる」とは?
競馬の専門用語として使われる「モタれる」は、馬がレース中にまっすぐ走らず、左右どちらかに寄ってしまう動作を指します。
一見すると些細なことのように思えますが、スピードを落としたり進路が塞がれたりする原因となるため、着順やレース展開に直結します。
実況や解説で「内にモタれている」「外にモタれて伸び切れない」といった表現を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
「もたれる」とは?
競走馬が「もたれる」とは、直線やコーナーで体のバランスを崩し、片方へ流れるように走る状態を意味します。
例えば右にモタれる馬は、直線で外側に膨れてしまい、前の馬を交わす際に大きなロスが生じやすくなります。
逆に左にモタれる馬は、内ラチに接触しそうになったり、他馬の進路を妨害する危険性もあります。
この「モタれる」という動作は、単なる癖として表れることもあれば、疲労や脚元の違和感といった身体的なサインであることもあります。
そのため予想を立てる上では「どのコースで、どちらにモタれるのか」を把握しておくことが重要です。

モタれる動作が起きる原因
競走馬が「モタれる」動きを見せるのには、いくつかの原因があります。
単なる癖で終わる場合もあれば、身体的な不調や気性面の問題、さらには騎手や馬具の影響など多岐にわたります。
原因を正しく理解することで、レース映像や過去成績を読み解きやすくなり、予想の精度を上げることにつながります。
身体的な要因
最も大きな要因の一つが、馬の身体的なコンディションです。
例えば左右の筋肉のバランスが崩れていると、力が均等に伝わらず、自然と一方に流れるような走りになります。
また、脚部の痛みや疲労が原因でどちらかに体重を逃がしてしまうケースも少なくありません。
特に長距離戦や馬場が悪化したレースでは疲労が溜まりやすく、直線で顕著にモタれる動作が出やすくなります。
こうした身体的な要因を見抜くには、調教内容や直近のレースぶりを確認することが重要です。
精神的な要因
次に挙げられるのが精神面です。
競走馬は非常に繊細な動物であり、気性の荒さや集中力不足が走行姿勢に影響します。
前を走る馬に怯えたり、観客の声やフラッシュに気を取られたりすることで、自然と進路がぶれてしまうのです。
また、他馬に馬体を寄せられると嫌がって外へ逃げるようにモタれることもあります。
このような精神的な原因は調教や経験を積むことで改善される場合が多いですが、若駒や気性難の馬にはよく見られる傾向といえるでしょう。

騎手やハミの影響
「競馬 ハミに もたれる」という表現があるように、ハミ(馬具)への依存もモタれる原因となります。
馬がハミを片側に強く噛むと、その方向に頼るように体が傾き、結果として左右どちらかへ流れてしまうのです。
また、騎手の手綱さばきや姿勢の影響で、馬が走りやすい方向に偏ることもあります。
特に経験の浅い馬にとっては、騎手のサポートが大きな要素となり、矯正の仕方次第でモタれ癖が軽減されることもあります。
このため、同じ馬でも騎手が替わると走りが安定するケースが見られるのです。
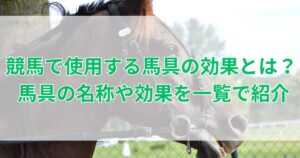
「モタれる」と「ささる」の違い
競馬中継や専門誌では「モタれる」と似た用語として「ささる」もよく使われます。
両者は混同されがちですが、実際には微妙に意味が異なります。
どちらも馬がスムーズに走れなくなる動作を指すものの、原因や走りの特徴には違いがあるため、予想や馬券検討では明確に区別して理解しておく必要があります。
「もたれる」と「ささる」の境界
「モタれる」は馬がバランスを崩して自然に左右へ流れる動作を指します。
例えば直線で外に膨らんでしまったり、内へ寄ってラチに接触しそうになったりと、身体の使い方がアンバランスになるのが特徴です。
一方で「ささる」は、馬が自ら進路を取るように内へ突っ込む動作を表します。
モタれるのほうが「受動的」な傾向が強く、ささるのほうは「能動的に内へ寄っていく」というニュアンスです。
この違いを把握しておくと、レース映像の見方が大きく変わります。
例えば「モタれる」馬は筋肉やバランスの問題が疑われやすく、調整や馬具による矯正で改善できることがあります。
一方で「ささる」馬は気性や集中力の問題であることが多く、矯正には経験や精神面での成長が必要です。
両者を混同すると、予想における馬の評価を誤るリスクがあるため、しっかり区別して考えることが重要です。

内にモタれる・外にモタれる
「モタれる」と一口にいっても、その方向によってレースへの影響は大きく変わります。
内にモタれる場合と外にモタれる場合では、失速の仕方や進路妨害のリスクが異なり、予想においてもチェックすべきポイントが変わります。
ここでは、代表的な「内にモタれる」「外にモタれる」の2パターンについて詳しく見ていきましょう。
内にモタれる場合
内にモタれる馬は、コーナーや直線でラチ沿いに寄りすぎる傾向があります。
直線で内ラチにぶつかりそうになったり、極端なケースでは前を走る馬に接触して進路を妨害してしまうこともあります。
また、内に入り込むことで馬自身のストライドが伸びず、力を出し切れないままゴールしてしまうことも少なくありません。
特に右回りコースで左にモタれる馬は危険で、コーナーでインに突っ込みすぎると致命的な不利を受ける可能性があります。
このため、過去に「内にモタれる」と指摘された馬は、右回りのレースで軽視されることが多いのです。
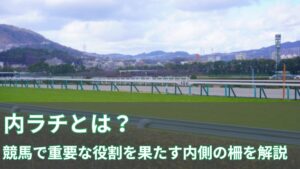
外にモタれる場合
外にモタれる馬は、直線で膨れてしまい、大きく外へロスをすることが特徴です。
特に東京や新潟のように直線が長い左回りコースでは、外にモタれる動きが出ると余計な距離を走ることになり、末脚をフルに発揮できません。
また、外に流れる馬は自分で走る意欲が強い反面、スタミナを無駄に消耗しやすい面もあります。
ただし外にモタれる場合は内に寄るほどの危険性は少なく、他馬の進路を妨害するリスクは低めです。
それでも直線勝負の舞台では結果に直結するため、外へ膨れる癖があるかどうかは映像チェックで必ず確認すべき要素です。
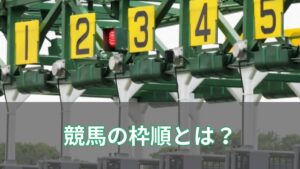
左右回りとモタれる傾向
競馬場には右回りと左回りがあり、馬によって得手不得手がはっきり分かれることがあります。
「モタれる」動作はコースの回り方によって顕著に表れるため、どちらの方向にモタれるかを把握することは予想を立てる上で大切です。
例えば「右にモタれる」馬は左回りで苦戦しやすく、「左にモタれる」馬は右回りで力を出し切れない傾向があります。
過去のレース結果やコメントを参考にしながら、左右回りの相性を見極めることが的中率アップにつながります。
右にモタれる馬
右にモタれる馬は、左回りの競馬場(東京・中京・新潟)で不利を受けやすいのが特徴です。
左回りでは直線で外側に流れる形になり、他馬より多くの距離を走ることになるため、スタミナのロスが大きくなります。
特に東京競馬場のように直線が長いコースでは致命的で、最後の伸びを欠いてしまうケースが頻発します。
ただし右回りの競馬場ではそれほど影響が出にくく、むしろ力を出しやすい傾向もあります。
このため「右にモタれる癖」がある馬は、出走する競馬場が右回りか左回りかを事前に確認しておくことが欠かせません。

左にモタれる馬
左にモタれる馬は、右回りの競馬場(中山・阪神・京都・小倉・札幌・函館・福島)で注意が必要です。
コーナーで内に突っ込みやすく、他馬の進路を塞いだり、内ラチに接触して走りがスムーズでなくなったりすることがあります。
直線でも内へ寄るため、ゴール前での接触や進路妨害に発展するケースも見られます。
一方、左回りでは外に流れる形になるため、走りやすくなることもあります。
つまり「左にモタれる馬」は、左回りコースのほうがパフォーマンスを発揮しやすく、右回りでは過信できない存在といえるのです。
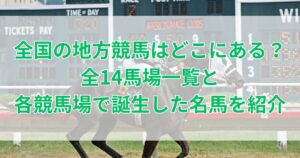
モタれる馬の改善方法と調整
モタれる癖は一度出るとクセになりやすく、レースで不利を受け続ける原因になります。
しかし陣営や騎手が工夫することで、ある程度は矯正できるものです。
調教でバランスを整えたり、馬具を工夫したりすることで走りが安定するケースもあり、改善方法を知っておくと予想に活かせます。
矯正方法
モタれる馬に対しては、主に調教と馬具の工夫で矯正が行われます。
調教では左右の筋肉をバランスよく鍛え、フォームが偏らないように矯正運動を繰り返します。
また、コース追いを繰り返すことで走りの姿勢を安定させ、真っ直ぐ走れるように導いていきます。
馬具面ではチークピーシズやブリンカーを着用し、視界を制限して集中力を高める方法が一般的です。
また「競馬 ハミに もたれる」といわれるように、ハミの種類や装着方法を工夫して片側に頼らせないよう調整することもあります。
さらにレースでは、矯正の得意な騎手が積極的に手綱を使い、直線で真っ直ぐ走らせるように修正することも可能です。
このように「モタれる癖がある=必ず不利」ではなく、陣営や騎手の対策によって克服する馬も少なくありません。
したがって過去の走りでモタれていたとしても、次走では改善されて力を発揮するケースがあることを予想に取り入れる必要があります。

モタれる馬を予想に活かすポイント
モタれる動作は不利につながる要素ですが、事前に把握しておけば予想に役立ちます。
どの方向にモタれるのか、どのコースでその傾向が出やすいのかを確認することで、信頼度の高い馬券戦略につなげられます。
ここでは「直線の長さ」「騎手との相性」「過去レース映像」という3つの観点から予想のポイントを整理していきます。
直線の長さと相性
モタれる馬は直線の長いコースと短いコースで評価が変わります。
東京や新潟のような長い直線では、外にモタれたり内に寄ったりする動きが大きなロスにつながり、最後の伸びを欠いてしまいます。
一方で小倉や中山のように直線が短いコースでは、多少モタれてもゴールまで一気に駆け抜けられるため、影響が小さく済む場合があります。
そのため「モタれる癖を持つ馬は長い直線コースでは割り引き、短い直線コースなら評価を下げすぎない」といった判断が有効です。
騎手との相性
モタれる馬は騎手の手腕によって走りが大きく変わります。
矯正が得意な騎手であれば、直線で真っ直ぐ走らせる工夫をして力を引き出せますが、経験の浅い騎手では修正が効かずに失速するケースもあります。
過去に同じ馬に騎乗した際に安定した走りを見せているかどうかを確認することで、モタれ癖がどの程度カバーされるかを判断できます。
騎手コメントに「外にモタれたが最後は修正できた」といった記述がある場合、その騎手は信頼できるといえるでしょう。

過去のレース映像をチェック
モタれる癖は一度出ると繰り返されることが多いため、過去のレース映像をチェックすることが重要です。
「競馬 右にモタれる」「競馬 左にモタれる」といった検索ワードを意識して動画を確認すれば、その馬がどの条件でモタれる傾向があるのか把握できます。
また、映像を通して「どのくらいロスをしているのか」「妨害につながりそうか」を具体的に確認することで、数値以上の判断材料が得られます。
新聞の短評や成績欄だけでは見抜けない要素なので、映像分析は予想精度を高めるうえで欠かせません。
競馬のモタれる:まとめ
競馬で使われる「モタれる」という言葉は、馬が左右どちらかに寄って真っすぐ走れなくなる動作を指します。
原因は筋肉のバランスや疲労といった身体的要因だけでなく、気性面やハミの影響などさまざまです。
「ささる」とは似て非なる動作であり、モタれるは受動的、ささるは能動的に進路を取る点で違いがあります。
また、内にモタれる場合と外にモタれる場合では不利の種類が異なり、右回り・左回りのコース相性によっても結果が左右されます。
ただし陣営や騎手が調整や矯正を行うことで改善されることもあるため、一度モタれ癖を見せた馬が次走で立て直すケースも少なくありません。
予想においては「どの方向にモタれるのか」「どの競馬場でその癖が出やすいのか」を意識し、過去レース映像や騎手コメントをチェックすることが大切です。
こうした情報を組み合わせて評価することで、馬券戦略の精度を高め、的中率や回収率アップにつなげられるでしょう。

