競走馬のトモをご存じでしょうか。
トモとは競走馬の馬体の部位の名称です。
パドックで予想される方にとっては特に重要な要素であるトモ。
パドックを全く見ずに予想される方には縁のない用語かもしれません。
ここでは、トモの役割、見方について説明します。
パドックに興味のある方の参考になれば幸いです。
競馬のトモとは?
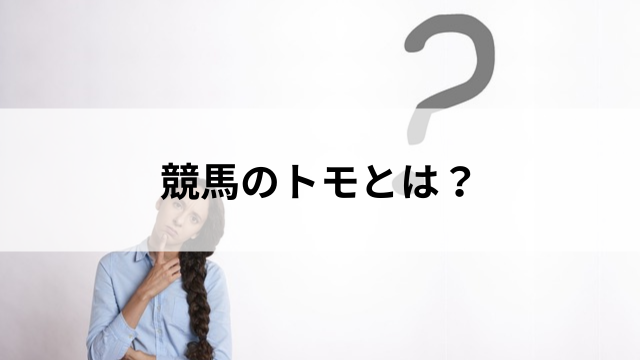
最初にトモについて解説します。
ひとことでまとめるとトモとは馬の後ろの部位のことです。
競走馬の馬体は2つに分けて表記します。
それぞれ【前躯(ぜんく)・後躯(こうく)】と呼び、トモの部位は後躯にあります。
後躯は馬の後ろ半身と思ってください。
そのうちの腰部、臀部(お尻の部分)・後肢の部分を総称してトモと呼びます。
競馬のトモの役割とパドックの見方

競走馬にとって後ろ脚は推進力を出すためになくてはならないものです。船で例えるなら後ろ脚はスクリューの役割を果たしています。
レースをするために生まれてきた競走馬にとってスピードを出すトモの役割は大きいですね。
しかしながら全手の馬が全く同じ形・大きさのトモではありません。
そのためトモの仕上がりも馬によって様々です。
その違いを見極められるのがパドックなのです。
パドックにおけるトモの見方①~大きさ~
では、パドックでトモをどのように見分けたらいいのでしょうか。
先ほどお伝えしたようにトモと呼ばれる範囲は腰部・臀部・後肢と意外と広いです。
その中でも
- 大きさ
- 張り
のこの点は注視していただきたいポイントになります。
まず、トモの大きさを見ていきましょう。
トモが大きいことは即ち後躯の筋肉が発達しているのです。
先ほど後ろ脚は船でいうスクリューであると例えました。
スクリューも大きいほど推進力が得られます。
競走馬も全く同じで、トモが大きいほうが推進力を発揮できるのです。
しかし、ただ大きいだけではいけません。
全体のバランスが重要になります。
前躯と後躯のバランスが悪ければトモにいくら筋肉がついていてもその力を活かすことができません。
また、トモにしなやかさがなければ一度のレースで疲労が蓄積され、次走以降の競馬に支障が出たり、故障の原因になることもあります。
トモはただ大きければいいというわけではなく、その馬の馬体に合わせたバランスと、柔らかさが重要なのです。
パドックにおけるトモの見方②~張り~
次にトモの張りを見ていきます。
トモの部位は幅広いのですが、特に
- トモの上部の張り
- トモの股の張り
の2点はパドックでチェックしたいところです。
トモの上部とは馬の背中から尻にかけての外線のことです。
後ろ脚を根元から支える非常に重要な部分で、ここが発達していると後肢全体に力を加えることが出来るため推進力を得てスピードを発揮することが出来ます。
この部分の見方としては背中から尻にかけてのラインがしっかりしていること。
ここがしっかりしている馬は好走することが多いですし、同時に前躯とのバランスが非常に大事な部位でもあります。
前躯とトモの上部の理想的なバランスは前躯と後躯のちょうど真ん中の背中のラインが横から見てくびれていて、前躯と後躯のバランスが釣り合っていることです。
前か後ろが張っていたりすると力の加え方にムラができるため、100%の力を発揮するにはバランスの取れた馬体が望ましいのです。
次に、トモの股の張りというのはちょうど馬の尻から股にかけての部位です。
ここが推進力を生みだす部位といってもいいでしょう。
人間にも備わっているバネのような役割を果たす場所です。
ここの見方はスラリとしていてラインが整っていることです。
シャープで無駄のない筋肉を持つ馬こそスピードを生み出す脚質をもちます。
また、後ろ脚から腹にかけて内側に筋肉が発達している馬はスピードを生み出しやすいです。
なぜなら、内側の筋肉がレースにおいて必要とされるスピードを生み出すからです。
パドックでは影になるため非常に分かりづらいですが、競馬場に足を運ぶ際は一度よく確認してみてください。
パドックにおけるトモの見方③~形~
馬のトモは様々な形があります。
平らな尻を持つ馬もいれば斜めに走った尻を持つ馬も存在します。
それぞれの形の特徴を見てみましょう。
平尻馬
骨盤が傾斜していなくてトモの上部が水平に近い馬が平尻タイプの馬です。
斜尻を持つ馬に比べて瞬発性は劣りますが、長く脚を使える馬が多く、逃げ・先行する馬が多く、短距離馬よりも中・長距離向けの馬が多いです。
また、逃げ・先行馬が有利といわれている乾いたダートコースでもこのタイプの馬が好走するケースは多いです。
斜尻馬
尻の部分が斜めに走っている馬はトモの筋肉を縮めて伸ばすことができるため瞬発性の優れた馬が多いです。
日本競馬を席巻したサンデーサイレンスが斜尻馬で、瞬発性に長けていました。
サンデーサイレンスの仔の多くはこの斜尻馬を持つ馬が多いのです。
ただ、パワーがないと腰の甘さに繋がるともいわれています。
レース毎にトモの役割は変わる

先ほど、トモの大きさ、形、張り具合を紹介しましたが、トモの役割はレースによって変わります。
競走馬のデビューは新馬戦からスタートしますがその新馬戦の中身は様々で、短距離のレースもあれば中距離のレースもあります。
距離の違ったレースで実戦経験のない馬の潜在能力をどう見極めている要素のひとつにトモが大きく関わってきます。
人間と同じで馬も体形・大きさは様々です。
そしてその馬の体形にあったレースは必ず存在します。
ここではレース毎に変わるトモの役割についてみていきます。
短距離レース
短距離戦はトップスピードの質が求められます。
一般的に馬が全力で走れる距離は800mが限界といわれています。
JRAで指定されるコースは最低でも1,000mです。そのためいかに速く走れるかが課題ですね。
短距離馬として求められるトモの役割は、中・長距離馬と比較して脚が太く短いのが条件です。なぜなら脚が短いほうが何度も地を蹴れるのでトップスピードを維持できるからです。
また、パワーが求められるため、トモの周りは筋肉で盛り上がっています。
トモの筋肉が盛り上がっている馬はパワーを発揮出来るため、前後のバランスこそ釣り合う必要はありますがトモは大きいほど好走に期待できます。
中・長距離レース
中・長距離の場合は短距離馬とは全く逆で、いかに長く脚を使えるかが求められます。
スピード以上にスタミナも求められ、瞬発性よりも持久力が試されます。
中・長距離レースにおいて求められるのは長くしなやかな脚を持った馬です。
人間でもマラソン選手は短距離選手と比較すると筋肉は豊富ではなく、むしろ手足はスラリと細長いです。
実は、競走馬もマラソン選手同様、細くて長い脚のほうが持久戦に強いといわれています。
その理由としては、一歩の歩幅が大きいため滞空時間が長く、体力の消耗を抑えられるからです。
また、中・長距離馬は短距離馬と比較しても筋肉量は少なめです。これは、筋肉が多すぎると身体全体が重くなってしまいスタミナの浪費につながるからです。
中・長距離馬をトモで判断するポイントは無駄な筋肉のない馬を見極める必要があります。
ただし一定水準以上の筋肉は必要です。
そして、目に見えない遅筋(体内の筋肉)を持つ馬もいます。
そのため一見筋肉のないように思える馬でも実は体内に筋肉がついている馬もいるため、パドックでそこまで見抜くのはプロでも難しいといわれています。
その場合は、過去の戦績から適正を見抜いたほうが手っ取り早いかもしれません。
トモのまとめ

今回はトモの見方と役割についてまとめました。
トモはパドックを見るにおいて非常に重要な要素です。
ただ、一目では分からないと思うので、なんともパドックや競走馬の写真を見ながら、馬を見る相馬眼を養ってください。
トモの特徴が自然と分かるようになれば、きっとパドックで適性のあった馬を見出すことができることでしょう。
当記事がパドック予想で少しでもお役に立てれば幸いです。

