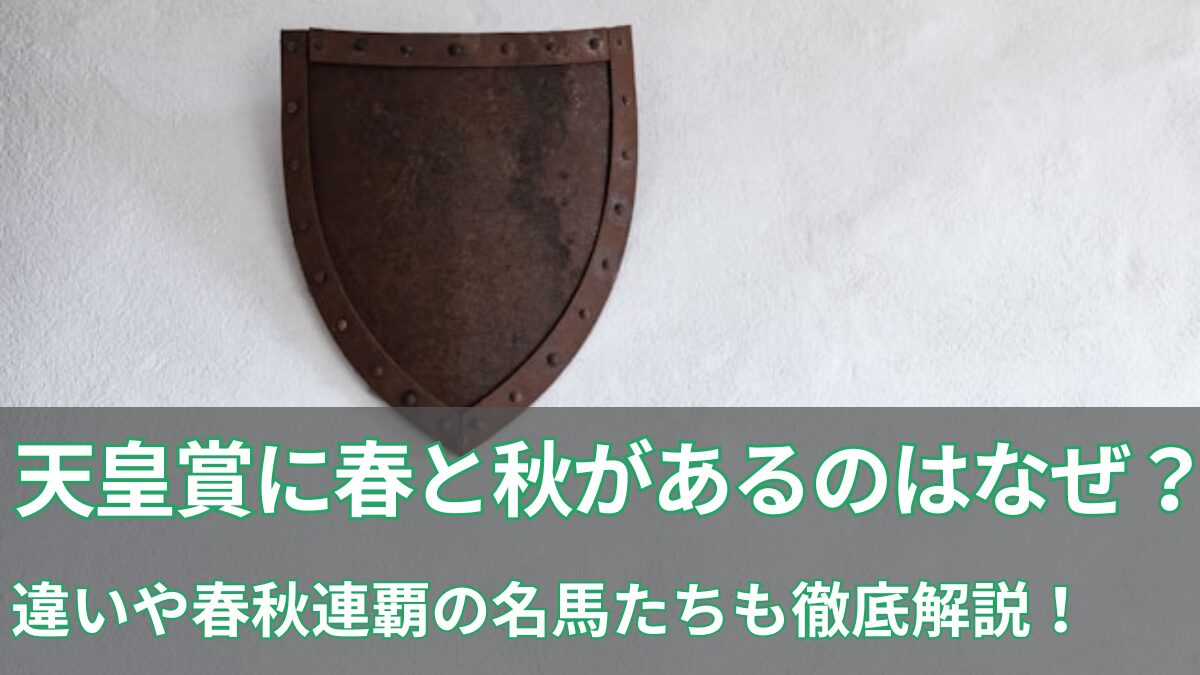競馬界で最も歴史と格式のあるレースのひとつ「天皇賞」。
実はこの天皇賞には「春」と「秋」の2回開催があり、それぞれに異なる魅力を持っています。
なぜ天皇賞には春と秋があるのか、その背景や歴史を詳しく知る人は意外と少ないかもしれません。
本記事では、天皇賞に春と秋が設けられた理由、レース内容の違い、さらに「春秋連覇」という偉業を成し遂げた名馬たちについても詳しく解説します。
天皇賞の奥深さを知れば、レース観戦がさらに面白くなること間違いなし!
ぜひ最後までご覧ください。
天皇賞に春と秋がある理由
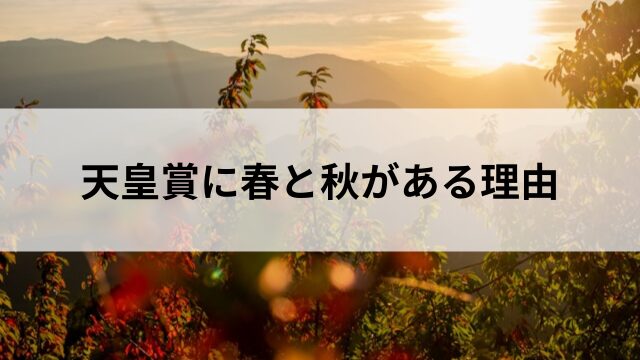
天皇賞は、競馬界で最も権威あるレースのひとつとして知られていますが、もともとは年1回だけ開催されていました
「帝室御賞典」という名前で始まったこのレースは、日本競馬の発展に伴い、1937年から春と秋の2回に分かれて行われるようになったのです。
なぜ年に2回開催されていたかというと、日本競馬の人気拡大と、実力馬の活躍の場を増やす必要性がありました。
当時、競走馬たちは成長スピードが上がり、年間1回の大レースだけでは有力馬の能力を発揮できる機会が限られていたのです。
また、観客動員や売上を伸ばすためにも、春秋2回の天皇賞開催は非常に効果的だったといわれています。
このように、競馬ファンの熱気と競走馬たちの進化に応える形で、天皇賞は春と秋に分けられ、現在に至るまで続いています。
かつては他のレースにも春と秋があった
かつて、天皇賞だけでなく、目黒記念や京都記念、中山大障害といったレースも、春と秋の年2回開催されていました。
しかし、1984年にグレード制が導入されると、目黒記念と京都記念はそれぞれ年1回開催へと移行し、現在に至っています。
この変更によって、レース体系や格付けがより明確に整理され、現代競馬にふさわしい形に整えられました。
また、中山大障害も長らく春と秋の2回実施されていましたが、1999年の障害競走改革により、春の中山大障害は廃止されました。
その代わりに、春には新たに「中山グランドジャンプ」が創設され、年末には従来通り中山大障害が施行される現在のスタイルへと変わっています。
このように、かつては複数回開催されていたレースも時代の流れとともに整理されていきましたが、天皇賞だけは例外的に春と秋の二大制を堅持し、今なお特別な存在として君臨し続けています。
天皇賞(春)と天皇賞(秋)の違い

天皇賞は「春」と「秋」の2回開催されますが、それぞれのレースには距離や求められる能力に明確な違いがあります。
まず、天皇賞(春)は、芝3,200メートルで行われる長距離レースです。
スタミナや持久力を問われるこのレースは、かつて「最強ステイヤー決定戦」とも称され、日本の競馬文化における長距離重視の伝統を象徴する存在となっています。
特に春の天皇賞では、序盤から緩やかなペースが続き、終盤は持久力勝負になる展開が多く見られます。
一方、天皇賞(秋)は、芝2,000メートルで行われる中距離レースです。
こちらはスピードや瞬発力が求められるレースであり、より広範な距離適性を持つ馬たちが集まります。
秋の天皇賞は、近年ではジャパンカップや有馬記念と並ぶ秋のG1戦線の重要な一角を占め、海外からも有力馬が参戦することがあるなど、国際色も豊かな一戦となっています。
このように、天皇賞(春)はスタミナ自慢のステイヤー向き、天皇賞(秋)はスピードと瞬発力に優れた馬向きと、それぞれ異なる個性を持つレースとなっているのです。
また、出走する馬のタイプにも違いが見られます。
春は菊花賞を経た長距離適性の高い馬や、体力自慢の馬が集結する一方、秋は中距離戦線を歩んできた古馬のトップホースや、実力のある3歳馬が果敢に挑戦する場面も増えています。
こうした違いを知って観戦すれば、天皇賞の楽しみ方はさらに深まるでしょう。
天皇賞「春秋連覇」はどれだけすごい?
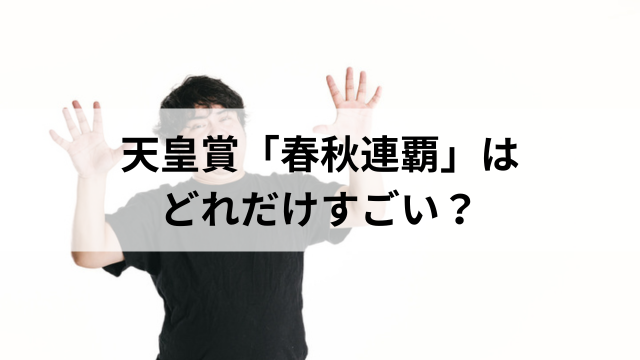
天皇賞(春)と天皇賞(秋)の両方を同一年に制覇することを「天皇賞春秋連覇」と呼びます。
この偉業は、競馬界でも特に価値の高い快挙とされています。
春の天皇賞は芝3,200メートルの長距離戦、秋の天皇賞は芝2,000メートルの中距離戦と、求められる適性がまったく異なるため、両方を勝つには並外れた総合力が必要です。
具体的にはスタミナとスピード、両方の能力を兼ね備え、さらにコンディションを整え続ける高い順応力も求められます。
また、ローテーションの難しさも無視できません。
春の天皇賞はゴールデンウィーク頃に開催され、秋の天皇賞は10月末から11月上旬に開催されます。
およそ半年にわたり好調を維持しなければならないため、馬自身の耐久力はもちろん、厩舎の管理能力や騎手の手腕も重要になります。
さらに、現代競馬はかつてよりレベルが上がり、分業化(長距離馬と中距離馬が別路線を歩む)が進んでいるため、春秋連覇を達成する難易度は年々高まっています。
実際、近年では春秋連覇を達成する馬はごく限られており、達成した馬は歴史に名を刻む名馬ばかりです。
次の項目では、そんな歴代の春秋連覇達成馬について詳しく紹介していきます。
歴代天皇賞春秋制覇を成し遂げた5頭の名馬

天皇賞(春)と天皇賞(秋)の両方を同一年に制した名馬たちは、日本競馬史においても特別な存在です。
ここでは、2024年までの期間で同一年内の春秋連覇を成し遂げた歴代の名馬たちを紹介していきます。
タマモクロス
| 生年月日 | 1984年5月23日 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 父 | シービークロス |
| 母 | グリーンシャトー |
| 母父 | シャトーゲイ |
| 生産牧場 | 錦野牧場 |
| 戦績 | 18戦9勝 |
| 主な勝ち鞍 | 天皇賞(春)(G1) 1988年 天皇賞(秋)(G1) 1988年 宝塚記念(G1) 1988年 鳴尾記念(G2) 1987年 阪神大賞典(G2) 1988年 金杯(西)(G3) 1988年 |
| 獲得賞金 | 4億9,161万4,000円 |
タマモクロスは1988年、天皇賞(春)と天皇賞(秋)の両方を制覇しました。
芝3,200mの春、芝2,000mの秋という異なる距離を克服し、見事な適応力を示し、史上初となる同年天皇賞連覇を成し遂げています。
古馬になってから追い込み馬として台頭し、春はは稍重馬場をものともせず押し切り、秋は名馬オグリキャップを破って優勝しました。
当時軽視されていた芦毛馬の代表格として台頭し、歴史に名を刻みました。
スペシャルウィーク
| 生年月日 | 1995年5月2日 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 父 | サンデーサイレンス |
| 母 | キャンペーンガール |
| 母父 | マルゼンスキー |
| 生産牧場 | 日高大洋牧場 |
| 戦績 | 17戦10勝 |
| 主な勝ち鞍 | 日本ダービー(G1) 1998年 天皇賞(春)(G1) 1999年 天皇賞(秋)(G1) 1999年 ジャパンカップ(G1) 1999年 弥生賞(G2) 1998年 京都新聞杯(G2) 1998年 AJCC(G2) 1999年 阪神大賞典(G2) 1999年 きさらぎ賞(G3) 1998年 |
| 獲得賞金 | 10億9,262万3,000円 |
スペシャルウィークは1999年、ダービー馬として天皇賞(春秋)連覇を達成しました。
エルコンドルパサーやグラスワンダー、キングヘイローにセイウンスカイといったメンツが同期の花の98世代のダービー馬です。。
天皇賞(春)では前年の天皇賞(春)を勝利したメジロブライトに先着し、天皇賞(秋)では同期のキングヘイローやセイウンスカイ、ツルマルツヨシ相手に先着し、史上2頭目となる同年春秋制覇を成し遂げています。
一時代を築いた名馬のひとつであり、特に秋の勝利は、その後のジャパンカップや有馬記念への弾みとなりました。
テイエムオペラオー
| 生年月日 | 1996年3月13日 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 父 | オペラハウス |
| 母 | ワンスウエド |
| 母父 | Blushing Groom |
| 生産牧場 | 杵臼牧場 |
| 戦績 | 236戦14勝 |
| 主な勝ち鞍 | 皐月賞(G1) 1999年 天皇賞(春)(G1) 2000・2001年 宝塚記念(G1) 2000年 天皇賞(秋)(G1) 2000年 ジャパンカップ(G1) 2000年 有馬記念(G1) 2000年 京都記念(G2) 2000年 阪神大賞典(G2) 2000年 京都大賞典(G2) 2000年・2001年 毎日杯(G3) 1999年 |
| 獲得賞金 | 18億3,518万9,000円 |
テイエムオペラオーは2000年、年間無敗グランドスラムという偉業の一環として春秋連覇を達成しました。
グランドスラムとは?
当時の芝レースにおける古馬中~長距離G1(天皇賞(春)、宝塚記念、天皇賞(秋)、ジャパンカップ、有馬記念)を一年内ですべて勝利することです。
春の天皇賞では瞬発力勝負に対応して優勝し、秋の天皇賞では先行しながら突き抜けて完勝しました。
どちらのレースもロスなく立ち回り、完成度の高さを見せつけました。
年間8戦8勝という前人未到の記録において、天皇賞春秋連覇はそのハイライトの一つとなっています。
メイショウサムソン
| 生年月日 | 2003年3月7日 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 父 | オペラハウス |
| 母 | マイヴィヴィアン |
| 母父 | ダンシングブレーヴ |
| 生産牧場 | 林孝輝 |
| 戦績 | 27戦9勝 |
| 主な勝ち鞍 | 皐月賞(G1) 2006年 日本ダービー(G1) 2006年 天皇賞(春)(G1) 2007年 天皇賞(秋) 2007年 スプリングステークス(G2) 2006年 産経大阪杯(G2) 2007年 |
| 獲得賞金 | 10億6,594万9,000円 |
メイショウサムソンは2007年に春秋連覇を達成した名馬です。
もともと皐月賞、日本ダービーを制した実績を持ち、中長距離での高い適性を誇っていました。
春の天皇賞では、早めに先頭に立って勝利を手にし、秋の天皇賞は空いた内から突き抜けて優勝しました。
古馬になってからのG1勝利はこの天皇賞の2勝にとどまりましたが、二冠馬として常に大舞台でしのぎを削っていたのです。
キタサンブラック
| 生年月日 | 2012年3月10日 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 父 | ブラックタイド |
| 母 | シュガーハート |
| 母父 | サクラバクシンオー |
| 生産牧場 | ヤナガワ牧場 |
| 戦績 | 20戦12勝 |
| 主な勝ち鞍 | 菊花賞(G1) 2015年 天皇賞(春)(G1) 2016・2017年 ジャパンカップ(G1) 2016年 大阪杯(G1) 2017年 天皇賞(秋)(G1) 2017年 有馬記念(G1) 2017年 スプリングステークス(G2) 2015年 セントライト記念(G2) 2015年 京都大賞典(G2) 2016年 |
| 獲得賞金 | 18億7,684万3,000円 |
キタサンブラックは2017年、春秋連覇を達成しました。
春の天皇賞では驚異的なタイム(3分12秒5)での圧勝し、ディープインパクトが持つレコード記録を更新しました。
続く秋の天皇賞は歴史的な不良馬場でスタート直後に出遅れてしまいましたが、最後の直線では力強い脚質で差し切りの勝利を手にし、異なる条件下でも一流のパフォーマンスを見せています。
スタミナ、スピード、道悪適性まで備えた圧倒的な万能性で、名実ともに日本競馬の歴史に名を刻みました。
引退後も初年度産駒のイクイノックスが輝かしい活躍を見せたことで、種牡馬としても成功しています。
天皇賞春と秋の違い:まとめ

天皇賞は、日本競馬の伝統と格式を象徴する特別なレースです。
もともとは年1回の開催だったものが、競馬人気の高まりと馬たちの活躍の場を広げるため、1937年から春と秋に分かれて実施されるようになりました。
天皇賞(春)は芝3,200メートルで行われるスタミナ重視の長距離戦、天皇賞(秋)は芝2,000メートルでスピードと瞬発力を競う中距離戦と、それぞれ異なる個性を持っています。
この違いこそが、天皇賞を二度楽しむ魅力にもつながっています。
また、天皇賞の春秋連覇は、両方の距離適性とシーズンを通じた高パフォーマンスが求められるため、達成するには並外れた能力と運が必要です。
これまで連覇を成し遂げた名馬たちは、いずれも日本競馬史にその名を残す存在ばかりでした。
天皇賞の背景や違い、そして名馬たちの偉業を知れば、レースを見る目もより一層深まるはずです。
今年の天皇賞でも、新たな歴史が刻まれる瞬間に立ち会えるかもしれません。
ぜひ、春と秋それぞれの天皇賞を、存分に楽しみましょう!