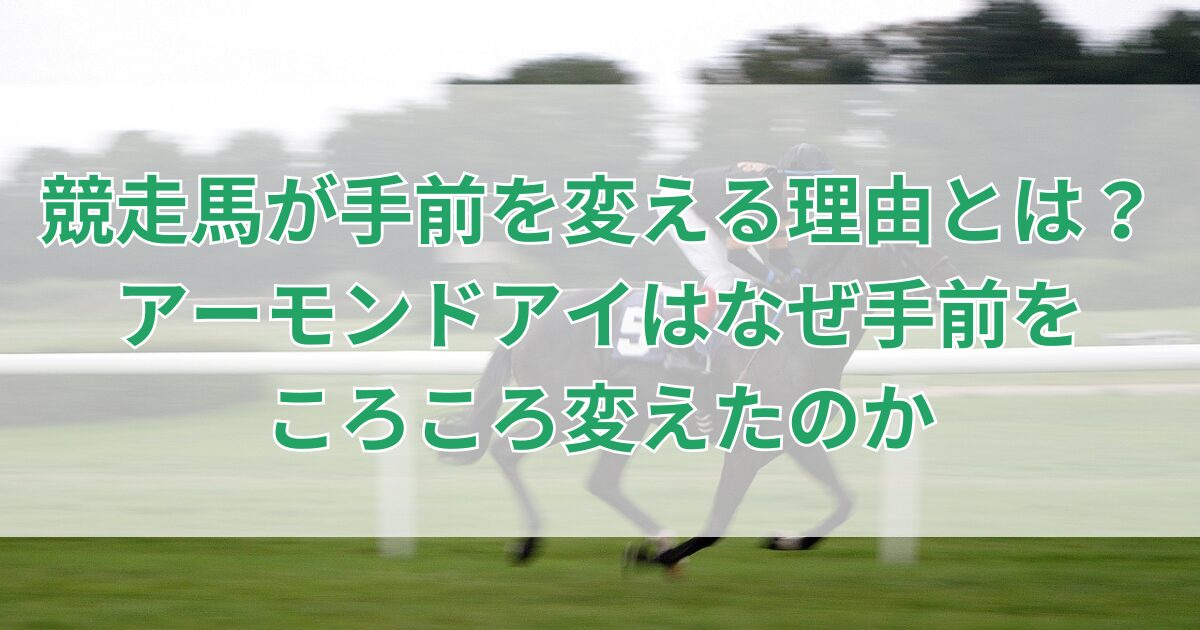皆さんは、競馬において『手前を変える』という言葉をご存じでしょうか?
これは、競走馬の走法のことをいい、簡易的なイメージとしては、右脚を中心に走っているのを左脚に中心を変えることです。
ただ、瞬足で動く競走馬の脚をみてもなかなか手前を変える行為が分かりづらく、理解するのも難しいです。
そこで今回は、手前を変えることについて、詳しく説明していきたいと思います。
競馬の手前を変えるとは?
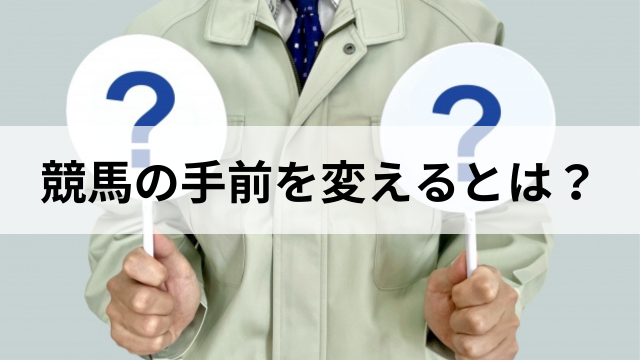
まずは、基礎知識として競走馬の走り方には、常歩・速歩・駈歩・襲歩といった4つの種類があります。
パドックでは常歩か速歩、返し馬で駈歩、レースでは襲歩といえば、分かりやすいかも知れません。
その中の襲歩には2種類あり、1つが交叉襲歩(こうさしゅうほ)とよばれるもので通常、競走馬が走る形です。
これは一般的にギャロップといわれ、左手前の場合、右後脚→左後脚→右前脚→左前脚の順で着地します。この走法は、脚の運び順に線を引くと線がXのように交差するため、そう呼ばれています。
そして、もう1つが回転襲歩(かいてんしゅうほ)といい、ゲートを出てから数完歩の走りを指します。
同じ左手前の場合でも左後脚→右後脚→右前脚→左前脚の順で着地しますが、交叉襲歩と少し違いがあることが分かりますか?
これが、交叉襲歩と回転襲歩の違いで、この時、着地する最後の脚が右前脚なら右手前、左前脚なら左手前といいます。
次に手前を変える時は、通常1完歩で交叉襲歩から回転襲歩に切り替えます。この瞬間に手前を変える行為が行われ、交叉襲歩になります。回転襲歩で前脚の手前を変えたあと、後脚の手前を次の1完歩で変える要領です。
つまり、右手前から左手前に切り替える時には左後脚、右後脚、右前脚、左前脚としてから、右後脚、左後脚、右前脚、左前脚として手前変換を完了します。
これが『手前を変える』という仕組みとなっています。
手前を変えないとどうなるのか 手前をころころ変える理由について

前述の通り、右手前で走る時は、左後脚、右後脚、左前脚、右前脚の順で脚を運びますが、
これによって、四肢の働きはそれぞれ違ってきます。
まず、右手前の交叉襲歩で最も推進力を生み出すのは、最初に着地する左後肢で最終的な舵取り役を行うのが右前肢となります。
この時、推進力は左後肢から右前肢の方向へ働いてるので、極端に言えば右斜め前方向に走っているともいえます。
そして、手前を変える行為でもっとも重要な場面はコーナーを走る時です。単純にコーナリングの際、右回りのコーナーでは右手前、左回りでは左手前で走ります。
これは、推進力と走る方向を一致させるためで、仮にコーナリングの際、通常とは逆の手前に変えてしまうと、コーナーを回れず外に逸走してしまうこともあります。
これが、手前を変えなければならない1つの理由です。
次に手前をころころ変える理由については、競走馬が走行中、四肢の中で最も負荷がかかるのは、反手前脚となります。右手前なら左前脚、左手前なら右前脚ということですね。
これは重心が前方向へ動く時に支えてるのが、反手前脚だからです。
たとえば、動物が歩行する時、生み出す推進力には、地面を蹴ることで生み出す能動的推進力と身体を傾けることで生み出す受動的な推進力があります。
受動的推進力というのは、振り子の要領で重心を前後させて、下り坂を歩くおもちゃをイメージすると分かりやすいかも知れません。
このおもちゃのように自重を利用して生み出される推進力が受動的推進力と呼ばれています。
競走馬も重心を前後させることで受動的推進力を生み出していますが、重心が前方に傾いて推進力を生み出す時に支えているのが、反手前脚でこの時の負荷が四肢の中で一番大きくなります。
また、このように四肢の負担は反手前脚側に偏るため、手前を変えることは、疲れを分散させる意味合いでも重要となってきます。
そして、一般的にスタート直後は、左右どちらか好きな方で走り、右回りのコースならコーナーでは右手前、直線部分では左手前に切り変えて、最後の直線でもう一度、手前を変える競走馬が多いです。
また、コーナーなら内側の手前脚に負荷がかかるとも思われますが、競走馬にとっては、反手前脚側の負荷の方が大きく、コーナーで手前脚側に負荷がかかるなら、直線で手前を変える必要がありません。
よって、手前を変えることは、適切なタイミングで行うのが理想だといえます。
騎手の合図で手前を変えることが可能なのか?

続いて、手前を変えるのは騎手の合図で変えることができるのかについて説明します。
競走馬が自分自身の意思で手前を変えることもありますが、騎手がバランスやハミ・鞭などで促して手前を変えることもあります。
これは、上手い騎手ほどスムーズに変換が行われ、手前変換が得意な馬ほど簡単に変えてくれるわけです。そのため、騎手の合図で競走馬の手前を変えることは可能です。
ただ、2歳などの若い競走馬は、直線に入ってもなかなか手前を変えない部分もありますが、そういった競走馬は調教によって解消されます。
競走馬にとっても手前を変えることがうまくなれば、スピードを落とさずに変換できますので、怪我を防ぐことにもつながりますので、早めの改善が理想です。
なお、競走馬が骨折する原因調査によると、手前変換時の不正着地が、過去に骨折や炎症を抱えていた既往症よりも多いとされています。
正しく手前を変えることができれば問題ないですが、逆に手前を変えることが下手な競走馬にとっては、これが怪我の原因となりかねません。
そうならないためにも速やかに改善できるかどうかは、競走馬の資質と合わせて調教スタッフの技量も問われるところです。
名牝アーモンドアイはどうしてころころ手前を変えたのか

※画像はnetkeibaより引用
日本競馬史上初の芝G1を9勝した名牝アーモンドアイは、手前をよく変えたことでも有名でした。
ただ、アーモンドアイには蹄に欠陥があり、左前の蹄の空洞化した部分に充填剤を詰めて競馬に臨んでいました。
それが手前を頻繁に変えた理由かどうかは判りませんが、アーモンドアイは他馬に併せて、さらに他馬を追い越すタイミングで加速するため、意図的に手前を変えていたといわれています。
確かにそう思いながら映像を振り返ってみると、追い越す時に手前を変えて、抜いた後に戻しているようにもみえました。
ただ、前述した通りに通常、競走馬は交叉襲歩で走ります。それは、交叉襲歩よりも回転襲歩の方が疲労度が高いためです。
なお、回転襲歩は主にチーターと同じ走法ですので、加速するのが早い分、疲れるのも早いということになります。
たとえば、チーターに追いかけられたシマウマなどの草食動物が、走り続けるとチーターは追いかけるのを諦めます。これは、回転襲歩のチーターが先に疲れてしまうことが理由です。
また、ネコ科のような走りといわれた三冠馬ナリタブライアンでも直線ではしっかりと交叉襲歩でぶっちぎりました。そう考えると、何度も手前を変えたアーモンドアイは通常よりも回転襲歩が多くなるため、他の馬よりも疲れたはずです。
しかし、他馬を寄せ付けない走りを披露し続けたアーモンドアイは、疲れを知らないチーター、まさに最強馬に相応しかったのも納得できますね。
手前を変えずに名馬になった馬

※画像はnetkeibaより引用
ここまで手前を変える重要性を説明してきましたが、中には手前を変えずに走り切る競走馬も存在しました。
2020年の皐月賞(G1)は、無敗の三冠馬コントレイルが前年の朝日杯FS(G1)を勝ったサリオスに対し半馬身差で勝利しました。
これには、賛否両論がありました。
それは、レース当日が雨の残った馬場で外側有利だという中で、内側に進路を取ったサリオスは、最後の直線で一度も手前を変えず走り切ったからです。
一方のコントレイルは、最終コーナーを回って直線に入る時に一度、手前を変えています。
そして、サリオスとは対照的に外側を走ったコントレイルは、距離ロスがあったとはいえ、勢いある走りでサリオスを封じ込めました。
もし仮にサリオスが一度でも手前を変えていたら、もっと際どい勝負になっていたかも知れません。
これは、あくまでも一例ですが、基本的に競走馬は、手前を変えながら走りますので、スタートからゴールまで手前を変えず走り切った競走馬は、なかなかいないと思います。
それでも2020年の皐月賞と聞くと、もしサリオスが手前を変えていたら…と思ってしまいますね。
手前を変えるのまとめ
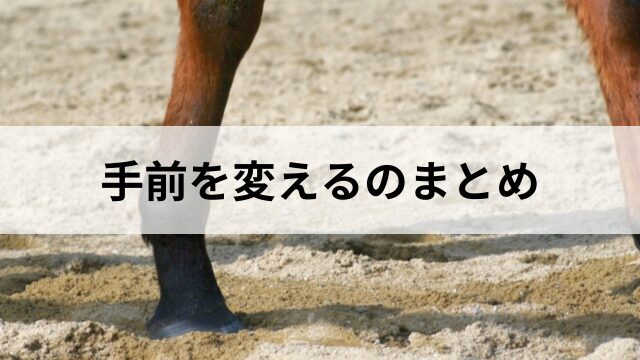
今回は、手前を変えることについて紹介しました。
冒頭でもお伝えしましたが、競走馬の走る姿をみても瞬時に動くため、脚の動きは非常に分かりづらいです。スロービデオでみてやっと分かるのが本音でしょうか。
ただし、手前を変える見極めとしては、人間でいうスキップをした状態が競走馬にとって、手前を変えている瞬間です。
分かりやすくいえば、後脚がフワッとスキップしているように見えます。もし興味のある方は、スロー再生で競走馬の走りを見てみてください。
また違った角度から競馬の楽しみ方が見つかるかも知れませんよ。