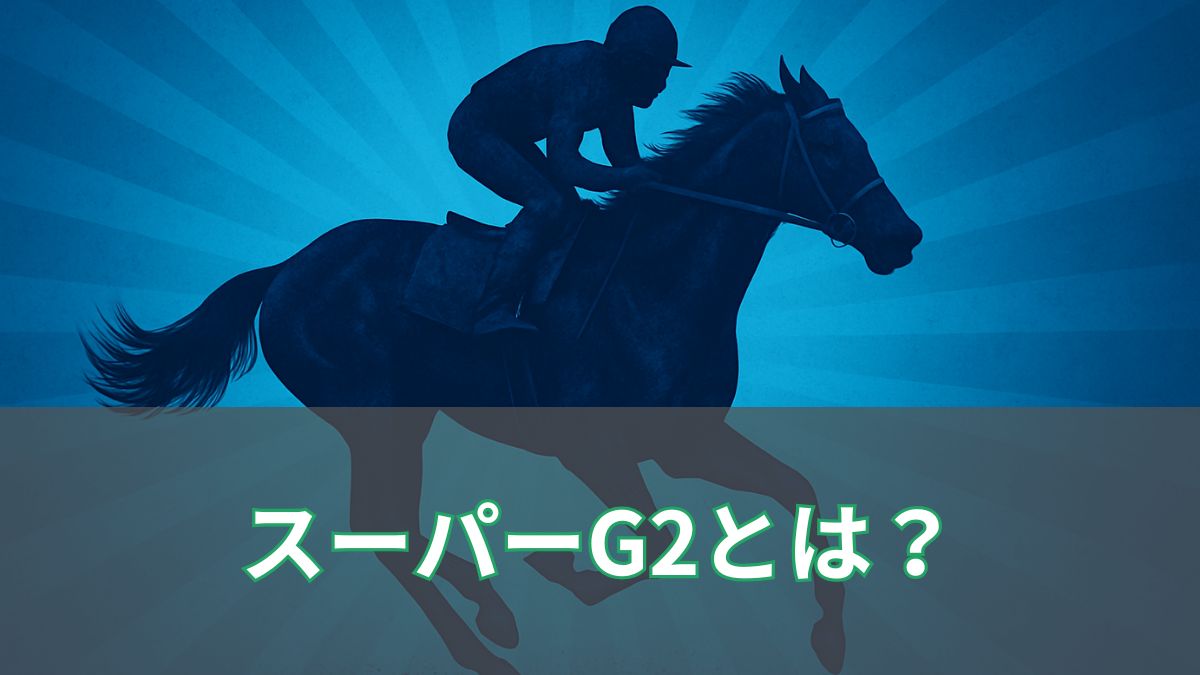「G2なのに、まるでG1級のメンバーが揃っている」
競馬ファンのあいだで“スーパーG2”と呼ばれる特別な重賞競走が存在します。
出走馬の顔ぶれを見れば、現役G1馬や海外遠征帰りの強豪、クラシック戦線で注目を集めた実力馬ばかり。
時にはその年の本番G1よりも高いレースレーティングを記録することもあり、ファンのあいだでは“裏G1”とも称されます。
この記事では、スーパーG2の定義や発生理由、代表的なレース、過去の名勝負などを総合的に紹介していきます。
「なぜG2のままなのか?」「本当にG1よりハイレベルなのか?」といった疑問にも答えながら、スーパーG2の魅力に迫っていきましょう。
スーパーG2とは何か
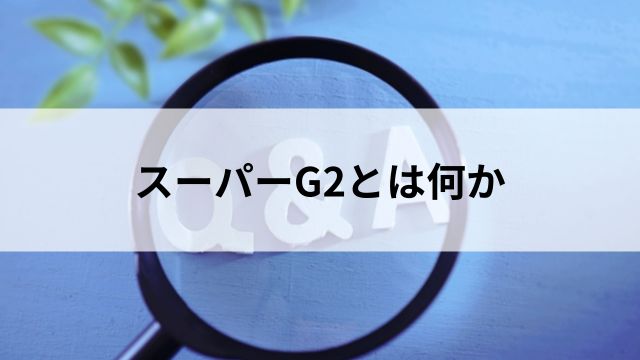
「スーパーG2」とは、G2という格付けでありながら、G1に匹敵する出走馬の実力やレース内容を誇る特別な重賞です。
有力馬の始動戦や本番前の試金石として機能しており、名勝負が数多く生まれています。
ここでは、なぜ“G2なのに強い馬が集まる”のか、その理由と背景を見ていきましょう。
G2なのにレベルが高い理由
G2競走は、もともとG1へのステップレースという位置づけですが、その中でも特に注目を集める“スーパーG2”という存在があります。
例えば、毎年のようにG1馬が複数出走し、レースレーティングが115を超えるようなハイレベルな一戦がそうです。
代表的な例としては、毎日王冠、札幌記念、金鯱賞などがあり、出走メンバーの豪華さは時にG1をも凌ぎます。
スーパーG2に出走する馬たちは、次走にG1を予定していることが多く、調整レースながらも高いパフォーマンスが求められます。
その結果、超一流の名勝負が生まれる確率も高く、「このレースこそ真のG1では?」という声も聞かれるようになりました。
スーパーG2の定義・条件
スーパーG2は公式な格付けではなく、競馬ファンや専門家のあいだで“通称”として使われている言葉です。
しかし、特定の条件を満たしたG2レースがこの称号を得やすい傾向にあります。
たとえば以下のような条件が挙げられます。
- G1に近い条件(距離や時期)で行われること
- 定量戦またはグレード別定戦であること
- 高額賞金が設定されていること
- G1への優先出走権が付与されること
- レースレーティングが115以上の年が多いこと
こうした条件が揃っていることで、有力馬が集まりやすくなり、自然とレースの格も上がっていきます。
また、開催地の気候やコースの個性なども、出走馬の選定に大きな影響を与えるため、毎年の出走傾向を追うことも重要です。
スーパーG2の代表例

ここでは、代表的な“スーパーG2”として知られる5つのレースを紹介していきます。
いずれもG1級の実力馬が集結し、レースレーティングも非常に高いことで知られています。
毎日王冠(マイルCSや天皇賞(秋)などへの前哨戦)
東京芝1,800mで行われる毎日王冠は、スーパーG2の代名詞といえるレースです。
1984年に現在の条件に定着してからは、数々の名勝負が生まれ、特にサイレンススズカ、グラスワンダー、エルコンドルパサーが激突した1998年は伝説となっています。
レースレーティングも非常に高く、2022年には117.25を記録。近年でも115を超える年が続いており、実質G1級のレースといえる水準にあります。
また、東京芝1,800mという絶妙な距離設定もあり、マイラーから中距離馬まで多様なタイプが集まる点も魅力です。
ただし、天皇賞(秋)までの間隔が中2週しかないため、近年はマイルチャンピオンシップや香港遠征を目指す陣営の選択肢になりつつあります。
札幌記念(天皇賞(秋)や海外遠征のステップ)
近年の“スーパーG2”筆頭といえば、間違いなくこの札幌記念でしょう。
洋芝の札幌競馬場で行われるこのレースは、近年のレースレーティング平均がG1に迫る116.54ポンド。
2021年には白毛のアイドルホース・ソダシがラヴズオンリーユーを下し、2022年にはジャックドールとパンサラッサが火花を散らしました。
2006年から定量戦に変更されたこともあり、有力馬が出走しやすい条件が整っています。
また、札幌開催という涼しい気候と、秋G1まで2ヶ月ほど空くローテーションも評価されています。
天皇賞(秋)への前哨戦だけでなく、凱旋門賞やBCターフなど海外遠征を視野に入れたローテとしても使われることが多く、現代競馬における最重要G2のひとつです。
金鯱賞(大阪杯の登竜門)
近年急速に“スーパーG2”としての地位を確立したのが、春の中京芝2,000mで行われる金鯱賞です。
大阪杯の前哨戦として位置づけられるようになったことで、G1馬の参戦が増加。2019年にはレースレーティングが驚異の120ポンドを記録しました。
その年はダノンプレミアム、リスグラシュー、エアウィンザーといった超豪華メンバーが出走し、今でも「G2の概念を超えた」と語られる一戦となっています。
2024年にはプログノーシスがドゥレッツァの連勝を止め、前年に続く連覇を達成するなど、近年は特に見ごたえ充分です。
ただし、G2に昇格したのが比較的最近なため、“伝統”という意味ではやや薄めです。
中山記念(ドバイや大阪杯へのステップ)
中山競馬場・芝1,800mで行われる中山記念は、シーズン最初の大舞台を目指す馬たちの始動戦として知られています。
ドバイターフや大阪杯への前哨戦としての意味合いが強く、近年ではジャスタウェイやリアルスティール、パンサラッサなどがこのレースを経由して海外G1を制しています。
2019年には、ウインブライト、ラッキーライラック、ディアドラ、スワーヴリチャードなどのG1馬が複数出走し、一時は“スーパーG2”の中でもトップクラスのメンバー構成を誇っていました。
レースレーティングはやや上下がありますが、出走馬の実績を見るとG1馬が多く、例年見逃せない好カードとなっています。
阪神大賞典(春の天皇賞への正統派ステップ)
阪神・芝3,000mで行われる阪神大賞典は、長距離G1である天皇賞(春)に直結するステップレースです。
1996年のナリタブライアンとマヤノトップガンの一騎打ちや、2012年のオルフェーヴル“阪神大笑点”など、数々の名シーンが誕生しました。
ただし、近年は長距離路線の需要が減ってきた影響で、レースレーティングはやや下降気味。
それでもディープボンドやジャスティンパレスなど、春のG1戦線で活躍する馬を輩出し続けています。
“スーパーG2”の中では地味な存在になりつつありますが、格式と伝統という点では今なお一目置かれるレースです。
スーパーG2のレーティング分析

スーパーG2と呼ばれるレースには、主観だけでなく“レースレーティング”という客観的な裏付けがあります。
この数値は出走馬の実力を示す指標であり、世界的な評価基準にも用いられています。
ここでは、レースレーティングの意味と、近年の上位レースの傾向について詳しく解説します。
レースレーティングとは?
レースの格付けを判断するうえで重要な指標となるのが「レースレーティング」です。
これは、そのレースの上位4頭がその年に記録したレーティング(国際基準の数値)の最高値を平均したもので、「その年の実力馬がどれだけ揃っていたか」を客観的に表しています。
JRAでは、このレースレーティングを用いて重賞の格付けの維持や昇格、降格を判断しています。
G2レースであれば、おおむね115ポンド以上を記録すれば、世界的に見ても非常に高水準とされ、場合によってはG1への昇格検討対象になることもあります。
ただし、この指標はレースそのもののレベルを直接評価するものではなく、あくまで「出走馬の実力」を反映したものです。
したがって、少頭数や逃げ切りの展開でも、出走馬の過去実績が優秀であれば高いレーティングになる可能性もある点には注意が必要です。
2019~2024年の上位G2ランキング
ここでは、直近6年の平均レースレーティングが115ポンドを超えた“スーパーG2”を紹介します。
いずれも出走馬の質が高く、実質G1と同等、あるいはそれ以上の価値があるといえるレースです。
1位:札幌記念(平均116.54)
→ 近年は毎年のようにG1馬が参戦。ソダシ、ジャックドール、パンサラッサらが熱戦を繰り広げた。
2位:毎日王冠(平均116.25)
→ アエロリット、サリオス、エルトンバローズなど、G1でも通用する馬が揃う。
3位:金鯱賞(平均116.00)
→ ダノンプレミアム、デアリングタクト、ジャックドールら豪華メンバーで話題に。
これらのレースは、開催時期や距離、賞金、レース条件などのバランスが非常に良く、G1を見据える陣営にとって魅力的なローテーションの一角となっています。
スーパーG2はなぜG2止まりなのか?
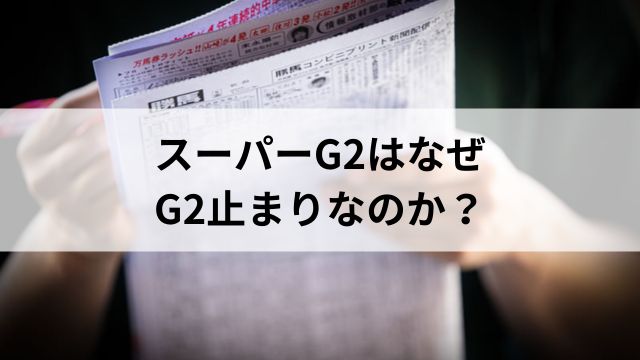
これだけハイレベルなレースであれば、G1に昇格してもおかしくない──そう思う方も多いでしょう。
しかし、スーパーG2があえてG2のままであるのには、複数の現実的な理由が存在します。
ここではその背景と、過去にG1昇格したレースの事例について見ていきます。
昇格には課題もある
スーパーG2のレースは、実力や人気、実績すべてにおいてG1と肩を並べる水準にあるにもかかわらず、なぜ格付けがG2のままなのか。
理由の一つは、G1の乱立による弊害です。
G1レースが増えすぎると、有力馬の出走が分散し、各レースの出走頭数やレベルが低下する懸念があります。
欧州でも、少頭数のG1が増えてしまった事例があり、JRAとしても慎重な姿勢をとっています。
また、札幌記念のように開催場の設備や運営面の課題もあるケースもあります。
札幌競馬場はG1開催に必要な来賓施設や観客動線が不十分で、現状のままではG1開催の条件を満たしていません。
過去に昇格した例
それでも過去には、スーパーG2からG1に昇格したレースも存在します。
- 高松宮杯 → 高松宮記念(1996年:距離変更+スプリントG1整備)
- 産経大阪杯 → 大阪杯(2017年:春古馬三冠構想により昇格)
- ホープフルステークス(2017年:中距離路線の2歳G1として昇格)
これらのレースは、レースの意義・距離体系の整備・時期の再構築などが重なり、G1昇格へと至りました。
現在、札幌記念や毎日王冠のG1昇格を望む声もありますが、現時点ではJRA側に具体的な計画はないとされています。
レースの質が高いからこそ、あえて“G2”のままであることに価値があるとも言えるでしょう。
スーパーG3との比較
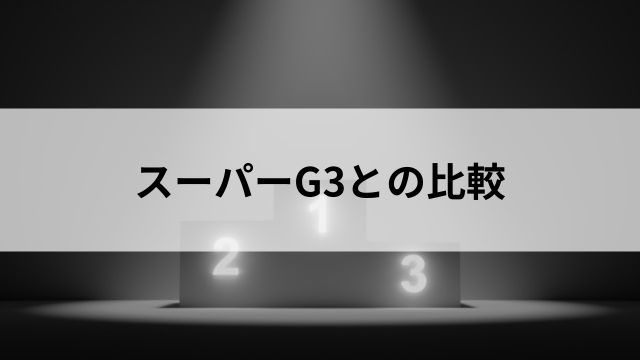
G2だけでなく、G3でもG1級の才能が集まる“スーパーG3”と呼ばれるレースが存在します。
ただし、G2との違いや境界線はやや曖昧な部分もあるため、整理しておくことは重要です。
ここでは、スーパーG3の定義と、スーパーG2との比較を通じてその位置づけを明確にしていきます。
スーパーG3とは?
「スーパーG2」と同様に、“G3なのにレベルが高い”として話題になるレースも存在します。
こうしたレースは“スーパーG3”とも呼ばれ、近年では共同通信杯や東京スポーツ杯2歳ステークスなどが該当します。
たとえば、東京スポーツ杯2歳Sは2021年にG2へ昇格しましたが、それ以前からコントレイルやワグネリアンなど、のちのG1馬を次々と輩出していました。
また、共同通信杯はクラシック候補が集う重要な一戦として、近年も高レベルな戦いが展開されています。
昇格前のチューリップ賞や富士ステークスなども、同様にスーパーG3として注目を集めていたレースです。
G2との違いと境界線
G3とG2の境界線は明確ではありませんが、スーパーG3と呼ばれるレースがG2と比べて一段落ちる点は、平均レースレーティングやG1馬の出走数にあります。
スーパーG2のレーティングが115ポンド以上で安定しているのに対し、スーパーG3は110〜113程度が多く、G1馬の数も少なめです。
ただし、育成段階の若駒が集う2歳戦やクラシック前の試金石となる3歳戦では、G3の枠でもレベルの高い一戦が生まれることは珍しくありません。
そうした意味で、スーパーG3は“将来のG1を見据えるための登竜門”として、スーパーG2とはまた違った重要性を持っています。
まとめ|スーパーG2は現代競馬の“裏G1”

スーパーG2とは、単なる前哨戦にとどまらず、出走馬の質やレース内容においてG1と同等、あるいはそれ以上の存在感を放つ重賞です。
毎日王冠や札幌記念、金鯱賞といったスーパーG2では、毎年のように現役のG1馬や実力馬が顔を揃え、ファンの期待を裏切らない名勝負が繰り広げられています。
レースレーティングが115ポンドを超えるという数字的な裏付けに加え、過去の名馬たちが刻んだ激戦の歴史も、これらのレースを特別なものにしています。
たとえ格付けはG2でも、競馬ファンにとっては“実質G1”とも言えるレース──
それが、スーパーG2です。
これからも、表向きはG2でも中身はG1級の名勝負に注目し、記憶に残るレースの数々を見届けていきましょう。