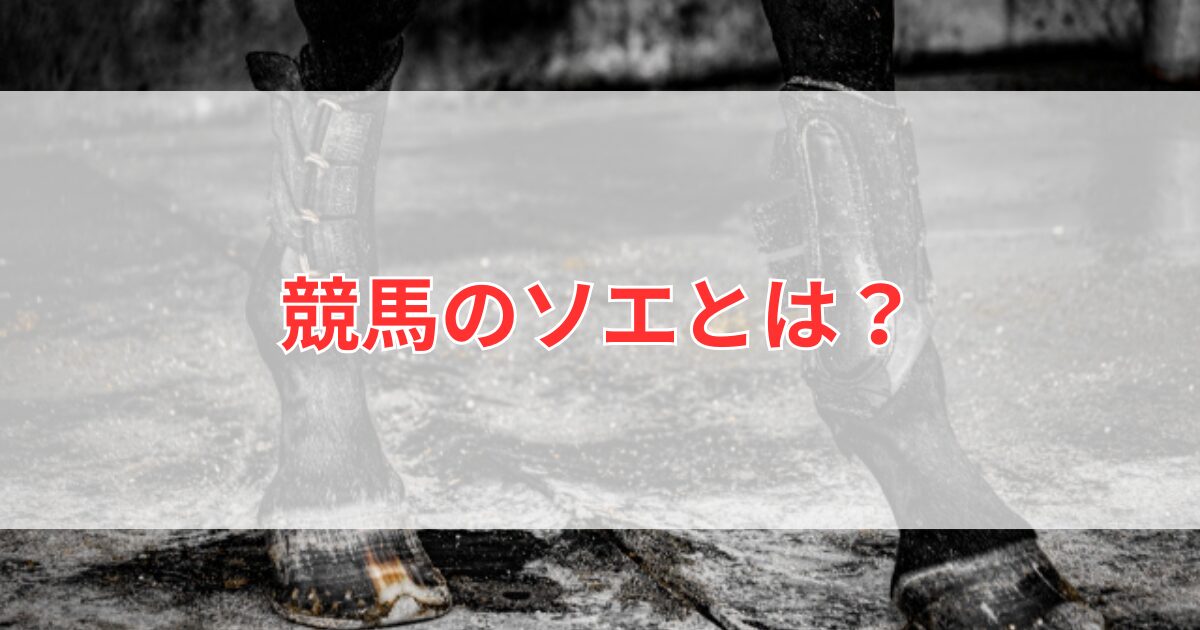2〜3歳の若駒が発症することの多いソエ。ソエが原因でデビュー戦が延期になったり、無事新馬戦を終えたものの、ソエが原因で休養に入ってしまう馬も少なくありません。
ところで、ソエという症状がどのような病気なのかご存じでしょうか。
この記事ではソエについて、その症状と原因、治療方法とあわせ、なぜ多くの若駒がソエを発症するのかを解説します。
ソエの症状と原因について

数多くある競走馬が発症する病気のひとつである、ソエ。その名前から、いったいどのような病気なのかイメージしにくいかもしれません。
ソエの正しい名称は【管骨骨膜炎(かんこつこつまくえん)】といい、その名のとおり管骨や骨膜の炎症によって引き起こされる病気です。
この章ではソエの具体的な症状と原因について解説します。
ソエの症状
ソエは主に管骨(第3中手骨)の前面に炎症が起きることによって発症します。
程度によって症状は様々で、軽度であれば患部に目立った症状は見られず、歩様が固くなったりするなどの歩様の乱れ、ハ行(跛行)の症状があらわれます。
症状が軽度の場合、早期に適切な治療ができれば、数日で完治する場合がほとんどです。
重度のソエの場合は、炎症を起こし熱感をおび、患部が腫れ上がり、激しい痛みを伴います。また、骨瘤(こつりゅう)として骨がコブのように異常形成され、その部分が骨折する可能性もあります。
特に骨瘤まで悪化してしまうと、完治までに3ヶ月以上かかると言われており、さらにそこから徐々にトレーニングを再開していくため、レースに復帰するまでにはさらに時間を要するでしょう。
また、骨瘤は治ったものの、ソエそのものが完治していない場合もあります。その場合はその馬にとって限界に近い強度のトレーニングがされていたということの証明であり、トレーニング強度の見直しが必要と言えます。
このように、一概にソエと言っても症状や治療期間は様々です。程度によっては骨折などの大きなケガに繋がってしまうのも、ソエの特徴と言えるでしょう。

ソエの原因
ソエは強いトレーニングや競走により、骨に繰り返し過度な負担がかかり続けることが原因で発症することがあります。
競走馬が時速60kmで走行した際、骨や腱などの脚部にはおよそ1tもの衝撃が加わるとされています。その衝撃により骨表面は伸びたり縮んだり、いわゆるしなっている状態になっており、これを繰り返すことにより、骨表面には細かいヒビが生じます。
つまり、ごく微細な骨折が起きているということであり、たとえ大事には至らない骨折であっても、その患部に炎症が起こることで痛みや熱感、腫れを伴い、ソエが発症します。
若駒がソエを発症する理由
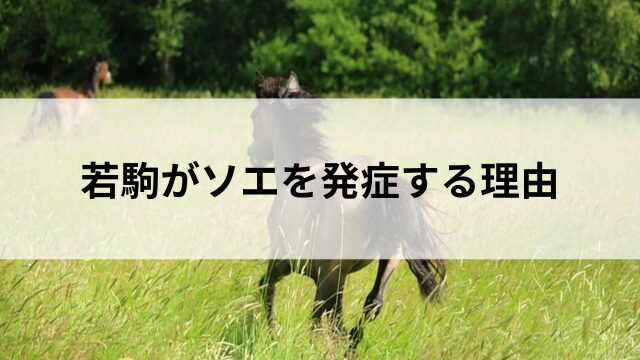
ソエの多くは、2〜3歳の主にデビュー前やデビュー直後の若駒が発症します。
その理由は【化骨(かこつ)】が完了していないからです。
化骨とは、競走馬が成長する段階で骨組織が形成される作用のことをいいます。この化骨の進み具合でトレーニングの強度や頻度を調整するのですが、若駒は化骨が完了していない場合が多く、古馬に比べると骨の強度は低く、その分骨もしなりやすい状態です。
先ほど解説したように、骨がしなると骨表面に微細な骨折が起こり、その部分が炎症するとソエに繋がります。そのため、化骨が完了しておらず、骨のしなりやすい若駒はソエを発症しやすいということです。
また、化骨が完了する3歳以降になると、骨の強度が高まるため骨はしならなくなり、ソエの発症リスクは大きく軽減します。しかし、その分走行時の衝撃や負担を骨全体で受け止めるため、今度は骨折のリスクが高まります。
ソエは重症化すると骨瘤ができ、患部の骨折につながる可能性もあるため、競走馬の将来を安全に確保するためにも、ソエは早期の発見と治療が望ましいでしょう。

ソエの治療方法は?ソエ焼きについても紹介
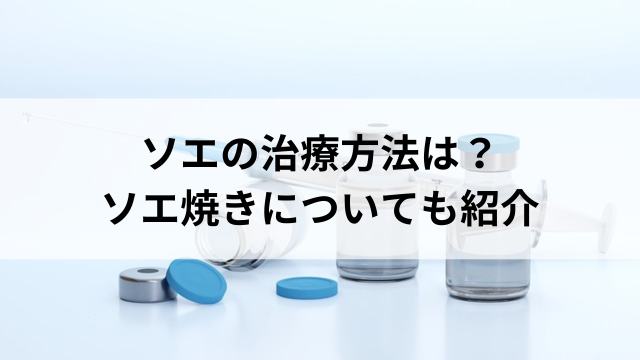
ソエの治療方法はその程度によって異なり、様々な治療方法が存在します。
主な治療方法は下記のとおりです。それぞれ、解説します。
- トレーニング強度を軽くする、または休養させる
- 患部を冷却する
- ショックウェーブ療法
- 圧迫包帯(バンテージ)を巻く
トレーニング強度を軽くする、または休養させる
軽度のソエの場合、トレーニングの強度や頻度を抑えたり、馬房で休養をとらせ、患部に負担をかけないようにすることで治療できます。
症状の軽いソエの一般的な治療方法と言えるでしょう。
患部を冷却する
患部を冷却する治療方法も、軽度なソエの一般的な治療方法です。
炎症している患部には、温度の影響を強く受ける酵素が集まっているため、その対症療法として冷却する処置がされます。
ショックウェーブ療法
ショックウェーブ療法は、患部に衝撃波を当てることにより周辺の細胞組織を刺激し、新しい細胞組織の形成を促すことで回復を早める治療方法です。
比較的新しい治療方法であるものの、従来から人間に対しても科学的根拠に基づいた治療方法として確立されていることから、競走馬にとっても有効な治療方法として処置されています。
圧迫包帯(バンテージ)を巻く
骨がしなることで引き起こされる微細な骨折を防ぐために、圧迫包帯(バンテージ)を巻くことも有効です。
これは治療方法としてとられる処置でもありますが、ソエの発症の防止にも繋がるため多くの若駒に見られる処置と言えます。
ソエ焼きについて
ここまでいくつかのソエの治療方法を解説していきましたが、過去には【ソエ焼き】という治療方法も存在していました。
ソエ焼きは、熱した鉄を患部に押し当てることで人為的に皮膚に急性炎症を負わせ、その回復とともにソエの回復も促進させるという治療方法で、実は、つい最近まではごく一般的な治療方法でした。
しかし近年、この行為自体に医学的な根拠がないことが判明し、馬にとってただ苦痛を与えているだけという批判の声もあがりかねない状態になったことから、2022年4月1日のJRA規約の改訂により禁止になりました。
同様に、ソエ焼きと同じ原理で有効とされていたブリスター療法(薬剤を用いて急性炎症を引き起こす処置)も同日に禁止となっています。
ソエのまとめ

今回の記事では若駒が発症しやすいソエの原因や症状、治療方法について解説してきました。
ソエは軽度な症状であれば数日で完治できるものの、重度になってしまうと復帰まで数ヶ月を要し、さらには骨折の原因にもなりかねない病気です。
医学が進歩した現在では、有効な治療方法が確立されており完治が難しい病気ではありません。しかし、競走馬の将来をしっかりと守るためにも、日々の管理が重要と言えるでしょう。