競馬中継や出馬表で、馬の名前の横に「セ」という表示を見かけたことはありませんか?
これは「セン馬(騙馬)」と呼ばれる馬を示す記号で、実は牡馬(オス馬)を去勢した馬のことを意味します。
競馬ファンの中でも意外と知られていない「セン馬」の世界。
なぜ去勢するのか、クラシックレースに出られないって本当? それでもG1を勝つセン馬は?
この記事では、「セン馬とは何か?」という基本から、その理由、活躍馬の例、引退後の道まで、わかりやすく解説します。
セン馬(騙馬)とは? その意味と誕生の理由
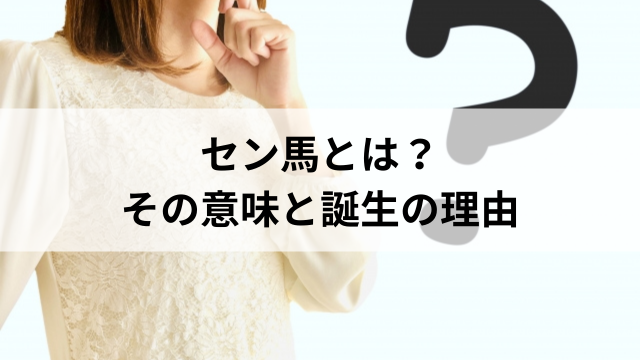
冒頭でも少し触れましたが、セン馬(騙馬)とは、去勢された牡馬(オス馬)のことを指します。
本来、牡馬は繁殖用の「種牡馬」としての価値も見込まれて育成されますが、中には気性が荒く、レースに集中できなかったり、他馬に迷惑をかけてしまうケースがあります。
その場合、「去勢手術」を行うことがあります。
なぜなら、去勢により性ホルモンのバランスが変化し、穏やかで扱いやすい性格になり、レースで安定した走りを見せるからです。
この章では、なぜ去勢するのか、どんな変化があるのかを詳しく見ていきましょう。
気性の荒さが改善される
牡馬は性成熟に伴い、攻撃的で集中力に欠ける傾向が強まることがあります。
特にパドックやレース中に他馬を気にして暴れたり、騎手の指示を無視するような行動が見られる場合、去勢が検討されます。
去勢を行うと、男性ホルモン(テストステロン)の分泌が抑制されることで、性欲や攻撃性が軽減され、精神的に落ち着くようになります。
その結果、レースに集中できるようになり、持っている能力を安定して発揮できるようになるのです。
体が柔らかくなる
去勢によってホルモンバランスが変化すると、筋肉の質や体の柔軟性にも影響が現れるとされています。
これは、男性ホルモンの減少により筋肉の硬さや張りが和らぎ、体全体がしなやかに動くようになるからです。
柔軟性の向上は、レース中のフォームやコーナリング、ストライドの伸びなどに良い影響を与えることがあります。
この変化により、セン馬はレースでのパフォーマンスをさらに引き出せるようになる場合も多いのです。
セン馬になるメリットとデメリット

セン馬にすることで、気性の安定や柔軟性の向上など、多くのメリットが期待できます。
一方で、去勢によって失われるものもあります。
この章では、セン馬になることで得られるメリットと、犠牲になるデメリットの両面についてまとめました。
気性が穏やかになり、扱いやすくなる
セン馬になる最大のメリットは、気性の安定です。
去勢によって男性ホルモンの分泌が抑えられることで、性欲や攻撃性が落ち着き、馬自身のストレスも減ります。
人や他馬に対して優しくなり、調教中やレース中でも暴れたり立ち上がるような行動が減少するため、騎手や厩務員にとっても扱いやすくなります。
この変化によって、持ち前の能力を安定して発揮できるようになり、成績が向上する例も少なくありません。
長期的に活躍できる
気性が安定することで、精神的な消耗が減り、レースへの集中力も持続しやすくなります。
このため、セン馬はベテランになっても第一線で活躍するケースが多く、7歳、8歳まで現役を続ける馬も珍しくありません。
また、セン馬は繁殖入りのタイミングが存在しないため、実力さえあれば年齢に関係なく走り続けられるという利点もあります。
長いキャリアを築ける点も、セン馬ならではの強みですね。
種牡馬の道が絶たれる
一方で、セン馬になるということは、将来的に「種牡馬」として繁殖に関わる道が閉ざされることを意味します。
現役時代にどれだけ優れた成績を残しても、去勢されていれば血を残すことはできません。
競走馬として成功しても、その才能を次世代に伝えることができないのは、血統ビジネスが根幹にある競馬界では大きなハンデと言えます。
特に、クラシック路線の馬にとっては、後述するように種牡馬入りの評価を受ける機会も限られてしまいます。
クラシックレースに出走できない
セン馬は、日本の競馬における「クラシック三冠(皐月賞・日本ダービー・菊花賞)」には出走できません。
これは、クラシック路線が将来の種牡馬を選抜する役割を持つため、去勢された馬は出走対象から外されているからです。
ただし、クラシック以外の重賞には多く出走可能なレースがあります。この点は次の章で詳しく解説します。
セン馬のクラシック制限と重賞成績|出走できるレースとは?
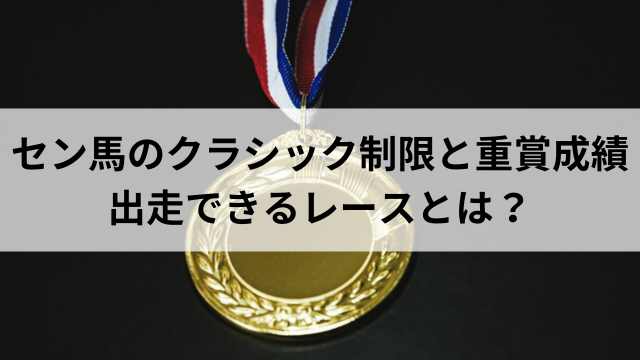
セン馬にはクラシック三冠をはじめ、一部の重賞レースに出走できないという制限があります。
これは「血統の継承」という競馬の重要なテーマと深く関わっており、種牡馬選抜としての性質を持つレースに限定されているのが特徴です。
ただし、全てのG1や重賞が対象外というわけではなく、出走可能な舞台も多く用意されています。
ここでは、セン馬が走れないレース、逆に出走できる重賞やG1について詳しく見ていきましょう。
セン馬はクラシック三冠に出走不可
日本の競馬で「クラシック三冠」と呼ばれるのは、3歳牡馬限定の大舞台である皐月賞・日本ダービー・菊花賞です。
これらのレースは、将来的に種牡馬となるべき素質馬を選抜するという意味合いが強く、去勢されたセン馬は出走することができません。
血統の継続を重視するJRAのレース構成上、種牡馬候補としての価値がないと判断されるセン馬は、早い段階でクラシック路線から外れることになります。
クラシックレース以外も出走不可能なレースがある
クラシック三冠に加え、セン馬が出走できない重賞レースは他にも存在します。
以下は代表的な「セン馬出走不可」のレースです。
- ホープフルステークス(G1)
- 朝日杯フューチュリティステークス(G1)
- NHKマイルカップ(G1)
- 神戸新聞杯(G2)
- ニュージーランドトロフィー(G2)
- スプリングステークス(G2)
2歳G1やNHKマイルカップは元より、神戸新聞杯やスプリングステークスも出場不可能なのは意外です。
一方で、似たような条件のレースでもセン馬の出走が可能な場合もあります。
- セントライト記念(G2):出走可
- 弥生賞ディープインパクト記念(G2):出走可
- チャーチルダウンズカップ(G3):出走可
こうした違いの明確な基準はJRAから公式に示されておらず、判断基準は非公開とされています。
古馬の重賞やG1は出走できる
クラシックや一部の3歳限定戦を除けば、セン馬も数多くの重賞・G1レースに出走できます。
特に古馬戦線(3・4歳以上)では、天皇賞や、宝塚記念、有馬記念、ジャパンカップなど、国内外のビッグレースにも多数の出走・好走例があります。
また、ダートG1や地方交流G1(Jpn1)では時々セン馬が優勝するケースも見られ、セン馬が第一線で活躍する場は数多く用意されています。
最強セン馬は誰だ?重賞・G1で活躍した名馬たち

気性難や体質改善のために去勢されたセン馬ですが、競走成績で見ると決して“格下”ではありません。
むしろ長く第一線で活躍する実力派も多く、G1タイトルを手にした名馬たちも存在します。
ここでは、数々のビッグレースで輝いた最強セン馬たちをご紹介します。
レガシーワールド

| 生年月日 | 1989年4月23日 |
|---|---|
| 性別 | セン馬 |
| 父 | モガミ |
| 母 | ドンナリディア |
| 母父 | ジムフレンチ |
| 生産牧場 | へいはた牧場 |
| 戦績 | 32戦7勝 |
| 主な勝ち鞍 | ジャパンカップ(G1) 1993年 セントライト記念(G2) 1992年 |
| 獲得賞金 | 4億2,377万4,000円 |
| 登録抹消日 | 1996年7月 |
「セン馬」の第一人者として有名なのが1993年のジャパンカップを勝利したレガシーワールドでしょう。
同期はミホノブルボンやライスシャワーがいる馬で、3歳(現2歳)のころからその気性難のため、なかなか結果を残せず、4歳(現3歳)で早くも去勢が行われました。
去勢されてからは打って変わって好成績を残しはじめ、セントライト記念ではのちの菊花賞馬であるライスシャワーに勝利、同年ジャパンカップで4着、有馬記念も2着と瞬く間にに活躍を見せました。
古馬になってからも安定した走りを見せており、1993年のジャパンカップではセン馬初となるG1制覇を成し遂げています。
その後は不振が続きましたが、その功績から功労馬として余生を送り、2021年8月まで生涯を全うしました。
サウンドトゥルー

| 生年月日 | 2010年5月15日 |
|---|---|
| 性別 | セン馬 |
| 父 | フレンチデピュティ |
| 母 | キョウエイトルース |
| 母父 | フジキセキ |
| 生産牧場 | 岡田スタッド |
| 戦績 | 68戦13勝 |
| 主な勝ち鞍 | チャンピオンズカップ(G1) 2016年 東京大賞典(G1) 2015年 JBCクラシック(Jpn1) 2017年 日本テレビ盃(Jpn2) 2015年 |
| 獲得賞金 | 7億6,002万8,000円 |
| 登録抹消日 | 2018年11月7日(中央) 2021年4月1日(地方) |
G1級競走を3勝したダート馬のサウンドトゥルーもセン馬として活躍していました。
去勢を行ったのは4歳のころです。性格は穏やかでしたが、当時存在していた降級制度で降級しても勝ち切れなかったことから、筋肉の柔軟を目的に去勢が行われました。
去勢後初戦のレースを勝利すると、その後は堅実にキャリアを重ね、2015年の東京大賞典を優勝、翌2016年のチャンピオンズカップも優勝し、2016年最優秀ダートホースに選出されています。
2018年に中央登録抹消されてからは地方に移籍し、そこでも堅実に走りましたが、最終的には11歳の2月のレースを最後に引退し、現在は故郷の岡田スタッドで繋養されています。
ノンコノユメ

| 生年月日 | 2012年3月28日 |
|---|---|
| 性別 | セン馬 |
| 父 | トワイニング |
| 母 | ノンコ |
| 母父 | アグネスタキオン |
| 生産牧場 | 社台ファーム |
| 戦績 | 46戦9勝 |
| 主な勝ち鞍 | フェブラリーステークス(G1) 2018年 ジャパンダートダービー(Jpn1) 2015年 ユニコーンステークス(G3) 2015年 武蔵野ステークス(G3) 2015年 根岸ステークス(G3) 2018年 |
| 獲得賞金 | 5億7,691万1,000円 |
| 登録抹消日 | 2022年7月22日 |
可愛らしい名前で有名なノンコノユメも去勢された馬です。
3歳のころはジャパンダートダービー(現在のジャパンダートクラシック)をはじめ、数多くの重賞を勝利していましたが、4歳の秋に去勢されました。
その後も長く活躍し、2018年のフェブラリーステークスは自身3度目の挑戦で見事優勝を果たしています。
地方に移籍してからも堅実に走っていましたが、最終的には脚部不安のため引退し、現在は故郷社台ファームで功労馬として余生を送っています。
セン馬の引退後はどうなる?乗馬・療養・功労馬としての道

競走馬としての役割を終えたセン馬たちは、引退後にどんな人生を歩むのでしょうか。
種牡馬としての道が閉ざされている彼らは、一般の牡馬や牝馬とは異なる引退後の進路をたどります。
ここでは、セン馬の引退後に待っている現実や、乗馬・功労馬としての新たな役割について解説します。
基本的には廃用
残念ながら、セン馬の引退後は厳しい現実が待っていることも少なくありません。
種牡馬としての価値がないため、繁殖入りは不可能。乗馬や功労馬としての適性がなければ「用途廃止」として処分されてしまうケースも存在します。
一部のセン馬は競走成績や性格によって引退後の余生が守られることもありますが、全てのセン馬が安心して余生を過ごせるとは限らないのが現実です。
近年は引退馬支援団体の活動も広がりつつありますが、現役時代の人気や実績が重要な要素になります。
引退後は乗馬クラブや功労馬になるケースもある
性格が穏やかで従順なセン馬は、乗馬クラブなどで再び活躍の場を得ることがあります。
去勢によって気性が落ち着いているため、初心者向けの乗馬やセラピーホースとして適しているのが大きな特徴です。
また、G1などで活躍した馬やファンの多かった馬は、引退後に「功労馬」として牧場で余生を過ごすケースもあります。
これらの馬は、競馬場や牧場でイベントに参加することもあり、ファンと再会できる貴重な存在となります。
功労馬になってから去勢される馬もいる
実は、現役時代には去勢されていなかったものの、引退後に去勢されるケースも存在します。
代表的な例が2018年の有馬記念勝ち馬・ブラストワンピースです。
引退後、功労馬として見学可能な形で北海道にあるノーザンホースパークで繋養されることが決まりましたが、余生を送るにあたって、安全性や管理面を考慮し、去勢処置が行われました。
繁殖に使われないことが決まっている馬にとって、穏やかな性格を維持することは、余生を平和に過ごすためにも重要な要素となるのです。
セン馬のまとめ

セン馬は、単なる「去勢された馬」ではなく、競走馬としてのパフォーマンスを安定させるための手段の一つです。
クラシック三冠には出走できないという制限はありますが、古馬戦線では多くの名馬たちがG1を制しています。
また、去勢により長く安定して活躍できるのもセン馬の魅力です。
出馬表に「セ」と書かれた馬を見かけたら、「なぜセン馬なのか」「どんなキャリアを歩むのか」に注目してみると、競馬がもっと面白くなるはずです。

