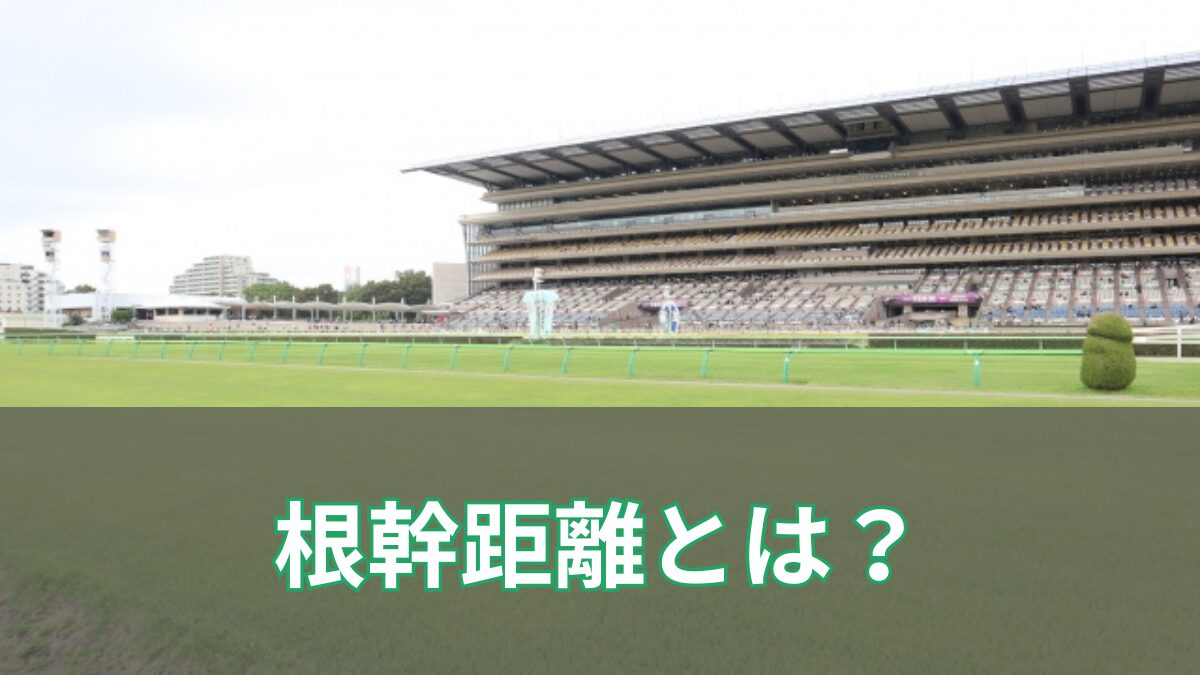競馬にハマってくると、よく目にするのが「根幹距離」や「非根幹距離」という言葉です。
専門的な雰囲気があるため、競馬初心者には少しとっつきにくく感じるかもしれません。
しかしこの「距離の区分け」を理解すると、レースの見方が大きく変わります。
どの馬に適性があり、どんなレース展開になりやすいのか。さらには「荒れやすいレース」の傾向も見えてくるのです。
この記事では、根幹距離の意味や定義、非根幹距離との違い、馬券に活かせる考え方などを初心者向けにわかりやすく解説します。
競馬をもっと深く楽しみたい方は、ぜひ最後までご覧ください!
根幹距離とは?
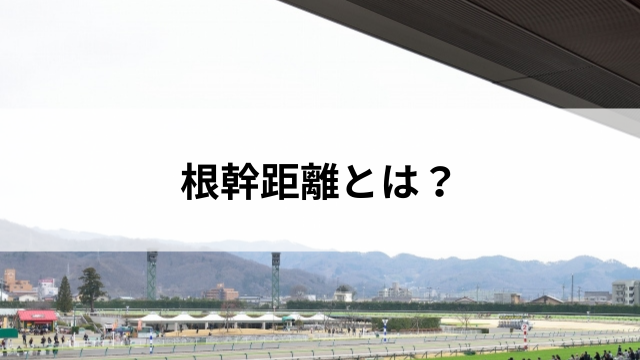
競馬において「根幹距離」という言葉は、レースの距離設定を理解するうえで非常に重要なキーワードです。
特にG1など格式の高いレースで多く採用されている距離であり、馬の能力比較がしやすいとも言われています。
ここでは、根幹距離の読み方や定義について解説します。
読み方は「こんかんきょり」
「根幹距離」は漢字で書くと少し難しそうに見えますが、読み方は「こんかんきょり」といいます。
競馬ファンの間ではごく一般的な用語として使われている言葉です。
聞き慣れない言葉かもしれませんが、意味を理解すれば、レースの見方が一段と広がります。
ちなみに「非根幹距離」は「ひこんかんきょり」と読みます。
根幹距離の定義とは
根幹距離とは、400で割り切れる距離のことを指します。例えば、よく見る以下の距離は根幹距離です。
- 芝1,200m
- 芝1,600m
- 芝2,000m
- 芝2,400m
- 芝3,200m
これらの距離は、日本競馬におけるG1レースでも数多く使われているのが特徴です。
なお、名称の由来としては、王道の路線や格式の高い重賞レースで多く用いられる距離設定であることから、「根幹=中心となる幹」という名前がつけられています。
非根幹距離とは?根幹距離との違い
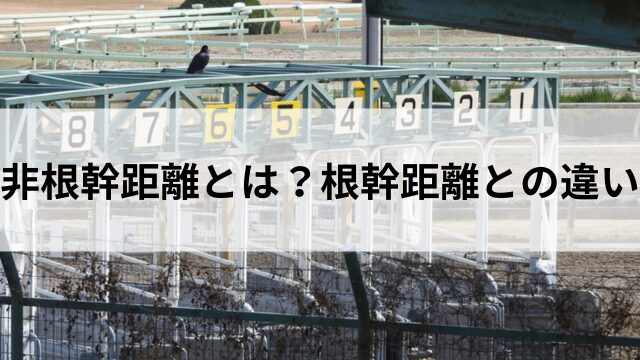
根幹距離が王道路線であるのに対し、非根幹距離はやや特殊な立ち位置の距離設定です。
主に条件戦やローカル重賞で用いられ、コース形態やペースにも独特の特徴があります。
ここでは非根幹距離の定義や、根幹距離との違いについて見ていきましょう。
非根幹距離は400で割れない距離
非根幹距離とは、400で割り切れない距離を指します。たとえば以下のような距離です。
- 芝1,800m
- 芝2,200m
- 芝2,500m
これらの距離はG1で使われることが比較的少ないですが、菊花賞(芝3,000m)や有馬記念(芝2,500m)、宝塚記念(芝2,200m)のようなビッグレースは非根幹距離に指定されています。
レース傾向やペース配分の違い
根幹距離と非根幹距離の大きな違いの一つが、ペース配分とレースのリズムです。
競走馬は一般的に400mごとにリズムが整いやすいと言われており、1,600mや2,400mのように400の倍数で構成される根幹距離では、スムーズに走れる傾向があります。
一方、非根幹距離は400で割り切れないため、途中でリズムを崩しやすく、能力どおりに決まりにくい側面があります。これは、急なギアチェンジを強いられたり、騎手のペース判断がより重要になるということでもあります。
また、非根幹距離は宝塚記念や有馬記念のように、開催後期に行われることから、もともとスタミナやパワーが問われやすい条件下で開催されることも珍しくありません。
その影響もあって、非根幹距離では思わぬ波乱が起きたり、人気薄の馬が好走することも見られます。
根幹距離は関係ないと言われる理由

根幹距離と非根幹距離の違いは、競馬を深く知るうえでの一つの指標となります。
しかし一方で、「根幹距離だからといって必ず有利とは限らない」「関係ない」と言われることも珍しくありません。
では、なぜそう言われるのでしょうか?その理由を掘り下げてみましょう。
必ずしも重要視しなくていい?
「根幹距離=王道」というイメージは強いですが、必ずしもこの区分けが絶対というわけではありません。
馬の個性や脚質、展開次第では、根幹距離でも凡走し、非根幹距離で激走するケースも多々あります。
また、コース形態や馬場状態、開催時期など、レースにはさまざまな要素が絡んでおり、「距離区分」だけでレースの結果を読み切るのは難しいのが現実です。
「あえて非根幹距離」を狙う妙味
競馬ファンの中には、非根幹距離=荒れやすいという傾向を狙って、積極的に高配当を狙うスタイルの人もいます。
なぜなら、非根幹距離では、人気馬が能力を出し切れずに敗れることも少なくなく、波乱含みの結果になりやすいからです。
非根幹距離は、実力だけではなく、展開や馬場状態に左右されやすく、騎手の判断力が試されるため、コース攻略に長けたベテランや中堅騎手が穴をあけることもあります。
このように、「根幹距離かどうか」は参考材料の一つとして考えつつも、馬券検討では他のファクターと合わせて多角的に判断することが大切です。
まとめ|根幹距離と非根幹距離を知ることで競馬はもっと面白くなる

「根幹距離」と「非根幹距離」は、単なる距離の数字以上に、レース展開や馬の適性に大きく関わる要素です。
根幹距離は王道の舞台であり、能力比較がしやすい一方、非根幹距離には独特のリズムや展開があり、波乱の要素も含んでいます。どちらが正解というわけではなく、それぞれの特徴を理解することで、より深く競馬を楽しむことができます。
特に馬券を買う際には、距離の区分けを参考に「どの馬がこの舞台に向いているか」を考えるだけでも、回収率アップのヒントになります。
ぜひ次のレースから、「この距離って根幹?それとも非根幹?」と意識してみてください。
競馬の世界が一段と奥深く、そして面白く見えてくるはずです。