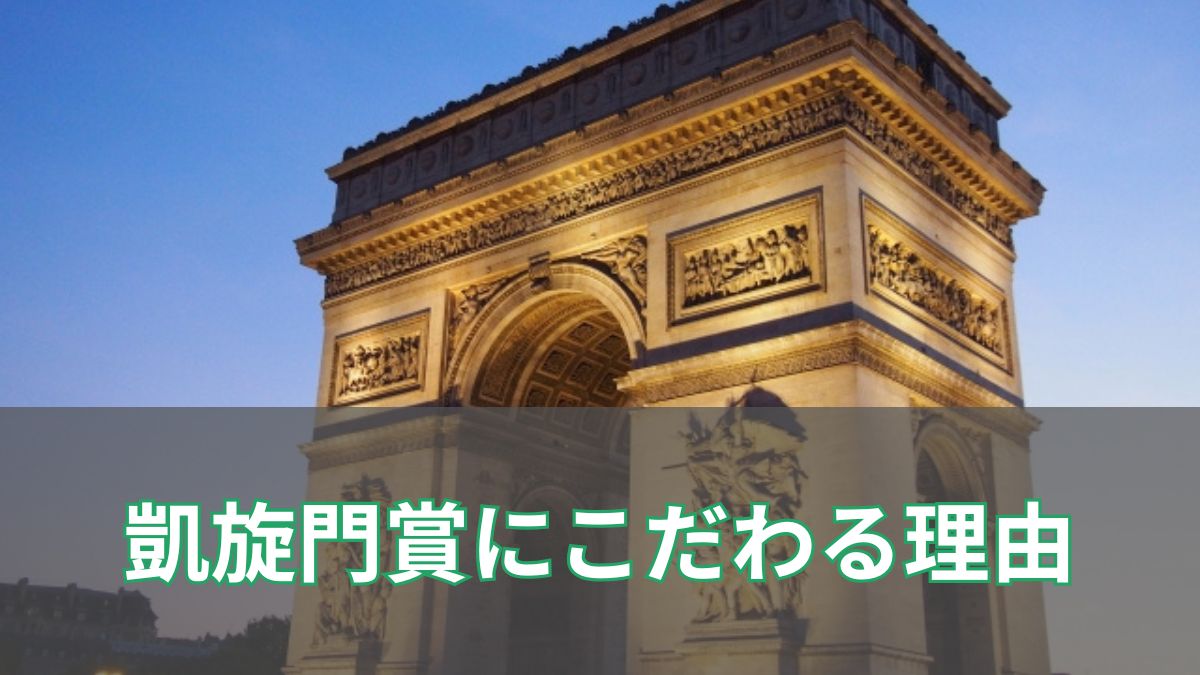凱旋門賞はフランス・パリロンシャン競馬場で行われる芝2,400mの世界最高峰レースです。
日本でも長年「夢の舞台」として憧れられ、シンボリルドルフやディープインパクト、オルフェーヴルといった名馬が挑戦してきました。
しかし惜敗が続き、いまだ日本馬は勝利をつかんでいません。
それでも挑戦が止まらないのは「あと一歩」の歴史が刻まれているからです。
2024年はシンエンペラーが出走し、新たな希望を背負いました。
なぜ日本人はここまで凱旋門賞にこだわるのか、その理由を探っていきましょう。
日本人が凱旋門賞に熱狂する理由
凱旋門賞は単なる海外G1ではなく、日本競馬の歴史や夢と深く結びついた特別な存在です。
数々の名馬が挑戦しながらも「あと一歩」で敗れてきた悔しさが、多くのファンを魅了し続けています。
ここからは、日本人がなぜこれほどまでに凱旋門賞に惹かれるのか、その背景を見ていきましょう。
名馬たちが繰り返した“惜敗の歴史”
日本馬の凱旋門賞挑戦は1969年、スピードシンボリから始まりました。
その後も名だたる名馬が挑み、1999年にはエルコンドルパサーが欧州最強馬モンジューに頭差まで迫る激走を披露。
2006年には三冠馬ディープインパクトが3着に入りましたが、薬物問題で失格となり、日本中を落胆させました。
さらに2010年のナカヤマフェスタはステイゴールド譲りの底力で2着に健闘し、2012年と2013年には三冠馬オルフェーヴルが連続して2着と、あと一歩で夢に届かず涙をのみました。
これらの挑戦はすべて「勝てそうで勝てなかった」という記憶として刻まれ、日本人の心を強く揺さぶり続けています。
だからこそ凱旋門賞は、単なる海外レースを超えて「日本競馬最大の悲願」となったのです。
日本競馬の路線と凱旋門賞の一致
日本競馬は「芝2,400m」を中心に発展してきました。
その象徴が日本ダービーやジャパンカップで、どちらも芝2,400mで行われるビッグレースです。
つまり、凱旋門賞と同じ舞台設定が日本競馬の“王道路線”として位置づけられているのです。
この距離を克服できる馬こそが日本競馬の頂点に立つ存在とされ、同時に「世界でも通用するのでは」という期待が自然と生まれました。
過去数十年にわたり、調教師や馬主、生産者がこの舞台を意識してきたのは必然と言えるでしょう。
日本のホースマンたちにとって凱旋門賞は、国内の頂点のさらに先にある「究極の目標」として強く意識されてきたのです。
血統・種牡馬ビジネスの影響
凱旋門賞での勝利は、単なる名誉にとどまりません。
その実績は馬の血統価値を大きく引き上げ、種牡馬や繁殖牝馬としての評価に直結します。
ヨーロッパでは凱旋門賞馬が種牡馬として重宝される傾向が強く、日本でもこの価値観が共有されています。
例えば、ディープインパクトは凱旋門賞では失格となったものの、挑戦そのものが世界的な知名度を高め、後に国際的な大種牡馬となりました。
もし日本馬が凱旋門賞を制することができれば、その血統は“世界基準”として認められ、セリ市場や国際取引における需要も格段に高まります。
このように、挑戦の背景にはロマンだけでなく「経済的リターン」という現実的な側面も存在しており、ホースマンたちを駆り立てる大きな動機となっているのです。
凱旋門賞で日本馬が勝てない理由
数多くの名馬が挑戦してきたものの、日本馬はいまだ凱旋門賞を制していません。
その背景には、ロンシャン特有のタフな馬場や坂、そして臨戦過程の難しさといった大きな壁があります。
ここからは、日本馬が苦戦を強いられてきた要因を整理していきましょう。
最大の壁「馬場と坂」
凱旋門賞が行われるロンシャン競馬場は、高低差10mという大きなアップダウンが待ち受けるタフな舞台です。
日本の競馬場で最も高低差がある中山競馬場でも約5.3mであり、ロンシャンの坂はその倍に近い厳しさを誇ります。
加えて、日本の芝は「高速馬場」と呼ばれるスピード決着になりやすいのに対し、ヨーロッパの芝は水分を含んで「重く」、力の持続やパワーが求められます。
このため、日本国内でいくら坂やタフな条件に強い馬であっても、欧州の舞台では同じような走りができないケースが多く見られました。
過去に挑戦したクロノジェネシスやタイトルホルダーといった国内G1馬も、馬場と坂の壁を越えられずに沈んだのはその典型例です。
つまり、日本馬にとって凱旋門賞最大の課題は「馬場と坂への対応力」であり、ここを克服しない限り勝利は見えてきません。
適性だけではなく“圧倒的実力”が必要
凱旋門賞で好走した日本馬を振り返ると、エルコンドルパサー、ディープインパクト、オルフェーヴルといった国内で突出した名馬ばかりです。
ナカヤマフェスタのように血統的な適性で2着に激走した例もありますが、それは例外に近いものでした。
欧州特有の重い馬場や長い坂を克服するためには、単なる「適性」だけでは足りません。
求められるのは、世界の強豪馬と互角以上に渡り合える圧倒的な能力です。
過去の挑戦でも、国内で無双した馬たちが初めて勝負になるレベルであり、国内で一歩抜けた存在でなければ凱旋門賞の舞台に立つ資格すら得られないとも言えるでしょう。
つまり、「適性+圧倒的な実力+勢い」が揃って初めて勝利のチャンスが生まれるのです。
臨戦過程とローテーションの課題
日本馬が凱旋門賞を目指す際、前哨戦として選ばれることが多いのがロンシャンのニエル賞やフォワ賞です。
同じ舞台を経験できるメリットはありますが、中2週で本番を迎えるため、仕上げの難しさが常につきまといます。
さらに現地への適応という意味でも、短期間の滞在では効果が限定的で、数週間で馬が欧州仕様に変わることはほとんどありません。
合田直弘氏も「順応に期待するより、各レースを勝ちに行きながら状態を整える方が重要」と指摘しています。
実際には、ヨークのインターナショナルSやヨークシャーオークス、アイルランドのチャンピオンS、さらにはドイツのバーデン大賞といったステップを使う選択肢もあります。
馬に合わせた柔軟なローテーションを組み、本番にピークを持っていくことが、日本馬に求められる新たな戦略と言えるでしょう。

シンエンペラーの凱旋門賞挑戦が示す可能性と現実
2024年、凱旋門賞に挑んだ日本調教馬シンエンペラーは、良血と実績を兼ね備えながらも結果は12着に終わりました。
前哨戦で欧州のトップホース相手に善戦したものの、本番では適性と実力の壁が立ちはだかりました。
この挑戦から、日本馬が勝つための条件と課題が改めて浮き彫りになったのです。
世界的良血でも通用しなかった現実
シンエンペラーは、父シユーニ、そして全兄に凱旋門賞馬ソットサスを持つ世界的良血馬として大きな注目を集めました。
日本でもホープフルステークス2着、日本ダービー3着などクラシック戦線で安定した成績を残し、世代の上位に位置づけられる存在でした。
そのため「欧州血統の強さと日本での実績を兼ね備えた馬なら凱旋門賞でも通用するのでは」と大きな期待を背負っていました。
しかし本番では直線で伸びを欠き、結果は12着に敗退。
良血や過去の国内成績だけでは凱旋門賞の厳しい舞台を突破できない現実が突きつけられました。
改めて“血統”は可能性を示すにすぎず、世界の頂点を争うには圧倒的な総合力が不可欠であることを証明した形となりました。
欧州での前哨戦好走も本番では不発
シンエンペラーは凱旋門賞本番前、アイルランドで行われたアイリッシュチャンピオンステークスに挑戦しました。
結果は欧州の強豪馬に混じって3着と健闘し、現地でも高い評価を獲得しています。
ブックメーカーの前売りオッズで3番人気に押し上げられるほど期待が高まり、日本のファンも大きな夢を抱くことになりました。
しかし、いざ凱旋門賞本番を迎えると、ロンシャン特有のタフな馬場や厳しい流れに対応できず、直線では力を出し切れず12着に敗退。
前哨戦での善戦がそのまま本番の結果に結びつかないことを改めて示す結果となりました。
欧州での経験は無駄ではありませんが、凱旋門賞は単なる“叩き台の延長”では突破できない、別格の舞台であることが浮き彫りになったのです。
チーム一丸の挑戦が残したもの
シンエンペラーの挑戦は結果こそ12着に終わりましたが、日本競馬にとって大きな意味を持つものでした。
管理する矢作芳人調教師は、世界を舞台に実績を積み重ねてきた名伯楽。
馬主の藤田晋氏は新進気鋭のホースマンとして積極的に世界的良血馬を購入し、日本競馬の国際化に貢献しています。
鞍上を務めた坂井瑠星騎手も、若手ながら海外経験を積み重ねており、新しい世代の騎手像を示しました。
結果は期待に届かなかったものの、この布陣で挑んだ姿勢そのものが「日本競馬は本気で世界の頂点を狙っている」という強いメッセージとなったのです。
敗北の経験は無駄ではなく、未来の挑戦に活かされる財産となります。
シンエンペラーの遠征は、悲願達成へ向けた日本競馬の挑戦が新しい段階に入ったことを示したといえるでしょう。
見えてきた勝利への条件
シンエンペラーの挑戦は、良血や前哨戦での健闘だけでは凱旋門賞を勝ち抜けないことを示しました。
勝利のためにはまず、欧州のタフな馬場に適応できる「適性」が欠かせません。
しかしそれ以上に重要なのは、世界の強豪馬を相手に押し切れるだけの「圧倒的な実力」と、どんな展開にも対応できる柔軟さです。
さらに、直近のレースで結果を残している勢いや充実度も大きな武器となります。
つまり、血統や過去の実績といった要素はあくまで一部であり、実力・適性・勢いの三拍子がそろって初めて勝利のチャンスが生まれるのです。
この条件を満たした馬が現れるまで、日本競馬の挑戦は続いていくでしょう。
「なぜ凱旋門賞にこだわるのか?」への答え
日本馬は幾度も挑戦しながら、いまだ凱旋門賞を勝てていません。
それでも挑戦が続くのは「あと一歩」という歴史が積み重なっているからです。
ここからは、海外競馬評論家・合田直弘氏が語った“こだわりの本質”を紹介します。
合田直弘氏の見解
「なぜ日本人は凱旋門賞にそこまでこだわるのか?」という問いに対し、長年海外競馬を取材してきた合田直弘氏は明確な答えを示しています。
それは「すでに2着が4回もあるから。ここまで来たら勝つまでやめられない」というものです。
エルコンドルパサー、ナカヤマフェスタ、そしてオルフェーヴルなど、惜しくも勝利を逃した名馬たちの姿は日本人の記憶に深く刻まれています。
あと一歩届かなかった悔しさが、むしろ次の挑戦への原動力となり、ホースマンもファンも“悲願達成”を夢見続けるのです。
合田氏はまた、日本の競馬体系そのものが芝2,400mを基軸に発展してきた歴史を指摘します。
その延長線上にある凱旋門賞を目標に据えるのは、決して不自然ではなく、日本競馬にとって必然の挑戦だと強調しています。
凱旋門賞にこだわる理由:まとめ
日本人が凱旋門賞にこだわるのは、単なる海外遠征の夢ではなく「あと一歩で勝てそうだった惜敗の歴史」があるからです。
エルコンドルパサー、ディープインパクト、オルフェーヴルらが示した名場面が記憶に刻まれ、「必ず日本馬で勝ちたい」という思いがホースマンとファンを突き動かしてきました。
しかしロンシャンの馬場や坂の壁は高く、良血や国内での実績だけでは通用しないことをシンエンペラーの12着という現実も改めて示しています。
勝利に必要なのは血統だけでなく、圧倒的な実力、適性、勢いを兼ね備えた総合力です。
それでも挑戦が続くのは、悲願を達成するその瞬間を見たいという情熱と、競馬というスポーツが持つロマンに他なりません。
日本競馬が世界の頂点に立つ日は、きっとそう遠くはないはずです。