「持ち回り開催」という言葉をニュースや競馬の話題で耳にしたことはありませんか。
持ち回りとは、同じ場所で固定的に行うのではなく、開催地や担当を順番に変えて実施する仕組みのことをいいます。
スポーツ大会や文化イベントでも採用されていますが、特に競馬ではブリーダーズカップやJBCシリーズのように、毎年開催地を変えることで地域ごとの特色を生かす運営スタイルとして知られています。
この記事では、持ち回りの基本的な意味から、競馬での具体的な事例までわかりやすく解説します。
持ち回りとは?(基本の意味)
「持ち回り」とは、特定の場所や人に固定せず、順番に回して行うことを意味します。
もともとは会議や行事などで、開催地や担当者を交代で務める仕組みを指す言葉です。
たとえば「持ち回り会議」「持ち回り開催」「持ち回り制」といった形で使われ、地域や組織の公平性を保つために導入されるケースが多くあります。
また、スポーツ大会や文化イベントでは、毎年異なる会場で開催することで地域ごとの特色を生かし、参加者に新鮮さを与える効果もあります。
競馬における持ち回り開催とは?
持ち回りという言葉は、ビジネスやイベントだけでなく、実は競馬の世界でも使われています。
競馬の場合は、同じレースを毎年異なる競馬場で開催するスタイルを指します。
その代表例がアメリカのブリーダーズカップと日本のJBCシリーズです。
ここからは、競馬における持ち回り開催の特徴と魅力を詳しく見ていきましょう。
毎年開催地が変わる仕組み
競馬における「持ち回り開催」とは、同じ大会を毎年異なる競馬場で行う運営方式のことです。
たとえばアメリカのブリーダーズカップは、サンタアニタパークやキーンランド、チャーチルダウンズなど、国内の主要競馬場を順番に回って開催されています。
日本でも同様に、地方競馬の祭典「JBCシリーズ」が金沢・盛岡・大井・佐賀などを巡って行われており、開催地ごとに距離設定やコース形態が少しずつ変化します。
こうした持ち回り制は、特定の競馬場に偏らない公平性を保ちながら、各地域のファンが自分の地元でトップレベルのレースを楽しめるようにする目的があります。
また、開催地ごとに馬場や気候、観客の雰囲気が異なるため、毎年異なるレース展開やドラマが生まれるのも大きな魅力です。
馬場やコースの違いによる魅力
持ち回り開催の最大の魅力は、競馬場ごとに異なる馬場やコース形態がレース展開に大きな変化をもたらすことです。
競馬場には全長の大きさや直線の長さ、高低差など、それぞれに特徴があります。
ダートの砂質や気温・湿度なども地域ごとに異なり、同じ距離でも求められる脚質やスタミナがまったく変わってきます。
そのため、毎年同じレースであっても「逃げが有利な年」「差しが決まる年」といった違いが生まれるのです。
また、ファンにとっても新しい競馬場で観戦できる楽しみがあり、地域色あふれる演出や名物料理などを味わえるのも魅力の一つです。
こうした多様性こそが、持ち回り開催が多くの競馬ファンに支持される理由といえるでしょう。
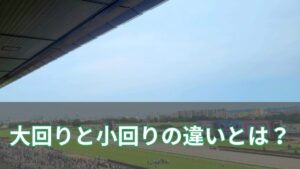
持ち回り開催の代表例①:ブリーダーズカップ(アメリカ)
アメリカ競馬の最高峰イベントであるブリーダーズカップは、世界的にも有名な持ち回り開催のレースシリーズです。
1984年に創設されて以来、サンタアニタパーク、キーンランド、チャーチルダウンズなど、全米各地の主要競馬場を巡回して行われています。
この方式により、アメリカ国内の多様な地域で競馬ファンが直接観戦できるほか、開催地ごとに異なる気候・馬場・雰囲気がレース結果に影響を与える点も魅力です。
カリフォルニア州の乾いた高速馬場ではスピード型の馬が有利になる一方、ケンタッキー州の湿り気を含んだ馬場ではパワー型の馬が台頭します。
同じG1でも開催地が変わることで展開がまったく違う顔を見せ、まさに「全米が主役」になるイベントとして、ブリーダーズカップは長年愛され続けています。
持ち回り開催の代表例②:JBCシリーズ(日本)
日本にも、アメリカのブリーダーズカップをモデルにした持ち回り開催のイベントが存在します。
それが地方競馬の祭典「JBCシリーズ(ジャパン・ブリーダーズ・カップ)」です。
毎年11月上旬の文化の日を中心に開催され、JBCクラシック・JBCスプリント・JBCレディスクラシックなどの統一G1(Jpn1)級レースが同日に行われます。
開催地は金沢、盛岡、大井、佐賀など地方競馬場を中心に持ち回りで決定され、近年はJRAの京都競馬場で実施されるケースもあります。
コース形態や馬場の特徴が会場ごとに異なるため、逃げ馬が有利な年もあれば、差し馬が突き抜ける年もあり、毎年違うドラマが生まれます。
さらに、地方競馬の認知度向上や地域活性化にもつながる点が高く評価されており、JBCは「日本版ブリーダーズカップ」として確固たる地位を築いています。
なぜ持ち回り方式が採用されるのか?
持ち回り方式が採用される理由は、公平性と地域貢献の両立にあります。
ひとつの会場だけで毎年開催すると、その地域ばかりが注目を集めてしまいますが、持ち回りにすることで全国の競馬場や自治体に開催のチャンスが巡り、ファンも自分の地元で大レースを楽しめます。
また、観光客の増加や地元経済の活性化といった効果も大きく、開催地にとってはまさに地域の一大イベントです。
さらに、馬場状態や気候の違いによりレース展開が多様化し、ファンにとっても毎年新鮮な見どころが生まれます。
このように、持ち回り方式は競馬文化を全国的に広げ、地域を盛り上げるための仕組みとして機能しているのです。
まとめ|持ち回りは地域と競馬をつなぐ仕組み
持ち回りとは、開催地や担当を固定せずに順番で実施する仕組みのことで、競馬ではブリーダーズカップやJBCシリーズに代表されます。
この方式は、地域ごとの特色を生かしながら競馬文化を広げる効果があり、ファンにとっても毎年異なる舞台で新たなドラマを楽しめる点が魅力です。
持ち回り開催は、単なる運営方法ではなく、競馬を全国的に盛り上げるための大切な文化的取り組みといえるでしょう。

