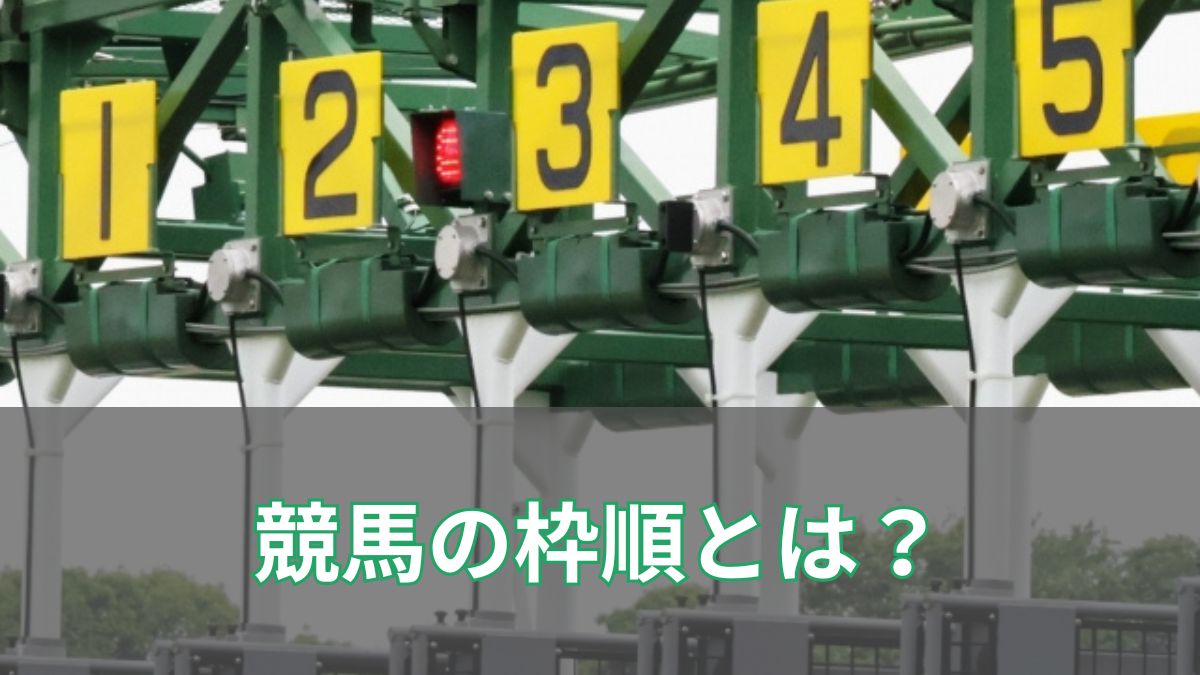競馬の出馬表を見ると必ず記載されている「枠順」。
数字や色が並んでいて、初心者の方には少し難しく感じるかもしれません。
しかし、枠順は単なる番号ではなく、スタート位置やレース展開に大きな影響を与える重要な要素です。
たとえば、コースによっては内側の枠(内枠)が有利だったり、逆に外枠が有利とされる条件もあります。
さらに、有馬記念などの大きなレースでは枠順の発表が特別なイベントとして行われることもあり、予想や注目度を高めるきっかけにもなります。
この記事では、競馬の枠順とは何か、決め方や色分け、有利不利まで詳しく解説していきます。
競馬の枠順とは何か
競馬の枠順とは、各馬がスタート地点で並ぶ位置を示すもので、1枠から8枠まで存在します。
この枠順によって、スタート時のコース取りやレース展開が大きく変わることがあり、馬券検討においても重要な判断材料となります。
ここでは、枠順と馬番の違いや並びの法則、決定方法や発表タイミングなど、基本的な情報を詳しく見ていきましょう。
枠順と馬番の違い
枠順とは、スタートゲートに並ぶ位置のことで、JRAでは1枠から8枠に分けられています。
一方で、馬番はそのレースに出走する各馬に付けられる番号で、枠順とは異なる概念です。
たとえば、出走頭数が16頭なら馬番は1〜16番まで存在しますが、枠順は8枠までしかありません。
このため、1つの枠に2~3頭が入ることもあり、同じ枠内でも馬番は異なります。
出馬表などでは「1枠1番」「5枠10番」などと記載されるため、枠と馬番の違いを理解しておくことで、予想や観戦もよりスムーズになるでしょう。
枠番号が小さいほど内ラチに近く、枠番号が大きいほど外ラチに近い場所から発走する
競馬場のコースには、内側と外側の境界線に「ラチ(柵)」が設けられています。
枠順は、このラチに対してどの位置からスタートするかを表しており、番号が小さい枠ほど内ラチ寄り、大きい枠ほど外ラチ寄りのスタート地点となります。
つまり、1枠はもっとも内側、8枠はもっとも外側からの発走となります。
この位置関係によって、スタート後の進路取りやコーナーへの入り方に違いが出てきます。
たとえば、スタート後すぐにカーブがあるコースでは、内枠が距離的に有利とされる一方、大外枠は外を回らされやすく不利になることもあります。
逆に芝スタートのダート短距離戦などでは、長く芝を踏むことができる外枠がスムーズに加速できるため有利とされるケースもあります。
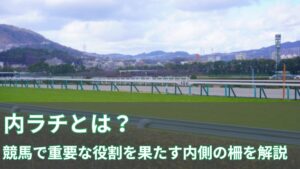
枠順はいつ決まる?
JRAのレースにおける枠順は、原則として出走予定日の前日に決定されます。
一般的な平地競走では前日の午前中に発表されることが多く、重賞レースの場合は金曜日の午前に発表されるのが基本です。
さらに、G1など注目度の高いレースでは発表が木曜日の午前に前倒しされることもあります。
たとえば有馬記念や天皇賞などは、早めに枠順が公開され、予想ファンの注目を集める要素となっています。
このように、レースの格が高くなるほど発表が早まる傾向があるため、注目レースの予想を行う際は、枠順の発表スケジュールもチェックしておくとよいでしょう。

枠順の決め方と抽選方法
JRAでは、全てのレースにおいてコンピューターによるランダム抽選で枠順を決定しています。
人為的な操作が一切入らないよう設計されており、公平性を保つために自動処理が導入されています。
この仕組みは重賞やG1レースであっても同じで、全馬の出走登録が確定したあと、JRAのシステムが無作為に馬番と枠番を割り当てます。
ただし、一部のG1レースではファンへの公開性を高める目的で、枠順抽選会を行う場合があります。
それでも最終的な決定自体はコンピューター抽選に基づくものです。
近年の有馬記念は公開枠順抽選会をテレビ中継する
年末の大一番として注目を集める有馬記念では、近年「公開枠順抽選会」が実施され、テレビ中継やYouTube配信が行われるほどのイベントになっています。
この抽選会では、各陣営の騎手や調教師、JRA関係者が会場に登場し、「出走順」を決めるくじを引きます。
最初に、ランダムにくじを引く順番を決め、用意された枠番のボールやカードを引くという形式で枠順を決めていきます。
ファンからは「演出が面白い」「枠抽選からドラマが始まっている」といった声も多く、馬券予想の一環として楽しみにしている人も少なくありません。
JRAとしてもプロモーションの一環として力を入れており、レース前から大きな盛り上がりを見せる要素の一つとなっています。
枠順の色と意味
競馬では、枠順ごとに特定の色が割り当てられており、1枠から8枠までそれぞれ異なる色が使われています。
この色分けは、パドックや本馬場入場、レース中の実況やテレビ観戦でも馬を識別しやすくするために用意されているものです。
特に出馬表や新聞、レース映像などで馬の視認性を高める役割を担っており、競馬ファンや関係者にとって非常に重要な情報となっています。
ここでは、枠順と色の対応、および馬番との関係について詳しく解説します。
枠ごとの色分け一覧
日本の競馬は中央競馬も地方競馬は、枠順の番号ごとに下記のような色が固定で割り当てられています。
この色はすべての競馬場・レースにおいて共通で、地方競馬でもほぼ同様の配色が採用されています。
特に、ジョッキーが被る帽子に枠番の色が反映されているため、遠目に見てもおおよそどの馬か判別可能です。
日本競馬における枠番と色は下記で統一されています。
| 枠番 | 色 |
|---|---|
| 1枠 | 白 |
| 2枠 | 黒 |
| 3枠 | 赤 |
| 4枠 | 青 |
| 5枠 | 黄 |
| 6枠 | 緑 |
| 7枠 | 橙 |
| 8枠 | 桃 |
たとえば「3枠5番」の馬は赤色の帽子をかぶり、赤色の帽子で出走します。
ただし、同じ5番でも8頭立ての場合は「5枠5番」となり、黄色の帽子で出走します。
この色分けは競馬を視覚的に楽しむための工夫として、非常に効果的に使われています。
馬番ごとの色分け一覧
馬番と枠順の対応は、出走頭数によって少しずつ異なります。以下に一般的な最大18頭立ての場合の色分け一覧表をまとめます。
| 頭数 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8頭以下 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 |
| 9頭 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8,9番 |
| 10頭 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7,8番 | 9,10番 |
| 11頭 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6,7番 | 8,9番 | 10,11番 |
| 12頭 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5,6番 | 7,8番 | 9,10番 | 11,12番 |
| 13頭 | 1番 | 2番 | 3番 | 4,5番 | 6,7番 | 8,9番 | 10,11番 | 12,13番 |
| 14頭 | 1番 | 2番 | 3,4番 | 5,6番 | 7,8番 | 9,10番 | 11,12番 | 13,14番 |
| 15頭 | 1番 | 2,3番 | 4,5番 | 6,7番 | 8,9番 | 10,11番 | 12,13番 | 14,15番 |
| 16頭 | 1,2番 | 3,4番 | 5,6番 | 7,8番 | 9,10番 | 11,12番 | 13,14番 | 15,16番 |
| 17頭 | 1,2番 | 3,4番 | 5,6番 | 7,8番 | 9,10番 | 11,12番 | 13,14番 | 15,16,17番 |
| 18頭 | 1,2番 | 3,4番 | 5,6番 | 7,8番 | 9,10番 | 11,12番 | 13,14,15番 | 16,17,18番 |
なお、8頭以下立ての場合は1枠〜8枠に1頭ずつが入るため、馬番=枠番となります。
9頭立て以上のレースの場合は外枠から1頭ずつ追加されます。
枠順の有利不利とは?
競馬において枠順は、単なるスタート位置の違いではなく、実際のレース結果にも大きく影響を及ぼします。
コースの形状や距離、芝・ダートの違い、さらには出走頭数や馬の脚質など、さまざまな条件によって枠順の有利不利が変わってきます。
ここでは、枠順によって有利・不利が生まれる代表的な要因や、具体的なコースの傾向を見ていきましょう。
コースによって異なる有利枠
競馬の枠順による有利不利は、各競馬場のコース形状によって大きく異なります。
たとえば、中山競馬場の芝,1600mはスタート直後に急カーブがあるため、内枠の馬がコーナーをロスなく回れる分、有利とされています。
一方で、東京競馬場の芝2,400mなどはスタートしてから最初のコーナーまでが長いため、枠順の有利不利が出にくい傾向にあります。
ダートの場合、特に短距離の1,200m戦や1,400mは芝スタートで外枠のほうがスピードに乗りやすい芝の部分が多いことから外枠有利とされるケースもあります。
新潟の芝1,000m通称【千直】も芝の痛みのない外ラチをスムーズに狙える外枠が有利と言われています。
このように、コースごとの傾向を知っておくことで、枠順の影響を加味した馬券選びができるようになります。
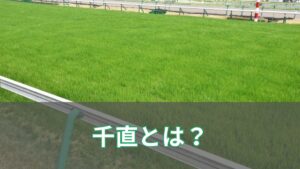
有馬記念における枠順の重要性
G1の中でも特に注目度が高い有馬記念では、枠順がレース展開を大きく左右することが知られています。
舞台となる中山競馬場の芝2,500mコースは、スタート直後にカーブがある特殊な形状をしており、外枠の馬は不利になりやすい傾向があります。
実際、過去の有馬記念では1枠や2枠などの内枠から好走する馬が多く、枠順が勝敗を分けることも少なくありません。
また、年末の大舞台ということもあり、ファン投票で選ばれた人気馬が内枠を引いた場合は、それだけで馬券の売れ方やオッズにも影響が出るほどです。
特に先行タイプの馬にとっては、内枠を引けるかどうかが勝敗を分ける要因になりやすく、レース前から注目が集まります。
有馬記念では、公開枠順抽選会も開催されることから、枠順は単なるスタート位置以上に“演出”としての役割も果たしています。
枠順を馬券予想に活かすには
競馬予想において、枠順の情報をうまく活用することは非常に重要です。
枠順だけで馬券の当否が決まるわけではありませんが、他の要素と組み合わせることで、より信頼性の高い予想につなげることができます。
特に脚質との相性や、コースごとの傾向を把握しておくことで、人気馬の取り捨てや穴馬の発見にも役立つでしょう。
ここでは、枠順と脚質の関係を中心に、予想への活かし方を紹介します。
枠順+脚質の組み合わせを読む
枠順だけで有利・不利を判断するのではなく、各馬の脚質と組み合わせて考えることが予想では重要です。
たとえば、逃げや先行タイプの馬は、内枠を引くとスムーズにハナを奪えるため有利になりやすいです。
逆に、差し・追い込み馬は外枠の方が他馬に包まれにくく、じっくりと自分のリズムでレースを進めやすい傾向があります。
また、スタートが速い馬であれば、外枠でもすぐに先行集団に取り付けるケースもあるため、単純な内外だけでなく、スタート力や位置取りの適性も加味する必要があります。
馬柱や調教コメントから脚質を確認し、その馬が引いた枠とどれだけ噛み合っているかを見ることが、精度の高い予想につながるポイントです。
展開予想と枠順の関係性を読み解くことで、思わぬ高配当につながるヒントを得られることもあります。
枠順とは?まとめ:予想にも観戦にも役立つ基本知識
この記事では、競馬における「枠順」の基本から、有利不利の傾向、色分けや抽選方法まで幅広く解説してきました。
枠順は、単なる数字の並びではなく、スタート位置や展開を左右する重要なファクターです。
コース形状や馬の脚質と組み合わせて考えることで、予想の的中率や精度を高めることも可能になります。
また、有馬記念のように、枠順そのものがイベントになることもあり、競馬を観戦する上でも楽しみの一つとなっています。
初心者の方はまず、枠順の意味と仕組みを理解することから始めてみましょう。
そして慣れてきたら、有利不利や脚質との相性まで踏み込んでみることで、より深い競馬の世界を味わえるようになります。