競馬で使用される芝コースには、大きく分けて「野芝」と「洋芝」の2種類があります。
芝の種類によってコースの性質や馬の走りやすさが変わり、「野芝と洋芝の違い」について知ることは競馬予想にも役立ちます。
本記事では、野芝と洋芝の基本的な違い(芝草の構造・生育環境・馬場傾向)や、各競馬場の芝構成、さらに芝の種類と馬の走法(ピッチ走法・ストライド走法)や適性の関係性、そして洋芝の馬場が「重い」(時計がかかる)と言われる理由について、初心者にもわかりやすく解説します。
野芝と洋芝とは?基本的な特徴と違い
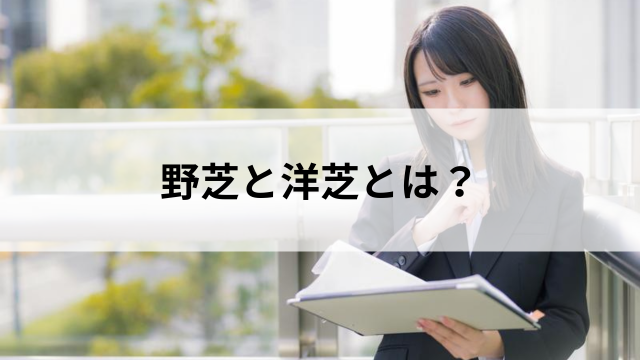
まずは野芝(日本在来の芝)と洋芝(西洋由来の芝)とは何か、それぞれの特徴を見ていきましょう。
「野芝」とは日本各地に自生する暖地型の芝草で、主にノシバ(Zoysia japonica)が使われます。
一方「洋芝」は西洋原産の寒地型芝草の総称で、競馬ではケンタッキーブルーグラスやトールフェスク、ライグラスなどの品種が利用されています。
それ以外にも、野芝と洋芝には下記のような違いがあります。
生育気候の違い
野芝は高温多湿の日本の夏に強く、真夏でも旺盛に生育する反面、冬になると休眠して葉が枯れ色(黄褐色)になります。
洋芝は寒冷な気候に強く、冬でも緑色を保ち低温下でよく成長しますが、暑さに弱く高温の夏には生育が衰えます。
簡単に言えば、野芝は夏に強く冬に弱いのに対し、洋芝は冬に強く夏に弱い性質があります。
芝草の構造の違い
野芝は地下茎を横に伸ばして密な芝生マットを形成する「ほふく茎」を持ち、地面を這うように広がります。
芝丈も短めで、競馬場では刈り揃えて約6〜8センチ前後の長さで管理されることが多いです。
一方、洋芝は種から育てる芝で、ケンタッキーブルーグラスは野芝同様に地下茎を持ち強度を担いますが、トールフェスクやライグラスは株立ち状に生育し、そのままだと雑草のように背丈が高く(10〜15cm以上)伸びます。
競馬場では洋芝も短く刈り込んで芝生状態にしますが、野芝より芝丈は長めとされています。
馬場コンディションへの影響(速さ・クッション性)
野芝の芝コースは表面が硬く締まった馬場になりやすく、馬にとっては地面からの反発力を得やすいのでスピードが出やすい(時計が速い)傾向があります。
一方で洋芝のコースは芝丈が長く密度もあるため走る抵抗が大きく、馬の脚が取られやすい(踏み込みに力が要る)のでスピードが出にくく時計がかかる傾向があります。
その代わり洋芝は芝そのものにクッション性があり、着地の衝撃を和らげるため馬の脚に優しいとも言われます。
要するに、野芝=「軽い」高速馬場、洋芝=「重い」持久力馬場というイメージです。
耐久性・管理の違い
野芝は丈夫で踏圧に強く、夏場の競馬開催でも芝生が剥がれにくい利点があります。
一方、洋芝は総じて繊細で耐久性では野芝にやや劣り、連続開催で芝が傷み剥がれると馬場が荒れてさらに時計がかかるケースもかつては見られました。
また前述の通り洋芝は乾燥や高温に弱く管理が難しいため、北海道以外の高温になる地域で年間を通じ洋芝だけで維持するのは困難です。これらを補うため、後述するオーバーシード(冬芝の播種)やエクイターフ(改良野芝などの工夫が行われています。
以上のような特徴をまとめると、野芝は暖地型で夏に強く速い馬場を作るが冬に枯れてしまう芝、洋芝は寒地型で冬も緑を保てクッション性が高いが高温に弱く馬場は重くなりがちな芝と言えます。
競馬場では季節に応じてこれらをうまく利用し、一年中レースができるよう芝コースを管理しています。
オーバーシードとは?
日本の主要競馬場では、「野芝」と「洋芝」を組み合わせて使うオーバーシードという手法が一般的です。
オーバーシードとは文字通り夏芝(野芝)が休眠する冬季に、冬芝(洋芝)の種を上から播いて一年中芝生を緑に保つ管理方法のことです。
具体的には、秋頃に野芝のコースにイタリアンライグラス(一年生の洋芝)など冬芝の種をまき、冬から春にかけてはその洋芝が生育して緑の芝馬場を提供します。
春〜初夏になると冬芝は高温で枯死し自然になくなるため、夏場は下層の野芝が主役になります。
これを毎年繰り返すことで、冬場でも芝コースを緑の良馬場で開催できるわけです。
このオーバーシードにより、「野芝+洋芝」のハイブリッド馬場が生まれます。
野芝が持つスピード能力と、洋芝のクッション性という両方の長所を活かせるため、「ある程度スピードが出せて、しかも馬の脚にも優しい」馬場になると言われています。
実際、東京競馬場や京都競馬場など多くの競馬場で採用されており、競走馬にとっても人間にとっても理想的なコースコンディションを維持しています。
もっとも、近年ではオーバーシード用の一年生洋芝だけでなく、JRAが開発した耐久性の高い改良野芝「エクイターフ」も導入されています。
エクイターフは野芝の一種ですが成長が早く根茎が強固で剥がれにくい特性があり、2008年に福島競馬場で初導入されて以降、札幌・函館を除く全国の競馬場で採用が進んでいます。
エクイターフ採用後は馬場の荒れが抑えられ、さらに高速化も進んだと言われます。つまり現在では、「野芝(エクイターフ)」+「洋芝(季節によってオーバーシード)」という構成が主流になりつつあります。
各競馬場の芝コースにおける芝種構成一覧

では、JRAの各競馬場では野芝と洋芝がどのように使われているのかを一覧表で見てみましょう。
実は札幌競馬場と函館競馬場の2場だけが特殊で、芝コースがオール洋芝となっています。
その他の本州以南の競馬場は基本的に野芝がベースですが、秋〜春開催時にはオーバーシードで洋芝も併用されています。
また新潟競馬場は冬期開催がないため野芝100%で維持されています。以下に主要競馬場の芝構成をまとめます。
| 競馬場 | 芝コースの芝構成 | 備考 |
|---|---|---|
| 札幌 (北海道) | 洋芝100% (寒地型多年生洋芝:ケンタッキーブルーグラス、トールフェスク、ペレニアルライグラス) | 野芝は寒冷地で育たないため洋芝のみ。「洋芝巧者」と呼ばれる洋芝適性の高い馬が活躍しやすい傾向。 |
| 函館 (北海道) | 洋芝100%(札幌と同じ洋芝3種混合) | 札幌と同様、オール洋芝のコース。洋芝は水分保持力が高く雨の影響を受けやすいため、函館では稍重〜重馬場になりやすいと言われる。 |
| 福島 (福島) | 野芝(土着&エクイターフ)+洋芝(オーバーシード) | 2008年にエクイターフを初導入した競馬場。野芝ベースに秋〜春はイタリアンライグラスを播種。 |
| 新潟 (新潟) | 野芝100%(エクイターフ) | 新潟開催は主に夏〜秋で冬開催なし。冬に枯れても問題ないため年間通じ野芝のみ使用。広大な直線と高速馬場で知られる。 |
| 東京 (東京) | 野芝(エクイターフ)+洋芝(オーバーシード) | 春・秋開催時にオーバーシード実施。世界レコードが度々出る高速馬場で有名(例:2018年ジャパンC 2400m 2:20.6)。 |
| 中山 (千葉) | 野芝(エクイターフ)+洋芝(オーバーシード) | 冬開催あり(1〜3月)なので冬芝をオーバーシード。中山は小回り急坂コースで、開催後半は野芝が傷んで時計がかかる。秋は全面野芝。 |
| 中京 (愛知) | 野芝(エクイターフ)+洋芝(オーバーシード) | 冬〜春開催あり。近年の改修で高速化。 |
| 京都 (京都) | 野芝(エクイターフ)+洋芝(オーバーシード) | 年始~春と秋に開催。オーバーシード採用。伝統的に「淀の高速馬場」と言われるが、冬~早春は洋芝が効き多少時計がかかる。 |
| 阪神 (兵庫) | 野芝(エクイターフ)+洋芝(オーバーシード) | 年間を通じ開催あり。春・冬シーズンは洋芝併用。梅雨時や開催後半は馬場が荒れやすく時計がかかる傾向。秋は全面野芝。 |
| 小倉 (福岡) | 野芝(エクイターフ)+洋芝)オーバーシード | 冬(2月)と夏(8月)に開催。冬開催に向けて洋芝を播種。夏は野芝全開で高速タイムも。 |
※地方競馬場では岩手の盛岡競馬場でも寒冷地のため洋芝が用いられていますが、ここでは主にJRAの中央競馬場について記載しています。
上記のように、「どこの競馬場が野芝で、どこが洋芝か」というと、札幌・函館のみ洋芝100%で、それ以外の競馬場は野芝主体+季節により洋芝併用という構成になっています。
これにより四季を通じた開催でも常に一定のクオリティの芝コースを維持できるわけです。
芝の種類と馬の走法・適性の関係性

芝コースの違いは、競走馬ごとの「走法」や「適性」にも影響を与えます。
競走馬の走法は大きくピッチ走法(細かいストライドで回転速く走るタイプ)とストライド走法(大きなストライドで伸びやかに走るタイプ)に分類されることがあります。
野芝のような高速馬場と、洋芝のような力の要る馬場では、この走り方の向き不向きが変わってくるのです。
ピッチ走法の馬
一完歩の歩幅が小さく足の回転が速いタイプで、頭の位置が高めで小柄な馬に多い走法です。
機動力がありコーナーリングが上手で、小回りコースや急坂も苦にしない器用さがあります。
こうしたピッチ走法の馬は稍重〜不良馬場など力の要る馬場を苦にせず、荒れた芝や洋芝コースでも安定した走りができる傾向があります。
実際、開催後半の荒れ馬場や重い洋芝を得意にする馬はピッチ走法であることが多く、馬場が渋ったときに台頭しやすいタイプです。
反面、一完歩が小さい分トップスピードの伸びは限界があり、直線の長い高速決着ではストライド型の馬に及ばないケースもあります。
ストライド走法の馬
一完歩の歩幅が大きく伸びやかなフットワークで走るタイプで、頭の位置が低く前傾姿勢で力強く地面を蹴ります。
スピードの持続力に優れ、中〜長距離のハイペース戦でも長く良い脚を使えるのが特徴です。
このタイプの馬は硬い良馬場で地面の反発力を最大限に活かし、大きなストライドで加速するため、東京や新潟のような直線の長い高速芝コースを得意とします。
しかし、その豪快な走りは馬場が緩むと滑ってパフォーマンスを発揮しにくくなる傾向があります。
実際に「良馬場で圧勝していた馬が洋芝の重い馬場で凡走する」ようなケースも珍しくなく、ストライド型の馬は洋芝や重馬場を苦手にすることが多いです。
走法によって適性が変わる
以上をまとめると、ピッチ走法の馬は野芝より洋芝向き(重い馬場も巧みにこなす)であり、ストライド走法の馬は洋芝より野芝向き(高速馬場で能力全開)と言えます。
もちろん馬それぞれの適性差はありますが、「洋芝巧者」と呼ばれる馬は総じて小刻みな走りでパワフルに地面を捉えるタイプが多いです。
例えば洋芝開催の函館記念を3連覇したエリモハリアーは「洋芝の鬼」とまで称されたほどで、札幌・函館で計6勝(通算9勝中)を挙げています。
逆に、芝2,400m世界レコードホルダーのアーモンドアイは切れ味重視の走法で知られ、欧州の深い芝では同じパフォーマンスは難しいとも言われました。そのため、世代トップの座に君臨しながらも欧州遠征は行っていません。
実際、フランスの凱旋門賞では日本のトップホースでも洋芝への適性が問われ、苦戦する例が多々あります。
このように馬場適性は走法や馬の体型・筋質にも関係し、「どの馬が野芝向きか洋芝向きか」を見極めることは予想上の重要なポイントになります。
血統面でも、欧州血統の産駒はパワー型で洋芝を苦にしない場合が多い一方、米国的なスピード血統は洋芝でスタミナ不足を露呈するケースがあるなど傾向があります。
ただし最終的には実際に走ってみないと分からない部分もあり、陣営も馬場状態を見て騎乗戦略を練るなど、洋芝・野芝それぞれへの対策を取っています。
洋芝の馬場はなぜ重い? 時計がかかる理由と具体例

最後に、よく言われる「洋芝の馬場は重い」(=タイムが遅くなる)理由について解説します。
上述の通り、洋芝コースは野芝コースに比べて走行抵抗が大きく、スピードが出にくいためですが、その背景には芝草の物理的な違いや気候条件があります。
いくつか、要員をまとめました。
芝の長さと密度の違い
洋芝は野芝より芝丈が長めに保たれるため、馬の蹄が芝生に沈み込みやすくなります。
いわばクッションの厚い絨毯の上を走るようなもので、蹄が踏み込むたびに抵抗がかかり推進力が奪われます。
その結果、一完歩ごとの進む距離が野芝よりわずかに短くなり、全体のタイムが遅くなるのです。
また洋芝は根と茎が絡み合ったマット層が厚く、この層がブレーキとなる面もあります。
一方、野芝コースは地表が硬く平坦なため蹄が沈まず、反発を得て滑るように走れるためタイムが速くなります。
保水性と馬場含水の違い
洋芝は芝生マットが厚く保水性が高いため、雨が降った際に水分を多く含みがちです。
下層まで水が浸透しにくく表面に水分が残りやすいため、稍重〜重馬場になりやすく、これも時計を要する要因です。
函館競馬場は洋芝100%で雨の影響を受けやすく重馬場に傾きやすいことが知られています。ただし同じ洋芝でも札幌競馬場はコース設計上水はけが非常に良く、不良馬場になったことがないほどです。
いずれにせよ、洋芝は乾燥していても芝そのものが柔らかくクッションが効くため、野芝良馬場ほどの硬い路面にはなりません。
実際のタイムの比較
洋芝と野芝のタイム差を具体的に示す例として、日本と欧州の芝コースの記録を比べてみましょう。
日本の東京競馬場(野芝+オーバーシード)で行われた2018年ジャパンカップ(芝2,400m)では、アーモンドアイが2分20秒6という世界レコードで走破しました。
一方、洋芝主体の欧州競馬の最高峰凱旋門賞(ロンシャン競馬場・芝2,400m)では、良馬場であっても例年2分25〜28秒程度かかっています。
過去最も速かったタイムでも2分23秒台(2017年シャンティイ開催時)で、日本の記録には及びません。
この差はコース形態やペースの違いもありますが、芝の違い(野芝はスピードが出やすく、洋芝は出にくい)によるところが大きいと指摘されています。
実際、「日本で無敵の馬がフランスの洋芝では力を発揮できなかった」というケースもあり、世界的に見ても日本の芝コースがいかに高速か(=洋芝がいかに時計を要するか)がわかります。
以上のような理由から、洋芝の馬場は「重い馬場」として位置づけられます。
野芝ベースの日本の主要競馬場では良馬場ならば速いタイムが出ますが、札幌・函館の開催や長雨で洋芝の比率が高まった馬場では、同じ距離でもタイムが遅くなる傾向があります。
競馬ファンの間でも「札幌や函館は洋芝だから時計がかかる」といった表現が使われますし、馬券検討でも洋芝開催では近走タイムの評価を割り引くなどの工夫がされています。
しかし、「重い」といっても決して悪いことばかりではありません。
洋芝のクッション性のおかげで馬の脚元への負担が軽減され、故障リスクが下がるメリットもあります。
また、スピードだけでなくパワーやスタミナが要求されるためレース展開に幅が出て、洋芝巧者と呼ばれる伏兵が活躍する面白さも提供してくれます。
逆に野芝の高速馬場はレコード連発で爽快ですが、その反面「高速すぎて馬の脚に負担が…」と懸念されたこともありました。
現在のJRAはエクイターフ導入などで適度にソフトな高速馬場を実現しつつありますが、洋芝と野芝それぞれの長所を活かしたコースづくりが求められています。
野芝と洋芝の違い:まとめ

野芝と洋芝の違い、その特徴や競馬への影響について解説してきました。簡潔に整理すると以下のようになります。
- 野芝(暖地型): 夏に強く冬に枯れる日本在来の芝。表面が硬く高速馬場になりやすい。馬の走破タイムは速くなる傾向だが、クッションが少なく脚への負担は大きめ。主に本州以南の競馬場でベースとして使用。近年はエクイターフと呼ばれる改良種も導入。
- 洋芝(寒地型): 冬も緑を保つ西洋芝。札幌・函館では洋芝のみを使用。クッション性が高く馬に優しい反面、芝丈が長く抵抗が大きいため時計がかかる馬場になる。寒冷地向きで高温多湿に弱い。多年草(ケンタッキーブルーグラス等)と一年草(ライグラス等)があり、本州の競馬場では主にオーバーシードで一年草洋芝を併用。
- 各競馬場の芝構成: 札幌・函館はオール洋芝、新潟は野芝100%。その他の競馬場は野芝主体で秋〜春に洋芝の種を播くオーバーシード方式。洋芝比率が高まる時期は馬場が重くなりやすいので注意。
- 走法・適性: ピッチ走法の馬は洋芝や道悪を得意とし、ストライド走法の馬は良馬場の高速決着を得意とする傾向。洋芝開催では普段実力伯仲のメンバーでも適性差で着順が入れ替わることがあり、洋芝巧者を見極めることが穴馬券のポイントになる。
- 洋芝が重い理由: 芝の物理的な抵抗・保水性の違いによりスピードが出にくいため。日本と欧州のタイム比較からも洋芝馬場の遅さが裏付けられる。しかし馬の負担軽減などメリットもある。
競馬において「芝コース」と一口に言っても、野芝と洋芝ではこれだけの違いがあります。
日本の競馬ファンにとっては普段あまり意識しない部分かもしれませんが、洋芝開催の夏競馬(札幌・函館)や道悪競馬ではこの知識が予想に役立つでしょう。
「野芝と洋芝の違い」を理解しておけば、例えば「この馬は洋芝替わりで一変しそうだ」や「時計のかかる馬場なら浮上する血統だ」といった考察もしやすくなります。
ぜひ芝コースの特性にも注目して、競馬観戦や予想をさらに楽しんでみてください。

