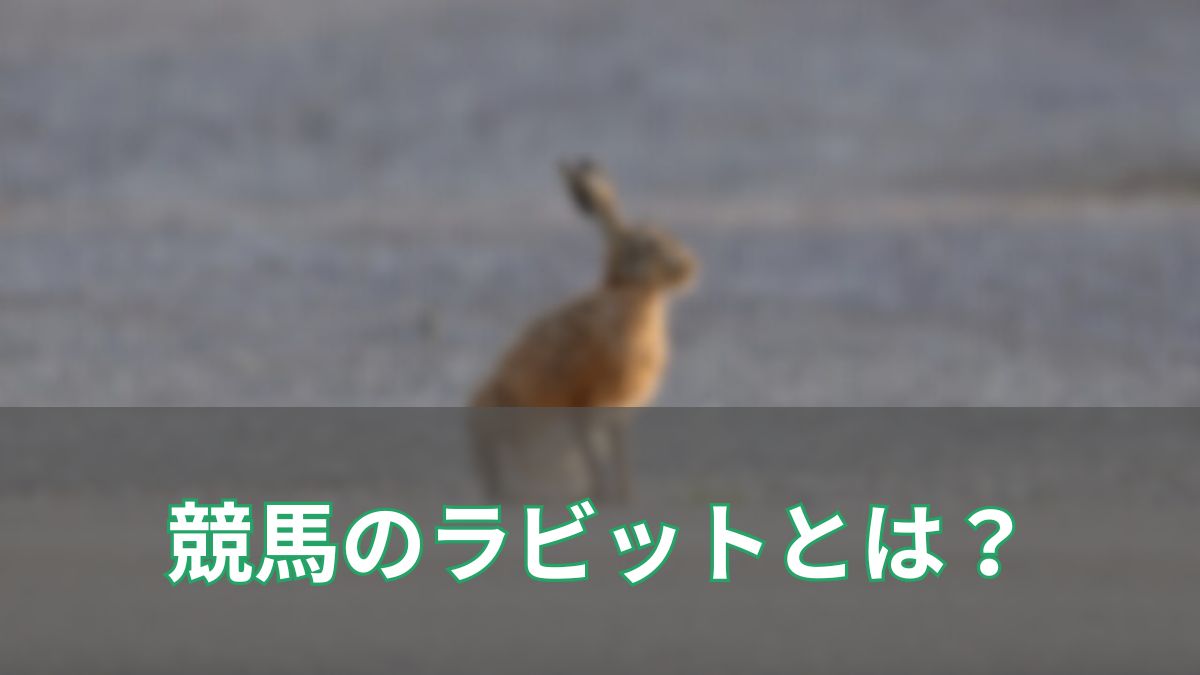競馬を見ていると、ときどき「ラビット」という言葉を耳にすることがあります。
ラビットは直訳のウサギではなく、レースの流れを作るために先行してペースを引っ張る役割を担う馬を指します。
欧州競馬では主力馬のために明確な「ペースメーカー」を置く戦術が一般的です。
一方、日本では公正競馬の観点から否定的に捉えられる場面が多く、「ラビット 禁止」というキーワードが検索される背景にもつながっています。
実際にはラビット自身が逃げ粘って勝利する例もあり、戦術と公正のせめぎ合いが話題になりやすい領域といえるでしょう。
ダイワスカーレットの名前とともに議論が再燃した時期もあり、ファンの間で「どこまでが戦術で、どこからが禁止なのか」という線引きが注目されました。
本記事では「競馬 ラビットとは」を軸に、意味や事例、海外と日本の違い、ルール面の考え方までを整理します。
競馬におけるラビットとは?
ラビットという言葉は、競馬における「ペースメーカー役」を意味します。
単に逃げ馬と同じではなく、主力馬の走りをサポートする目的を持って先頭に立ち、意図的にレースの流れを作る点に特徴があります。
特に欧州競馬では、名門厩舎が勝たせたい馬のためにラビットを用意することが一般的で、戦術として定着しています。
一方で日本競馬においては、ラビット行為が公正競馬に反すると見なされやすく、明確に禁止の対象となる場合もあります。
そのため「競馬 ラビットとは」というテーマは、国や文化ごとの競馬観の違いを理解するうえで重要な要素となります。
ラビットの意味
ラビットは、本来勝利を狙うのではなく、他の馬のためにレースを先導する役割を担います。
スタートから積極的にハイペースを作ることで、後ろに控えるエース馬の得意な展開を引き出したり、ライバルの脚を削るのが目的です。
「逃げ馬」との違いは、逃げ馬が自らの勝利を狙うのに対し、ラビットはあくまで味方の勝利を後押しすることにあります。
欧州では戦術として広く認められており、観客も自然に受け止めていますが、日本では「八百長に近い行為」とみなされやすいため議論を呼ぶ存在となっています。
ラビットと勝利の関係
ラビットは基本的に勝つための馬ではありません。
しかし競馬は生き物同士のレースであるため、想定外の展開になることがあります。
逃げたラビットが後続を突き放してしまい、そのままゴール板を駆け抜けて勝利するケースもごくまれに見られます。
このような「ラビット勝利」はファンの間で話題になり、戦術としての面白さや不公平感の両面で議論を生み出してきました。
本来の役割と結果のギャップがあるからこそ、ラビットは競馬において注目され続ける存在といえるでしょう。
日本競馬におけるラビットの扱い
日本競馬では「ラビット」という存在が特に話題になりやすいです。
欧州では当たり前の戦術として受け入れられているものの、日本では公正競馬の理念に基づき、ラビット行為を認めない方針が取られてきました。
ただし完全に存在しなかったわけではなく、実際に過去のレースでは「ラビットではないか?」と議論を呼んだ事例もあります。
ファンやメディアで取り上げられ、ルールや解釈について議論が繰り返されてきたのです。
ここでは、過去のラビットの例を二つ紹介した上で、ラビットが禁止されている理由について解説します。
2008年天皇賞(秋)のダイワスカーレット
2008年11月2日の天皇賞(秋)は、ウオッカ・ダイワスカーレット・ディープスカイが激突した「三強対決」として大きな注目を集めました。
このレースで先手を取ったのはダイワスカーレットでしたが、彼女には厳しい条件がそろっていました。大阪杯以来の休み明け、初の東京コース、さらにパドックからテンションが高く発汗が目立っていたのです。
加えて、ウオッカと同じ角居厩舎のトーセンキャプテンが序盤から執拗に競りかけ、逃げ馬にとって大きなプレッシャーとなりました。
結果として「ウオッカのためのラビット役を果たしたのではないか」とファンや関係者から指摘され、松田国調教師もペリエ騎手の騎乗を皮肉交じりに批判しています。
レースは直線でウオッカ、ディープスカイが迫り、壮絶な叩き合いに。最終的には写真判定の末、わずか2センチ差でウオッカが勝利。
しかし、この時のトーセンキャプテンの動きは「ラビットではないか」という議論を呼び、日本競馬におけるラビットの是非が改めて注目されるきっかけとなりました。
2016年有馬記念でのサトノダイヤモンドとサトノノブレス
第61回有馬記念(2016年12月25日、中山芝2,500m)は、3歳馬サトノダイヤモンドが1番人気に支持され、キタサンブラックやゴールドアクターらと激突する大一番となりました。
逃げを宣言していたマルターズアポジーが先頭を奪い、キタサンブラックはその直後を追走。サトノダイヤモンドは中団外目からレースを進めていました。
勝負どころとなったのは向正面から3コーナーにかけてです。
ここで同じ池江厩舎のサトノノブレス(騎乗:シュミノー)が外から一気に進出し、キタサンブラックを急追。結果的にキタサンにプレッシャーを与え、ペースを早めさせる展開を作りました。
この場面について、武豊騎手は「あのワンプレーが痛かった」と語り、サトノノブレスがチーム戦術的に動いたことを示唆しています。
実際、シュミノーはレース中に何度も後方を振り返り、僚馬サトノダイヤモンドの進路を塞がないよう意識していた様子がパトロールビデオから確認できました。
最終的に直線でサトノダイヤモンドが鋭く伸び、キタサンブラックとゴールドアクターを差し切って勝利。
サトノノブレスは11着に敗れましたが、その役割は「ラビット的な動き」として議論を呼びました。
この一戦は、日本でもラビットに近い“チームプレー”が存在するのではないかという疑念を残し、公正競馬の観点から「どこまで許されるのか」が再び話題になったレースといえます。
日本でラビットが禁止されている理由
日本競馬においてラビットが明確に禁止されているのは、「公正競馬」の理念を守るためです。
本来、すべての出走馬は自らの勝利を目指して全力で走るべきとされています。
ところが、ラビットの存在は「特定の馬を勝たせるために走る馬」がいることを意味し、馬券を購入するファンからすれば不公平な要素となってしまいます。
JRAは長年「八百長や出来レース」と誤解される行為を強く排除してきました。
騎手や調教師が意図的にペースメーカーを仕込むことが発覚すれば、処分や制裁の対象となります。
特に日本は馬券の売上が競馬の基盤であり、ファンの信頼を損ねる行為は即座に競馬そのものの信用低下につながるため、欧州と比べても厳格な姿勢が取られているのです。
もっとも、2008年の天皇賞秋や2016年の有馬記念のように「実質的にラビットではないか」と議論されるケースはあります。
しかし、それはあくまで「偶然の展開」や「チーム戦術の一環」とされるにとどまり、公にラビットを認めることはありません。
つまり、日本競馬では「全馬が勝利を目指す」という建前を絶対に崩さないことで、公平性とファンの信頼を守っているのです。
欧州・海外競馬におけるラビット
日本では禁止されているラビットですが、欧州や海外競馬では戦術の一部として広く認められています。
特にアイルランドやイギリスでは、名門厩舎が主力馬を勝たせるために明確にペースメーカーを出走させることが一般的です。
観客や馬券購入者も「それが作戦のひとつ」と理解しているため、文化として根付いている点が日本との大きな違いです。
ここからは海外競馬におけるラビットについて解説します。
欧州競馬でのラビットの役割
欧州競馬では「レースの質を高めるため」にラビットが起用されます。
例えば、名門オブライエン厩舎はクラシックや国際G1に出走させる際、主力馬のために複数頭を送り込み、その中の1頭がラビット役を担うケースが多く見られます。
ハイペースで流れを作り、実力馬に適した展開を演出することは当然の戦略とされており、むしろラビットなしではスローペースになってレースの見応えが減るとさえ考えられています。
そのため、欧州ではラビット役の存在が「レースを盛り上げる要素」として肯定的に受け止められる傾向が強いのです。
海外と日本のラビットの違い
欧州でのラビットが戦術として浸透しているのに対し、日本では「公正競馬」を損なうとして禁止されています。
海外では「厩舎のチームプレー」として理解されるのに対し、日本では「馬券購入者への裏切り」と解釈されるため、文化や制度そのものが異なります。
また、欧州の大レースは馬主や厩舎の意向が強く反映されるのに対し、日本の競馬は公営ギャンブルとしての透明性を重視しており、ラビットを公式に認めることはありません。
この違いは、競馬が「スポーツ」として発展した欧州と、「公営競技」として発展した日本の歴史の差が表れているといえるでしょう。
競馬におけるラビットの是非を考える
ラビットは競馬に深みを与える一方で、公平性を揺るがす存在として常に議論の対象となってきました。
欧州では「戦術」として自然に受け入れられているのに対し、日本では「公正競馬の妨げ」として排除されている点に、その賛否の分かれ目があります。
ファンにとっても「展開を読む上で重要な要素」として肯定する声があれば、「馬券購入者を欺く行為だ」と否定する声も根強いのです。
果たしてラビットは必要か、それとも不必要なのか、考えます。
ラビットは必要か不必要か?
ラビットを肯定する意見としては、以下のようなものがあります。
・主力馬の能力を最大限に引き出すために必要な戦術
・スローペースによる凡戦を防ぎ、レースの質を高める効果がある
・観戦する立場からすると迫力ある展開が見られる
一方で否定的な意見も少なくありません。
・ラビットは「勝利を目指さない馬」であり、公平性を欠く
・馬券を購入するファンにとっては、想定外の不利益を被るリスクがある
・騎手や厩舎のチームプレーが強すぎると「出来レース」と見られ、競馬の信頼性を損なう
つまり、ラビットは競馬の魅力を広げる存在でもあり、公正を揺るがす要素でもある両面性を持っています。
日本で禁止され、欧州で受け入れられているのは、それぞれの競馬文化と制度の違いを如実に示しているといえるでしょう。
ラビットのまとめ
「ラビット」とは、主力馬を勝たせるためにペースを作る役割を担う馬のことです。
欧州競馬ではチーム戦術として自然に用いられ、名門厩舎が積極的にラビットを投入することで、レースの質を高めることにもつながっています。
一方、日本では「公正競馬」を重視する立場からラビットは明確に禁止されており、公式に認められることはありません。
それでも2008年天皇賞秋(ウオッカvsダイワスカーレット)や2016年有馬記念(サトノダイヤモンドとサトノノブレス)といったレースでは、ラビット的な走りが議論を呼んできました。
ラビットは競馬を奥深くする戦術であると同時に、公平性を揺るがす存在でもあります。
どちらの立場に立つかで評価は分かれますが、この存在を理解することで競馬の見方がより広がり、展開を読む楽しみも増えるでしょう。