競走馬や乗用馬において、見過ごせない健康トラブルの一つが「食道閉塞(しょくどうへいそく)」、いわゆる「チョーク」と呼ばれる症状です。
これは、馬の食道に餌や異物が詰まり、飲み込めなくなる状態を指します。
場合によっては重篤な合併症を引き起こすこともあり、早期の発見と適切な処置が欠かせません。
本記事では、食道閉塞の原因や症状、治療法から、実際にこの症状を患った競走馬の例まで詳しく解説します。
食道閉塞とは?
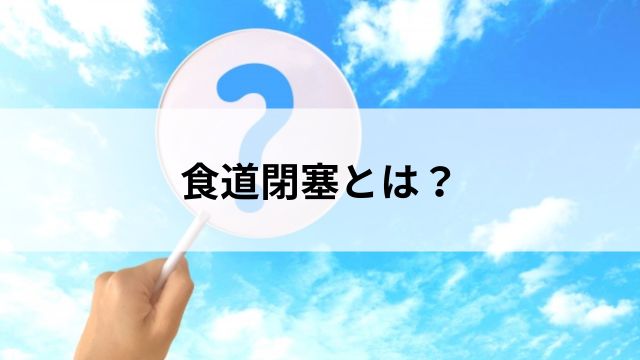
食道閉塞とは、馬の食道に餌や異物が詰まり、飲み込めなくなる状態を指します。競馬関係者のあいだでは「チョーク」とも呼ばれ、緊急対応が必要な疾患の一つです。
馬は人と違って嘔吐ができないため、食道に物が詰まると逆流して鼻から唾液や餌が出たり、苦しそうに咳き込む様子が見られます。
長時間放置すると誤嚥性肺炎などの合併症を引き起こす可能性があり、早期発見と迅速な処置が求められます。
食道閉塞の原因とリスク
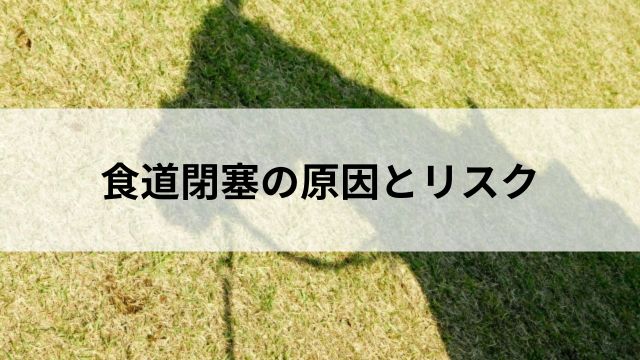
馬の食道閉塞は、日々の飼養管理の中に潜むさまざまな要因によって引き起こされます。
とくに餌の種類や与え方、咀嚼の問題、さらには輸送時のストレスなどが密接に関係しており、ちょっとした油断が重度の閉塞につながることもあります。
ここでは代表的な4つの原因と、そのリスクについて詳しく見ていきましょう。
咀嚼不足と速食い
歯の不整合や老化によって、馬が餌を十分に噛めなくなると、大きな餌の塊をそのまま飲み込んでしまい、食道内で詰まりやすくなります。
また、環境の影響で落ち着きなく急いで食べる「速食い」をする馬も要注意です。
とくに競走馬や繊細な性格の馬は、他馬との食事競争や精神的緊張から咀嚼が雑になりやすく、閉塞のリスクが高まります。
餌の種類・乾燥飼料
乾燥したペレットやビートパルプ、細断チモシーなどは、食道内で水分を奪われやすく、塊になって閉塞を引き起こす危険があります。
とくに水を飲まずに乾飼料を急いで食べた場合や、戻し忘れたビートパルプをそのまま与えた場合などは高リスクです。
一見、栄養価の高い飼料でも、与え方を誤れば大きなトラブルにつながります。
異物の誤飲
馬が敷料の麦わらや木片、干し草の芯などを噛まずに飲み込んでしまった場合、これらが食道に引っかかることがあります。
また、にんじんやりんごといったご褒美を丸ごと与える習慣も、実は危険です。
とくに切り方が雑だったり、大きすぎる塊は詰まりやすく、誤飲による閉塞は予防できるケースが多いのが特徴です。
輸送やストレス
長距離輸送や環境の急変によって、馬が極度の緊張状態になると、水分摂取量が減り、胃腸の働きも鈍くなります。
その結果、食道の動きが鈍くなり、詰まりやすくなるのです。
とくに、競走馬の遠征中やレース当日のストレスは見過ごされがちですが、食道閉塞の大きな誘因になり得るため、事前の対策が重要です。
食道閉塞の症状と診断・治療方法

食道閉塞は、早期発見と迅速な処置が何より重要です。
発症すると馬は急激に苦しみ出し、鼻からの逆流や異常行動など目に見える症状が現れます。
見逃すと誤嚥性肺炎などの合併症を引き起こすリスクもあり、治療が遅れるほど深刻な状態に陥ります。
ここでは、食道閉塞の代表的な症状と、獣医師による診断方法、そして治療の流れについて詳しく解説します。
食道閉塞の診断方法
診断はまず外見的な観察から始まります。視診では、鼻孔から泡立った唾液や未消化の餌が逆流しているかを確認し、触診では頸部に腫れやしこりがないかをチェックします。
次に、胃チューブを鼻孔から挿入し、胃までスムーズに通過しない場合は、途中で閉塞が起きていると判断されます。
さらに詳細を調べるためには内視鏡検査が行われ、カメラを使って食道内の閉塞物の位置や大きさ、粘膜の損傷の有無まで確認できます。
また、必要に応じてエコー検査を併用し、外からは見えない頸部内部の状態や周囲組織の炎症、腫脹の有無などを把握します。
これらの診断手法を組み合わせることで、正確な位置と状態を把握し、最適な治療方針を決定していきます。
食道閉塞の治療方法
治療はまず、閉塞の悪化や誤嚥を防ぐために、餌や水の摂取を完全に止める「絶食・絶水」から始まります。
次に、鎮静剤や筋弛緩薬を投与して、馬の緊張を和らげつつ、食道のけいれんを抑え、自然排出を促します。
それでも詰まりが解消されない場合は、胃チューブを使ってぬるま湯をゆっくり注入する「温水ラバージュ」を行い、閉塞物を柔らかくして流し出す処置が行われます。
多くのケースはここまでで解消しますが、重度の場合は立位での処置が難しく、全身麻酔下での対応が必要になります。
このときは内視鏡を用いて閉塞物を直接除去するか、最終手段として食道を切開する外科的手術が実施されることもあります。
症状の程度によって処置の難易度が大きく変わるため、いかに早く異常に気づくかが治療成否の鍵となります。
食道閉塞のリスク
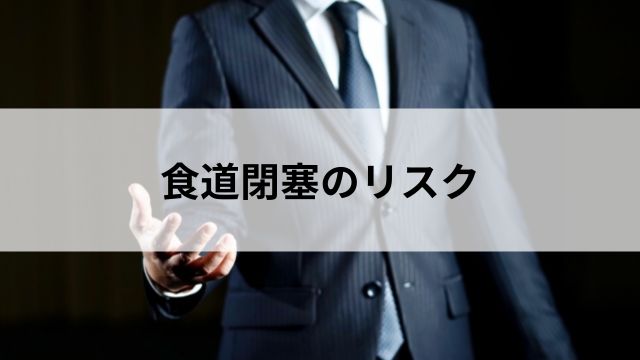
食道閉塞は、単に「食べ物が詰まっただけ」と軽視することのできない、深刻な二次被害を引き起こす可能性がある疾患です。
とくに注意すべきリスクのひとつが、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)です。
これは、逆流した唾液や餌の成分が気管から肺に入ってしまい、細菌感染によって肺が炎症を起こす状態で、治療が遅れれば命に関わる恐れもあります。
また、食道に長時間異物が留まると、粘膜が炎症や潰瘍を起こし、治癒後に狭窄(きょうさく)が残ることがあります。
この狭窄により、食道が再び詰まりやすくなるという悪循環が生まれ、慢性的な閉塞症状に発展するケースも見られます。
さらに、閉塞による唾液の流出と飲水不能によって脱水や電解質バランスの異常が生じ、体調全体に悪影響を及ぼすこともあります。
まれではありますが、放置や過剰なチューブ処置などにより食道が破裂するケースも報告されており、この場合は外科手術でも救命が困難です。
食道閉塞は、適切に対処すれば回復が見込める一方で、対応が遅れれば重篤な状態に陥るリスクも高い疾患といえます。
したがって、予防と早期対応が最も重要なポイントとなります。
食道閉塞を患ったメイショウハリオの例

2025年7月、G1レース「帝王賞」に出走登録していたメイショウハリオが輸送中に食道閉塞を発症し、急きょ競走除外となる事態がありました。
岡田調教師によると「初めての症状で、発汗や発熱が見られた」ようです。
その後、獣医師の判断により抗生剤などを用いた初期治療が行われ、発熱も収まり、誤嚥性肺炎を防ぐためのケアが続けられました。
幸い症状は軽度で済み、現在は安静にしながら回復が進んでいます。
この一件からも、輸送ストレスや水分管理の重要性が改めて浮き彫りになりました。
食道閉塞のまとめ

馬の食道閉塞は、見た目以上に深刻な疾患であり、放置すると誤嚥性肺炎や再発リスクを伴います。
速食いや乾燥飼料の与え方、歯の健康状態など、日常管理の中で予防可能な要因が多いため、飼育者や厩舎関係者は特に注意が必要です。
実際に競走馬でも発症するほど一般的な病気であり、症状を見逃さず、早期の対応が命を守るポイントになります。

