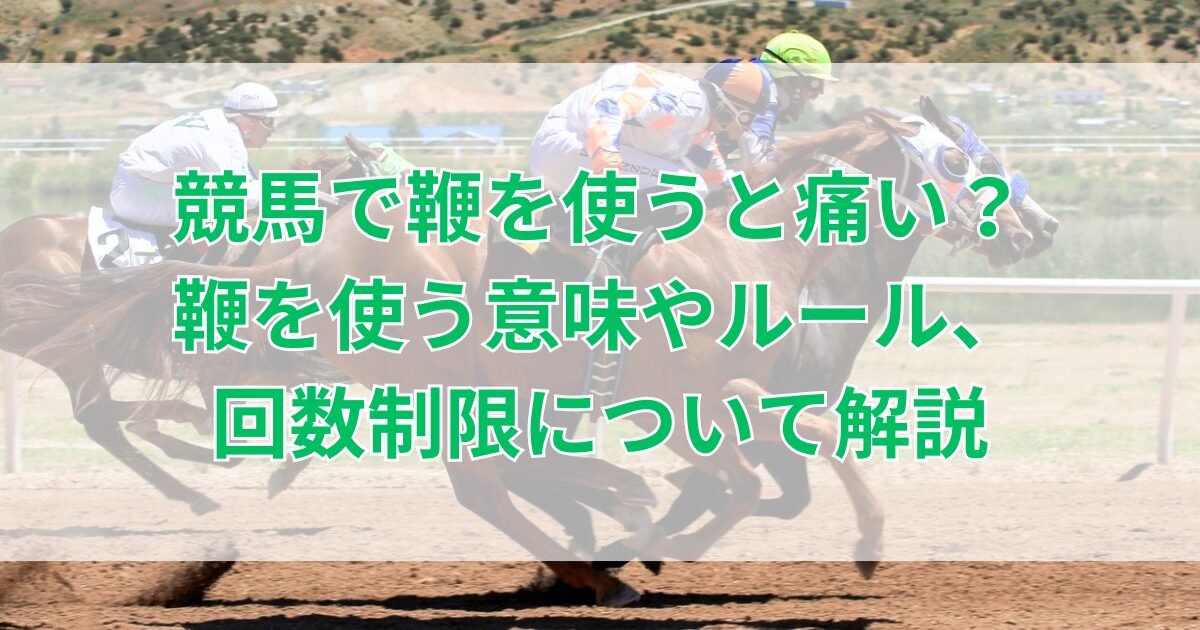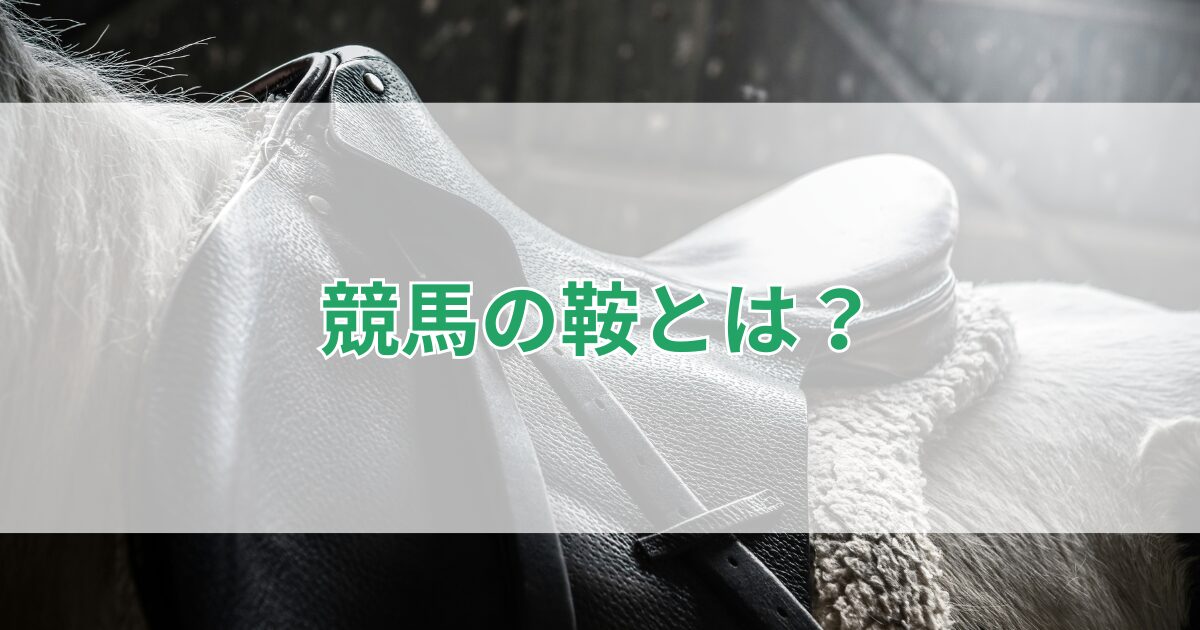競馬において、競走馬が身に着けている鞍はレースに欠かせない道具です。
しかしながら、競馬になじみが薄い方からしたら、鞍の役割や重要性についていまいち理解しづらいかもしれません。
そこで、当記事では競走馬の鞍の役割や種類、重さについて解説します。
人間と馬と鞍の歴史について
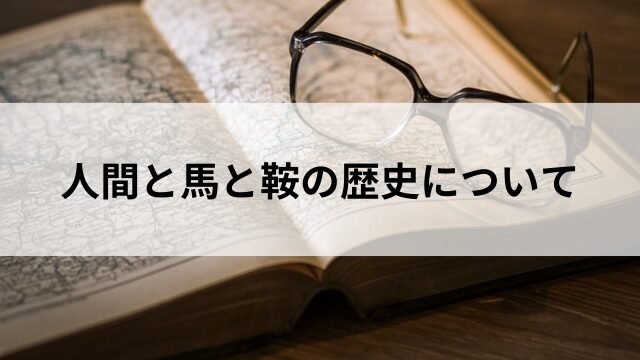
少し話は脱線しますが、最初に人間と馬の歴史に軽く触れます。
人間と馬のかかわりは、古くからありました。
例えば日本では戦国時代の武将が馬上で指揮を執る姿が象徴的ですし、中国の三国志においても、武将が馬に乗って敵陣に突入する勇ましい姿が描かれています。
そして、西洋の歴史においても例外ではなく、フランスの画家、ジャック=ルイ・ダヴィッドが描いた「アルプス越えのナポレオン」は、ナポレオンが愛馬マレン後にまたがる姿を捉え、広く知られました。
近代史に目を向けると、明治時代の北海道開拓では、ばん馬が農耕作業で重要な役割を果たし、日露戦争では、伊予松山(愛媛県)出身の秋山好古が日本近代史初となる騎兵隊を創設し、活躍しました。このお話は司馬遼太郎さんの代表作である「坂の上の雲」に詳しく書かれています。
このように、馬と人との関わりは歴史を通じて深まってきましたが、馬の骨格は人を乗せるために特化してはいません。何も装着せずに馬の背中に直接乗ることは不安定であり、馬にも負担がかかります。
そこで登場したのが、鞍をはじめとする馬具なのです。
鞍は、人が安全に乗馬するための安定性を確保すると同時に、人の体重による馬への負担を軽減する役割を担っています。
古来から人間は馬と共生してきましたが、鞍は人間と馬が共に安全かつ快適に活動するための重要な道具だったのです。
鞍の種類と重さについて
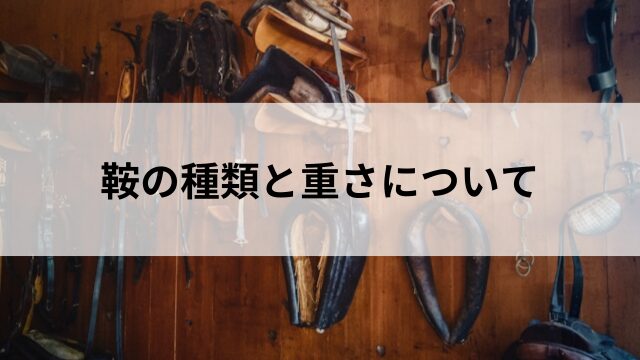
鞍にはさまざまな種類がありますが、競馬における鞍は大きく分けて2種類存在しています。
- 競馬鞍
- 障害鞍
また、それ以外の鞍としては馬場鞍と総合鞍という鞍もあります。
本章では競馬や競馬以外で使用される鞍について解説します。併せて鞍の素材についても紹介します。
鞍の素材
鞍を装着することで人が乗っても馬の負担は軽減されるようになりましたが、鞍自体はどのような素材を使われているのでしょうか。
現在の鞍は合成素材と革製を使用しており、革製は乗馬や調教で、合成素材の鞍はレースで使用するようです。
かつては木製の鞍が使用されていたようですが、硬くて重く、馬の背中に直接的な圧迫感を与えていたようです。
一方、革製の鞍は木製鞍と比較しても柔らかく、馬の背中にフィットしやすいため、圧力を分散する効果があります。
なお、レースで使う鞍もかつては革製でしたが、合成素材のほうが丈夫で軽いようなので、現在は合成素材が主流になっています。
競馬鞍
レースで使われている多くの鞍はこの競馬鞍です。レース鞍やレースサドルとも呼ばれます。
競馬鞍は一般的に1キロ弱のものが主流ですが、モノによっては500グラムや150グラムしかない鞍もあるようです。
体重制限がある騎手にとっては鞍の重さは死活問題につながるため、軽い鞍ほどいい鞍といわれています。
なお、競馬鞍は基本的に座る部分しかありません。
鐙(あぶみ・鞍の両わきに下げて脚をかけるもの)もつま先がわずかにかかる程度の大きさしかなく、素人ではとても扱えない代物です。
障害鞍
障害鞍は主に障害レースで使われています。
障害競走では平場とは違ってコース上に設置されたさまざまな障害を人馬一体となって乗り越えなければいけないので、後矯(こうきょう)と呼ばれる椅子の背もたれのようなものが付いています。
これは、障害を飛越した際、騎手が後ろの倒れるのを防ぐ安全装置です。
また、膝あての部分が柔らかく、あおり革がせり出しているのも特徴です。
これにより、騎手は膝をしっかりと固定でき、安定した前傾姿勢を取りやすくなります。
馬場鞍
馬場鞍は馬場馬術で使用する鞍です。
正反動という、お尻を鞍にくっつけたまま乗馬する乗り方に適した形状をしているのが特徴で、後矯(こうきょう)が長く、お尻が付く部分も深く、しっかりと座れるように設計されているため、騎手はバランスを取りやすく、長時間乗馬するのに適しています。
総合鞍
総合鞍という鞍もあります。
総合鞍は乗馬クラブなどで使用される鞍で、障害鞍と馬場鞍の良さを足して二で割った鞍です。
柔らかい素材でできており、乗馬に不慣れな初心者の方でも安心して使用できるのが特徴的です。
競馬における鞍の3つの役割
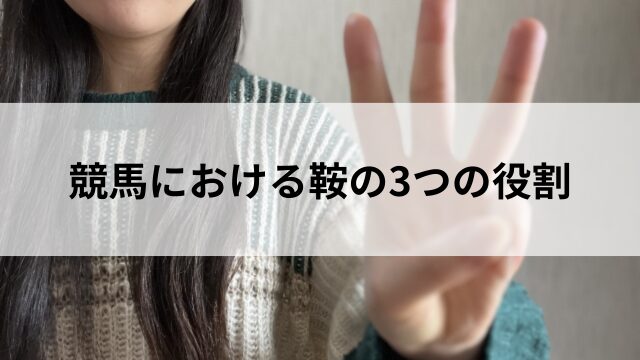
競馬における騎乗姿勢は、馬を両足で挟むようにして騎乗します。平場競走でも障害競走でも、完全に鞍に座るわけではなく、鐙(あぶみ)に足をかけて前かがみの姿勢で騎乗します。
これは、少しでも背筋が高いと風の影響を受けてしまうため、極力上半身を水平に近い形にするためです。スピードを最大限に発揮させるには、鞍も極力風の抵抗を受けない水平なものが採用されます。
ここで疑問に思うのは、鐙は存在理由が明確ですが、レース中に座らないのであれば鞍はそこまで重要なのかという点でしょう。鐙は足をぶら下げるために存在しますが、ぶら下げるだけなら鞍でなくても良いように思えます。しかしながら、鞍には鞍にしかない役割があるのです。
ここからは3つの鞍の役割について解説します。
負担を分散する
一つ目の役割は、負担を分散することです。
確かに、レース中は騎手が馬の背中に座る光景は見られません。
しかしながら、それ以外の場面、例えばパドックや誘導されているとき、ゲートに入って発走を待っている間、騎手は馬の背中に座っています。
確かに、パドックからレース発走までは時間がかかるため、ずっと鐙だけで身体を支えるのは騎手にとって負担でしかなりません。
また、鞍なしで座ると馬に座った時の反動がダイレクトに伝わるため、緩衝という意味でも鞍は役立っています。
安全性の向上
鞍は人馬の安全性も高めています。
レース中は自動車並みの速度で人馬ともにわずかな防具を付けて走るため、もしも落馬や転倒してしまったら大事故につながりかねません。
一つ上の見出しでも触れましたが、鞍には緩衝材という効果もあるため、仮に大事故になった場合でも鞍があった丘でげ重傷を避けられるケースも珍しくないのです。
もちろん、鞍を付けている競走馬だけではなく、騎手にとっても鞍はクッションとしての役割があるので安全面でも鞍は一役買っています。
斤量の調整で使われる
鞍は斤量調整する際も使用されます。
競馬のレースは主に定量戦と別定戦、ハンデ戦の3種類に分けられ、それぞれ斤量が異なります。
一日で複数のレースに騎乗する騎手にとって、毎回異なる斤量に対応できるのは、鞍の存在が大きいです。
騎手は自身の体重に加え、レースで定められた斤量分の鉄製鉛板を装備します。
鉛板の重さは決まっており、装着する枚数によって出走条件を満たします。
この鉛板は騎手が身に着けているプロテクターのポケットに入れるだけでなく、鞍の内側にも専用のポケットが付いているのです。
プロテクターに全ての鉛板を装備することも可能ですが、過度に装着するとレース中の動作が鈍くなってしまいます。
かといって、全ての鉛板を鞍に入れると今度は馬の動きが鈍るため、騎手はプロテクターと鞍に鉛板を分散しているのです。
このように、鞍は斤量調整においても重要な役割を担っています。
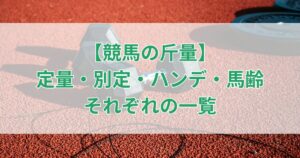
鞍の取り付けは苦しくない?

鞍は競馬にとって欠かせない馬具です。
しかしながら、競走馬にとって鞍を装着されるのは不快ではないのでしょうか。
正直なところ、競走馬にとって体に固定される鞍は不快です。これは、競走馬の中でもエリート集団といわれるJRAの馬にとっても例外ではありません。
しかしながら、レースを見ても鞍を嫌がる素振りは見せません。
実は、全ての競走馬はデビュー前に、鞍に慣れるためのトレーニングが行われています。なぜなら、鞍に慣れていない状態で無理やり鞍を装着させると、大暴れするからで、事故の原因につながるからです。
各厩舎では馬房内にあるストラップという革製の帯を鞍が取り付けられる場所に固定し、圧迫感に慣れさせます。
このストラップは、トレーニング中だけではなく、馬房内でも極力長時間装着することで、馬に鞍の感覚を覚えさせています。
こうして鞍に慣れればいきなり鞍を装着されても嫌がることが減ります。また、ストラップで強く固定されることに慣れているため、鞍でしっかり固定されても動揺せずに済むのです。
競馬の鞍 まとめ

今回は競馬の鞍についてまとめました。
騎手はレース中、鞍の上に座ることがないため、鞍の存在理由がよく分からなかった人も多かったかもしれません。
しかしながら、鞍には安全性向上や負担軽減、斤量調整など、装着することでさまざまな恩恵があるのです。
馬具の中で鞍はそこまで目立つものではありませんが、鞍が競馬に及ぼす役割は決して小さくありませんでした。
鞍のさまざまな役割を実感しながら、今後も競馬を楽しみましょう。