競馬ファンなら一度は疑問に思ったことがあるかもしれません。
「香港の競馬って、なぜセン馬ばかりなの?」と。
日本ではクラシック三冠をはじめ、多くのビッグレースが牡馬・牝馬限定で行われ、去勢されたセン馬は基本的にそうした舞台には立てません。
しかし、香港の馬の多くがセン馬として活躍しており、日本とはまったく異なるスタイルに驚く人も多いでしょう。
この記事では、「なぜ香港ではセン馬が主流なのか?」という疑問に対して、制度的背景や文化的な違い、さらには引退後の扱いや、セン馬以外の馬の存在など、さまざまな角度から解説していきます。
セン馬という存在を通じて、香港競馬の魅力や独自性を少しでも深く知ってもらえたら幸いです。
香港競馬でセン馬が多いのはなぜか?
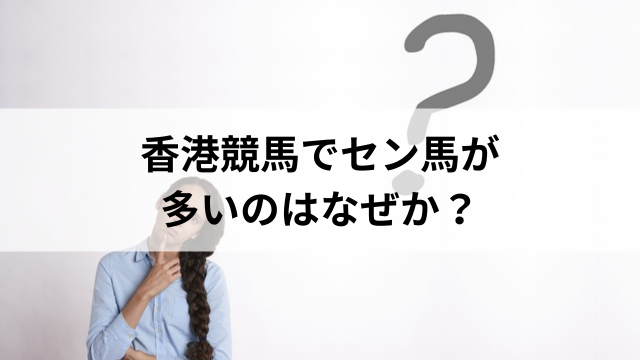
香港競馬を観戦していると、気づくことがあります。
それは、多くの有力馬が「セン馬(去勢された牡馬)」であるということでしょう。
日本ではクラシック競走に出走できないセン馬は少数派ですが、香港ではトップクラスの馬たちがセン馬として活躍しています。
なぜこれほどまでにセン馬が多いのでしょうか?
この章では、まずセン馬の基本から始め、その理由を詳しく解説していきます。

セン馬とは?簡単なおさらい
セン馬とは、去勢手術を施された牡馬のことを指します。
競走馬において去勢を行う目的は、主に「気性の安定」です。
牡馬は本能的に闘争心が強く、繁殖期には特に気性が荒くなることがあります。
こうした性格が競走に悪影響を及ぼす場合、去勢によって精神を落ち着かせ、競走能力の安定化を図ります。
去勢を行うメリットは気性が穏やかになり、調教やレースでのパフォーマンスが安定する点です。
具体的には、去勢によって男性ホルモン(テストステロン)の分泌が抑えられることで、筋肉の緊張が和らぎ、身体が柔らかくなるとされます。その結果、柔軟性が増し、競走馬としてのパフォーマンスが向上するケースもあります。
また、去勢を行うことで男性ホルモンが減少し、身体が柔らかくなることで競走馬としての能力を高めることもできます。
一方で、デメリットは繁殖に使えないことが挙げられます。去勢してしまうとどれだけ活躍しても「血統を後世に残す」ことができません。
ただ、それでも香港の馬は去勢が主流とされています。
その理由は次の見出しで紹介します。
なぜ香港ではセン馬が主流なのか
香港でセン馬が多くなる背景には、競馬制度や馬の流通事情、そして実利を重視する文化があります。
まず第一に、香港には日本のような「クラシック三冠」制度が存在しません。そのため、セン馬であることが出走制限の対象にならず、他の馬と同じ土俵で活躍することが可能です。
むしろ、安定した走りが期待できるという理由から、積極的にセン馬が選ばれています。
第二に、香港では競走馬のほとんどが外国からの輸入馬です。なぜなら、国内で生産するための施設(牧場)がないからです。
そのため、ニュージーランドやオーストラリア、イギリスといった国から馬を購入しています。
これらの国では、すでに去勢された状態で出荷される馬も多く、セン馬が自然と主流になるのです。
そして第三に、香港に輸入される馬の多くは短距離向きで、血統的にも気性の荒さが目立つ馬が多いです。
競馬の開催枠が限られており、即戦力が求められる香港では、調教に時間がかかるよりも「去勢してすぐに戦える馬」が重宝されます。
このように、勝てる確率を最大化するために去勢が積極的に行われるという背景があります。
「セン馬 もったいない」という声に対して
日本のファンからすると、「こんなに強い馬なのに血を残せないのはもったいない」と感じることもあるでしょう。
しかし香港競馬は、血統を残す文化よりも、「今この瞬間に勝てる馬」を優先する現実主義の世界です。
だからこそ、強くなれる可能性があるなら迷わず去勢が選ばれます。
さらに、近年は優秀なセン馬が賞金を稼ぎ、引退後には適切な施設で余生を過ごすというシステムも整ってきており、去勢された馬にも引退後の道が増えてきています。
香港のセン馬たちの引退後

競走馬として活躍したセン馬たちは、引退後にどのような道を歩むのでしょうか。
日本では種牡馬・繁殖牝馬としての第二のキャリアが一般的ですが、セン馬にはその選択肢がありません。
では香港では、セン馬たちの引退後の生活はどのように保障されているのでしょうか。
この章では、香港の引退馬事情と、日本との違いについて詳しく見ていきます。
セン馬の引退後の選択肢
香港で引退したセン馬たちは、いくつかの選択肢のもとで余生を送ります。
最も多いのは、乗馬用として再教育されるケースです。特に性格が穏やかで扱いやすいセン馬は、乗馬クラブやセラピーホースとして重宝されます。
また、香港ジョッキークラブHKJC)は引退馬の福祉に力を入れており、功労馬として余生を過ごせる施設も用意されています。
施設の多くは香港国外、特に中国本土やオーストラリアなどの牧場と連携しており、自然豊かな環境で馬たちが静かに過ごせるよう配慮されています。
さらに、元騎手や厩務員など、馬に関わってきた人々が引き取るケースもあります。
セン馬であっても、活躍した馬への感謝の気持ちから、手厚いケアが行われているのが香港の特徴です。
日本との違いとその背景
日本では、引退後に種牡馬・繁殖牝馬としてのキャリアが重要視されるため、去勢されていない馬の方が価値が高くなります。
そのため、セン馬は早期引退や乗馬転用が多く、「使い捨て」のようなイメージを持たれることもあります。
一方、香港では初めから「競走馬としての生涯」を重視して育成・管理が行われるため、引退後に繁殖を考える必要がなく、そのぶん競走能力や気性の安定性を優先した育成が可能です。
また、引退後の福祉制度も整っており、香港ジョッキークラブが主導して再就職支援や余生サポートが実施されています。
セン馬だからといって粗末に扱われることはなく、むしろ競走馬としての役割を全うした存在として、丁重に扱われているのが香港流の引退馬文化と言えるでしょう。
香港にセン馬以外の馬はいるの?
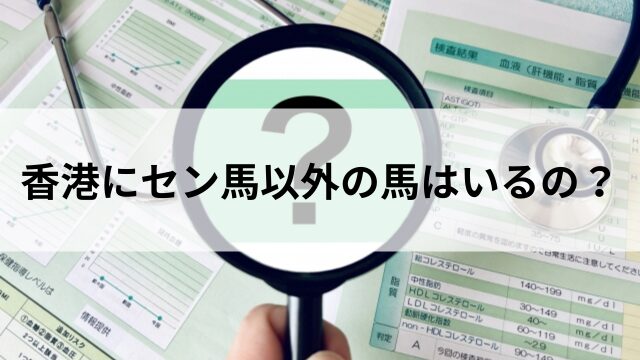
ここまで読んで、「じゃあ香港の競馬は全部セン馬ばかりなの?」と思った方もいるかもしれません。
確かにセン馬の割合は非常に高いものの、実は去勢されていない牡馬や牝馬も存在します。
この章では、香港競馬におけるセン馬以外の馬たちの存在と、その少なさの理由について解説します。
香港にも存在する牡馬・牝馬
香港の競走馬の大半がセン馬であるのは事実ですが、去勢されていない牡馬や牝馬も少数ながら在籍しています。
特にデビュー前に気性の問題が見られなかった馬や、血統的な背景から将来の種牡馬価値が評価されている一部の馬は、去勢を回避して現役生活を送っています。
牝馬も競走馬として登録されていますが、その数は稀少で、2022年の時点で香港馬は1,166頭いましたが、そのうち牝馬は3頭しかいませんでした。
なぜセン馬以外は少ないのか
香港でセン馬以外の馬が主流にならない理由は、やはり実利主義の香港競馬ならではの事情によるものです。
気性の荒さや調教の難しさは、レースで安定した成績を求められる香港にとって大きなリスクです。
加えて、セン馬にすることで管理がしやすくなり、怪我や事故のリスクも軽減されるため、去勢は合理的な選択とされています。
また、種牡馬・繁殖牝馬としての将来性がない以上、去勢による能力安定化のメリットがそのまま「賞金につながる可能性」として評価されるのも大きな要因です。
結果として、セン馬が競走馬として最もコストパフォーマンスに優れるという現実が、セン馬中心の状況を作り出しているのです。
香港とセン馬 まとめ

香港競馬において、セン馬は単なる選択肢のひとつではなく、競走馬として成功するための戦略的な形態です。
制度の違いや輸入中心の市場、そして現実主義的な運営方針がセン馬の増加を後押ししています。
その背景を知れば知るほど、「なぜこの馬はセン馬なのか?」という視点がレースをより面白くしてくれるでしょう。
日本とは異なる競馬文化を知ることで、国際競走の見方が一段と深まり、馬たちへの理解もより一層広がるはずです。
これから国際舞台で香港馬を見かけたときは、その背景にあるセン馬文化にもぜひ思いを馳せてみてください。

