ばんえい競馬を見たことがある人やどんな競技か知っている人は「馬がかわいそう」と感じたことがある人もいるかもしれません。
実際に動物愛護の観点から廃止すべきでは?と疑問を持たれることもあります。
そこで今回は、ばんえい競馬の馬がかわいそうと言われる理由についてまとめました。
実際のレースの様子や、馬たちの飼育環境についても詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
ばんえい競馬とは?

まずばんえい競馬とは、北海道・帯広市にある帯広競馬場で開催されている地方競馬です。
通常の競馬とは異なり、ばん馬が鉄製のソリに騎手を乗せてふたつの障害(山)を乗り越え、ゴールを目指す競馬です。
このばんえい競馬の主役である「ばん馬」とは、開拓時代に農耕馬として活躍していた馬のことで、「お祭りばん馬」と呼ばれる娯楽でその馬の力自慢を競い合っていたことがルーツとなっています。
かつては北海道内各地で行われていたばんえい競馬は、今では世界でも帯広競馬場でしか見ることが出来ず、唯一無二のレースを見に多くの人が訪れています。

ばんえい競馬が「かわいそう」「廃止しろ」と言われる理由
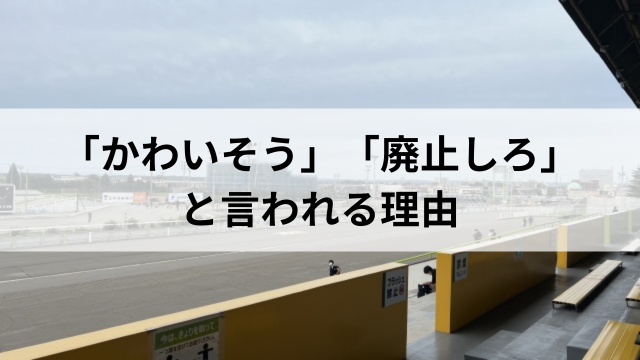
しかしながら、ばんえい競馬を見た人の中には「かわいそう」「廃止しろ」という声が上がるのも実情です。
どうして、ばんえい競馬は廃止すべきという声が上がるのでしょうか?
実は、いくつかの理由から「馬がかわいそう」と感じる人も少なくありません。
ここからは、ばんえい競馬に対するそうした声の背景をいくつか解説します。
馬への負担が大きそうに見える
ばんえい競馬は一般的な競馬と違い、400キロ以上あるソリを引いた上で坂(障害)を越えなければなりません。
さらにコースは砂で出来ているため足場も悪く、ただ早く走るだけの競馬よりも、体力・スタミナがとても必要になるので負荷が大きく見えるのでしょう。
しかし、ばん馬は元々農耕馬であり、体も大きくスタミナやパワーに特化した馬です。そのため、ばんえい競馬はそのばん馬の特徴を生かした競技であると言えます。
ゴールできない馬や倒れる馬がいる
ばんえい競馬のコース内にはふたつの障害(山)がありますが、いくら力のあるばん馬でも重たいソリを引きながら障害を乗り越えるのは大変です。
そのため、レース中、地面に腹や膝を着いたりして障害を登り切れない馬もたまに見ます。
その時は無理に登らせることはなく、ソリから馬を開放し、ソリはトラクターでスタート地点まで運びます。
また、3着がゴールしてから2分以内(重賞であれば3分以内)にゴールできなければ失格となるため、長時間登れずに苦しむこともありません。
最近の出来事としては、2018年のばんえい記念ではニュータカラコマが競争中、第二障害を越えた後倒れこみ、残念ながらそのまま亡くなってしまいました。
当時は「鞭の打ちすぎが原因では?」と噂されましたが、診断の結果、心臓発作であったため鞭の打ちすぎとは関係ありませんでした。
ただ、知らない人が見れば衝撃も大きく、かわいそうと思う人も多かったかもしれません。
鞭の使用シーンがセンシティブに映る
ばんえい競馬は一般的な競馬と違い、レースの進行がゆっくりなので、鞭を入れる場面が見えやすいです。そのため、「かわいそう」と思われやすいのかもしれません。
しかし、実際にはばんえい競馬で使用されるのは鞭ではなく手綱の余った部分で、馬にとっては合図程度のものです。
競馬ではむやみやたらに鞭を打つことはなく、動物福祉に則ったルールの中で使用しているということは知っておいていただきたいです。
騎手が馬を蹴った事件
しかし、2021年には悲しい事件がありました。
デビュー前に行われる能力検査中、障害を越えられず座り込んだドウナンヒメの顔を鈴木恵介騎手が蹴り上げ当面の出場を自粛、戒告処分となりました。
鈴木騎手は坂の障害で動かなくなった馬の顔を上げさせるために蹴ったと話していますが、どんな理由であれ馬の顔を蹴り上げるのはよくないことだと、誰もが感じると思います。
これに対し、ばんえい競馬公式サイトにある「いただいたご意見についての回答」のページ内に、公式からの回答がありましたので引用します。
この度の行為は、決して認められるものではありませんが、馬とともにゴールを目指そうとした結果の行為であり、みだりに動物を虐待した行為とは考えていません。ばんえい競馬は、人と馬との信頼関係のもと、さまざまな厳しいルールに基づいて行われています。今後も、馬に愛情を持って接することはもとより、能力検査における必要なルールの見直しを行うなど、再発防止に努めながらばんえい競馬の適切な運営を行ってまいります。
ばんえい競馬に対する動物愛護団体の見解
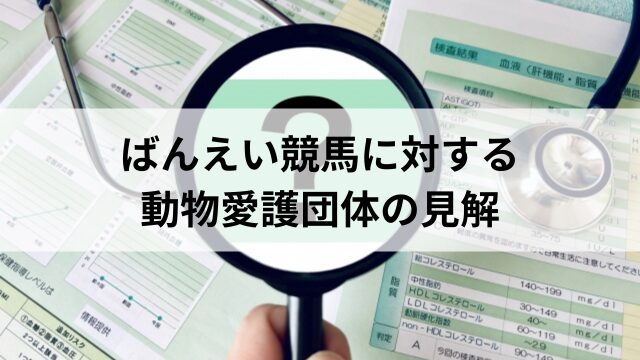
先ほどの事件を受け、福祉協会Evaは56の動物愛護団体等とともに、ばんえい競馬廃止の要望書を帯広市長に提出しています。 一部を引用します。
2021年4月18日に、北海道帯広競馬場で行われた能力検査にて、第2障害の上り坂でひざをつき、立てない牝馬ドウナンヒメの顔を、騎手が足で2度蹴った行為に対し、ソーシャル・ネットワーキング・サービス上を中心に大きな波紋を呼んでいることは貴殿も把握されていることと存じます。
(中略)
そもそもばんえい競馬は、最大1トンにもなる重い鉄ソリを馬にひかせること、またソリをひかせながら更に加重される山を登らせること、足場の悪い砂場で競わすこと、そしてレース中の手綱による過度な強い鞭打ちなど、馬にとって非常に過酷で苦痛を伴う競技といえます。また「レースの見どころ」とされている第2障害では、ひざをつく馬、障害で力尽き倒れこむ馬が頻発し、2018年にはニュータカラコマが心臓発作でレース中に死亡しています。近代日本の動物愛護運動は、明治時代に苛酷な重労働を強いられていた牛馬の保護から始まりました。立つこともままならぬ極限状態の馬の姿を「見どころ」として賭博に用いることは、動物への福祉を著しく逸脱した時代錯誤なレースと言わざるを得ません。また、公正を害する行為や競馬法違反を見ても「世界唯一」不名誉な競馬ではないでしょうか。
ただ、これはSNSで大きく広まった事件に対し、反応したのではないかという意見もありました。
突然廃止してしまってはばんえい競馬の収入がなくなってしまい、その後の残された馬たちの生活が困難になってしまいます。
本当に馬を想うのであればもっと内情をよく知り、運営と意見交換などをしっかりとした上で提案できたらよいのかなと個人的には思います。
ばんえい競馬に対する海外の反応
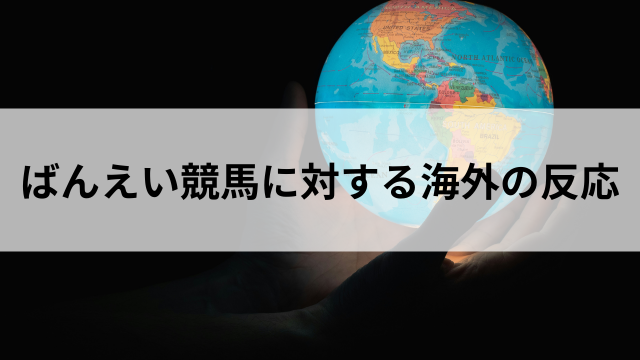
海外のネット上での反応には、肯定的な意見と否定的な意見がありました。
肯定的な意見としては、「これは文化の一部である」と捉える人が多く、馬車のようなものであり、馬は実際にこのような仕事を楽しんでいるという考えが書かれていました。こうした意見は、馬の本来の役割やその文化的背景を理解し、評価されていることがわかります。
一方、否定的な意見もあります。こちらは、馬に過酷な負担をかけていると感じ、見ていて辛いという意見が中心です。動物の福祉や倫理的な観点から、こうした活動に疑問を投げかける声も少なくありません。
とはいえ、この競技が珍しいこともあり、実際に海外から見に来る人もいます。それだけ魅力があるということでもあり、異なる文化や新しい体験に興味を持つ人々にとっては、貴重な機会となっているとも言えます。
実際のばんえい競馬の管理体制
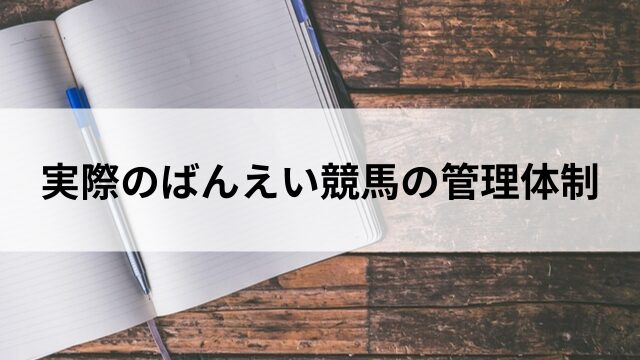
実際にばんえい競馬はどのような管理がされているか、解説します。
馬を管理している厩舎では、獣医師による24時間体制の健康管理や診察が行われています。また、常駐の装蹄師もいて蹄のケアや治療にあたれるよう万全の管理がされています。
厩務員は1人で4~5頭ほど担当し、1日4回の給餌、日光浴、馬房の清掃、トレーニング後の馬の洗浄など丁寧に馬の手入れをしています。
先述しましたが、ばんえい競馬では鞭を使わず、手綱のあまった部分を使用することにより打つ力が制限され、条件反射を刺激する程度になっています。
また、ばん馬はそもそも重量作業に適した品種であり、さらに馬の能力にあわせて重量も変えているので、無茶な重さを引くこともありません。
馬の管理から競馬のルールまで、しっかりと決められた中で運営されていることを改めて知っておいていただけたらと思います。
ばんえい競馬はかわいそう?のまとめ
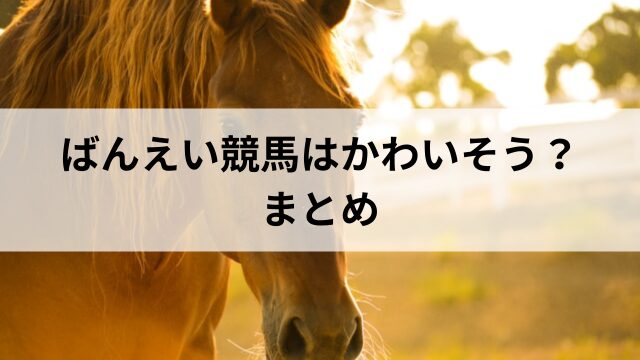
ばんえい競馬は、ばん馬が活躍できる数少ない場として設けられており、北海道における開拓時代の歴史や文化を現代に受け継いだものです。
かわいそうという意見もありますが、動物福祉に則って正しく開催し、今後もばんば馬の活躍の場として、ばんえい競馬を残していってほしいです。

