レース中、突如として失速してしまいジョッキーが下馬する場面を目にしたことがある競馬ファンは多いかと思います。
直近では2021年の年度代表馬、エフフォーリアの京都記念での競走中止が記憶に新しいでしょう。
エフフォーリアの競走中止の原因は、今回紹介する心房細動でした。
人間でもときどき発症する心房細動は、競走馬も発症することがあります。
この記事では心房細動について、その原因や治療方法、発症したその後について、実際に心房細動を発症した名馬とあわせて解説します。
そもそも心房細動とは?【症状と原因、発症率と再発率について】
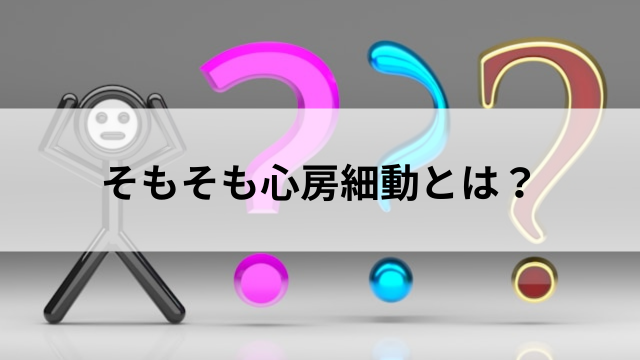
心房細動とは、心臓の電気信号が異常に伝わることで心房が不規則に震え、心拍が速くなったり乱れたりする不整脈の一種です。
この状態が続くと、動悸や息切れ、めまいなどの症状が現れることがあり、場合によっては血栓ができて脳梗塞のリスクが高まることもあります。
この章では、心房細動の具体的な症状や原因について詳しく解説していきます。
心房細動の症状
心房細動は、一定のリズムを刻んでいた心拍が突如として不規則に乱れます。これにより全身に送られていた血流がうまく送られなくなり、レース中に発症した場合は急激に減速し、冒頭に紹介したエフフォーリアのように、競走中止に至るケースも多くあります。
また、レース中に発症したものの急激な減速なく無事にゴールしたとしても、酸素を運ぶ血液がうまく送られていないため、激しい息切れや、普段より早くにスタミナ切れを起こすことも心房細動の症状の1つです。
心房細動の原因
心房細動の原因は、未だ解明されておりませんが、ひとついえるのは、そのため、発症を予測することは難しいとされています。
ただ、心臓が大きければ大きいほどその発症するリスクは高まると言われており、人間であっても心臓の小さな日本人よりも心臓の大きな西洋人の方が心房細動を発症しやすいと言われています。
心房細動の発症率と再発率
競馬や競走馬についてのあらゆる研究を行っている「JRA競走馬研究所」の研究によると、1988〜1997年の間に出走したのべ404,090頭中、115頭(123例)が心房細動を発症したというデータがあります。
実頭数にすると39,302頭ということを踏まえ、頭数当たりの発症率にすると、およそ0.29%となりました。条件別にデータをみると、「4歳以上」「芝レース」「長距離レース」においてそのほかの条件よりも発症率が高いことも明らかになっています。
また、115頭(123例)というデータがあらわしているように、再発した競走馬も存在します。115頭中7頭が再発したとされ、それを確率に直すと6.1%になります。
これらの数字は決して高い数字ではありませんが、たとえばレース最終盤で発症した馬やレースに影響を及ぼさないほどの短期間しか発症しなかった馬は調査対象から外れているため、実際の数字はいずれの数値よりも若干多いことが考えられます。
心房細動の治療方法とその後のケースについて
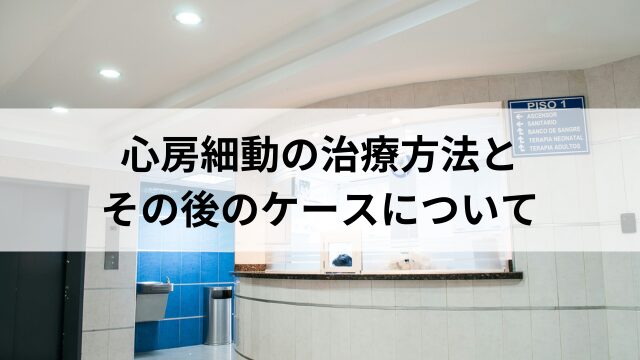
この章では、競走馬における心房細動の治療方法と、治療後の競走能力への影響について詳しく解説します。
心房細動は適切な治療を行えば回復する場合もありますが、再発のリスクやパフォーマンスの低下が懸念されることもあります。
また、重症化すると競走能力を大きく損ない、最悪の場合、競走馬としてのキャリアを終えるだけでなく、予後不良となる可能性もあります。
本章では、これらの点について詳しく見ていきます。
心房細動の治療方法
心房細動の多くは、およそ48時間以内に正常な心拍を取り戻すと言われており、特に決まった治療方法はありません。
しかし、ごく稀に心拍の乱れが48時間以降も継続してしまうケースもあり、この場合は病気として捉え、早期の電気刺激(除細動)や薬物投与が必要になります。
心房細動を発症したその後
心房細動は発作性の場合が多く、発症したとしても正常な心拍を取り戻せばまた従来の能力を発揮できるとされています。
※発作性とは?
症状が突然発生し、一定の時間が経過すると自然に消失する性質のこと
実際に、2022年9月のオールカマーで心房細動を発症し、2番人気で13着に敗れたソーヴァリアントは、およそ2ヶ月後のチャレンジカップを1番人気の期待に応え優勝しました。
また、2021年8月の札幌記念で発症し、競走を中止したステイフーリッシュも、1ヶ月後にはレースに復帰し、その後も安定したレースを続け海外遠征。レッドシーターフやドバイゴールドカップといった海外重賞を連勝しています。
心房細動が原因で死亡・予後不良になる可能性
心房細動は発症から48時間以内に正常な心拍を取り戻すことが多く、発作的に発症し、死亡・予後不良になる可能性は低いとされています。
しかし、重度であった場合や、慢性的に心房細動が持続し適切な治療が施されない場合、心不全や血栓により、突然死に至る可能性があります。
また、たとえ回復したとしても一度発症した心房細動を学習・記憶し精神的ダメージを与えるなど、馬のメンタルに悪影響を与える場合もあり、それにより競走本能が削がれ、そのまま引退を余儀なくされる馬も存在します。
心房細動を患った名馬3頭

ここからは、実際に心房細動を発症し、競走馬としてのキャリアに影響を受けた名馬たちを紹介します。
心房細動は競走能力に大きな影響を与えることがあり、これが原因で引退を余儀なくされた馬もいれば、治療や調整を経て再び輝きを取り戻した馬もいます。
競馬界を沸かせた名馬たちがどのような運命をたどったのか、そのエピソードを詳しく見ていきましょう。
今回紹介するのは、下記の3頭です。
- エフフォーリア
- ブラストワンピース
- ヴァーミリアン
エフフォーリア
| 生年月日 | 2018年3月10日 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 父 | エピファネイア |
| 母 | ケイティーズハート |
| 母父 | ハーツクライ |
| 生産牧場 | ノーザンファーム |
| 戦績 | 11戦6勝 |
| 主な勝ち鞍 | 皐月賞(G1) 2021年 天皇賞(秋)(G1) 2021年 有馬記念(G1) 2021年 共同通信杯(G3) 2021年 |
| 獲得賞金 | 7億7,663万6,000円 |
最初に紹介するのはエフフォーリアです。
2021年の有馬記念ではファン投票歴代1位の26万742票を集め、そうそうたるメンバーを破り見事優勝を果たすなどし、2021年の年度代表馬、最優秀3歳牡馬に選出された、記憶に新しい名馬です。
横山武史ジョッキーとのコンビも印象深く、同ジョッキーが初めてG1勝利をあげたのはエフフォーリアに騎乗してのものでした。そんなエフフォーリアが心房細動を発症したのは2023年5歳を迎えたばかりの2月に開催された京都記念です。
3歳時には大きな活躍をしていたものの、4歳は度重なるハイペースに進むレースに苦戦しその活躍は影を潜め、5歳を迎えた初戦、京都記念は前年のダービー馬のドウデュースに次ぐ2番人気と大きな期待がこめられていました。
道中、第3コーナーまでは2番手と絶好の位置をキープしていたものの、第4コーナーに差し掛かると急激に失速、後退します。直線に入った時点では最後方まで後退してしまい、ゴール手前で横山ジョッキーが下馬。競走中止となります。
その後JRAからは心房細動を発症していたことが発表され、美浦に戻った後の検査では異常が見られなかったものの、関係者間で協議された結果、現役引退と種牡馬入りが決定しました。
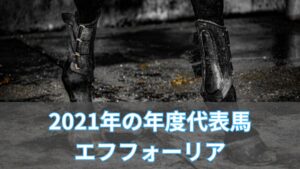
ブラストワンピース
| 生年月日 | 2022年1月20日 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 父 | ハービンジャー |
| 母 | ツルマルワンピース |
| 母父 | キングカメハメハ |
| 生産牧場 | ノーザンファーム |
| 戦績 | 18戦7勝 |
| 主な勝ち鞍 | 有馬記念(G1) 2018年 札幌記念(G2) 2019年 AJCC(G2) 2020年 毎日杯(G3) 2018年 新潟記念(G3) 2018年 |
| 獲得賞金 | 5億8,942万1,000円 |
2018年に有馬記念を制し、最優秀3歳牡馬に選出され、その後も札幌記念やアメリカジョッキークラブカップなども勝利し、重賞通算5勝をあげたブラストワンピースもまた心房細動を患った馬です。
ブラストワンピースが心房細動を発症したのは、2021年からの連覇を目指した2022年有馬記念でした。道中は2番手を進んでいたものの、心房細動を発症し、2周目の第3コーナー付近で失速・後退し始め、最後の直線で競走中止となります。
もっとも、大事には至らず、翌年の6月、鳴尾記念で復帰し3着、8月の札幌記念を5着と好走しましたが、その後右前球節に痛みが生じたため放牧に入ります。
復帰を目指して調整されていたものの患部の症状の改善が思わしいものではなく、まもなく引退が発表されました。
引退後は種牡馬入りも考えられましたが、父であるハービンジャーが現役の種牡馬で活躍していたことや、中長距離血統を持つ種牡馬の需要などが勘案され、種牡馬入りせず、ノーザンホースパークにて乗馬としてその余生を過ごしています。
ヴァーミリアン
| 生年月日 | 2002年4月10日 |
|---|---|
| 性別 | 牡 |
| 父 | エルコンドルパサー |
| 母 | スカーレットレディ |
| 母父 | サンデーサイレンス |
| 生産牧場 | ノーザンファーム |
| 戦績 | 34戦15勝 |
| 主な勝ち鞍 | ジャパンカップダート(G1) 2007年 フェブラリーステークス(G1) 2008年 川崎記念(Jpn1) 2007・2010年 JBCクラシック(Jpn1) 2007~2009年 東京大賞典(Jpn1) 2007年 帝王賞(Jpn1) 2009年 浦和記念(Jpn2) 2005年 ダイオライト記念(Jpn2) 2006年 名古屋グランプリ(Jpn2) 2006年 ラジオたんぱ杯2歳ステークス(G3) 2004年 |
| 獲得賞金 | 11億6,860万7,500円 |
2007年と2009年川崎記念、2007から2009年のJBCクラシックを3連覇、2007年ジャパンカップダート、東京大賞典、2008年フェブラリーステークス、2009年帝王賞など、G1レースを9つ制し、2016年まではJRA史上最多G1勝利数を誇ったのがヴァーミリアンです。
さらに、7年連続重賞勝利や、5つの競馬場でG1勝利、ダート最多獲得賞金など、数々の伝説を持ち、誰もが認める名馬と言えるでしょう。
そんなヴァーミリアンが心房細動を発症したのは2006年、4歳の時でした。
ダイオライト記念において2着馬に6馬身差をつけ圧勝した次のレース、東海ステークスのレース中に発症し、1.8倍の1番人気に推されていたものの最下位の13着に敗れます。
これにより当初予定されていた帝王賞は回避せざるを得なくなってしまいました。
もしこの時に心房細動を発症していなかったらコパノリッキーやホッコータルマエに並ぶ2桁G1勝利をあげていたかもしれません。
もっとも、復帰後も心房細動発症前と変わらず活躍をみせ、重賞10勝(うちG1を9勝)をあげ、8歳になっても川崎記念をレコード勝ちするなど、ダート戦線を大きく盛り上げました。
心房細動のまとめ

今回の記事では、競走馬が発症すると血液をうまく循環させることができず、競走中止や競走能力の低下につながる心房細動について解説しました。
心房細動は発症すると突然の失速や動悸、息切れなどを引き起こし、最悪の場合、競走馬としてのキャリアに終止符を打つこともあります。
現在のところ、その発症メカニズムや明確な原因は完全には解明されておらず、予防策も確立されていません。
今後の獣医学や競走馬の管理方法の進歩によって、心房細動の原因が究明され、より効果的な予防や治療法が確立されることが強く望まれます。

