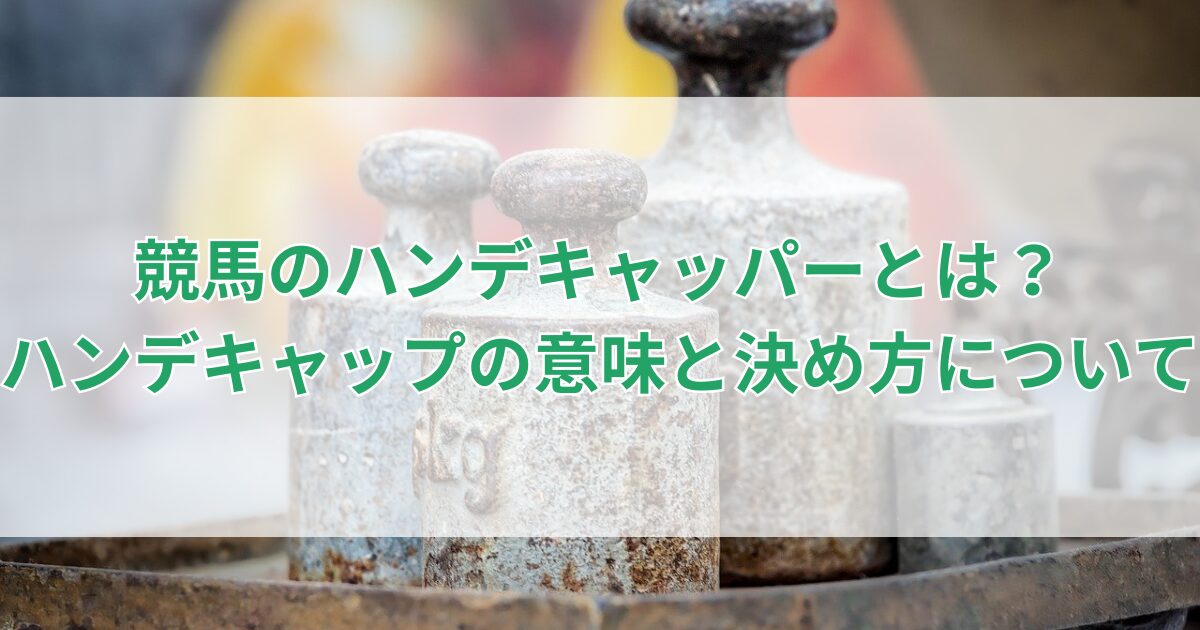近年は、一昔に比べて、牝馬の活躍がとても目立つようになりました。
そのような状況下にあっても現行のレース体系での負担重量は、牝馬の方が牡馬より2キロ軽いことは変わりありません。
そして、もっと突き詰めていえば、そのハンデってどうやって決めているの?誰が決めているの?と素朴な疑問が浮かびました。
そこで今回は、競馬のハンデについて、また、それを決定するハンデキャッパーについて紹介したいと思います。
一般的には、知られていない部分が多くあると思いますので、是非とも参考にしてみてください。
競馬のハンデキャッパーって何?
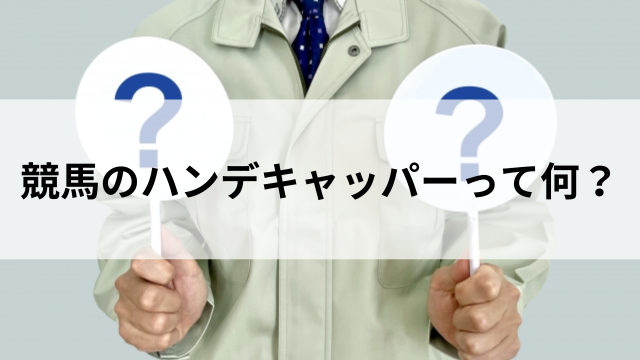
競馬には、出走する競走馬の能力差を均等にし、どの競走馬にも勝つチャンスを与えるため、ハンデ差を付けて行われるレースがあります。いわゆるハンデ戦と呼ばれるレースです。
そこでハンデキャッパーの登場です。
ハンデキャッパーとは、ハンデキャップ競走における負担重量の決定を行う役職に付いている方々のことをいいます。
適切なハンデキャップを設定するため、日々JRAが主催する競走成績はもちろん、地方競馬など他主催側が開催するレースに出走した競走馬の競走成績もチェックする必要があります。
なお、JRAのハンデキャッパーは2021年現在12名。元獣医の方など、全員が様々な部署で経験を積んできたメンバーで構成され、各開催競馬場を担当するのは3名ずつとなっています。
ハンデキャッパーのハンデを決め方
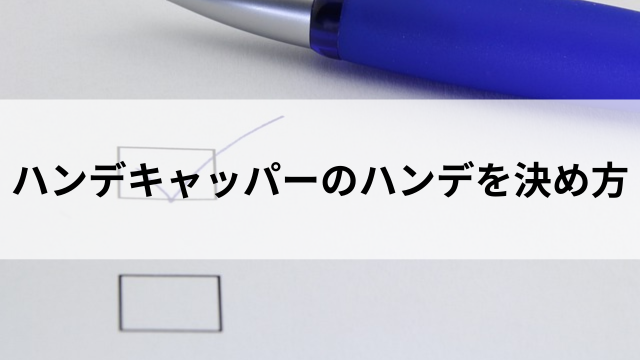
次にハンデキャッパーは、どのようにしてハンデを決めているのかについて紹介します。
まずは、年間でハンデ戦といわれるレースがどれくらい番組構成されているのでしょうか。
2020年度でみますと、JRAの平地競走は3331レースありました。そのうちハンデ戦は198レースです。ちなみにハンデ戦は、古馬2勝クラス以上のクラスにしかありません。
なお、ハンデ戦の内訳は、まずはオープンクラスで61レース、そのうち重賞が27レース。続いて、3勝クラスが75レース、2勝クラスが62レースとなっています。
これらのほとんどが芝コースであり、ダートコースは、マーチステークス(G3)およびシリウスステークス(G3)のダート重賞2競走のみです。
また、牝馬限定のハンデ戦は愛知杯(G3)、中山牝馬ステークス(G3)、マーメイドステークス(G3)、ターコイズステークス(G3)といった重賞4競走のみとなっています。
あと例外として、3歳限定のラジオNIKKEI賞(G3)もハンデ戦となっています。
なお、オーストラリアのメルボルンカップ(豪G1)のように海外競馬には、ハンデ戦のG1もありますが、日本の競馬では、優勝劣敗の原理に基づき、現在のところG1レースにハンデ戦はありません。
この約200レースのハンデ戦は、すべて特別競走として行なわれます。そのため、レース前週の日曜日に特別登録が行われます。
そこで、各ハンデキャッパーは、特別登録された競走馬の面子をみながら、まずは1人で負担重量を決めていきます。
一般的に、1番大きい負担重量の競走馬、いわゆるトップハンデと呼ばれる競走馬を最初に決めて、次に出走登録各馬の負担重量を順番に決めていきます。
この際、『負担重量の重い馬(馬齢重量との差分)及び上位3頭に対して優先出走(同斤量で複数頭が並んだ場合は抽選で3頭)』となります。
※『』内は、日本中央競馬会競馬番組一般事項Vの2の(2)のホ「ハンデキャップ競走への優先出走について」より抜粋
なお、ハンデ戦による最低負担重量は、オープン戦の場合は49キログラム、それ以外は50キログラムとなります。
そこから0.5キログラム単位で調整されるのですが、重い場合には上限はありません。もっとも、実際には63キログラム以上が課されることは滅多にないです。
その後、各々が考えたハンデ案を翌日、月曜日の朝に持ち寄って会議を行います。
そこから、会議の席上、合議によって決定されるのですが、時には「あの競走馬のハンデは少なすぎる」や「この競走馬にこのハンデは酷ではないか」など、激論になることもあるといいます。
なお、各競走馬の負担重量の発表は、月曜日の15時と定められていますので、実際にハンデキャッパーは、24時間程度でハンデを計算し、決定後、発表する必要があります。
そして、発表されたハンデを確認した調教師は、自厩舎の馬の負担重量に問題ないかどうかを判断してから、木曜日の最終登録(出馬投票)に臨むこととなります。
よって、ハンデキャッパーとは、このような短時間で各競走馬のハンデを決めなければならない過酷な業務といえますね。
さらに全競走馬の走破タイムや成績などを常に確認しておく必要もありますので、重要かつ責務ある役割です。
なお、参考までにハンデは、1キロの差で0.2秒(約1馬身)ほどの影響が出ることを知っていただくと、馬券の予想に役立つかも知れません。
現在のハンデは昔に比べたら軽いの?
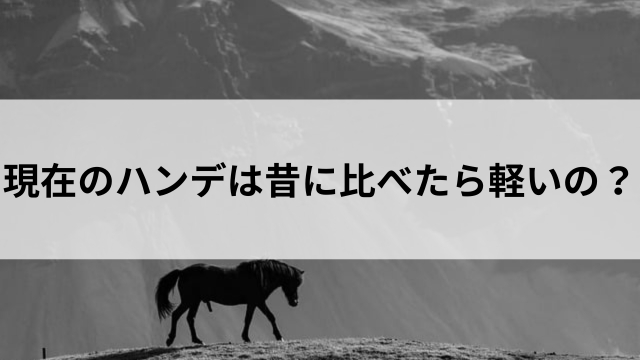
JRAにグレード制が導入されたのは、1984年からですが、それまでは今のようなG1やG2といった制度がなく、現在の重賞競走は、すべてオープンクラスに一括りされていました。
そのような状況下にあったため、オーブンクラスの競走馬にハンデを付けるには、負担重量しかなかったのです。
そのため、必然的に一昔の日本競馬では、強い競走馬ほどハンデが重くなっていたのはやむを得ずといったところでしょう。
しかし、ある出来事によって、負担重量の見直しが行われました。
そのキッカケとなったのが、今から約50年前に日本競馬の一時代を築いた悲運の名馬・テンポイントだったといわれています。
テンポイントは、1977年の年度代表馬になったほどの名馬で生い立ちはもちろん、陽に映える栗毛と額の流星、バランスの取れた気品ある馬体も注目を集め、いつしか「流星の貴公子」と呼ばれるようになりました。
そして、トウショウボーイやグリーングラスといった日本競馬を代表する名馬たちとライバル関係を構築し、凌ぎを削り合います。
それを競馬ファンは、3頭の頭文字を取った”TTG時代”と呼びました。
しかし、テンポイントが活躍していた当時は、関東の競走馬が強かった時代です。
そこで関西の新星として現れたテンポイントは、西の大将格となり、関西期待の競走馬となっていきます。
そんな中、1977年の有馬記念では、引退レースとなったライバル馬のトウショウボーイに劇的勝利し、前述の通り、年度代表馬に輝きました。
そして、翌年2月に海外遠征の壮行レースとして選んだのが、地元・京都での日経新春杯だったのです。ただし、レースでの負担重量は、今では考えられない66.5キログラムでした。
それでもテンポイント陣営が出走に踏み切ったのは、関西の競馬ファンの前でお披露目するとの意味も含め、レースに出走せざるを得なかった状況だったことが理由の1つに挙げられます。
しかし、2月の海外遠征前のレースと考えれば、結局のところ、このレースしか選択肢がなかったのです。ただ、陣営からすれば、ハンデが67キログラムなら出走しなかったという話もありました。
そして、66.5キログラムという負担重量を背負い出走したテンポイントは、レース中に骨折といったアクシデントに見舞われ、43日間におよぶ治療の末、亡くなりました。
こうして、同事故以降は、勝利数の多い競走馬の負担重量を重くする方針から、逆に勝利度数の少ない競走馬の負担重量を軽くする方針に転換したのです。
競馬のハンデキャッパー まとめ
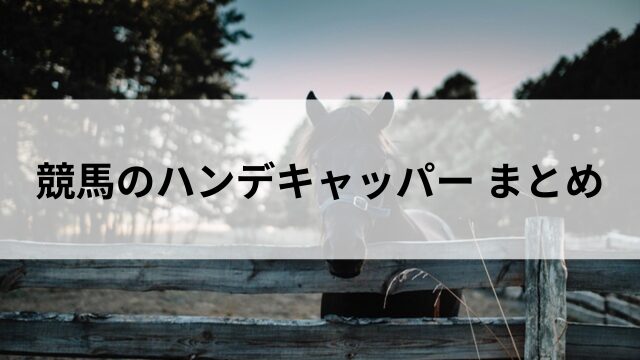
今回は、ハンデキャッパーについて紹介しました。
ハンデ戦においての負担重量に関しては、公式発表などがありませんので、その仕組みなど知る機会が少ないと思います。この記事にて少しでもハンデ戦やハンデキャッパーについて知っていただけましたら嬉しい限りですし、是非とも参考にしてみてください。