競馬でよく使われるデータのひとつに「複勝率」があります。
この複勝率は、馬がどれだけ安定して上位に入っているかを示す指標で、予想や馬券を組み立てる際に非常に役立ちます。
特に「人気の馬は本当に来るのか?」「どの騎手が安定して成績を残しているのか?」といった疑問を考えるとき、複勝率の活用は欠かせません。
この記事では、複勝率の定義や計算方法から、人気別や騎手別の複勝率データ、さらに連対率との違いまでを詳しく解説していきます。
データを使った予想精度の向上を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
複勝率とは?競馬での定義と役割
競馬で馬券を買う際、「この馬はどれくらいの確率で馬券に絡むのか?」という判断は非常に重要です。
その判断材料のひとつが「複勝率」です。
この項目では、まず複勝率の基本的な意味と定義を確認し、連対率や勝率といった他の指標との違いについても整理していきます。
複勝率の意味と定義
複勝率とは、ある馬や騎手が出走したレースのうち、3着以内に入った割合を示す数値です。
競馬において「安定して馬券に絡むかどうか」を評価するための代表的な指標のひとつで、勝率や連対率と並んで使われます。
特に複勝馬券(1〜3着以内に入れば的中)の購入を検討する際、この数値の高さは信頼度の裏付けになります。
また、複勝率が高い馬は「崩れにくい馬」ともいえ、馬連や3連複といった連系馬券の軸選びにも活用されることが多いです。
連対率・勝率との違い
複勝率に似た指標として、「勝率」と「連対率」があります。
勝率は1着に入った割合、連対率は1〜2着に入った割合を指し、いずれも馬や騎手の実力を表すものです。
これに対し、複勝率は1〜3着までを対象とするため、最も範囲が広く、安定性を測るうえで重宝されます。
たとえば勝率20%・連対率40%・複勝率60%といった馬は、「勝ち切る力もあるが、最低でも3着以内には来やすい」と判断できるわけです。
これら3つの数字を組み合わせて分析することで、より精度の高い予想が可能になります。
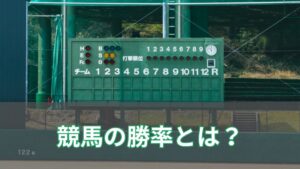
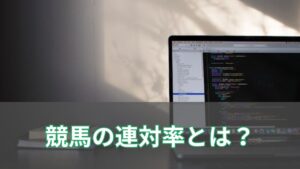
複勝率の計算方法と見方
複勝率はただの「3着以内の数」ではなく、レース全体の出走回数に対してどれだけ安定して上位に入ったかをパーセンテージで表したものです。
この項目では、複勝率の計算式や、実際の成績データをもとにした具体例を交えながら、どうやって数値を読み解くかを解説します。
計算式と具体例
複勝率の計算式は非常にシンプルで、下記の数式で求められます。
【複勝率(%)=(1着数+2着数+3着数)÷出走数×100
たとえば、10戦して1着3回、2着2回、3着1回だった場合は、3+2+1=6回が複勝圏となるので、複勝率は60%になります。
また、30戦して9回しか3着以内がない馬であれば、複勝率は30%です。
この数値が高ければ高いほど、「安定して馬券に絡んでいる」という評価につながります。
複勝率の見方と活かし方
複勝率はその馬や騎手が「崩れにくいかどうか」を判断するための指標です。
30%〜40%以上あれば安定性が高いとされ、特に馬連・3連複の「軸馬」として重宝されます。
ただし、出走回数が少ない場合は数値が高くても参考にしづらいため、最低でも5〜10戦以上のデータを前提に考えると信頼度が上がります。
また、複勝率を見る際は、過去10走で安定しているか、コースや距離別の傾向もチェックするとさらに精度が増します。
h2. 人気別の複勝率データと傾向(約500文字)
競馬では馬の「人気」と「実際の成績」が必ずしも一致するとは限りません。
とくに複勝率と人気の関係性を知っておくことで、どの人気帯が安定して好走しているか、あるいは過剰評価・過小評価されているかを見抜くヒントになります。
この項目では、1番人気から4番人気までの複勝率を中心に、複勝率100%に近いパターンについても解説していきます。
1番人気〜4番人気の複勝率は?
JRAの全体データを見てみると、1番人気馬の複勝率はおおむね65〜75%で推移しています。
つまり、およそ3回に2回は3着以内に入る計算になります。
2番人気は約55〜60%、3番人気は約45〜50%、4番人気になると40%前後まで下がってきます。
このように、人気が下がるほど複勝率も減少する傾向が見られますが、4番人気でも40%前後と高い水準を保っているため、軽視は禁物です。
複勝馬券だけでなく、馬連や3連複の軸候補としても狙い目となります。
複勝率100%に近い人気馬の特徴
稀に「複勝率100%」という極端に安定した馬も存在しますが、多くは出走数が少ない新馬や条件戦での事例です。
また、少頭数のレースや、能力差が大きいメンバー構成の中では1番人気が圧倒的な複勝率を記録するケースもあります。
特に逃げ馬や先行馬で展開に恵まれるタイプは、高い複勝率を維持しやすい傾向があります。
とはいえ、複勝率が100%に近いからといって盲信するのではなく、出走数や相手関係なども合わせて慎重に見極めることが大切です。
騎手別の複勝率|信頼できるジョッキーは誰か
競馬で複勝率を語るうえで、馬だけでなく「騎手」の存在も見逃せません。
騎手にはそれぞれ得意なコースや脚質があり、複勝率にも大きな差が表れます。
この項目では、複勝率が高いジョッキーや、人気との組み合わせで注目すべきポイントについて解説していきます。
複勝率の高い騎手とは?
JRAで活躍する騎手の中でも、ルメール騎手・川田将雅騎手・坂井瑠星騎手などは複勝率が高いことで知られています。
これらのトップジョッキーは、毎年30%〜45%以上の複勝率を記録しており、どの馬に騎乗していても安定感を発揮します。
リーディング上位の騎手は総じて複勝率が高い傾向があります。
一方で、ローカル開催や特定条件では複勝率が低下する騎手もいるため、開催場や季節ごとの得意・不得意を押さえておくとより精度の高い分析が可能です。
騎手と人気の組み合わせで狙う
「複勝率の高い騎手×中穴人気」の組み合わせは、馬券的に妙味がある狙い目です。
たとえば、7番人気の馬でも川田騎手が乗っていれば「騎手買い」で好走するケースも少なくありません。
一方、複勝率の高い騎手が1番人気に乗っていると過剰に評価される場合もあり、オッズが極端に下がる傾向もあります。
人気と複勝率、そして騎手の癖や相性を合わせて判断することで、見逃しがちな好配当馬にたどり着ける可能性があります。
複勝率と複勝回収率の違い
複勝率が高い=儲かる、と思われがちですが、実際にはそれだけでは不十分です。
いくら3着以内に入っても、配当が低ければ収支はマイナスになることもあります。
この項目では、複勝率と複勝回収率の違いを明確にしつつ、どのようにバランスを取ればいいのかを解説します。
複勝率が高くても儲かるとは限らない
複勝率は「当てやすさ」を示す指標であり、「儲かりやすさ」とは異なります。
たとえば、1番人気の複勝率が70%あっても、複勝オッズが1.1倍しかない場合は、10回に7回当てても利益はごくわずかです。
むしろ残り3回で全額を失えば、収支はマイナスになります。
このように、的中率と回収率は別軸で考えることが重要です。

回収率とのバランスを見る
回収率とは、投じた金額に対して払い戻された額の割合です。
複勝率と回収率をセットで考えると、どの馬に投資価値があるかが見えてきます。
たとえば、複勝率30%で複勝オッズが平均4.0倍の馬は、期待値的には十分にプラスになる可能性があります。
「複勝率×オッズ」のバランスに注目することで、安定性だけでなく妙味ある買い目も見つけやすくなります。
複勝率を使った馬券の組み立て方
複勝率は「どの馬を信頼して馬券を組み立てるか」を判断するうえで極めて有効です。
とくに、馬連や3連複といった連系馬券では、1頭でも着外になると不的中となるため、軸馬の安定感が重要になります。
ここでは、複勝率をもとにした軸馬選びと、人気とのギャップから狙い目を見つける視点を紹介します。
複勝率から軸馬を選ぶ
馬券で利益を上げるには、まず信頼できる「軸馬」を見つけることが第一歩です。
複勝率が40%以上の馬は、3着以内に来る可能性が高く、馬連や3連複の中心に据えるのに適しています。
過去10戦中7戦以上で複勝圏に入っているような馬は、展開や馬場に左右されにくい安定型と見なせます。
出走頭数が多いレースでも、こうした馬を軸に据えることで的中率が向上します。
人気と複勝率のギャップに注目
複勝率は高いのに人気がない馬は「過小評価」されている可能性があり、絶好の狙い目です。
例えば、7番人気ながら複勝率が35%ある馬がいれば、オッズとのバランスから妙味十分です。
逆に、人気があるのに複勝率が低い馬は「過剰人気」であることも多く、注意が必要です。
人気順と実力(複勝率)のギャップに着目することで、思わぬ高配当を狙うチャンスが広がります。
まとめ:複勝率で安定性を見極め、的中精度を高めよう
複勝率は、馬や騎手の「安定感」を数値で可視化できる便利な指標です。
特に馬券を組み立てる際には、信頼できる軸馬を見つけるための材料として重宝されます。
また、人気別・騎手別の複勝率や、複勝率とオッズのバランスを見ることで、狙うべき馬や買い目の妙味も見えてきます。
ただし、複勝率が高ければ必ず儲かるわけではないため、複勝回収率や期待値とのバランスも意識することが重要です。
数字に基づいた予想を心がければ、的中率だけでなく長期的な回収率の向上にもつながるでしょう。

