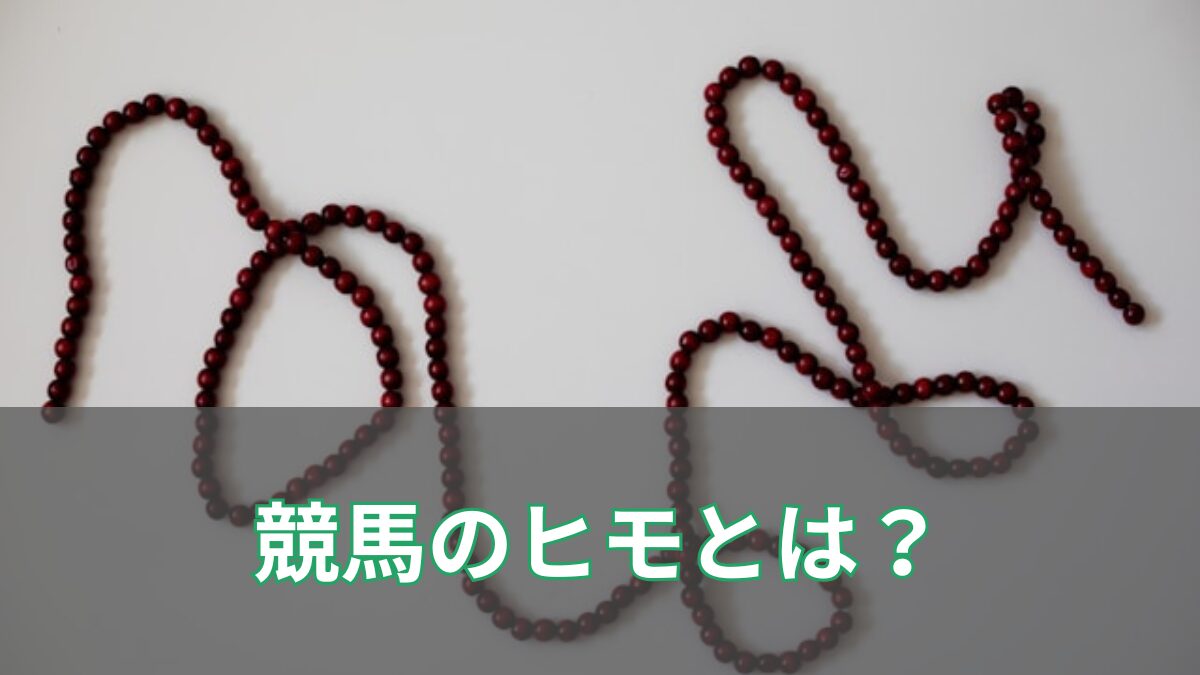競馬ファンのあいだでよく使われる「ヒモ」という言葉。
なんとなく聞いたことはあっても、その正確な意味や使い方を知らない方も多いのではないでしょうか。
ヒモとは、軸馬に対する「相手馬」のことであり、特に馬連や三連系の馬券では、このヒモ選びが的中率・回収率を左右する重要なポイントになります。
この記事では、「ヒモとは何か」という基本から、紐決着・ヒモ抜け・ヒモ荒れといった関連用語の意味、さらに失敗しないヒモの選び方まで、わかりやすく解説していきます。
これから馬券戦略を組み立てるうえで、必ず役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
競馬における「ヒモ」とは?
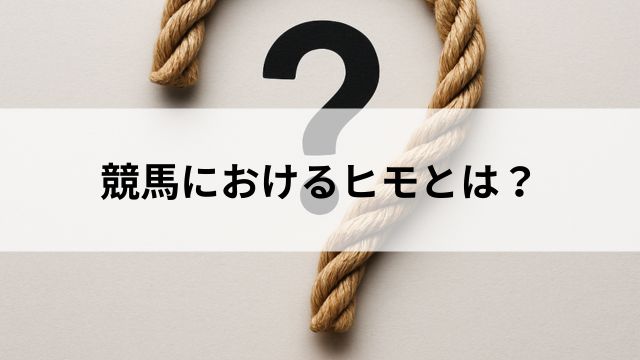
競馬における「ヒモ」とは、軸馬に対して一緒に馬券に絡める“相手馬”のことを指します。
馬連や三連複、三連単といった券種では、1着になる馬(軸)だけでなく、2着・3着に入る馬の予想も必要です。
このとき、軸以外の選択肢として選ばれる馬が「ヒモ」と呼ばれています。
もともとは「1着が堅いとされるレースで、2着に来ると思われる馬」という意味で使われていましたが、現在ではより広い意味で、軸馬以外の全ての相手馬を指す言葉として定着しています。
「ヒモ抜け」「ヒモ荒れ」「紐決着」などの関連表現も多く、競馬予想における重要な概念のひとつです。
馬券を的中させるためには、ヒモの精度が鍵となるため、しっかりと理解しておくことが大切です。
ヒモに関連する言葉の意味と用法
「ヒモ」という言葉には、いくつかの関連用語があります。
まず代表的なのが「ヒモ抜け」です。これは軸馬は来たのに、ヒモとして選んだ相手馬が馬券に絡まず、的中を逃すことを指します。
次に「ヒモ荒れ」は、軸馬は人気馬などで無難に走ったものの、ヒモに人気薄の馬が来たことで配当が大きく跳ねた状況のこと。
さらに「紐決着」とは、軸馬が凡走し、ヒモに選んだ馬たちだけで馬券圏内が決まってしまうことを意味します。
これらの表現は、予想の反省やレース後の振り返りで頻繁に使われます。
正しく理解しておくことで、馬券が外れた原因を客観的に分析できるようになり、次回の予想精度向上にもつながるでしょう。
ヒモが重要になる馬券の種類
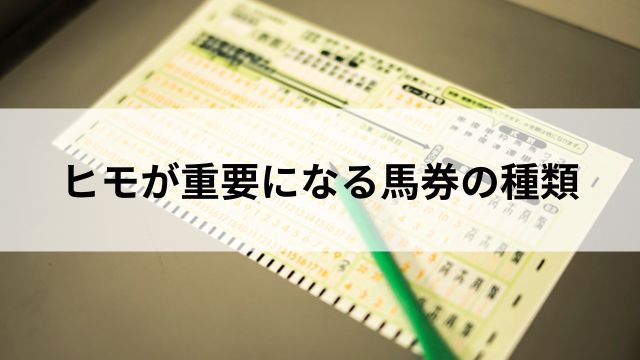
「ヒモ」という存在が特に重要になるのは、複数の馬を組み合わせて当てる馬券を購入する場合です。
単勝や複勝では必要ありませんが、馬連・馬単・ワイド・三連複・三連単などでは、軸馬に加えて相手馬=ヒモの選定が的中の鍵を握ります。
特に三連複や三連単のような三頭を当てる券種では、ヒモを何頭選ぶかで買い目の点数も配当の期待値も大きく変わってきます。
ヒモが的中すれば高配当も狙える一方、外れれば「ヒモ抜け」で大損になることも珍しくありません。
そのため、どの券種を選ぶかによって、ヒモに求められる精度や役割も変わってくるのです。
初心者はワイドや馬連など、ヒモ選びの難易度が低い券種から始め、徐々に三連系へとステップアップするのも一つの方法です。
各券種におけるヒモの役割
馬券の種類によって、ヒモに求められる役割や重要度は異なります。
まず馬連や馬単では、軸馬に対する相手を1頭だけ選ぶため、ヒモの選定精度が非常に重要です。
ワイドは3着以内に入った2頭の組み合わせを当てる券種で、着順を問わないためヒモ選びのハードルは低く、初心者向きといえるでしょう。
三連複になると、1~3着すべての馬を選ばなければならず、ヒモは2頭以上必要になります。
さらに三連単では着順まで正確に当てなければならず、ヒモ選びがもっとも困難かつ重要なポイントとなります。
このように、券種ごとにヒモの求められる役割が異なるため、自分の予想スタイルや経験に合わせて馬券とヒモの選び方を工夫することが大切です。
ヒモの選び方|失敗しないための基本戦略

ヒモ選びは、馬券の的中率と回収率を左右する極めて重要なプロセスです。
しかし、ただ人気順に並べるだけでは高配当を狙えず、かといって無計画に人気薄を並べると的中率が下がります。
そこで、ヒモを精度よく選ぶための基本戦略を紹介します。
まず有効なのは消去法です。明らかに来なさそうな馬(距離不適、展開不利、直近成績が極端に悪い馬など)をヒモ候補から先に外すことで、残る馬に集中できます。
次に重要なのが軸馬との相性です。レース展開を想定し、逃げ馬が残る展開なら先行馬をヒモに、差しが届きやすそうなら末脚に期待できる馬をピックアップします。
また、オッズと人気バランスにも注目しましょう。軸が人気馬であればヒモに中穴を、軸が中穴なら人気馬を加えることで、的中率と配当のバランスが取れます。
さらに、騎手の乗り替わりや重賞実績、過去の同条件成績なども参考になります。
これらの視点を組み合わせれば、勘や感覚に頼らず、理論的にヒモ馬を選べるようになるでしょう。
ここからは、4つの要素について詳しく解説します。
来ない馬を先に除外する
ヒモ選びの第一歩は、「来そうにない馬を外す」ことです。
すべての出走馬を対象にヒモ候補を探そうとすると、選択肢が多すぎて絞りきれなくなってしまいます。
そのため、まずは明確な根拠をもって“切る馬”を決めることが大切です。
たとえば、近走で大きく負け続けている馬、距離や馬場に実績のない馬、過去に同じ舞台で凡走している馬などは、ヒモ候補から外して構いません。
特に単勝人気が12番以下の馬は、過去の統計上、複勝率も回収率も大きく落ちるため、よほどの理由がなければ消すべきです。
三連系の馬券では、1頭除外するだけで買い目が大幅に減らせるので、回収率を上げたい人ほどこの“消去法”を意識して取り入れましょう。
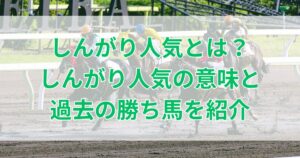
軸馬との脚質・展開の相性を見る
ヒモを選ぶ際は、単に強そうな馬を拾うだけでなく、軸馬との“相性”にも目を向ける必要があります。
特に重要なのが、脚質と展開のバランスです。
たとえば、逃げ馬を軸にした場合、前が止まらない展開が予想されるなら、同じく前で運べる先行馬がヒモ候補になります。
逆にハイペース濃厚で差し・追い込みが決まりそうなら、脚を溜めて末脚を伸ばせるタイプを選ぶべきです。
また、枠順やコース形態によって有利不利が生じる場合もあるため、軸馬が得意な条件下で力を発揮できる馬をヒモに選ぶと、レース全体の流れに沿った予想が組み立てられます。
軸馬の勝ちパターンに合ったヒモ馬を選ぶことで、馬券の精度をより高めることができるでしょう。
人気・オッズ帯のバランスを取る
ヒモ選びでは、オッズ帯のバランスを意識することも重要です。
すべて人気馬で固めてしまえば的中率は上がるかもしれませんが、配当妙味に欠け、回収率が伸びにくくなります。
逆に人気薄ばかりを狙うと一撃の夢はありますが、的中率が極端に下がり、長期的に見ると資金が持たなくなります。
そこで意識したいのが、軸馬のオッズに応じてヒモのオッズ帯を変える戦略です。
たとえば、軸馬が1番人気や2番人気なら、ヒモには中穴(オッズ10倍〜30倍)の馬を選び、高配当の可能性を狙います。
一方で、軸馬が中穴〜人気薄なら、ヒモに人気上位馬を絡めて的中の現実味を持たせましょう。
このように、人気とオッズのバランスを取ることで、的中率と回収率のバランスが良い買い目を作ることができます。
騎手・血統・ローテーションも加味する
ヒモ候補を絞る際は、数字だけでなく“人”や“背景”にも注目しましょう。
まず騎手については、乗り替わりによる上昇効果に期待できるケースがあります。
たとえば、実績あるベテラン騎手や重賞巧者への乗り替わりは、人気薄でも一発があるためヒモ候補として有力です。
また、血統も意外に重要です。
小回りコースや重馬場適性など、条件にマッチした血統背景を持つ馬は、近走成績にかかわらず走ってくるケースが少なくありません。
加えて、ローテーション(出走間隔)にも注意しましょう。
間隔を詰めて叩き2戦目で調子を上げてくる馬や、休み明けで一変するタイプは過去の傾向から拾うことができます。
データに表れない“裏要素”にも目を向けることで、人気に隠れたヒモを発見できる可能性が高まります。
ヒモの予想に役立つ情報源
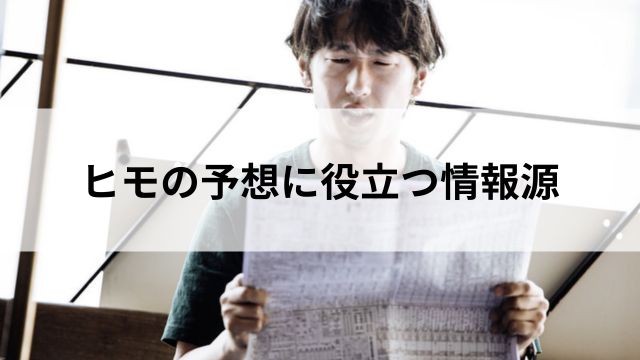
ヒモを効率よく選ぶためには、信頼できる情報源の活用も大切です。
まず定番は競馬新聞やスポーツ紙の印。展開予想やスピード指数、記者の見解からヒモ候補を絞ることができます。
次にJRA-VANやターゲットフロンティアなどの競馬データベースも有用で、コース適性や騎手成績、過去レースの分析などが可能です。
また、YouTubeやX(旧Twitter)などで発信されている予想家の見解も参考になりますが、鵜呑みにせず“なぜその馬をヒモにするのか”という根拠に注目しましょう。
複数の情報源を照らし合わせることで、精度の高いヒモ選びが実現できます。
まとめ:ヒモ選びは回収率アップのカギ
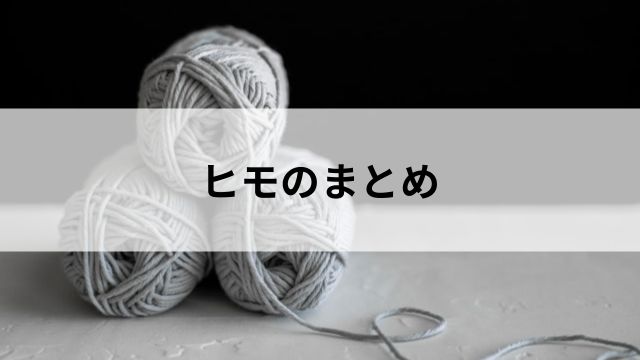
競馬における「ヒモ」は、単なる“相手馬”というだけでなく、馬券戦略を左右する重要な存在です。
的中率を高めるには、軸馬だけでなく、展開や条件に合ったヒモを選ぶ力が求められます。
消去法やオッズのバランス、脚質・血統・騎手などを多角的に分析すれば、精度の高いヒモ選びが可能になります。
また、ヒモが多くなりすぎた場合はレースを見送る判断も重要です。
高配当を狙いつつ、回収率を意識した買い方を実践することで、ヒモ選びはあなたの競馬力を大きく向上させる武器となるでしょう。