競馬ファンや馬券予想家のあいだで時折耳にする「滞在競馬」という言葉。
これは、レース当日に輸送するのではなく、数日前から開催地の競馬場に滞在して調整を行い、そのままレースに臨むというスタイルを指します。
輸送によるストレスを軽減し、落ち着いた状態で実力を発揮できることから、特に夏のローカル開催や輸送が苦手な馬にとって重要な戦術となっています。
本記事では、滞在競馬の定義や目的、メリット・デメリット、さらに向いている馬の特徴や近年の傾向について詳しく解説します。
滞在競馬とは何か?
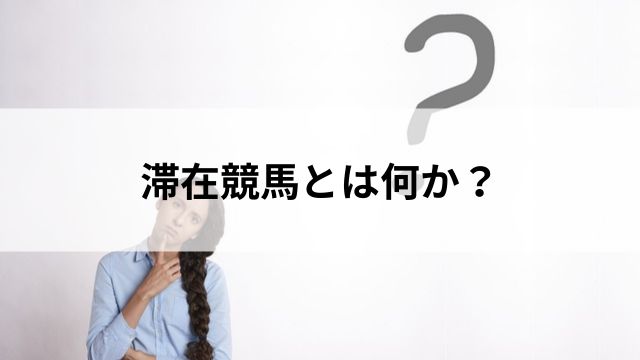
競馬における「滞在競馬」とは、レースの当日ではなく、数日前から出走予定の競馬場に入厩し、現地で調教を積んでからレースに挑むスタイルのことを指します。
かつては新潟・小倉・福島・函館など、トレーニングセンター(美浦・栗東)からの当日輸送が難しい競馬場では広く行われていましたが、現在では当日輸送が主流となり、完全な滞在型は減少傾向にあります。
それでも、馬の性格や体調、過去の傾向によっては滞在競馬が選択されるケースも多く、特に輸送に弱い馬や夏のローカル開催などでは、今もなお有効な戦術として活用されています。
また、北海道シリーズでは函館に滞在しながら札幌で走るといった“準滞在型”も一般的で、競走馬のコンディションを整える上で重要な選択肢の一つとなっています。
滞在競馬が行われる理由とは?
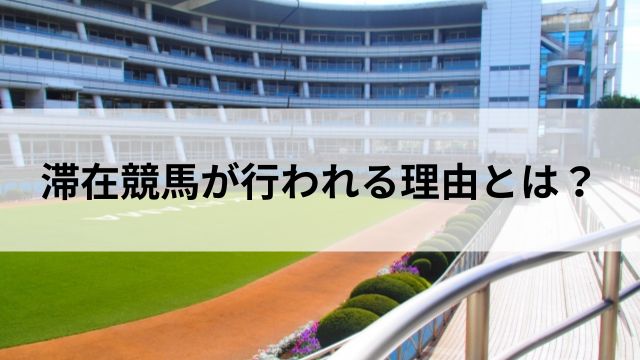
滞在競馬が選ばれる背景には、馬にかかる輸送の負担があります。
とくに繊細な性格の馬や長距離輸送に不安のある馬にとって、移動はパフォーマンス低下の原因になりかねません。
そのため、あらかじめ開催地に滞在することで落ち着いた状態を保ち、調教からレースまで一貫した流れで臨めるようにするのが目的です。
以下では、滞在競馬が行われる具体的な理由を2つの視点から解説します。
輸送によるストレスを回避するため
競走馬は非常に繊細な動物であり、輸送時の振動や環境の変化、馬運車内での長時間拘束といった要素は、大きなストレスになります。
特に、神経質な馬や初めて長距離輸送を経験する2歳馬などは、こうした移動によって馬体重が減ったり、レース前にテンションが上がってしまう傾向があります。
滞在競馬を選ぶことで、これらのリスクを大幅に抑えることができ、馬が本来の力を発揮しやすくなるのです。
環境に慣らしてパフォーマンス向上を図る
競馬場の音や匂い、人の多さなど、普段とは違う環境に置かれると、精神的にナーバスになる馬もいます。
滞在競馬では、数日前から現地入りすることで、調教中に競馬場の雰囲気に慣れさせることができ、レース当日の入れ込みや無駄な消耗を防ぐ効果が期待されます。
また、開催地の馬場傾向や気温、湿度に合わせた調整も可能になるため、最終仕上げの精度が上がり、結果的に好走率も向上しやすくなるのです。
滞在競馬のメリットとデメリット

滞在競馬は、馬の状態を安定させて力を引き出すための有効な戦術ですが、決して万能ではありません。
費用や管理面での課題も多く、すべての馬に適しているとは限らないのです。
ここでは、滞在競馬の代表的なメリットとデメリットを具体的に見ていきましょう。
滞在競馬のメリット
最大の利点は、輸送による馬の疲労やストレスを軽減できる点です。
特に気性の難しい馬や若駒にとっては、落ち着いて現地で調整できることが大きなアドバンテージとなります。
また、開催地の馬場状態や気候に合わせて柔軟な調教を行えるため、レース当日の適応力も高まりやすくなります。
さらに、北海道シリーズのように複数開催を跨いで出走する場合、現地に滞在することで無理のないローテーションを組むことが可能になります。
こうした環境的な安定が、好走率や馬の成長につながることも少なくありません。
滞在競馬のデメリット
一方で、滞在競馬にはコストや管理面での負担も伴います。
馬房や調教施設の確保、スタッフの出張、輸送費などが重なり、経済的な負担が大きくなりがちです。
また、すべての馬が環境の変化に順応できるわけではなく、現地で気性が荒くなったり体調を崩すケースもあります。
慣れない土地での飼養や調教により、本来の力を発揮できなくなる可能性もあるため、陣営は慎重な判断が求められます。
加えて、現地調整を選んだ場合でも、レース当日は地元馬と同条件とは限らず、不利な環境下での戦いになることも考慮すべきです。
滞在競馬が向いている馬の特徴とは?
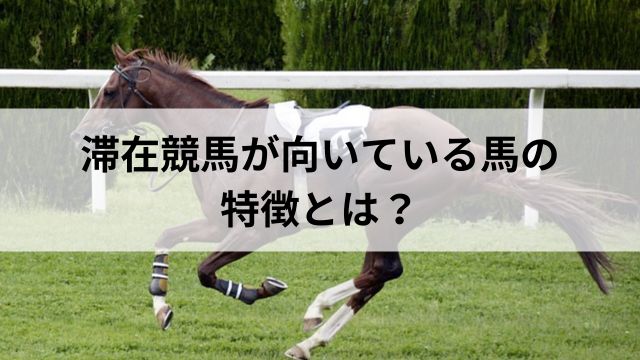
滞在競馬はすべての馬に適しているわけではありません。
その効果を最大限に発揮できるのは、輸送によるダメージを受けやすい馬や、精神的に不安定なタイプ、あるいは特定のローテーションで出走する馬に限られます。
ここでは、どのような馬が滞在競馬に向いているのか、代表的な3つのタイプを紹介します。
輸送に弱い馬
馬運車での移動中に大きく馬体重を減らす、あるいはレース前に疲労が見られる馬は、典型的な“輸送に弱いタイプ”です。
このような馬は、当日輸送では本来の力を出し切れないことが多いため、事前に現地入りして滞在調整を行うことでコンディションが安定し、好走につながるケースが目立ちます。
精神的に繊細な馬
周囲の物音や人混み、初めての環境に過敏に反応するような気性の難しい馬も、滞在競馬が向いています。
事前に滞在して環境に慣れさせることで、レース当日の入れ込みやパドックでの消耗を軽減できるため、落ち着いた精神状態でレースに臨むことが可能になります。
北海道シリーズに出走予定の若駒
函館・札幌で行われる2歳新馬戦では、北海道で初めて競馬場を経験する馬も多く登場します。
こうした若駒にとって、長距離輸送を省いて現地でデビューを迎える滞在競馬は、ストレスを最小限に抑えるうえで非常に効果的です。
特に初戦で良い印象を持たせることは、今後の競走生活にも好影響を与える可能性があります。
滞在競馬の現在と今後の展望

かつてはローカル開催で主流だった滞在競馬ですが、輸送技術や道路事情の改善により、近年では当日輸送が主流となりつつあります。
それでもなお、馬の個性や出走ローテーションに応じて滞在を選ぶケースもあり、特に夏季の特定開催では重要な戦略として健在です。
ここでは、現在の滞在競馬の運用実態と、今後も続くであろうケースを紹介します。
小倉や福島、新潟は滞在競馬か?
一昔前までは、関東馬が小倉へ、関西馬が新潟・福島へ参戦する際には、現地に滞在して調整するスタイルが一般的でした。
しかし現在は、トレセンで調教を行い、レース当日に馬運車で競馬場入りする「当日輸送」が主流になっています。
とはいえ、関西馬にとっての福島や新潟、関東馬にとっての小倉など、物理的な距離が長い競馬場に出走する際には、滞在を選ぶ厩舎も一定数存在します。
馬の気性や過去の輸送実績を考慮したうえで、慎重に判断されているのが現状です。
北海道開催における実例
現在でも滞在競馬が色濃く残っているのが、函館や札幌で行われる北海道シリーズです。
多くの馬は函館競馬場に滞在し、そこで調整を行ったうえで、必要に応じて札幌へ輸送して出走する“準滞在型”が主流です。
とくに2歳馬のデビュー戦では、長距離輸送の負担を避ける目的で現地滞在が重視されており、育成牧場からそのまま函館に直行するケースも見られます。
こうした滞在は、精神面の安定にもつながるため、今後も北海道開催では主要な調整スタイルとして続いていくでしょう。
滞在競馬のまとめ|勝負仕上げのカギになる戦略
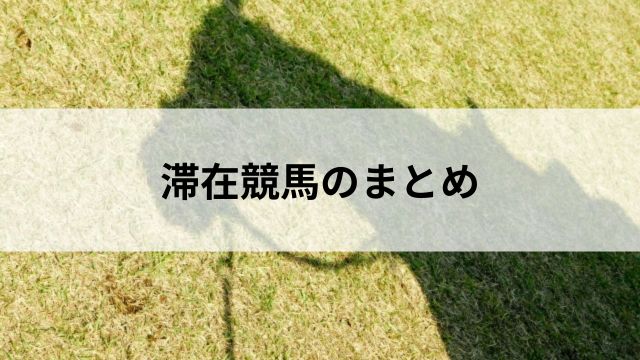
滞在競馬は、輸送によるストレスを回避し、落ち着いた環境でレースに臨ませるための有効な戦略です。
とくに輸送に弱い馬や若駒にとっては、パフォーマンスを安定させる上で大きなメリットがあります。
一方で、コストや管理の負担、環境への適応といった課題もあるため、すべての馬に適しているとは限りません。
それでも、北海道シリーズや夏のローカル開催など、今後も滞在競馬が重要な戦術となるシーンは多く残されています。
馬の個性を理解し、最適な環境でレースに臨ませることが、好走への第一歩と言えるでしょう。

