2021年のダービー馬・シャフリヤールが、種牡馬入りからわずか半年で引退するというニュースが競馬界に衝撃を与えました。
その理由は「受胎率の低さ」。
種牡馬として成功するには、優れた競走成績だけでなく、繁殖面での実績も不可欠です。
この記事では、受胎率とは何か、なぜ重要視されるのかを解説しながら、シャフリヤールの引退理由や過去の類似例についても掘り下げていきます。
競馬の受胎率とは?
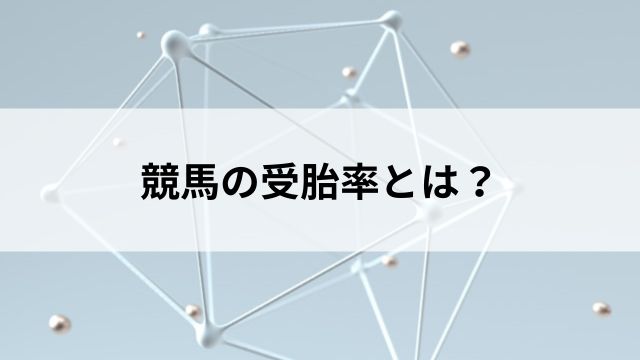
競馬における「受胎率」とは、種牡馬と繁殖牝馬が交配した際に、実際に受胎が成立する割合を示す数値です。
この指標は、種牡馬の繁殖能力を評価するうえで非常に重要な役割を果たしています。
生産現場では、限られた期間で多くの繁殖牝馬に受胎させる必要があるため、受胎率の高さは種牡馬としての価値に直結します。
ここでは、受胎率の平均値や計算方法、そしてシャフリヤールの実例をもとに詳しく見ていきましょう。
受胎率の平均は?
受胎率の平均は一概には言えませんが、目安としてはおおむね80%前後が一般的とされています。
ただし、これは種牡馬の個体差だけでなく、交配する繁殖牝馬の健康状態や管理体制、種付けの時期などによっても大きく変動します。
いわば、馬の「生産性」を左右する重要な数値です。
受胎率の求め方
受胎率は、次のような計算式で求められます。
(受胎頭数 ÷ 種付けまたは人工授精頭数) × 100
例えば、100頭の繁殖牝馬に種付けして80頭が受胎すれば、受胎率は80%です。
この数値が高いほど、生産者にとっては経済的かつ効率的な種牡馬と評価されやすくなります。
シャフリヤールの受胎率は何%だったか
2025年に種牡馬入りしたシャフリヤールは、初年度に74頭の繁殖牝馬と交配しました。
しかし受胎が確認されたのは、わずか10頭のみです。
この結果、受胎率は約13.5%にとどまり、平均とされる80%と比べて大きく劣っていました。
期待のダービー馬でありながら、わずか半年で種牡馬を引退する決断に至った背景には、この低すぎる受胎率があったのです。
なぜシャフリヤールは半年で種牡馬引退となったのか
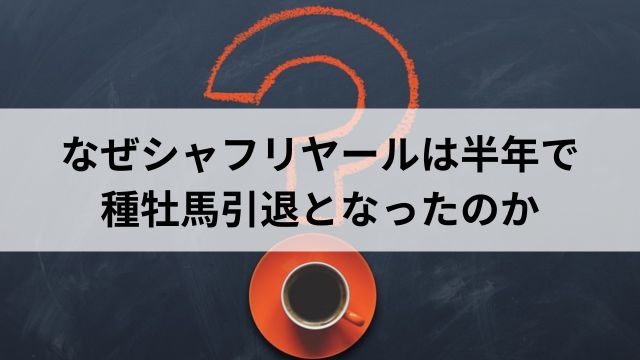
2021年のダービー馬として注目を集めたシャフリヤールは、2025年に種牡馬入りを果たしました。
しかし、そのわずか半年後に種牡馬引退という異例の事態となりました。
ここでは、シャフリヤールの早期引退の背景にあった「受胎率の低さ」や「ライバル種牡馬との競争」など、複数の要因を詳しく見ていきます。
受胎率が低かったから
シャフリヤールが種牡馬として失敗に終わった最大の理由は、極端に低い受胎率です。
74頭の牝馬と交配して受胎したのはわずか10頭、受胎率は約13.5%。
この数値では、生産者側としても翌年以降の種付けを依頼しにくく、経済的なリスクが大きくなります。
さらに、睾丸の疾患を患っていた可能性も指摘されており、健康状態が交配能力に影響を与えたと考えられます。
体調面の問題が繁殖成績に直結することは珍しくなく、わずか半年での引退という決断に至ったのは致し方ないとも言えるでしょう。
ライバル種牡馬が多くいた
もうひとつの要因は、シャフリヤールと同じディープインパクト産駒のライバルが多かったことです。
ディープの代表的な後継馬としては、すでに成功を収めているキズナや、無敗三冠馬のコントレイルがいます。
さらに、シャフリヤールの全兄であるアルアインも先に種牡馬入りしており、血統的な魅力の差別化が難しい状況でした。
結果として、生産者から「他のディープ後継で十分」と判断されることも多く、シャフリヤールの需要は限定的だったと考えられます。
血統・実績ともに優秀であっても、市場競争の中で選ばれなければ、種牡馬としての立場を維持するのは困難です。
受胎率が低かった名種牡馬

受胎率の低さは種牡馬として大きなハンデになりますが、それでも一部の馬は、限られた産駒数から後世に影響を与える名馬を輩出し、評価を高めてきました。
ここでは、代表的な例としてメジロアサマとウォーエンブレムという2頭の種牡馬に注目し、その特徴と実績を紹介します。
メジロアサマ
1970年の天皇賞(秋)を制した名馬・メジロアサマは、引退後に種牡馬入りしましたが、極端に受胎率が低く、大きな壁に直面します。
原因は、現役時代に感染した馬インフルエンザの治療に使われた抗生物質の影響とされ、精子の量が極端に少なく、受精能力が著しく低下していたのです。
このため、一時は「種牡馬失格」とさえ言われました。
それでも、オーナー北野豊吉氏は諦めず、試行錯誤の末にわずか20頭の産駒を残すことに成功します。
その中には、のちに天皇賞を制すメジロティターン、そしてその息子であり名ステイヤーとして知られるメジロマックイーンの姿がありました。
さらにメジロマックイーンはブルードメアサイアーとしても活躍し、特にステイゴールド系との交配で生まれた子からはオルフェーヴルとゴールドシップへいう、個性的な実力馬を輩出するに至ります。
メジロアサマと北野豊吉氏の尽力が、天皇賞親子制覇、史上7頭目のクラシック三冠馬の礎になったのでした。
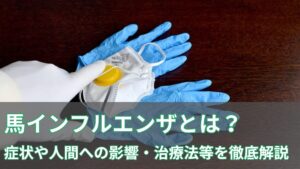
ウォーエンブレム
ウォーエンブレムは2002年にケンタッキーダービーとプリークネスステークスを制したアメリカ二冠馬です。
社台グループが21億円で導入し、日本で種牡馬入りしましたが、極端に性癖が偏っており、小柄な栗毛にしか興味を示さなかったのです。
それ以外の馬には興味を示さなかったことから、供用1年目の種付け数は7頭、2年目こそ関係者の尽力で50頭ほどの交配に成功しましたが、3年目は9頭、4年目は1頭のみになったのでした。
ウォーエンブレムの性格のため、シンジケートを組んだにもかかわらず、産駒数には恵まれませんでした。
しかしながら、数少ない産駒の中から秋華賞馬ブラックエンブレムや阪神JFを制したローブティサージュ、ダートの川崎記念を制したオールブラッシュなど、芝・ダート問わずG1馬が出ています。
もしもウォーエンブレムがまともに種付けを行っていたらもっと産駒に恵まれていましたし、サンデーサイレンスのように競馬界を覆すような種牡馬になれたかもしれません。
2026年 シャフリヤールの供用続投が決定
シャフリヤールはその受胎率の低さから、一時は種牡馬引退が発表されていました。
ところが、2025年11月の情報によると、2026年以降も種牡馬を続投するようです。
管理するノーザンファームの吉田勝己氏によると、一時は引退も考えていたようですが、しばらくして交配したところ、うまくいったようで、これなら受胎率回復にも期待できるようでした。
一時は絶望的な受胎率ですが、今後も種牡馬として供用されるということで、シャフリヤールの仔の誕生に期待したいです。
まとめ:受胎率は種牡馬にとって非常に重要

競走馬としてどれほど実績があっても、「受胎率」は種牡馬としての未来を左右する極めて重要な指標です。
シャフリヤールはあまりに低い受胎率により、種牡馬入りから半年で引退に追い込まれましたが、その後交配したところ、問題なく受胎したことで種牡馬続投が決まりました。
シャフリヤールの件は極めて珍しいですが、まずは種牡馬として今後も活躍できるようで何よりです。
メジロアサマやウォーエンブレムのように困難を乗り越えて「価値ある血」をつないだ名馬たちと同様、彼にも新たな役割が期待されています。

