競馬を見ていると、解説や新聞のコメントなどで「叩き」「叩き台」「叩き合い」といった言葉を目にすることがあります。
とくに「今回は叩きだから度外視できる」「叩き二戦目で上昇」といった表現はよく使われていますが、意味を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。
この記事では、競馬用語としての「叩き」の意味をわかりやすく解説します。
あわせて、「叩き台」や「叩き合い」、「鉄砲型」など関連用語の違い、そして叩きレースの見抜き方についても紹介します。
初心者の方でもすぐに実践に役立てられる内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。
競馬の叩きとは?叩きに関する用語も紹介

競馬の世界では「叩き」という言葉がさまざまな場面で使われます。
初心者の方にとっては少し分かりにくい専門用語かもしれませんが、叩きの意味を理解することで、馬の仕上がりや陣営の意図が読み取りやすくなります。
ここでは「叩き」の基本的な意味に加えて、「叩き合い」や「叩き台」、「鉄砲型」といった関連用語についてもわかりやすく解説していきます。
叩きとは休養明けでレースに出走すること
競馬用語での「叩き」とは、休養明けの馬が実戦を使って調子を上げていく過程を指します。
つまり「叩き」とは、目標レースに向けた調整として使われるレースのことです。
例えば、秋のG1に備えて夏に一度レースを使うような場合、その出走は「叩き」とみなされます。
この叩きレースでの着順よりも、その後の上昇度を重視するのがポイントです。
叩き合いは直線で複数の馬が競り合うこと
「叩き合い」とは、ゴール前で2頭以上の馬が激しく競り合うことを表す表現です。
レース実況などで「壮絶な叩き合い!」といったフレーズを聞いたことがある方も多いでしょう。
この場合の「叩き」は、騎手が馬にムチを入れたり、馬同士が全力を出し合って力をぶつけ合っている様子を指しています。
調整レースとしての「叩き」とは全く意味が異なるため、混同しないよう注意が必要です。
叩き台は一回使って良化に期待すること
「叩き台」とは、目標レースに向けて一度レースを使い、状態を整える目的での出走を意味します。
本番に向けて馬のコンディションやレース勘を取り戻すために行う実戦調整です。
例えば、「天皇賞(秋)を本番と見て毎日王冠は叩き台」といった使い方をします。
この場合、毎日王冠での成績が振るわなくても、本番でのパフォーマンス向上が目的なので、そこまで気にする必要はありません。
叩き良化型は一回使ったほうが状態が良くなる馬のこと
「叩き良化型」とは、休養明けよりも一度使ったほうがレース内容が良くなるタイプの馬を指します。
つまり、実戦を通じて状態が仕上がってくる馬です。
このタイプは、叩き初戦では本来の走りができなくても、二戦目・三戦目で一変することがあります。
馬柱に「叩き良化」と書かれているときは、このタイプの可能性が高いと言えるでしょう。
久々でも結果を残す馬を鉄砲が利くという
「鉄砲が利く」とは、休み明けの一戦目でもいきなり好走できる馬のことを指します。
このタイプは調教だけでもある程度仕上がり、本番に合わせてしっかり力を出せるのが特徴です。
血統や体質、気性などによって鉄砲の利きやすさは異なり、叩き良化型の馬とは対照的な存在といえます。
「休み明けでも買える馬」かどうかを見極める上で、鉄砲型かどうかの判断は重要です。
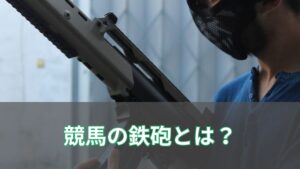
ファンが誤解しやすい「ムチの叩き」とは違う意味
「叩き」という言葉から、ムチで馬を叩くシーンを連想する方も多いかもしれません。
たしかにレース終盤で鞭を入れる場面はありますが、競馬用語としての「叩き」はそれとは別の意味です。
JRAではムチの使用回数にもルールがあり、過剰な使用には制裁もあります。
今回の記事で解説する「叩き」はあくまでレースを通じた調整や状態の良化を指すもので、ムチの使用とは無関係です。
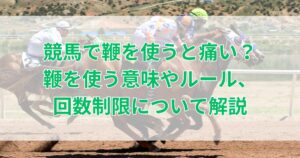
競走馬は一叩きしたほうが勝率が上がる?
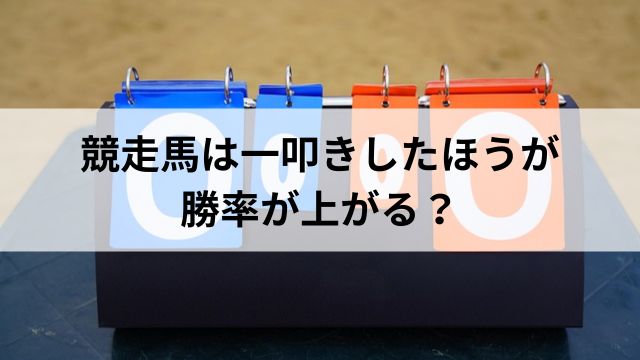
競馬では「一叩きして状態が良くなる」と言われることが多く、実際に休み明け2戦目でパフォーマンスを上げてくる馬も少なくありません。
とはいえ、すべての馬にこの傾向が当てはまるわけではなく、タイプによって明確な違いが見られます。
ここでは「叩き良化型」と「鉄砲型」の特徴を比較しながら、見極め方のポイントを紹介していきます。
競走馬によって異なる
叩きレースでの反応は、すべての競走馬に共通するわけではありません。
体質が強く、初戦から力を出せる馬もいれば、実戦を重ねて調子を上げていくタイプもいます。
年齢や性別、過去のローテーションや調教師の方針によっても違いが出るため、個々の馬の特徴を見極めることが重要です。
一概に「叩き二戦目が有利」と決めつけず、馬ごとの傾向に注目するようにしましょう。
叩き良化型と鉄砲型の見極め方は成績を見ると分かる
叩き良化型と鉄砲型を見分けるうえで最も参考になるのが、過去のレース成績です。
具体的には、休み明け初戦(○ヶ月ぶりなどと表記)で凡走し、2戦目や3戦目で成績が上がっている場合は叩き良化型の可能性が高いです。
一方、長期休養明けでもいきなり好走している馬は鉄砲が利くタイプといえるでしょう。
また、調教師のコメントや調教時計の出方、レース当日の馬体重の増減も補足的な判断材料となります。
馬柱だけでなく、前後の状況を合わせて読むことが大切です。
叩きレースを見抜くポイント

競馬予想において、「今回は叩きか、それとも本気か」を見極めることは非常に重要です。
なぜなら、調整目的で出走している馬を本気で買ってしまうと、的中率や回収率が大きく下がってしまうからです。
逆に、叩き台で凡走したあとに本番で一変するパターンを見抜ければ、人気薄の馬でも高配当を狙うことができます。
ここでは、陣営の本気度や仕上がり具合を読み解くための具体的な判断ポイントを紹介していきます。
G1レースの前哨戦やトライアルレースは叩きの可能性がある
中央競馬のすべてのG1レースの前には前哨戦やトライアルレースが設けられています。
前哨戦やトライアルレースは優先出走権や収得賞金が得られるほか、いきなりG1に挑むのは身体が仕上がっていない可能性があるため、一戦使うことで良化するための措置として役割を担っています。
しかしながら、近年は外厩整備の充実に伴い、前哨戦やトライアルレースで一叩きしなくてもぶっつけG1で結果を残せるようになりました。
外厩施設で高レベルの調整が可能になったことで、実戦を使わずとも叩きに近い効果を得られるようになったのです。
そのため、前哨戦の役割は優先出走権や収得賞金に集中しています。
それでも、G1に出走するための収得賞金をすでに持っている馬が、前哨戦やトライアルに出てくる場合は、叩きとして使っている可能性が高いです。
2023年のソールオリエンスは皐月賞を制したクラシックホースなので、菊花賞の賞金に余裕がありましたが、トライアルレースのセントライト記念に挑んでいました。
結果は2着でしたが、一叩きしたことで良化したのか、菊花賞では3着に好走しています。
ソールオリエンスのセントライト記念はまさに典型的な叩き台といえるでしょう。
叩きかどうか見極める際は、収得賞金を参考にするのも面白いですよ。
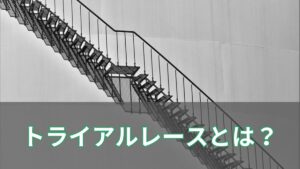
陣営コメントや調教の内容から本気度を見抜く
叩きか本気かを見極めるうえで、陣営のコメントや調教内容は非常に重要な判断材料になります。
特に競馬新聞や公式サイト、YouTubeの調教VTRなどに目を通すと、調教師や騎手の意図が見えてきます。
たとえば「本番は次」「使ってから良くなるタイプ」などのコメントがあれば、今回のレースはあくまで叩き台としての出走である可能性が高いでしょう。
一方で「ここが目標」「仕上がりには自信がある」などの前向きなコメントが出ていれば、仕上げも本気度も高いと見てよさそうです。
また、調教の時計や内容も参考になります。
全体時計を出すだけでなく、ラスト1F(1ハロン)の伸び、終い重点かどうか、併せ馬で遅れていないか、などもチェックポイントです。
叩き台として出走している場合は、1週前や直前追い切りの負荷が軽く、全体的に「無理をしていない」調教内容になっていることが多く見られます。
逆に、本気で勝ちに来ている馬は、調教でもしっかりと負荷をかけてきます。
とくに直前追い切りで強めに追っていたり、併せ馬でしっかり先着していたりすると、勝負気配が高いと判断できます。
コメントと調教内容をセットで見ることで、陣営の狙いや馬の状態をより的確に把握できるようになります。
どちらか一方だけでは判断が難しいため、総合的に読み取ることが予想精度を高めるカギとなります。
競馬の叩きとは?まとめ

競馬における「叩き」とは、目標レースに向けて調子を上げるための調整レースのことを指します。
叩き台や叩き良化型といった関連用語を理解することで、馬の仕上がりや陣営の意図をより深く読み取れるようになります。
また、鉄砲型のように初戦から結果を出せる馬もいるため、過去の成績や調教内容、陣営コメントなどを総合的に判断することが重要です。
G1の前哨戦やトライアルでは叩きの可能性もあるため、収得賞金や調整内容から見極める目を養いましょう。
叩きレースを見抜けるようになれば、人気薄から高配当を狙えるチャンスも広がります。
ぜひ、今後の予想に活かしてみてください。

