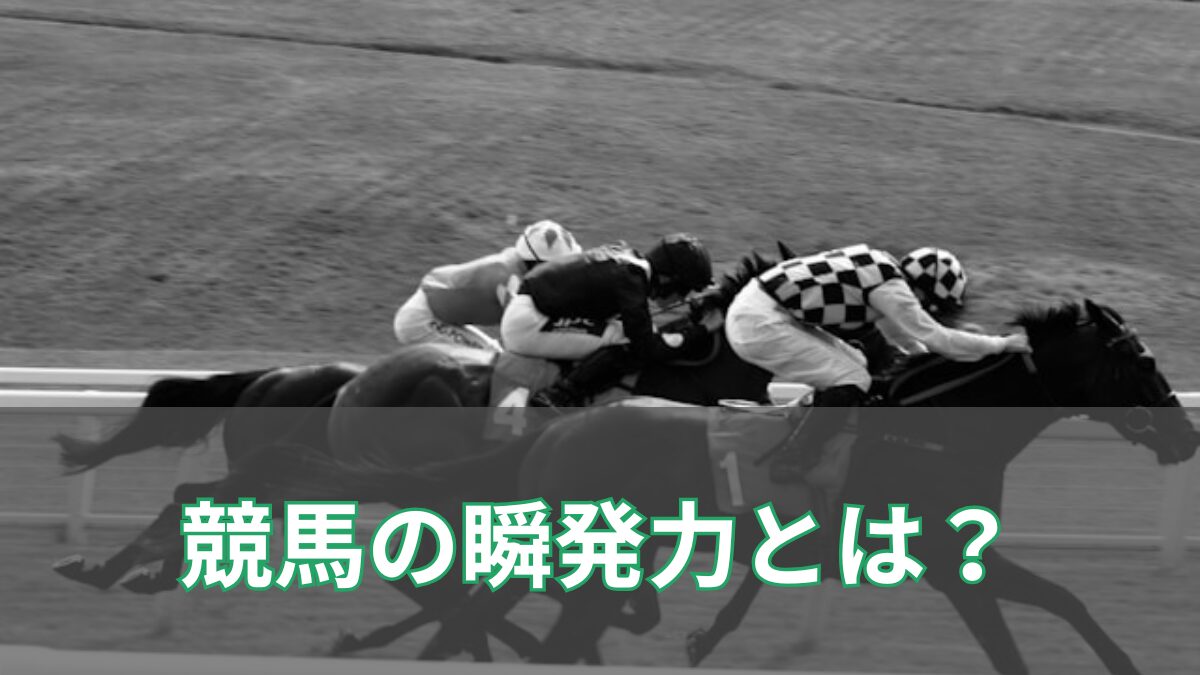競馬において「瞬発力」とは、馬が一気にスピードを加速する力を指します。
直線での末脚勝負や、前が止まった瞬間に差し切るような走りは、まさに瞬発力の賜物です。
英語では「ターンオブフット」とも呼ばれ、日本競馬では「切れ味」という言葉で表現されることもあります。
では、この瞬発力とは具体的にどのような能力で、どんなレース展開で活かされるのでしょうか。
また、瞬発力とよく比較される「持続力」との違いや、血統や馬体によってどう見分けるのかなど、競馬ファンなら知っておきたい知識は多岐にわたります。
この記事では、「瞬発力勝負とは何か?」という基本から、瞬発力に優れる馬の見極め方、そして馬券戦略への活かし方まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説していきます。
瞬発力勝負とは?
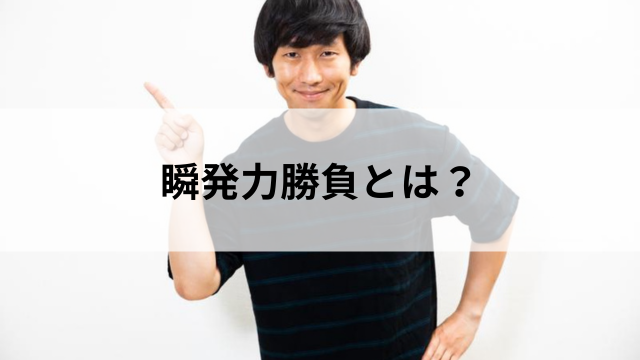
競馬中継などで「今日は瞬発力勝負になりましたね」といった解説を耳にすることがあります。
これはレース展開がスローペースで進み、最後の直線で各馬が一斉にスパートをかける形になったことを指しています。
「ヨーイドンの競馬」とも表現されるように、スタートから直線入口までは各馬が軽いジョギング程度のゆったりしたペースで進み、最後の直線に入った瞬間に一斉に本気で走り出す展開です。
瞬発力勝負では上がり3ハロンの瞬間的な脚で勝敗が決まるため、基本的には瞬発力の優れた馬が有利になります。
しかし同時に、位置取り(ポジション)も重要です。なぜなら、どの馬もスタミナを十分温存したまま最後の直線に入るので、前の方にいる馬がそのまま有利になりやすいからです。
前にいた馬も余力十分で33秒台の上がりを繰り出せるため、後ろにいた馬が勝つにはそれを上回る32秒台前半などの猛烈な末脚が必要になります。
32秒台の末脚はG1級の一握りの名馬にしか出せないタイムであり、平均的な馬ではまず不可能です。
このため、後方待機の馬にとって瞬発力勝負の展開は一見チャンスのようでいて、実は「届かない上がり勝負」に終わってしまうケースも多いのです。
一方で、展開が逆のハイペースになった場合は「消耗戦」とも呼ばれ、各馬が序盤から速いペースで飛ばすためスタミナの消耗が激しく、後半は持久力勝負になります。
ハイペースでは逃げ・先行馬はバテやすく、代わりにスタミナ豊富で長く脚を使える持続力タイプの馬が台頭しやすくなります。
このようにレースの質(瞬発力勝負か持久力勝負か)は展開次第で大きく変わり、それに有利な馬のタイプも変わってくるのです。
まとめると、瞬発力勝負とは「序盤が遅く、最後の直線で一気に各馬が加速する展開」のことであり、切れ味勝負とも言われます。
観客からすれば最後の瞬間まで勝負がもつれるスリリングな展開ですが、騎手や馬にとっては位置取りと加速力が命運を握る難しい戦いです。
瞬発力と持続力の違い
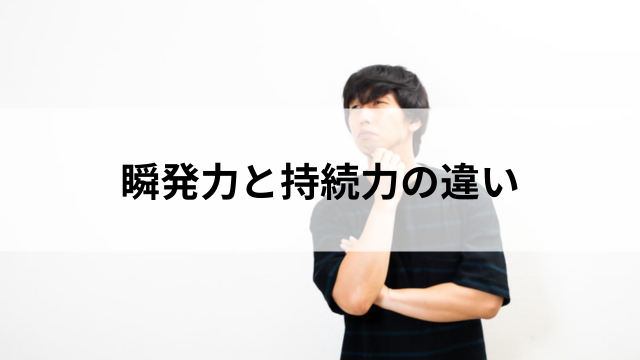
では「瞬発力」と対比される「持続力」とは何でしょうか。
持続力とは文字通りスピードを持続する力のことです。
すなわち、一度上げたスピードを長い距離に渡って維持できる能力や、長くいい脚を使える能力を指します。
瞬発力が「短い距離で一気に加速する力」だとすれば、持続力は「長い距離で高いスピードを維持する力」と言えます。
ここからは、瞬発力と持続力の違いについて解説します。
短い脚 vs. 長い脚
瞬発力タイプの馬は、ギュッと短い距離で速い脚を使う反面、その速い脚は長くは続きません。
俗に「切れるけど持たない」という表現がされ、例えば「ラスト200mだけ猛烈に伸びるが、そこまでに仕掛けると勢いが続かない」ような馬です。
一方、持続力タイプの馬は瞬間的な加速こそ穏やかですが、一度トップスピードに乗ってからは長くその速度を保てます。
まさに「いい脚を長く使える」タイプで、800m〜1,000mに渡ってジリジリと速いラップを踏み続けるような底力があります。
別の言い方をすると、瞬発力タイプはMAXスピードを2〜3ハロン(400〜600m)程度しか続けられない馬で、持続力タイプは3ハロン以上に渡って高いスピードを維持できる馬とも言えます。
もちろん一概には言えませんが、瞬発力と持続力はある種トレードオフの関係になりやすいのです。
実際、多くの馬はどちらかに偏った特徴を持ち、アーモンドアイのように切れる末脚を持つ馬とゴールドシップのような長く末脚を使える馬は好対照な例としてよく語られます。
両馬はともに実力馬でしたが、レース運びの型や得意な展開が異なりっており、どちらも自身の最大限の力を発揮して大舞台で結果を残しています。
ギアチェンジの違い
瞬発力タイプと持続力タイプの違いを、よく自動車に例えることがあります。
瞬発力タイプの馬はまるでオートマ車のように、一瞬でローギアからトップギアへとシフトアップできるのが特徴です。一方、持続力タイプの馬はマニュアル車のように、ギアを徐々に上げながら加速していくイメージです。
オートマ車的な瞬発力タイプは、レース中盤まではエネルギーを温存し、勝負どころで一気にトップスピードに持っていけます。
スローペースで馬群が固まった展開でも、直線で「瞬間移動」のように馬群を縫って抜け出すことがあります。
ただし、その「使える脚の長さ」は短めなので、できれば直線は短い方が理想です。
短い直線で一気に加速し、そのままゴールまで押し切るのが理想形と言えます。
一方、マニュアル車的な持続力タイプは、じわじわとスピードに乗っていく代わりに豊富なスタミナを武器としています。速い流れやタフな展開でもバテにくく、一度エンジンがかかれば長い直線でも減速せずに走り切る底力があります。
逆に言えば、一旦スピードを落としてしまうと再加速に時間がかかるのが弱点で、囲まれてブレーキを踏まされるリスクのある内枠は不利になりがちです。
持続力タイプの馬は、自分のリズムで長く脚を使うことが勝利の鍵なので、多少ロスがあっても外めの進路から徐々にポジションを上げていく方が力を発揮できます。
レース展開への対応
瞬発力タイプと持続力タイプは、そのレース展開への対応の仕方にも明確な差が現れます。
スローペースの瞬発力勝負になった場合、瞬発力タイプの馬は直線までじっと追い出しを我慢して最後に懸けるのに対し、持続力タイプの馬はペースが遅いことを嫌って早めに動くケースがよく見られます。
例えば、道中後方にいた馬が3コーナーあたりから一気にまくって先頭近くまで押し上げるような動きを見せたら、その馬は間違いなく持続力タイプでしょう。
逆に、直線に入るまでじっくり脚を溜めていた馬は瞬発力タイプである可能性が高いです。
こうした動きの違いは、騎手がその馬の持ち味を理解して乗っている証拠とも言えます。
また、瞬発力タイプの馬はハイペースになった場合でも諦める必要はありません。
前が飛ばしすぎて直線で止まる展開になれば、後方から一瞬の切れ味でまとめて差し切るチャンスがあります。
一方、持続力タイプの馬はスローペースでも展開利がないだけでなく、瞬発力勝負についていけず不発に終わるリスクがあります。
したがって、持続力タイプの陣営は敢えて自らペースを上げる戦法をとることもあります。
例えば、2012年有馬記念でゴールドシップが向正面からロングスパートをかけて先頭に並びかけたように、自分から動いて持久力勝負に持ち込むのです。
このように、瞬発力タイプと持続力タイプでは得意な展開と戦法が異なるため、レースを観る際には各馬の動きにも注目すると面白いでしょう。
血統から見る瞬発力の傾向

瞬発力に優れた馬を見極めるうえで、血統は非常に重要なヒントになります。
競走馬の能力や走りの特徴は、父系・母系から色濃く受け継がれることが多く、「切れ味のある産駒が多い系統」や「スタミナ豊富で持続力に長けた系統」など、血統ごとに得意な能力傾向が存在します。
ここでは、瞬発力に影響する血統の系統や代表的な種牡馬を紹介しながら、それぞれの特徴を解説していきます。
瞬発力に優れる血統
日本競馬において瞬発力と聞いて真っ先に名前が挙がるのが、名種牡馬サンデーサイレンス系の血統です。
サンデーサイレンス自身がアメリカ生まれながら卓越した瞬発力を武器にしており、その産駒たちも日本の高速馬場で大成功を収めました。
現代競馬は中盤でペースをセーブして直線勝負という傾向が強いため、この瞬発力に優れるサンデーサイレンス系は非常に活躍しやすく、日本の競走馬の主流となっています。
サンデーサイレンス直子の代表的存在であるディープインパクトは瞬発力と持久力を高次元で両立した名馬でした。
その産駒(ディープインパクト系)は一般的に切れる末脚を受け継いでおり、芝のマイル〜中距離戦で抜群の決め手を発揮する馬が多いです。
例えば産駒のジェンティルドンナやグランアレグリア、さらには祖母にサンデーサイレンスがいるアーモンドアイが見せた他馬を置き去りにする豪快な瞬発力は、サンデーサイレンスの血の成せる技と言えるでしょう。
また、サンデー系以外ではキングカメハメハ系(キングカメハメハ産駒およびその後継)の血統も、優れた瞬発力とスピードを伝えることで知られます。
キングカメハメハ自身はパワーとスピードのバランスが良い馬でしたが、産駒には芝GI馬のドゥラメンテ(鋭い瞬発力で日本ダービー制覇)や牝馬三冠のアパパネなど、切れ味も兼ね備えた名馬が多くいます。
キングカメハメハ系はサンデーサイレンス系と配合されることも多く、その場合さらにキレが増す傾向があります。
この他、欧米の血統でも瞬発力を武器にする系統は存在します。
例えばノーザンダンサー系の中でもリファール系は日本の芝適性が高く「日本向きのスピードと瞬発力」に優れるとされ、ディープインパクトも血統表内にリファールの血を持っていました。
総じて、短距離〜中距離で活躍する血統には瞬発力に富んだものが多く、芝1,600m〜2,000mのGI戦線ではそうした血統の馬同士が熾烈な瞬発力比べを演じています。

持続力型の血統
反対に、持続力型の資質を伝える血統もあります。
典型的なのはスタミナと底力に富む欧州型の血統です。例えばステイゴールド系(サンデーサイレンス系ですがスタミナ寄り)は、瞬発力ではディープインパクト系に一歩譲るものの長く脚を使える傾向があり、中長距離戦で持ち味を発揮します。
ステイゴールド産駒の代表であるゴールドシップは瞬発力勝負では切れ負けすることもありましたが、淀みない流れでの持久力比べでは無類の強さを見せました。
またハーツクライ産駒(これもサンデー系ですが持続力タイプが多い)も、ディープ産駒ほどの瞬発力はなくとも長くいい脚を使える馬が多く、GI馬ジャスタウェイやスワーヴリチャードなどはロングスパート勝負で勝利を掴んでいます。
欧州血統では、ガリレオ系やモンジュー系などスタミナ優位の系統がこれに当たります。
日本では欧州血統は敬遠されがちでしたが、それでも一定の需要はあり、現在も輸入種牡馬として導入されています。
ダート血統では、アメリカ型のミスタープロスペクター系やエーピィインディ系は序盤からハイペースで飛ばすスピードとパワーが持ち味ですが、ラストの瞬発力という点では芝のサンデー系には及ばない印象です。
そのためダート戦は総じて持続力勝負になりやすく、米国血統の持つパワーと持久力がものを言います。
血統面から見ても、芝の瞬発力勝負とダートの持久力勝負という構図が浮かび上がってきます。
血統と調教の補足
興味深い話として、「血統による瞬発力を引き出すのは調教師の腕次第」というものがあります。
血統が持つポテンシャルを活かすも殺すも調教次第で、例えば持続力型の血統でも調教で瞬発力強化メニューを取り入れることで瞬発力に磨きをかけることは可能です。
一方で瞬発力型の血統でも、無理にスタミナを付けようとすると持ち味のキレを損なってしまう恐れがあります。
実際、調教師は馬の血統特性を見極めて「この馬は瞬発力が武器だからそれを伸ばそう」「この馬は長く脚を使えそうだから早め先行策に耐えられるよう鍛えよう」などと方針を立てています。
血統はあくまで先天的な素質ですが、それをどう活かすかで馬のタイプがより明確に伸びていくわけです。
瞬発力を活かす馬券戦略
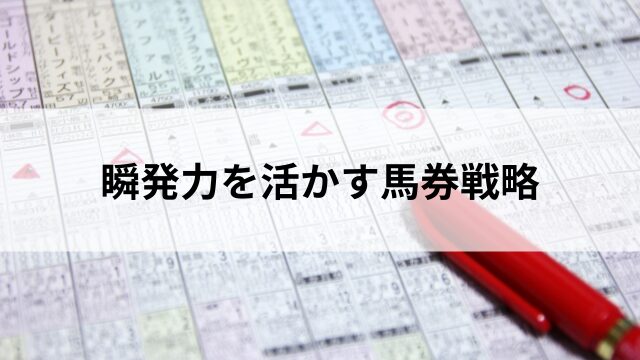
ここまで瞬発力の基本や特徴、馬体や血統による見極め方などを解説してきましたが、ではこの「瞬発力」という視点を実際の競馬予想や馬券購入にどう活かせばよいのでしょうか。
競馬は展開ひとつで有利不利が一変する世界です。
特に「瞬発力勝負になるか、持続力勝負になるか」の見立ては、馬券の方向性を大きく左右します。
もしレース前にある程度その展開を予測できれば、瞬発力型の馬が活きる舞台かどうかが判断できるようになり、狙うべき馬や券種の組み立ても的確になっていきます。
ここからは、展開の読み方やコース・馬場との相性を踏まえながら、「瞬発力を活かして勝つための馬券戦略」について詳しく解説していきます。
展開を読む – スローかハイか?
まず重要なのは展開予想です。
逃げ馬・先行馬の頭数や脚質を見て、スローペースになりそうか、ハイペースになりそうかを判断します。
もし有力な逃げ馬が見当たらず、先行勢も控えそうなメンバー構成なら、スローペース濃厚=瞬発力勝負と見てよいでしょう。
この場合、最後の直線での決め手比べになるので、過去に上がり最速を何度も記録している馬や、切れる末脚が武器の馬を重視します。
具体的には「前走○○ステークスで上がり33秒台の追い込みを見せた○○」といった馬は有力候補です。
逆に、ハナ争いが激しくなりそうだったり明らかな逃げ馬が多数いる場合は、ハイペース=持久力勝負になりやすいです。
そういう時は、先行勢総崩れの展開を見越して差し・追い込みでもスタミナのあるタイプを狙ったり、思い切って粘り腰の先行馬を信頼する手もあります。
持続力に自信がある馬ならハイペースでも止まらず粘り込む可能性があります。
コース適性・距離適性を見る
次にコース特徴も重要です。
冒頭で触れたように、東京競馬場や新潟外回り、京都や阪神の外回りなどは直線が長く平坦で、瞬発力勝負になりやすいコースです。
実際、東京芝では上がり3ハロン32秒台〜33秒台前半の電撃の末脚が頻繁に飛び出します。
したがって東京コースの重賞では、切れ味自慢のサンデーサイレンス系や上がり最速常連の馬を高く評価すべきでしょう。
反対に、中山競馬場や阪神・京都競馬場の内回りのように直線に急坂があるコースでは、一瞬のキレだけでは差し切れずパワーと持久力が問われます。
こうしたコースでは長く脚を使えるタイプが台頭しやすく、差し馬でも早めに動ける持続力型の馬や、自分からまくっていける馬に注目すると良いでしょう。
具体例として、東京芝2,400m(日本ダービーなど)は典型的な瞬発力勝負の舞台で、「上がり勝負に強いディープインパクト産駒が毎年のように好走する」といった傾向があります。
一方、中山芝2,500m(有馬記念)はスタミナとパワーが要求されるため、瞬発力一辺倒の馬よりもタフな展開に強い馬が馬券に絡みやすいです。
近年の有馬記念では、菊花賞など長距離実績のある馬や、道悪や坂のあるコースで結果を出してきた馬が上位に来るケースが多く見られます。これはコース適性=瞬発力vs持続力適性がはっきり出た例と言えるでしょう。
距離適性も見逃せません。
一般に、短距離戦(1,200m前後)は序盤から全力に近いスピードで行くため持続力勝負になりやすく、瞬発力よりも二の脚の速さが重視されます。
一方、中距離戦(1,800m〜2,000m)はペース次第で瞬発力戦にも持久力戦にもなり得る微妙な領域です。
近年は中距離でもスロー傾向が強く、瞬発力が重要になるケースが多いですが、メンバー構成や馬場状態によっては平均ペースで流れて持続力勝負になることもあります。
また長距離戦(2,500m以上)は基本的にスタミナ比べです。
ペースが遅くても瞬発力というより底力(ラストまでバテない力)が問われますし、ペースが速ければなおさら持久力が物を言います。したがって、長距離戦では瞬発力型の馬より持久力・底力型の馬を重視するのがセオリーです。

馬券の組み立て方
展開と適性を踏まえたら、実際の馬券を組み立てます。
例えば「瞬発力勝負になる」と読んだ場合、そのレースでは瞬発力上位の馬を軸に据えると良いでしょう。
具体的には、直近のレースで上がり最速を記録していた馬や、過去に同じような条件で鋭い末脚を使って勝っている馬を中心にします。
そして相手には、同じく瞬発力に優れる差し馬を選ぶのが基本ですが、加えて先行馬の中から瞬発力がある馬をピックアップするのも重要です。
スローペースだと先行有利とはいえ、逃げ・先行馬全てが瞬発力に欠ける場合、結局差し馬に差されてしまいます。
ですから先行勢の中にも「この馬は切れる脚も持っている」というタイプがいれば、積極的にヒモや相手に組み込みます。反対に、持続力型の先行馬はスローでは切れ負けする恐れがあるため評価を下げます。
一方「持続力勝負になりそう」と読めば、スタミナ自慢の馬を中心に考えます。
ハイペースが見込まれるなら、あえて逃げ・先行馬を軽視し、中団からロングスパートできる馬やバテない追い込み馬を重視します。具体的には、過去のハイペースのレースで善戦した経験がある馬や、長距離の実績がある馬(スタミナ豊富)を軸に据えます。
さらに、ハイペースになりやすいレースでは穴でまくり馬に注目という手もあります。
道中後方から早めに動いていく「まくり」を得意とする馬は、持続力タイプであることが多く、展開が嵌れば大駆けする可能性があります。
馬券の種類にもよりますが、瞬発力vs持続力の視点は三連単や三連複の組み立てにも応用できます。
例えば極端な瞬発力勝負と読んだら、思い切って瞬発力型の差し・追い込み馬ばかりで上位独占を狙うのも一手ですし、逆に先行勢総崩れの消耗戦と読んで差し馬の台頭だけを狙う手もあります。的中率は下がりますが、展開がハマった時には高配当を得られるロジックです。
また馬場状態も忘れてはいけません。
雨で馬場が重くなれば瞬発力勝負にはなりにくく、持久力・パワー勝負に傾きます。実際、稍重以上の馬場では上がりタイムがかかるため、瞬発力型の末脚は鈍りがちです。
そのため道悪巧者(パワー型、持続力型の馬)を重視し、瞬発力頼みの馬は割引くべきでしょう。
このように、展開・コース・距離・馬場といった要因を総合して考えることで、「今回は瞬発力がカギだ」「今回は持続力勝負だ」という見立てが立ち、それが馬券戦略の指針となります。
競馬の瞬発力:まとめ

以上、競馬における「瞬発力」について、その意味や瞬発力勝負の展開、持続力との違い、見分け方や血統・馬体の観点、さらに予想への活かし方まで幅広く解説しました。
競馬は一瞬の切れ味で勝負が決まることもあれば、消耗戦を制するスタミナがものを言うこともあります。
瞬発力と持続力はどちらが欠けても名勝負は生まれませんし、名馬も生まれません。
それぞれの馬が持つ個性を理解し、その適性を見極めることで、レース観戦はさらに奥深く、予想も的確になっていくでしょう。
初心者の方も、まずはレース後の結果分析からでも構いません。
「このレースは瞬発力勝負だったな」「なぜこの馬が負けたのか?持続力勝負になって切れ負けしたのかも」といった視点で振り返ってみてください。
繰り返すうちに展開の読みと馬の適性が結びつき、競馬を見る目が養われていくはずです。
競馬は奥が深く、そしてそれを学ぶ過程もまた大きな楽しみです
。瞬発力というキーワードをきっかけに、自分なりの予想スタイルや観戦ポイントを見つけ、より競馬を楽しんでいただければ幸いです。あなたの予想に「瞬発力」が増すことを願っています!