競馬における「上がり」とは、レース終盤の脚の使い方やスピードを表す重要な要素です。
なかでも注目されるのが、ゴール前600mのタイムを示す「上がり3ハロン」です。
レース結果や新聞では頻繁に取り上げられ、馬の瞬発力を測る指標として広く活用されています。
では、この「上がり3ハロン」や「上がり最速」とは具体的に何を意味し、どのように馬券検討に役立てられるのでしょうか。
当記事では競馬の上がりについて解説します。
競馬の上がりとは?
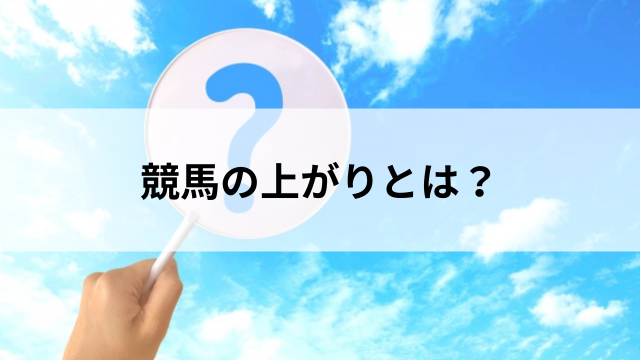
競馬における「上がり」とは、レース終盤の脚の速さを示す重要な指標です。
特に上がり3ハロン(最後の600m)のタイムは、馬の瞬発力や末脚の能力を数値化する際に用いられ、勝敗を左右することもあります。
ここでは、上がりの意味や見方に加え、「上がり最速」や「上がり勝負」などの関連用語、さらには「上がりがかかる」レース展開についても詳しく解説していきます。
上がり3ハロンとは?
競馬の上がり3ハロンとは、ゴールまで残り3ハロン(=600m)の区間タイムのことです。
1ハロンは約200mですので、3ハロンはちょうど600mになります。
レース結果の表示や競馬新聞では、各馬の上がり3F(Fはハロン=furlongの略)という形で数値が公表されます。
例えば「上がり3F:34.0秒」という場合、その馬が最後の600mを34秒0で走破したことを意味します。
JRA(日本中央競馬会)では、各レースの全体ラップタイムに加えて出走各馬の上がり3ハロンが公式発表されます。
そのレース中で一番速い上がりタイムを出した馬は上がり最速や上がり最速馬といいます。
反対に、終盤であまり速い脚を使えない馬に対して上がりがないや上がりが遅いという表現が使われることもあります。
上がり最速とは?
競馬の上がり最速とは、そのレースにおける最も速い上がり3ハロンタイムを意味します。
つまり、出走馬の中で最後の600mを最短時間で駆け抜けた馬が上がり最速の馬です。
「上がり○位」と順位で表現することもあり、1位の馬は他馬よりも優秀な末脚(レース終盤の脚力)を発揮したことになります。
例えばあるレースで最速上がりが33秒0なら、そのタイムを記録した馬が上がり最速馬です。
上がり最速の馬はレース終盤に最も脚を伸ばした馬と言えますが、必ずしもその馬が勝利したとは限らない点に注意が必要です。
上がり最速はしばしば差し馬・追い込み馬(後方から追い上げる脚質の馬)が記録しやすく、レース展開やコース形状によって生まれやすい傾向があります。
上がり勝負とは?
競馬の上がり勝負とは、レース展開が終盤の瞬発力比べになることを指します。
具体的には、序盤から中盤にかけてペースが遅く(スローペース)進み、各馬がスタミナを温存した状態で直線に入り、一斉にスパートをかける展開です。
このような場合、レースの勝敗は最後の600m(上がり)の速さ=瞬発力で決まるため上がり勝負と呼ばれます。
上がり勝負のレースでは、上がりタイム自体は全体的に速くなりやすく、末脚の鋭い馬が有利です。
一方、瞬発力に欠ける持久型の馬にとっては厳しい展開になります。
典型的な例として、前半がゆったり流れたG1レースで最後だけ各馬が33秒台の脚を使うようなケースでは、完全に上がり勝負の競馬と言えるでしょう。
上がり勝負になるかどうかはペース次第ですが、一般に芝の中長距離戦でスローペースになった場合によく見られます。
騎手もその展開を読んで、早めに仕掛けず直線勝負に賭けることがあり、ファンからは「瞬発力勝負」などとも表現されます。

上がりがかかるとは?
競馬で上がりがかかるとは、終盤に時間がかかる=上がりタイムが遅くなることを意味します。
これは「ゴール前の脚比べに時間を要した」というニュアンスで使われ、具体的には最後の600mのタイムが平時より遅めになる状況を指します。
なぜ上がりがかかるかというと、主な原因はペースや馬場状態です。
例えば、前半からハイペースで飛ばす展開になれば、最後の直線で各馬のスタミナが切れてしまい、結果的に上がりタイムは遅くなります。
重馬場(雨などで馬場が悪い状態)や長距離戦でも、脚が上がってゴール前の速度が落ち、上がりがかかる傾向があります。
こうしたレースでは上がり勝負とは逆に、スタミナと持久力に優れた馬に分があり、瞬発力タイプの馬には厳しい展開となります。
「上がりがかかったレースだった」という場合、勝ち馬の上がりタイムが36秒台や37秒台といったように平時より遅めだったことが多いです。
要するに、「上がりが速い」「上がり勝負」という表現が瞬発力中心の展開を示すのに対し、「上がりがかかる」は消耗戦・スタミナ勝負の展開を示す言い回しになります。
競走馬にはそれぞれ得意不得意があり、上がりがかかるタフな競馬を得意とする馬もいれば、その反対に速い上がりの決着を得意とする馬もいます。

上がりタイムの見方と実例

上がりタイムの見方として、上がり3ハロンの数値から何が読み取れるかを理解しましょう。
基本的に上がりタイムは小さい(速い)ほど良いですが、単純に数字だけで比較する際には注意点もあります。
多くの芝レースでは、上がり34秒~35秒程度が一つの平均的な目安とされており、これより速い33秒台や32秒台のタイムは切れ味が鋭いと評価できます。
ただし、コースや距離、ペースによってもタイムは変動します。
まず競馬場ごとの特徴です。
例えば新潟競馬場の芝コースは最後の直線が約658mと非常に長く平坦なため、他場よりも速い上がりタイムが出やすい傾向にあります。
実際、新潟では33秒台前半、場合によっては32秒台の末脚が飛び出すことも珍しくありません。
一方、東京競馬場の芝コースは直線こそ長いものの途中に高低差2mほどの坂があるため、同じ末脚自慢の馬でも新潟ほど速いタイムは出にくいです。
また、小回りで最後の600m地点にカーブが含まれる小倉競馬場などでは、コーナリングによる減速もあり上がりが少し余計にかかります。したがって、上がりタイムはコース条件を考慮して評価する必要があります。
さらにレースの距離やペースも重要です。
短距離戦ではレース全体が短いため終盤に余力が残りやすく、上がりが速くなりがちです。
一方、長距離戦では全体的に消耗戦となり、ゴール前で脚色が鈍って上がりが遅くなるケースが多いです。
また、同じ馬でもスローペースの時は32秒台の豪脚を繰り出せても、ハイペースの時は35秒以上かかる、ということが起こります。
したがって上がりタイムを他と比較するときは、その数値が出た背景(距離・ペース・馬場・コース)を考慮することが大切です。
リバティアイランドの驚異的な上がり3F31.4秒
具体的な実例として、近年話題になった驚異的な上がりタイムを見てみましょう。
2022年7月、新潟競馬場の新馬戦(2歳新馬・芝1,600m)でデビューしたリバティアイランドという馬が記録した上がり3ハロン31秒4というタイムです。31秒台など信じられない数字ですが、これはJRA史上最速タイ記録にあたります。
リバティアイランドが新馬戦で圧巻の末脚を発揮し、他馬を突き放した場面。このレースでリバティアイランドは上がり3ハロン31秒4という豪脚を披露し、2着馬に3馬身差をつけて快勝しました。
当日の勝ちタイム自体は1分35秒8と平凡でしたが、終盤の600mだけで見れば31秒4という衝撃的な数字です。
参考までに、この記録と並ぶ31秒4を出したもう1頭は同年5月に新潟で開催された韋駄天ステークス(オープン)の例があります。
5着のルッジェーロが同じ時計を記録していますが、韋駄天ステークスはカーブのない新潟芝1,000m、いわゆる千直の舞台で特殊な条件でのタイムでした。
それと比べても、2歳馬がデビュー戦で平坦な新潟とはいえ1,600m戦の終盤に同じタイムを叩き出したのは驚異的と言えます。
リバティアイランドの末脚がいかに図抜けていたかは、同じレースに出走していた他馬と比較すると分かりやすいでしょう。2着馬クルゼイロドスルの上がりは32秒4でしたから、リバティアイランドは1.0秒も速い脚を繰り出した計算になります。
この圧倒的な切れ味を武器に、リバティアイランドは後に牝馬三冠を達成する名馬へと成長しました。
上がりタイムはその馬の潜在能力やレースで発揮できる瞬発力の目安となり得ることを示す好例です。
上がりタイムの見方としてまとめると、「数値そのものの大小」に加えて「出た条件」をセットで考えることが重要です。
例えば上がり最速が必ずしも勝利を意味しないように、上がりタイム単体ではなくレース展開も踏まえて評価しましょう。
高速馬場での32秒と、タフな馬場での34秒では価値の重みが違う場合もあります。
こうした視点でデータを読むと、より競馬予想に活かせるでしょう。
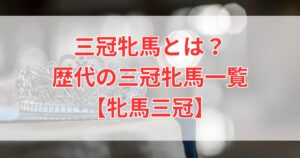
上がり最速=勝てるとは限らない理由
上がり最速の末脚を使える馬は魅力的ですが、競馬では「上がり最速=勝利」とは限らない点に注意が必要です。
終盤の脚がいくら速くても、それまでの位置取りやペース次第では届かないことがあるためです。
典型的なケースはスローペースの逃げ残りです。
序盤ゆったりとしたペースで逃げ・先行馬が楽にレースを運ぶと、後続の差し馬はスタミナを十分に温存できます。
しかし先行勢も余力を持っているため、残り600mからスパートしても前との差がなかなか詰まりません。
結果的に差し馬がそのレースで最速の上がりタイム(上がり1位)を記録しても、逃げ馬を捕らえきれずに敗れるということが起こります。
実際に2024年の高松宮記念(芝1,200m)でも、そんな展開が見られました。
このレースは前半600mが34秒9、後半600m(上がり)が34秒0というスローペースとなり、逃げ馬のマッドクールが直線でも脚色衰えずに粘り込みました。
マッドクールは上がり3ハロン33秒7で走破し、僅差で1着となっています。
一方、後方待機から追い込んだナムラクレアはこのレースで最速の上がり33秒2をマークしましたが、前を行くマッドクールに届かずアタマ差の2着に敗れました。
つまり、ナムラクレアが上がり最速だったものの勝ったのはマッドクールという結果です。
この例が示すように、レース展開(ペース)によって上がり最速馬が勝てないことがあるのです。
逆にハイペースになれば先行馬がバテて、後方から最速上がりを繰り出す馬が差し切り勝ちする場面も増えます。
要は上がりタイムは相対的な指標だということです。
同じ馬が次走でも再び上がり最速を出せるかも、そのレースがどういう流れになるかに左右されます。
したがって予想を立てる際には、単純に過去の上がり最速馬だからといって鵜呑みにせず、今回はこの馬の末脚が活きる流れになるか?を読むことが重要です。
もう一つ、位置取りも勝敗に影響します。
いくら末脚に自信がある馬でも、直線に入る時点で先頭からあまりにも離されていては届きません。
また進路取りに手間取ったり、前が壁になる不利があれば上がりタイム自体も発揮しきれなくなります。
リバティアイランドが2戦目に挑んだアルテミスステークス(G3)において、最後の直線でリバティアイランドは前が壁になって思うように末脚を活かせず、結果的に外から伸びたラヴェルの2着に敗れてしまいました。
いくら末脚に定評があっても位置取りで力を発揮できなければレースの勝敗にも大きな影響を及ぼします。
このように上がり最速=絶対勝利ではない理由は、(1)レースのペース配分、(2)ポジショニングや進路などの展開面にあると言えます。
極端な例を挙げれば、どんなに強烈な末脚を持つ馬でも、超スローペースで前残りになれば差し届かず、逆に自身が先行してハイペースを演出してしまえば最後は失速してしまうでしょう。
上がりタイムの裏側には常にそうした文脈があることを踏まえておく必要があります。
上がりに強い馬の5つの特徴

では、上がりに強い馬とは、いったいどのような特徴を備えているのでしょうか。
ゴール前で一気に加速し、他馬を突き放すような鋭い末脚を繰り出せる馬には、共通する資質や適性があります。
瞬発力の高さはもちろん、気性やレース運び、さらには血統や馬体のバランスも重要な要素です。
ここでは、そんな上がり型の馬に見られる代表的な特徴を5つ紹介していきます。
瞬発力と加速力が高い
上がりタイムを速くするには、短い距離で一気にトップスピードに乗る加速力が求められます。
上がりに強い馬は瞬時にギアを上げて速度を増すことができ、残り600mからのラップが他馬より明らかに優秀です。
レース映像でも、直線半ばからグングン加速して差を詰めるような馬は上がりが速い馬の典型です。
折り合いが良くスタミナを温存できる
切れる末脚を発揮するには、それまで無駄なエネルギーを使っていないことが前提です。
道中で引っ掛からずリラックスして走れる馬は、末脚に必要な体力を残して直線に向くことができます。
逆に道中で力んでしまう馬は上がりの伸びを欠きがちです。
上がりに強い馬は総じて折り合いがつきやすく、終盤に余力を残せる気性であることが多いと言えます。
軽い馬場や長い直線を得意とする
上がりの速い馬は、上がりの時計が出やすい舞台で好走するケースが多いです。
例えば東京競馬場のように直線が長く広いコースは、後方待機馬でも伸び伸び末脚を使えるため、上がり最速がそのまま勝利につながりやすい傾向にあります。
反対に小回りの短い直線や重い馬場では、本来の瞬発力を発揮しにくくなるため、上がり自慢の馬でも能力を出し切れないことがあります。
上がりに強い馬の戦績を見ると、良馬場で高速決着になったレースで好走歴が多い傾向が見られます。
過去に速い上がりタイムの実績がある
データ面では、過去のレースで何度も上がり最速や2位以内を記録している馬は安定して末脚が使えるタイプと判断できます。
特に芝レースで上がり34秒を切った経験が何度もある馬は潜在能力が高く、条件さえ合えば毎回でも速い上がりを出せる素質を秘めています。
そうした馬は展開待ちの面もありますが、ペースがまったく向かなかった場合を除き大崩れしにくいのも特徴です。
血統や体質的な傾向
細かい点ですが、瞬発力の優れた血統や馬体というものも存在します。
例えばディープインパクト産駒は切れ味鋭い末脚を持つ馬が多いとされますし、母系や近親にマイラーやスプリンタータイプがいる馬も終いのスピード能力が高いことが多いです。
また馬体重が軽めで瞬発力勝負に強いタイプ、逆にパワー型で上がりがかかる競馬が得意なタイプなど、馬の体質・適性も影響します。
上がりに強い馬は往々にしてスラっとした体型で切れ者と評されることが多いですが、一概ではなく鍛え方や成長によっても変わってきます。
競馬の上がり:まとめ
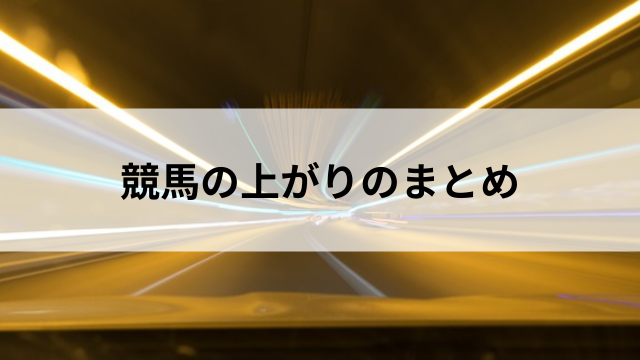
「上がり」とは競馬の終盤、特に最後の3ハロン(600m)のタイムを指し、レースの局面や馬の能力を評価する重要な指標です。
上がり3ハロンという具体的なタイムで各馬の末脚が数値化され、「上がり最速」の馬はそのレースで最も速い末脚を使ったことを示します。
一方で、レース展開によっては上がり最速馬が必ず勝つわけではなく、「上がり勝負」や「上がりがかかる」といった展開用語も生まれています。
上がり勝負は瞬発力比べの展開、上がりがかかる競馬はスタミナを問われる消耗戦の展開です。
上がりタイムの見方としては、単純な数字の大小に加えて競馬場ごとの特徴やペース配分を考慮する必要があります。
極端な高速タイムの例としてリバティアイランドの31.4秒という記録も紹介しましたが、それだけの末脚を引き出すには条件が整っていたことも確かです
。逆に言えば、条件次第で平凡なタイムでも勝負に勝てるのが競馬の奥深さです。
上がりに強い馬の特徴としては、優れた瞬発力と折り合いの良さを持ち、適切な条件下では何度でも速い末脚を繰り出せるという点が挙げられます。
こうした馬を見極め、展開を予想に織り込んで上がりタイムを活用することで、競馬予想の的中率向上も期待できるでしょう。
初心者の方も、競馬中継や結果表で「上がり○ハロン○秒」という表現に注目してみてください。
その数字は各馬のドラマを物語る重要なキーであり、競馬を更に楽しむための指標となってくれるはずです。
今後レースを見る際は、ぜひ上がりタイムにも注目し、愛馬たちの末脚比べを堪能してみてください。

