競馬で的中率を高めるためには、馬の能力や展開予想だけでなく、「馬場の傾向」を見極めることが重要です。
その鍵を握るのがトラックバイアスという考え方です。
聞き慣れない言葉かもしれませんが、これはレースごとに変化する“見えない馬場のクセ”のようなものです。
たとえば「内を通った馬が伸びる」「外差しが決まりやすい」といった傾向を把握できれば、人気馬の取捨や穴馬の発見にも役立ちます。
本記事では、トラックバイアスの意味や調べ方、実際のレースでの活用方法までを初心者にも分かりやすく解説します。
馬券戦略をワンランクアップさせたい方は、ぜひ参考にしてください。
トラックバイアスとは何か
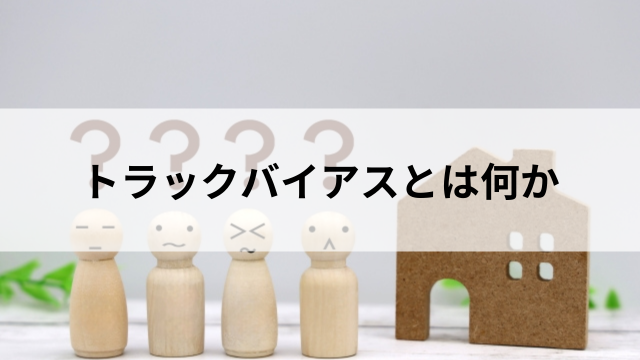
競馬でよく耳にする「トラックバイアス」とは、馬場状態やコース形状などによって生じる有利・不利の偏りのことです。
その日のコースがどの枠順やどの脚質の馬に有利かという馬場のクセを指します。
たとえば、「今日は内側を通った馬が有利そうだ」「前の方を走る馬が有利な馬場だ」といった傾向があるかどうか、という意味です。
競馬では晴雨にかかわらずレースが開催され、多くの場合同じ競馬場で何週にもわたって連続開催されます。
そのため、天候(雨や乾燥)や開催週数による芝の傷み具合、コースの形状(直線の長さやコーナーのきつさ)などによって、馬場のコンディションは刻々と変化します。
トラックバイアスもそれに伴い常に変化します。
馬券を買う際には、その時々の馬場傾向(トラックバイアス)を把握しておくと予想の精度向上に役立ちます。
芝のトラックバイアス傾向

芝コース(洋芝などの芝生コース)は、季節や天候、開催の進行状況によってコンディションが大きく変わります。
それに伴い、内外の有利不利や先行馬・差し馬の有利不利も変化します。
ここでは芝コースで見られる代表的なバイアス傾向を紹介します。
晴天続きの「高速馬場」は内枠・先行有利
雨が降らず晴天が続くと芝の生育は良好で馬場は硬く締まり、タイムが速く出やすい高速馬場になります。
高速馬場では、内側の経済コースを立ち回る先行馬が有利になりやすいです。
時計が速くなると後方から追い込んでくる馬が届きにくく、先頭付近で粘る馬がそのまま上位を独占するといったレースが増えます。
特に小回りで直線の短いローカル競馬場(例: 小倉競馬場や函館競馬場)では、この傾向が顕著です。
ただし、後ろの馬もスピード自体は出るため、ハイペースで前が総崩れになった際は台頭することも多々見られます。
雨で荒れた馬場や開催後半の「外差し馬場」
一方、雨が降って芝が柔らかくなった馬場では、芝のクッションが効かずスピードが出にくくなります。
こうした重い馬場(稍重・重馬場・不良馬場)では前に行く馬がペースを落としても後続も加速しづらいため、先行馬が有利になる場合が多いです。
また、開催が進んで芝の内側が踏み荒らされると、コースの内と外で走りやすさに差が出ることがあります。
内側の傷んだ部分を嫌って各馬が徐々に外めに進路を取るようになると、最後の直線では外を伸びてくる馬が台頭しやすくなります。
このように内よりも外を通った馬が有利なコンディションを俗に「外差し馬場」と呼びます。
例えば2024年の宝塚記念(京都)では、開催10週目で芝の内側が荒れ、各馬が直線で外へ持ち出す状況でした。
その結果、外から追い込んだ馬が上位を占め、内ラチ沿いを通った馬には厳しいレースとなりました。
このように馬場の偏りひとつでレース展開や結果が大きく左右されることもあるのです。

ダートのトラックバイアス傾向

ダートコース(砂のコース)でも馬場状態による偏りは存在しますが、芝に比べると内外の有利不利は出にくい傾向があります。
ただし、砂の状態や水分量によって主にレースの脚質面(先行有利・差し有利)で顕著な傾向が現れます。
ダートにおけるトラックバイアスについて解説します。
ダートでトラックバイアスが出にくい理由
芝コースに比べると、ダートコースではトラックバイアスが目立ちにくい傾向があります。
その理由は、ダートコースはレースごとに整地(ハロー掛け)が行われるからです。内外の差が生じにくく、均一な馬場状態が保たれやすいのです。
また、開催が進んでも芝コースほど見た目の変化がありません。
目視ではバイアスの傾向が見えにくいのも相対的にトラックバイアスが出にくい理由につながるのです。
雨で「高速ダート」化すると先行馬が圧倒
ダートコースは水はけが良く乾燥すると砂埃が舞いますが、雨で適度に湿ると砂が締まり走りやすくなります。
大雨でダートが重・不良になると砂が締まり、タイムがかえって速くなります。
そのため、ダートではあまり求められないスピードに長けた馬が台頭するケースも珍しくないのです。
とはいえ、ダートは基本的に良馬場開催が多く、良馬場時は差しや追込がスピードの乗りづらいことから相対的に逃げ・先行馬が有利です。
そのため、ダートでは常に前に行ける馬を重視するのがセオリーです。
トラックバイアスの調べ方

では、実際にレース当日のトラックバイアスをどのように把握すれば良いのでしょうか。初心者〜中級者の方でもできる調べ方をいくつか紹介します。
まず基本は、JRA公式の馬場情報を確認することです。
JRAのホームページには開催当週の「馬場情報」が掲載されており、芝・ダートそれぞれの含水率や使用コース(内柵の位置)などが公表されています。
馬場が雨でどれくらい湿っているか、開催何週目で内側が荒れていそうか、といった見通しを立てられます。
JRAのホームページで馬場状態を確認する手順は以下の通りです。(パソコン版)
- JRAの公式ホームページにアクセス
- ページ上部の【競馬メニュー】をクリック
- ページ内の【今週の開催情報】の欄にある【馬場情報】をクリック
- 開催競馬場ごとに馬場傾向が表示される
次に、当日および前日までのレース傾向を確認するのも有効です。
実際のレース結果ほど馬場傾向を物語るものはありません。開催日の前半のレースや前日の結果を見て、どの枠の馬が馬券に絡んでいるか、どの脚質で勝ち負けしているかを観察してみましょう。
より精密に把握したい方には、JRA-VANやTARGET frontier JVといったデータ分析ツールの活用もおすすめです。
これらを使えば、過去レースの通過順・通過位置・上がりタイムといった細かなデータから、より正確にバイアスを読み解くことが可能になります。
トラックバイアスの考え方と馬券への活用

最後に、トラックバイアスを予想に活かす上での考え方のポイントをまとめます。
馬場傾向を掴んだら、それを馬券戦略に反映させることが重要です。
まず基本として、その日のバイアスにフィットしそうな馬を重視します。
例えば明らかに「前有利」の馬場なら逃げ・先行馬を中心に据え、反対に「差しが届く馬場」だと判断したなら末脚自慢の馬にも積極的に目を向けます。
枠順もヒントになります。「内枠有利」と感じたら最内〜内めの枠の馬を評価アップし、「外差し馬場」なら外枠でも伸びてこれる馬を狙う、といった具合です。
実際の例として、開催後半の中山芝では内ラチ沿いの芝が荒れてくるため、差し馬や外枠の馬が台頭する傾向があります。
そうしたタイミングで逃げ馬が1番人気に支持されている場合には、「馬場と真逆のタイプ」として思い切って評価を下げる判断も有効です。
ただし、トラックバイアスは絶対ではなく、レースのペース次第で覆る可能性もあります。
また、急な天候変化で馬場状態が一変することもあります。したがってレースごとに臨機応変に考え、バイアスに頼りすぎないバランス感覚も重要です。
トラックバイアスを読む力は、経験を積むことで徐々に磨かれていきます。
その日の馬場傾向に目を配り、予想に反映する練習を重ねれば、きっと予想の精度向上や回収率アップにつながるはずです。AI予想やデータ分析と組み合わせることで、さらに精度の高い読みも可能になります。
まとめ:馬場を制する者が競馬を制す!

トラックバイアスは、いわば「競馬場の癖」を見抜くための重要な視点です。
枠順・脚質・位置取りに影響を与えるため、馬の能力とは別の切り口からレースを読み解く武器になります。
初心者でも「なぜこの馬が来たのか」が分かるようになり、中級者以上の方は「人気馬の取捨」や「穴馬の発見」に役立てることができます。
レース当日の傾向に注目し、馬場という“見えない敵”を味方に付けましょう。

