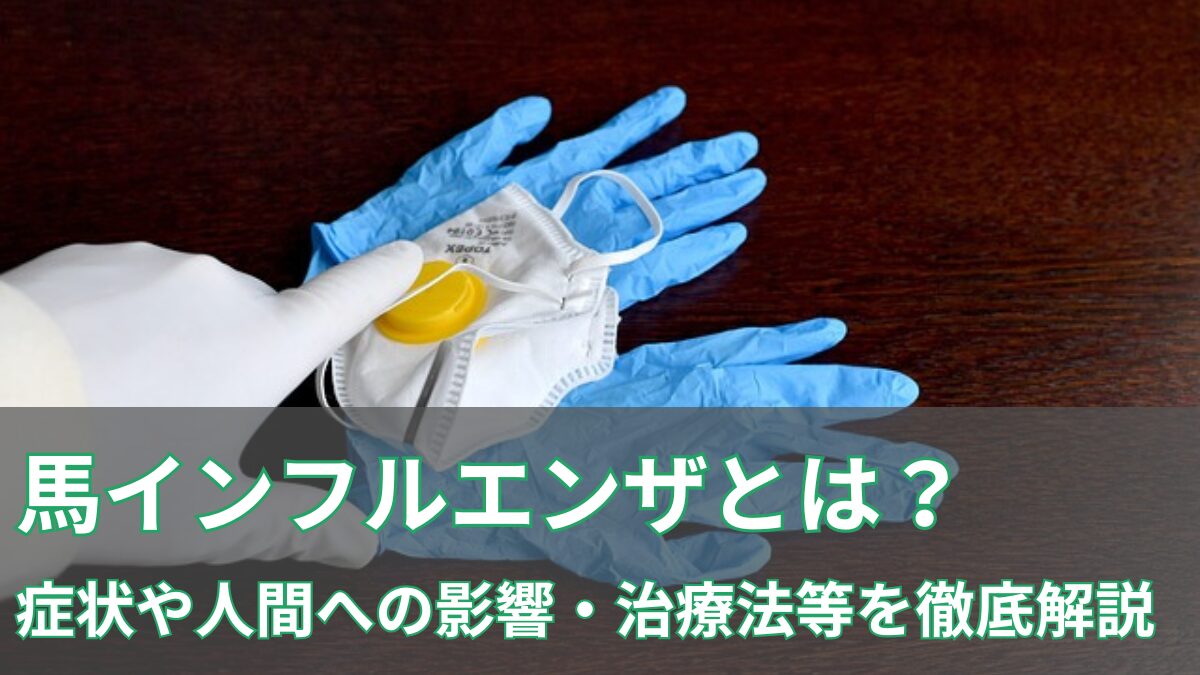競馬ファンにとって、「馬インフルエンザ」という言葉は無視できない存在です。
特に、1971年に日本で発生した際には競馬開催が中順延・中止になるなど、大きな騒動となりました。
馬インフルエンザは、非常に感染力が強く、集団飼育される競走馬や乗用馬に深刻な影響を及ぼす感染症です。
しかし、正しい知識があれば予防や早期対策が可能であり、命に関わることはほとんどありません。
この記事では、馬インフルエンザとはどのような病気なのか、症状、人間への影響、治療法や予防策について、初心者にも分かりやすく解説していきます。
馬インフルエンザとは?
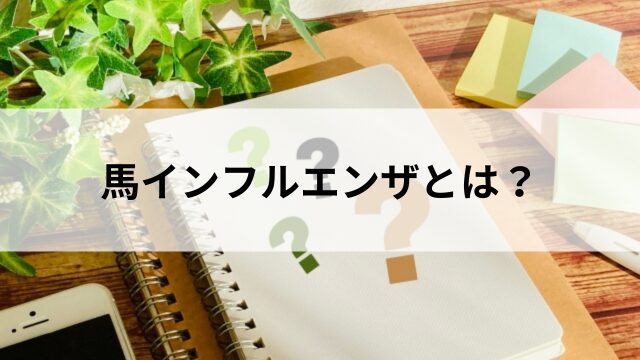
馬インフルエンザは、馬に特有のインフルエンザウイルス(A型ウイルス)によって引き起こされる呼吸器系の感染症です。
特に特徴的なのは、その非常に強い感染力にあります。感染馬の咳や鼻水に含まれるウイルスが空気中に飛散し、わずかな接触でも周囲の馬へ急速に広がります。
ウイルスに感染すると、馬は短期間のうちに発熱や咳などの症状を示し、通常の運動が困難になります。
また、集団飼育されている施設では爆発的な感染拡大を招きやすいため、競馬開催の中止や大規模な検疫措置が必要となるケースもあります。1971年12月に日本で流行した際は、開催延期や中止、競走馬の出走取消が行われました。
また、この時期は有馬記念や東京大賞典などのビッグレースの時期に発生してしまったため、このようなレースにも影響を及ぼし、話題となりました。
なお、馬インフルエンザは基本的に馬専用のウイルスであり、人間への感染リスクは極めて低いとされています。
馬インフルエンザの症状

馬インフルエンザに感染した馬は、主に呼吸器系を中心とした症状を示します。
感染から1~3日程度の短い潜伏期間を経て、急速に以下の症状が現れます。
- 39~41度の発熱
- 乾いた咳
- 鼻汁や鼻水
- 食欲不振
- 元気消失
特に咳は目立つ症状で、運動時だけでなく安静時にも繰り返し見られるケースが目立ちます。
また、発熱によって体力が著しく低下し、普段どおりのトレーニングや競技参加が困難になります。
症状が軽度であれば数日で回復する場合もありますが、重症化した場合には数週間にわたる療養が必要となるケースもあります。
さらに、回復後もしばらくは運動能力が完全に戻らないことがあり、特に競走馬にとっては長期的な影響が懸念されることもあるのです。
馬インフルエンザの影響

馬インフルエンザは、発症しても命にかかわることは少ない感染症ですが、競走馬や馬産業全体に深刻な影響をもたらします。
ここでは、馬インフルエンザの影響、そして、気になる人間への影響についても解説します。
競走馬に及ぼす影響
馬インフルエンザに感染しても、馬が直接死亡するケースは非常にまれです。
しかし、高熱や激しい咳によって体力が消耗し、運動能力が著しく低下します。特に競走馬の場合、
- 出走取り消し
- 長期間の休養
- 調教再開までの大幅な遅れ
このような影響を受けるため、競走成績やキャリアプランに大きな影響を与えるリスクがあります。
また、完治後も体調が完全には戻らず、パフォーマンス低下を招く場合もあるため、馬主・調教師にとっては非常に頭の痛い問題です。
競馬界では感染拡大を防ぐため、感染予防の措置や感染疑いが出た段階で速やかな隔離措置と競馬開催の中止が行われるケースもあります。
実際、1971年には日本中央競馬会JRA主催の競馬に大きな影響を及ぼし、社会問題となりました。
人間に及ぼす影響
馬インフルエンザウイルスは、基本的に馬のみに感染するタイプです。
そのため、通常の状況下では人間に感染する心配はありません。
馬インフルエンザの治療方法
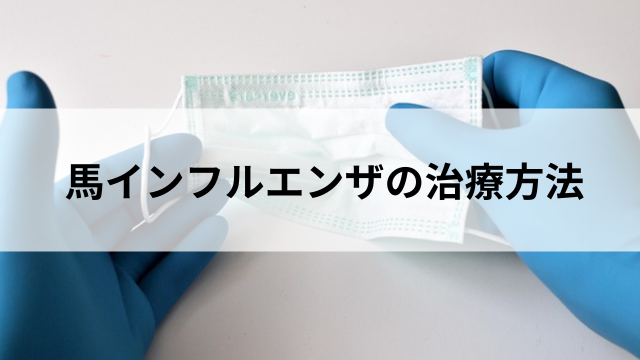
馬インフルエンザは人間には感染しないものの、競走馬に大きな影響を及ぼします。
そのため、馬インフルエンザにかからないことが常に求められています。
ここからは、馬インフルエンザの予防や治療方法について紹介します。
ワクチン投与で予防
馬用のインフルエンザワクチンは、定期的な接種によって発症や感染拡大を予防する役割を果たします。
ワクチン接種によって、仮に感染しても症状が軽く済み、回復もスムーズになる傾向があります。
特に競走馬や乗用馬など、移動や集団行動が多い馬は、最初に2回打ち、その後は半年ごとにワクチンを接種することが推奨されています。
感染発覚後も、適切な治療とワクチン効果によって、数週間以内に回復するケースが大半です。
また、感染馬には必要に応じて抗生物質が処方され、二次感染(細菌感染)を防止します。
感染したら安静する
馬インフルエンザに感染した場合、治療の基本は安静と対症療法です。
人間のインフルエンザと同じく、ウイルスそのものを直接退治する薬は存在しないため、症状を和らげながら自然治癒を促すことが中心となります。
特に発熱や咳が続く間は運動を控え、十分な休養と水分補給を行うことが重要です。
また、感染拡大を防ぐため、感染馬は厳重な隔離管理が求められます。
馬インフルエンザの影響で後遺症が残ったケース
馬インフルエンザに対する予防や治療はすでに確立しており、現在、馬インフルエンザが大きな影響を及ぼすことはほとんどありません。
しかし過去には、馬インフルエンザが間接的に、ある競走馬の馬生を狂わす事態がありました。
その馬の名は、メジロアサマです。
メジロアサマは当時芝3,200mで行われていた1970年の天皇賞(秋)を制した名馬で、当時最強クラスのステイヤーとして活躍していましたが、1971年に馬インフルエンザが流行し、この影響で、同年の有馬記念への出走を断念しています。
幸い、馬インフルエンザに対して投与された抗生物質の効果もあり、現役時代は大きな問題なく引退を迎えました。
しかしその後、種牡馬となったメジロアサマには思わぬ影響が現れます。
治療に用いられた抗生物質の影響で、極端に精子の量が少なくなり、受精能力が低いことが判明したのです。
このため、一時は「種牡馬失格」とも評されましたが、オーナーの北野豊吉氏は諦めず、子孫を残す努力を重ねました。
その結果、メジロアサマはわずか20頭の産駒を残すことに成功します。
数少ない産駒のひとつ、メジロティターンは、父と同じく天皇賞(秋)を制覇しました。
さらにその仔、メジロマックイーンは1990年代を代表するステイヤーとして名を馳せました。
また、メジロマックイーンの娘であるオリエンタルアートは、のちに三冠馬オルフェーヴルを産み、同じく娘のポイントフラッグは、芦毛の怪物と呼ばれたゴールドシップを誕生させています。
オルフェーヴルもゴールドシップも、2025年時点で種牡馬として活躍し、複数のG1馬を輩出しました。
こうして過去のアクシデントを乗り越えた血脈が、今も日本競馬界を支えていることを改めて実感させられます。
馬インフルエンザのまとめ

馬インフルエンザは、馬にとって非常に感染力の強い呼吸器系の感染症です。
発症すると高熱や咳などの症状が現れ、競走馬や乗用馬のパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。
命にかかわることはほとんどないものの、回復には時間がかかり、後遺症が残るケースもあるため、注意が必要です。
現在では、定期的なワクチン接種によって予防が可能となっており、発症リスクや感染拡大リスクを大きく下げることができます。
また、人間への感染は基本的にないため、過度な心配は不要です。
馬インフルエンザへの正しい理解と対策は、競馬界や馬産業を守るうえで欠かせないものです。
今後も予防体制の強化と早期対応が求められていくでしょう。