テレビなどで競馬中継を観ていると、「挫跖(ざせき)による出走取消」といったアナウンスを耳にすることがあります。
2025年の桜花賞に出走登録していたランフォーヴァウや皐月賞に登録していたジーティーアダマンも挫跖のため、クラシックレースの出走を回避しました。
しかし、「挫跖」といわれても聞きなれない言葉でピンとこない方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は挫跖について、原因と症状、治療方法と発症したことによる影響を詳しく解説します。
挫跖とは?読み方やその原因、症状を解説
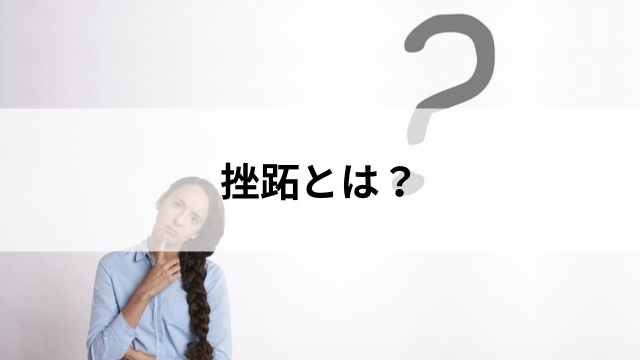
挫跖は「ざせき」と読み、人間で言うところの足の裏である蹄が、走行中の様々な要因による衝撃や圧迫により傷つき、内出血や痛み、炎症を起こしている状態のことを言います。
蹄の浅い、または薄い馬や走行時の前肢と後肢のバランスが悪い馬、地面を踏み込む力が強い馬が発症しやすいとされています。
では、具体的にどのような原因で挫跖が引き起こされるのでしょうか。
最初に、挫跖の原因や症状についてまとめました。
挫跖の原因
先ほども解説したように、挫跖の原因は蹄への衝撃や圧迫によるものです。
主な原因は下記のとおりです。
- 固いものを踏んでしまう
- 走行中に前肢と後肢の蹄がぶつかってしまう
固いものを踏んでしまう
具体的には、地面に落ちている石などの固いものを強く踏んでしまった時や、ウッドチップを踏んで蹄に刺さってしまった場合が挙げられます。
先ほども解説したように、地面を踏み込む力が強い馬や蹄が浅い馬は、このことが原因で発症するケースが多いと言えるでしょう。
また、歩行中よりも強度の高いトレーニング中やレース中など、速いスピードで走行しているとその分蹄に与えられる衝撃も大きくなるため、その分発症のリスクが高まることも特徴です。
走行中に前肢と後肢の蹄がぶつかってしまう
走行する際、前肢と後肢のバランスが悪く、前肢と後肢の蹄がぶつかり、打撲という形で挫跖が発症するケースもあります。
これは、オーバーリーチと言って走行時に後肢の踏み込みが大きいフォームが特徴的な馬や、そうでない馬であってもフォームが乱れた際に、前肢と後肢の動きのバランスが崩れ、それらがぶつかってしまうことで、挫跖の発症に繋がります。
挫跖の症状
挫跖の主な症状は下記のとおりです。
- 歩様の乱れ(ハ行)が見られる
- 蹄に熱感を帯びる
挫跖を発症した馬は、歩く際に違和感を見せたり、痛みから足をかばうような仕草を取ることがあります。また、患部を触ると嫌がったり、反応を示すことも少なくありません。具体的に紹介します。
歩様の乱れ(ハ行)が見られる
地面に直接接する蹄に痛みが生じていることから、患部に体重をかけないように歩くなど、歩様の乱れ、いわゆるハ行の症状が多く見られます。
症状が軽度の場合は少し違和感がある程度ですが、重度になると明らかに片脚をかばうような歩き方になり、歩行自体を嫌がることもあります。

蹄に熱感を帯びる
たとえハ行の症状が見られなくても、患部に熱感を帯びていることから挫跖の発症が判明することもあります。
挫跖の治療方法について
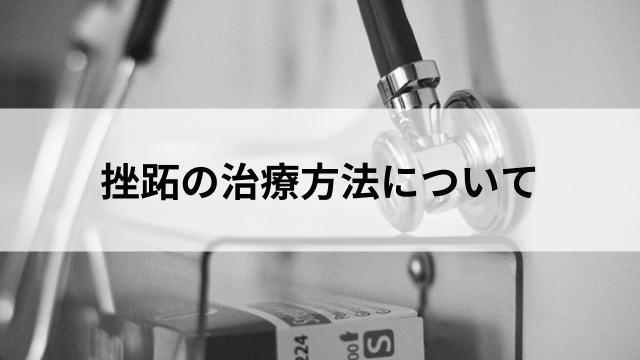
挫跖の治療方法は主に下記の2つです。
- 患部を冷やす
- 消炎剤を投与する
それぞれ、詳しく解説します。
患部を冷やす
挫跖の治療方法として最も多く用いられる方法として、患部を冷やすことが挙げられます。
挫跖は、蹄の内出血による炎症によるものであるため、それを冷水などを用いて取り除いてあげるのが最も効果的かつ早急な治療方法です。
実際の例として、レース前日に挫跖を発症し、厩舎スタッフが夜通し冷水をかけ、ギリギリまで出走を諦めなかったという例もあることから、有効な治療方法と言うことがわかります。
消炎剤を投与する
患部を冷却するのが最も効果的かつ早急な治療方法ではありますが、直前にレースを控えていない場合など、早急な手当が必要でない場合は、消炎剤を投与して炎症を抑える治療方法もとられます。
これは湿布などの消炎剤を用いる手法で、馬自身の自然回復力とあわせ、じっくりと回復させていく方法です。
挫跖の発症が競走馬に与える影響は?

挫跖の発症が与える影響の1つに、蹄の炎症による痛みから普段通りの能力を発揮して走ることができないということが挙げられます。
しかし、このことはどのケガにおいても同様であると言えるでしょう。
挫跖が他のケガや病気と違うのは、いくら防ごうとも、いつ石を踏んで挫跖を発症するかわからず、先ほどの治療方法の章で解説したように、レース前日に挫跖を発症してしまう可能性もあると言うことです。
この例の続きのお話しをすると、陣営は夜を徹して冷却の処置をして直前までレースへ出走することを諦めませんでしたが、最終的にはそのレースに出走することはできず、次回のレースの再検討を余儀なくされました。
この、いつ発症するかわからない挫跖が与える影響として、突然発症した挫跖によって「当初予定していたレースを直前で回避しなければいけない」、「回復するまでの期間トレーニングを満足に行えない」、「今後のレースプランやローテーションの再構築をしなければいけない」ことなどが挙げられるでしょう。
ここからは、挫跖の発症によってレースを回避、レースプランを改めて検討しなければならなくなった実際の例を紹介します。
ゴンバデカーブースの例
2歳新馬、サウジアラビアロイヤルカップ(G3)とデビューから2連勝を飾り、翌年のクラシック戦線を期待されていたゴンバデカーブース。
当初の予定では、皐月賞(G1)へ直行することを目標にトレーニングを進めていましたが、直前に重度の挫跖を発症します。
そのため、皐月賞(G1)は回避せざるを得なくなり、ローテーションの見直しを余儀なくされました。それでも、この馬の能力を見込んでいた陣営は、乗り込みは不足しているし、メンタル的な不安はあるとしながらも、皐月賞からおよそ1ヶ月後に開催されるNHKマイルカップ(G1)に焦点をあてトレーニングを再開。結果、4着と好走しました。
2歳時はクラシック戦線を期待されていたものの、挫跖によりローテーションの変更を余儀なくされたゴンバデカーブース。何事もなく十分なトレーニングを積んで皐月賞に出走していたら、どのような結果になっていたのでしょう。
メイショウハリオの例
2022・2023年の帝王賞(G1)、2023年のかしわ記念(G1)を勝利するなど、8歳となった2025年現在でもダート戦線で活躍しているメイショウハリオ。
メイショウハリオが挫跖を発症したのは2023年帝王賞連覇を飾り、JBCクラシック競走(G1)に向けて、一度放牧に出され、その放牧先で発症しました。
それほど重度な挫跖ではなかったため、当初の予定どおりJBCクラシック競走に出走したものの、やはり挫跖の影響により十分なトレーニングを消化することができず、1番人気に推されながらも4着に敗れています。
挫跖のまとめ

今回は、挫跖についてその原因と症状、治療方法を、発症によって競走馬に与える影響を解説しました。
いつ発症するかわからない挫跖。応援している馬が挫跖で突如出走を回避した際は悲しいですが、挫跖は引退に追いやられたり、長期の休養が必要とされるようなケガではありません。
多くの馬が再びターフに戻ってくるので、無理をさせず、しっかりと治療と休養を重ねたうえで、元気な姿で戻ってくる日を楽しみに待ちましょう。

