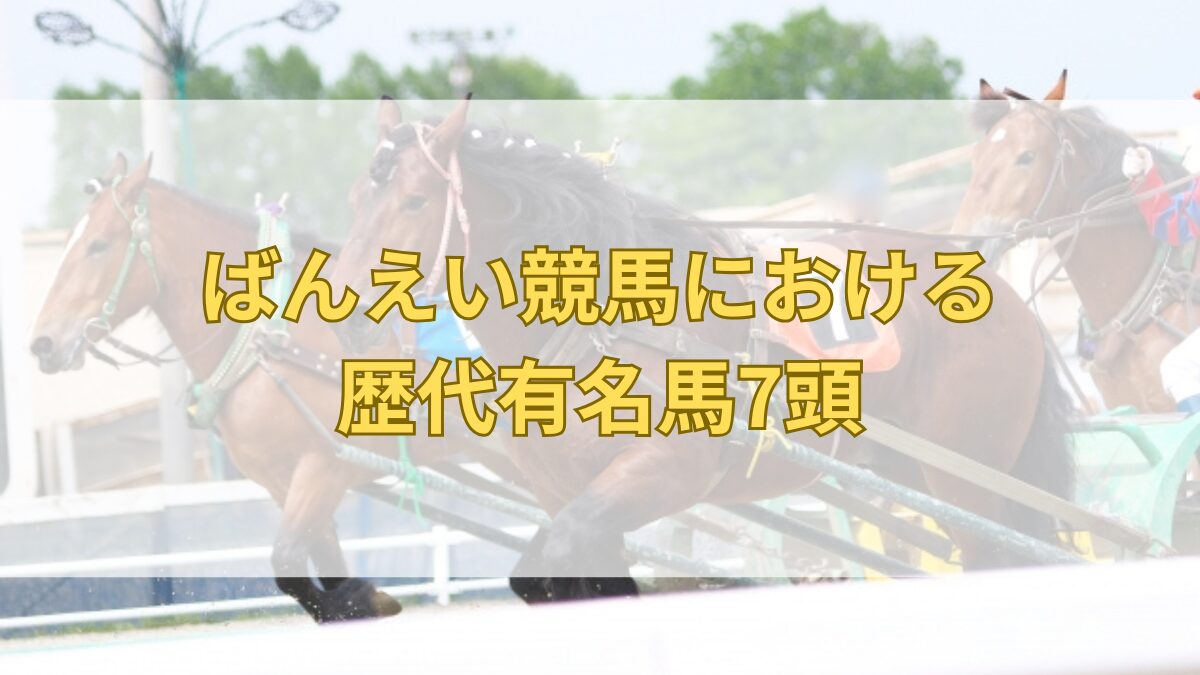ばんえい競馬は1953年から始まり、数多くの名馬たちが歴史を彩ってきました。
記録更新や、ファンを熱狂させた最強馬など、その勇姿は今も語り継がれています。
今回は、そんな伝説の名馬たちを7頭に絞ってご紹介します。
史上初の獲得賞金1億円馬 キンタロー
農林水産大臣賞典 (1983,1985,1986)
岩見沢記念(1982,1985,1986)
旭シルバーカップ(1984,1985,1986)
旭王冠賞(1983) など重賞14勝
102戦32勝
キンタローは農林水産大臣賞典(現在のばんえい記念)を3度優勝するなど、重賞レースで14勝を挙げた名馬です。ばんえい競馬史上初めて生涯獲得賞金が1億円を超え、賞金総額(1億1672万5000円)は、現在もばんえい競馬の記録として残っています。
当時の騎手は、「キンタローは馬体のつくりが素晴らしく綺麗な見た目であった。スタートは遅いが障害に強く、他の馬を置いていくような走りだった。」と語っています。
キンタローは5歳から素質を開花し、10歳にして農林水産大臣賞典3勝を達成しました。
この頃は帯広競馬場だけでなく旭川や北見、岩見沢など各地で開催されていたため、開催場所が変わってもなお3勝できたのは偉業であったと言えます。
ばんえい競馬は当時11歳で定年引退となるルールがあり、キンタローもそれに従って引退が決まりました。
引退レースとなった蛍の光賞ですが、これまでの獲得賞金でソリの重量が決まります。キンタローは獲得賞金の多さから、異例の70キロハンデの870キロを背負いますが、堂々1位でゴールしました。
これを見た人達はキンタローはまだまだ走れると騒がれ、惜しむ声も上がったほどでした。まさに「最強馬」と呼ぶにふさわしい活躍だったと言えるでしょう。
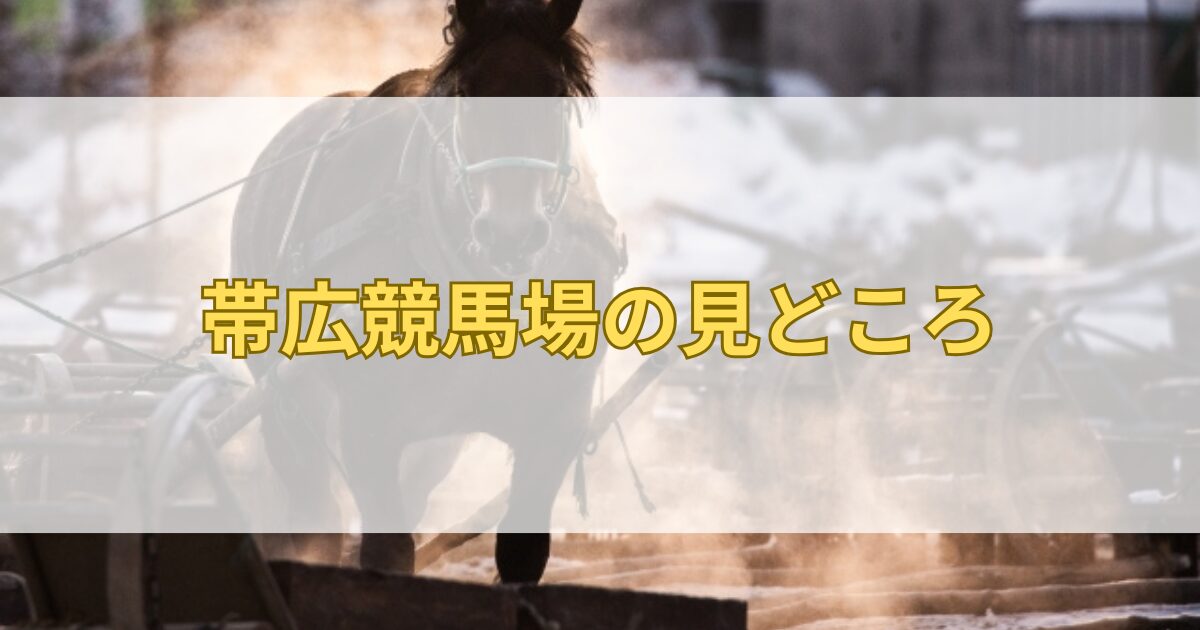
ばんえい記念唯一の3勝牝馬 キヨヒメ
ばんえい記念(1979,1981,1982)
岩見沢記念(1981)
ばんえいプリンセス賞(1977)4歳牝馬限定 など重賞6勝
168戦20勝
キヨヒメはばんえい記念を3勝した名牝です。
1977年に最高重量が1000キロと定められてからの牝馬での優勝を果たしたのはキヨヒメのみで、彼女は1979年、1981年、1982年の3度にわたりその栄冠を手にしました。
旭川、帯広、北見といった異なる競馬場で、さらに馬場の水分状態も異なる中で、3度も優勝するというのは並外れた実力を証明しています。その3勝目では、最強馬と言われたキンタローを2着に抑えての勝利でした。
キヨヒメは7歳時、レースの斤量が830キロから990キロの間という高重量レースを得意としていました。
また、9歳時には馬体重が最も重い時で1050キロに達しています。当時の牝馬の平均馬体重が969キロであったことから、彼女がいかに大柄であったかがうかがえます。
牝馬でこれほどのパワーを持っていたキヨヒメは、今後も語り継がれる名馬になることでしょう。
伝説のばんえい記念4連覇 スーパーペガサス
ばんえい記念(2003~2006)
帯広記念 (2005)
旭王冠賞 (2001,2003,2005)
岩見沢記念 (2002,2003)
北見記念 (2002,2003)
ばんえいグランプリ(2004,2005) など重賞20勝
155戦42勝
スーパーペガサスは、2000年代に活躍したばんえい競走馬です。 障害を一気に越えるスピードはないものの、粘り強く腰を入れてソリを引く強さが魅力でした。
スーパーペガサスの印象と言えば、なんといっても2003年から2006年にかけてばんえい記念を4連覇するという、史上初の記録を達成したことです。この記録は、当時「史上最強」と言われたキンタローさえも成し得なかった大偉業です。また、2002年から2005年まで4年連続でNARグランプリばんえい最優秀馬に選出されるなど、その実力を証明しました。
さらに、2005年には帯広記念を制覇し、旭川、岩見沢、北見、帯広と、4つの競馬場で行われた記念レースをすべて制覇。この記録は、タカラフジ号に次いで、ばんえい競馬史上2頭目の快挙です。加えて、スーパーペガサスは、獲得賞金1億円を突破し、ばんえい競馬史上7頭目となるこの大きな達成を果たしました。
2007年には、ばんえい記念での5連覇が期待されましたが、裂蹄の影響で出走を断念。結果的にそのまま引退となりました。
今もなおばんえい競馬の歴史に名を残す名馬として、多くのファンに愛されている馬です。
1トンをひと腰で上げる障害巧者 ナリタボブサップ
帯広記念(2008)
旭川記念(2008)
北見記念(2007)
ばんえいグランプリ(2010) など重賞21勝
291戦55勝
現役最強と名高いメムロボブサップの父であるナリタボブサップは、【ボブサップ】の名にふさわしい1200キロ超えの大柄な馬体でした。
一番印象に残っているのは2010年のばんえい記念です。
ばんえい競馬のレースの中で最も重い1トンものソリをひくばんえい記念で、第二障害をなんと一腰で越しというとんでもないパワーを見せてくれました。
普段のレースでも第二障害を一腰であげるのは難しいとされているのにも関わらず、一番過酷なレースでこの力強さを出せるのは名馬と言ってよいでしょう。
ただ、ばんえい記念では2度、3着には入ったものの1着を獲ることはありませんでした。
2008年のNARグランプリではばんえい最優秀馬にも選ばれています。
メムロボブサップとあわせて親子共々、名馬として名を残してほしいです。
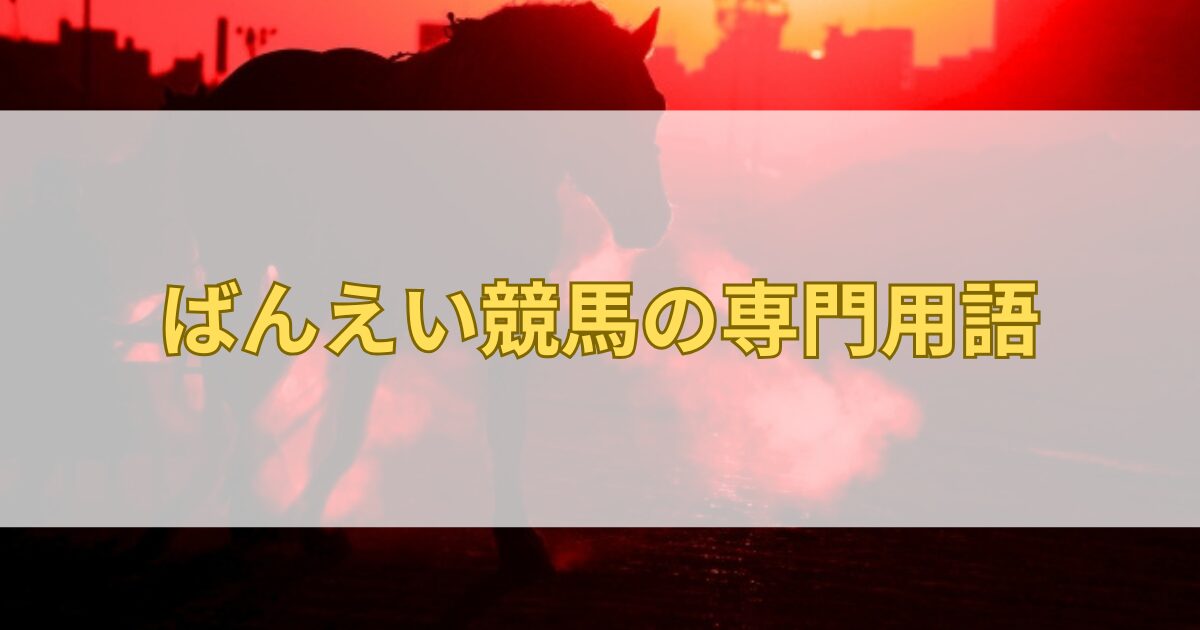
漆黒のナイフ カネサブラック
ばんえい記念(2011,2013)
帯広記念(2012,2013)
旭川記念(2006,2011,2012)
岩見沢記念(2009,2012) など重賞21勝
186戦72勝
2019年にオレノココロ号に記録を更新されるまで、長らく重賞競走最多勝利記録保持者として君臨していました。
その強さはNARグランプリにおけるばんえい最優秀馬に4度も輝いたことが雄弁に物語っています。(2009年、2011年、2012年、2013年)。
同時期に活躍したライバル、ナリタボブサップとは対照的に、決して恵まれた馬体ではありませんでした。しかし、その卓越した切れ味は【漆黒のナイフ】と称され、多くのファンを魅了しました。
2013年の引退レースとなったばんえい記念では、単勝オッズ1.0倍という圧倒的な支持に応えて見事勝利。有終の美を飾り、多くのファンに惜しまれながらターフを去りました。
カネサブラックの勇姿は、今もなお語り継がれるばんえい競馬の伝説として、人々の記憶に深く刻まれています。
史上最多の31連勝 ホクショウマサル
ばんえい記念(2021)
ばんえいダービー(2014)
イレネー記念(2014) 重賞3勝
125戦48勝
ホクショウマサルは日本競馬史上最多となる31連勝を成し遂げた名馬です。
2013年にデビューし、2014年には重賞を2勝します。 しかし、2016年に喘鳴症(気管の病気)を発症し、手術を受けることになりました。 2年4ヶ月という長い休養期間中には、クラスが最下級まで降格。 それでも、ホクショウマサルは諦めませんでした。
2018年に復帰レースで勝利すると、そこから破竹の勢いで連勝街道を突き進みます。 2020年には、ついに31連勝を達成し、ばんえい競馬の連勝記録を塗り替えるとともに、地方・中央競馬を通じた国内公営競馬史上最多連勝記録を更新しました。
連勝は2020年のばんえい記念でストップしたものの、翌2021年には見事同レースを制覇し、ばんえい競馬の頂点に立ちました。 しかし、その後は体調を崩し、同年6月に息を引き取りました。
ホクショウマサルの特徴は、なんといってもその圧倒的な強さでした。 連勝記録はもちろんのこと、復帰後の快進撃は多くのファンを魅了しました。 また、1トンという重いソリを引いたことによる後遺症を乗り越えてばんえい記念を制したことは、彼の不屈の精神を物語っています。
重賞勝利数こそ他の名馬たちに及ばないものの、ホクショウマサルは多くの人々の記憶に残る名馬でした。
重賞勝利数最多記録の25勝 オレノココロ
ばんえい記念(2017,2018,2020)
帯広記念(2016,2017,2019,2021)
旭川記念(2017,2018,2019)
岩見沢記念(2017) など重賞25勝
175戦52勝
オレノココロは、ばんえい競馬の重賞を25勝し、重賞勝利数歴代最多記録を保持しています。そのほかにも、NARグランプリばんえい最優秀馬を3度(2017年、2018年、2020年)受賞するなど、その実力は圧倒的です。
2017年のばんえい記念では、最後の直線で豪快に差し切り、2着のキタノタイショウに24秒の差をつけて圧勝しました。この劇的な勝利は、競馬ファンの記憶に残る名シーンとなりました。
2018年には、史上10頭目となるばんえい記念連覇を達成し、スターホースの仲間入りを果たします。その後も、9歳を迎えたオレノココロは夏頃から連敗が続き、ばんえい記念でも惜しくも2着となり、3連覇は果たせませんでしたが、2020年には再びばんえい記念を制し、その強さを証明しました。
オレノココロはその数々の記録を残すだけでなく、ばんえいアワードで4年連続ベストホースに輝くなど、競馬界でも高く評価されました。また、楽天競馬で行われた歴代ばんえい最強馬ファン投票では1位に選ばれるなど、多くの人々から愛され続けた名馬でした。
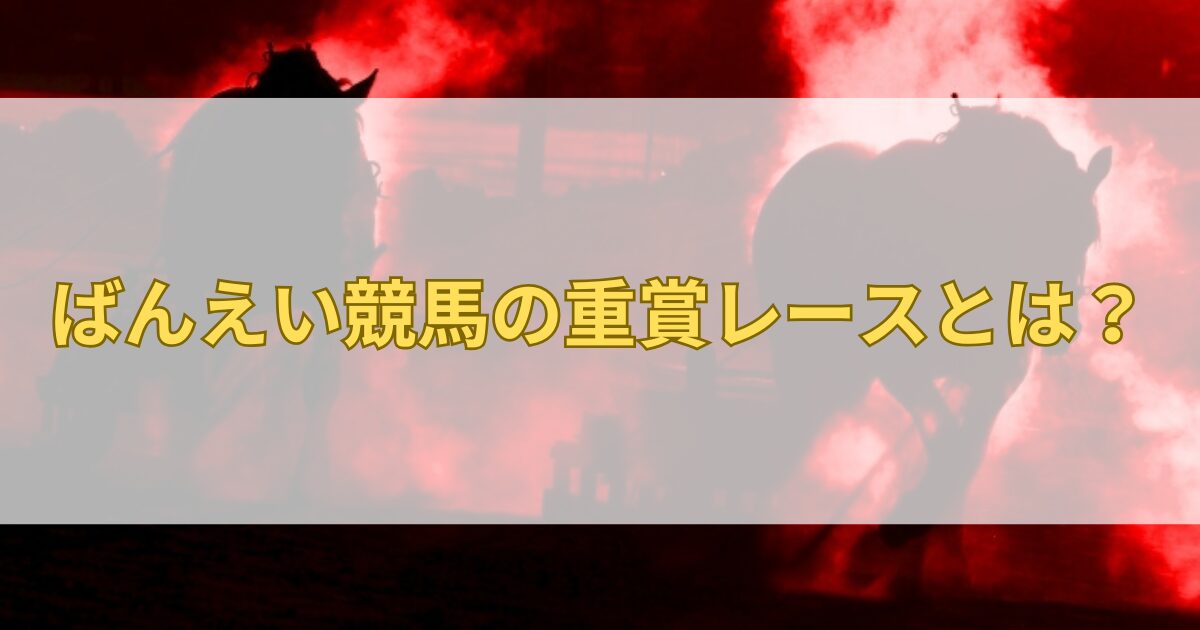
ばんえい競馬の歴代有名馬のまとめ

今回はばんえい競馬の歴史に残る名馬を7頭ご紹介しましたが、実際にはまだまだたくさんの名馬がいます。
これらの名馬たちは、ばんえい競馬をもっと魅力的にして、たくさんの人に感動を与えてきました。
これからもばんえい競馬に新たな名馬が誕生することを期待したいですね。