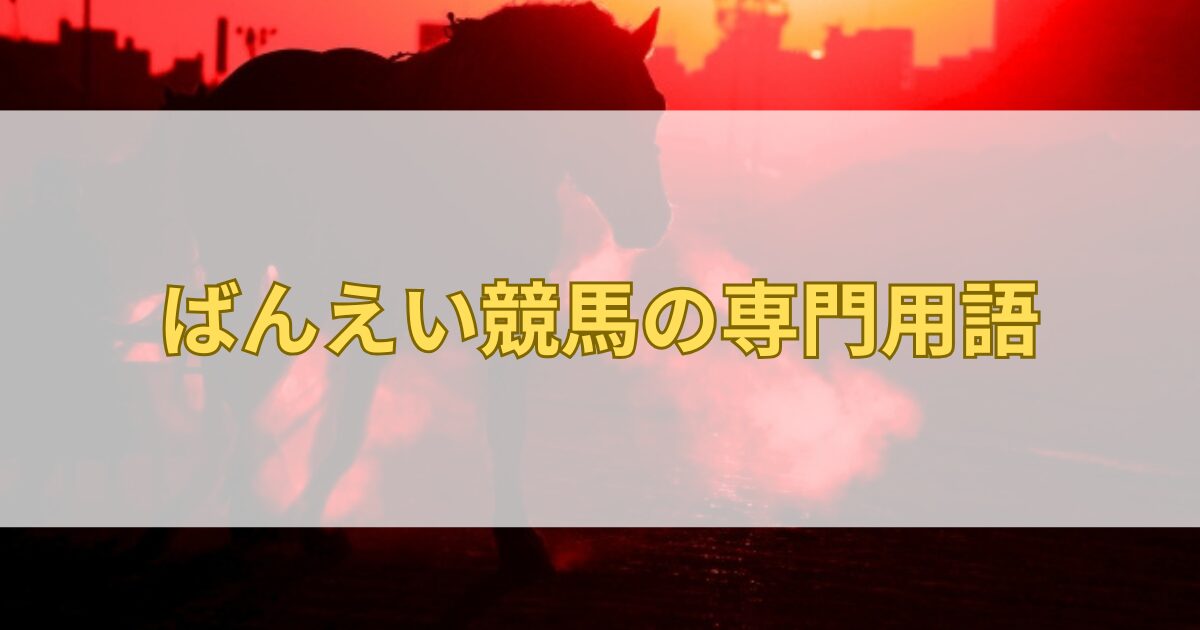競馬に触れていると【差す】や【粘る】など、様々な専門用語を耳にしますが、ばんえい競馬にも独自の専門用語があります。
特にサラブレッドのレースでは全く聞かないような専門用語も複数あるため、はじめてばんえい競馬に触れる人からしたらなんのことかよくわからないと思います。
そこで、今回は観戦するにあたって知っておきたいばんえい競馬の専門用語をまとめました。
ばんえい競馬で使用される用語が気になる方はぜひ参考にしてください。
ばんえい競馬で使用される専門用語12選
冒頭でも触れましたが、ばんえい競馬にはさまざまな専門用語があります。
ここからは、ばんえい競馬の用語の中でも特にメジャーな12の用語についてまとめました。
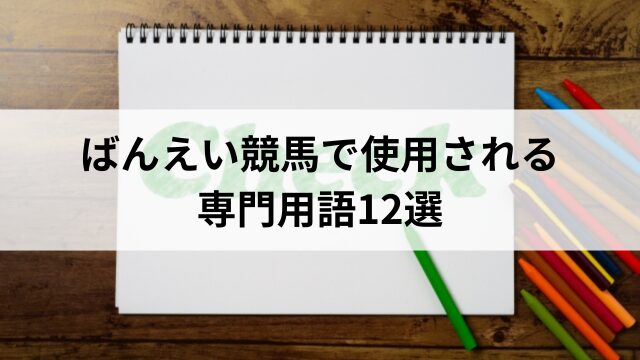
内詰め・外詰め(うちづめ・そとづめ)
内詰め・外詰めとはフルゲート未満のレースにおいて、どちらか片方に詰めてレースを行うことを言います。具体的には内詰めは1コース側、外詰めは10コース側に詰めます。
なぜ、内詰めや外詰めを行うかというと、砂の摩耗をできるだけ差がないようにするためです。
砂は摩耗すると粒が小さくなり脚抜けがよくなるので、これにより開催年度終盤にはタイムが出やすくなるのです。
そのため、奇数開催日の奇数レースは内詰め、偶数レースは外詰めで、偶数開催日の奇数レースは外詰め、偶数レースは内詰めと交互に使用するように決まっています。
なお、ばんえい競馬の場合、1開催とは土・日・月曜日と、翌週土・日・月曜日の計6日間が基本で、1開催を通して1日目から6日目と表記をします。年末年始などは不定期な開催日程もあるので、開催日は出走表のタイトルで確認することができます。
刻む (きざむ)
刻むとは、騎手が戦略的に馬を止めて体力やペース配分をコントロールする方法です。
ばんえい競馬は全長200mのコースですが、コースの間に第一障害と第二障害という小山のような障害が存在しています。
各馬は二つの障害コースを駆け抜けながらゴールを目指しますが、スタートからゴールまで止まらずにゴールできる馬はほとんどいません。
ほぼすべての馬が途中で脚を止めて休みながら進みます。
休むことで馬は息を整え、障害を超えるだけの体力を回復します。ただ、止まりすぎるとほかの馬から遅れをとり、休まなさすぎると体力がなくなりゴールまで体力が持ちません。
そのため、騎手が馬の調子をみながら体力やペース配分をコントロールし、刻みながらゴールを目指すのです。
詰まる(詰まる)
詰まるとは、第二障害とゴールまでの間で停止してしまうことです。
基本的にばんえい競馬では先ほど紹介したように「刻みながら」ゴールを目指しますが、第二障害を越えた後は騎手の合図で止めてはいけません。
しかしながら、第二障害を越えたあとにバテてしまう馬も少なくなく、ゴールまでの緩い登り勾配の途中で馬が疲れて止まってしまうことを【詰まる】といいます。
見てる分には変わらないかもしれませんが、刻むは「騎手が止めること」で、詰まるは「馬が止まること」なので全く別の意味合いです。
そして、第二障害からゴールまでの間はルール上、刻むことができないため、その道中で脚が止まっている場合は馬の意思で脚が止まっているのです。
べん(鞭)打ち
ばんえい競馬では、鞭を使うのではなく長い手綱の余った部分で馬を刺激します。これをべん(鞭)打ちと言います。しばしば「馬が可哀そう」と批判されるのが騎手のべん打ちですが、体重一トンの馬にとって手綱で打たれるのは、人間でいえば肩をポンと叩かれるのと同程度の刺激です。
騎手はべん打ちによって「頑張れ」と馬に気合いを入れているのです。
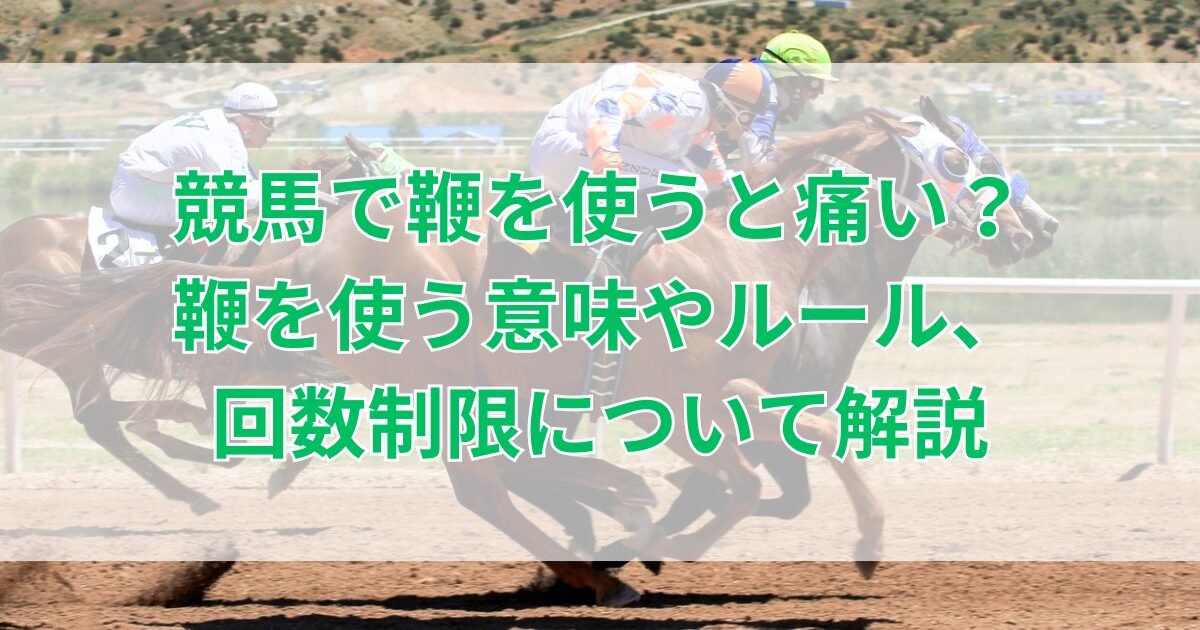
バイキ
バイキとは、障害を登っている途中や、砂障害で止まっている馬を動かすために騎手が手綱を大きく引き、その反動で馬を前進させることです。
ばんえい競馬における騎手の鞭入れの一種で、理屈としてはバネを縮めてポンと離す要領と同じです。
バイキを行うことで、体重の3倍はあると言われている馬の瞬発的な力を引き出すことができます。
掛かり(かかり)
ばんえい競馬における掛かりとは、第二障害をどこまで上がれるかをいいます。
具体的には上がる勢いやどこまで上がれるかを【障害の掛かり】と言い、馬が障害を越えるための勢いが増した時に【掛かりが良くなった】と言います。
なお、サラブレッドの競馬においても掛かるという言葉は使われますが、こちらの掛かりは競走馬が騎手の指示を無視して積極的に前に行きたがることを言うので、ばんえい競馬とは意味が全く異なります。
一腰・二腰(ひとこし・ふたこし)
一腰と二腰とは、第二障害を攻略する際、馬が勢いをつけて駆け上がる回数をいいます。
第二障害手前の状態から一回で一気に頂上まで駆け上がることを【一腰で上げる】と言います。坂の途中で止まることなく一気に障害を突破するため、ばんえい競馬においては一腰で上がるのが理想の形です。
坂の途中で脚が止まってしまった馬は息を整えて再度頂上を目指しますが、2回目で上がれれば二腰、3回目なら三腰となります。
膝を折る(ひざをおる)
膝を折るとは、競走馬が障害を超える際に脚が止まって膝が地面に付くことを指します。
ばんえい競馬の障害は第一障害と第二障害がありますが、第二障害は息を整えなければ登坂は難しいです。競走馬の中には坂の途中で膝を折る馬も少なくありません。
膝を折ってからすぐに立て直せる場合もありますが、馬具が邪魔をし立てなくなった馬は競走中止になることもありますし、最悪の場合は予後不良になるケースもあるので極力膝を折らずに登坂出来ることが望ましいです。
なお、膝を折るとは言いますが、実際に骨折しているわけではなく競争中止となった場合でもしっかりと歩いて帰ることがほとんどです。
天板(てんばん)
天板とは第二障害の坂の頂上のことです。
障害コースは台形のような形をしており、頂点は平らになっています。
前脚が天板にかかればそのままソリを上げやすくなるので、ここに届くことが馬にとって障害を越えるための目標になります。
砂障害
砂障害とは第二障害を超えた後の最後の平らなコースです。
第二障害後はゴールまでの間に高さ50cmほどの道のりがありますが、実は平たんではなく高低差0.5mの上り傾斜となっているため、砂障害と呼ばれています。
若干の上り坂があるおかげで砂障害があるおかげで、第二障害を越えた後もエキサイティングな接戦を楽しむことができますよ。
なお、冬の期間は走路の凍結節のため、コース内に埋め込まれているロードヒーティングが稼働します。
ロードヒーティングが入っているおかげで真冬の北海道でもレースが行われていますが、砂障害があるとロードヒーティングの効果がなくなるため、冬時期は砂障害が撤去された状態でレースが行われています。
能力検査
能力検査とは、競走馬のタイムを図る検査のことです。
デビュー前の馬たちは「能力検査」を行い、指定されたタイム内にゴールしなければデビューすることができません。
新年度に入る前の4月の能力検査はデビュー前の2歳馬が数多く受検するため特に注目を集めます。能力検査におけるタイムやレースの様子は、新馬戦の予想をするために重要なファクターになります。
能力検査の様子はYoutubeで生配信されていますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
キンタロー
キンタローとは1980年代に活躍したばん馬で、現役時代はばんえい優駿やばんえい菊花賞、ばんえい大賞典を制してばんえい三冠馬になりました。
それだけではなく、古馬になってからも重賞で結果を残し、最終的には重賞14勝、獲得賞金1億円を突破したばんえいを代表する名馬です。
しかしながら、現在キンタローといったらばんえい専用の競馬新聞である「キンタロー」を指すケースが強いです。キンタローは帯広競馬場内の売店で入手でき、ネット新聞でもチェックできますよ。
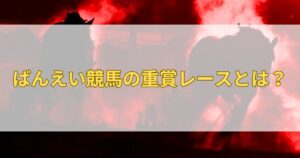
ばんえい競馬の専門用語のまとめ
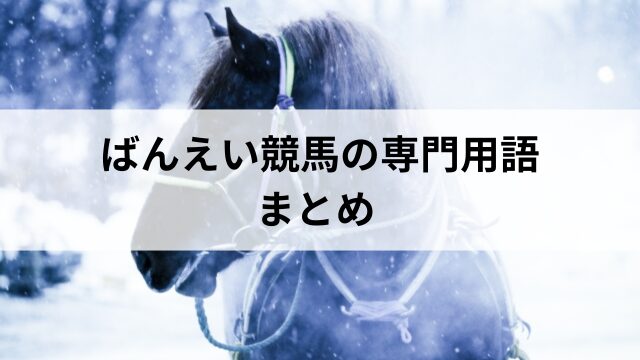
今回はばんえい競馬に関する様々な専門用語を解説しました。
これらを知っておくと、レース実況やばんえい競馬に関する記事をより深く理解することができ、よりばんえい競馬の魅力に気付けるのではないでしょうか。
用語を知るだけでもばんえい競馬をますます楽しめると思うので、ぜひ覚えていただけたらと思います。